キッチンの調理監視団 [猫と暮らせば] [編集]
キッチンの調理監視団
カミさんの骨折を機にぼくも毎日料理をするようになって一年ちょっとが過ぎて、今ではカミさんの腕もほぼ治って料理もできるようになったのだが、ぼくも毎日夕食の時はキッチンに立っている。まだ自分で全ての献立を決めるようにはなっていないけれど、一品は作るようにしている。
最初は良くぶつかっていたキッチンでのカミさんとの動線も何となく交差しなくなったのと、自分で書いておいたメモを見ないでも作れるようになってきたメニューも増えてきたというのが進歩といえば進歩かも知れない。
新米料理人に対して今でも時折カミさんの厳しい目が光ることがあるけれど、それ以外にも目を光らせている者がいる。キッチンの見学者というかぼくは厳格な調理検査官(strict cooking inspector)と呼んでいるけれども、毎回のように調理をしているぼくの目の前で目を光らせている。
最初は良くぶつかっていたキッチンでのカミさんとの動線も何となく交差しなくなったのと、自分で書いておいたメモを見ないでも作れるようになってきたメニューも増えてきたというのが進歩といえば進歩かも知れない。
新米料理人に対して今でも時折カミさんの厳しい目が光ることがあるけれど、それ以外にも目を光らせている者がいる。キッチンの見学者というかぼくは厳格な調理検査官(strict cooking inspector)と呼んでいるけれども、毎回のように調理をしているぼくの目の前で目を光らせている。
そもそも見学に来るようになったのはハルが最初で、好奇心が強いからぼくがキッチンに立つようになって何をしているんだろうと訝ってそばに寄ってきて観察するようになった。最初はカウンターに上がらずに前に置いたテーブルの端から見ていたのだが、そのうちカウンターに上がってきてしげしげと見るようになった。今は腰を落ち着かせて腕組みして見ている。
その内レオも何だろうと思ってか、近づいて来るようになった。レオが近づいて来る理由はハルのように好奇心からではなくて、自分に隠れてハルが何か美味しそうなものを貰っているのじゃないかという気持ちからなのは、その態度でみえみえなのだけれど…。
猫たちは先にご飯をもらっているのでハルは純粋に好奇心で見ているのだが、レオは調理の肉なんかがまな板に乗ると、当然自分の分け前もあるものだと思い込んでソワソワしだす。手は出さないがこちらは包丁を持っているので気が気ではない。一日も早くこの厳しい二人の調理監視団の調理検査官に合格をもらって一人前の主夫になりたいものだ。
その内レオも何だろうと思ってか、近づいて来るようになった。レオが近づいて来る理由はハルのように好奇心からではなくて、自分に隠れてハルが何か美味しそうなものを貰っているのじゃないかという気持ちからなのは、その態度でみえみえなのだけれど…。
猫たちは先にご飯をもらっているのでハルは純粋に好奇心で見ているのだが、レオは調理の肉なんかがまな板に乗ると、当然自分の分け前もあるものだと思い込んでソワソワしだす。手は出さないがこちらは包丁を持っているので気が気ではない。一日も早くこの厳しい二人の調理監視団の調理検査官に合格をもらって一人前の主夫になりたいものだ。


Facebook コメント
カレンダー
このブログの更新情報が届きます
すでにブログをお持ちの方は[こちら]gillman*s Memories 小原古邨
I remember...


小原古邨(祥邨)
お正月になると小原古邨の祥邨時代の版画「雪中南天に瑠璃鳥」が大好きなので、それを飾るのだけれど、先年茅ケ崎市美術館で行われた「The新版画」展でこの作品の原画(下絵)を見てちょっと驚いた。
この絵は当初はタイトルも「雪中南天に鶫(つぐみ)」という題で、そこに描かれている鳥は今の瑠璃鳥のように鮮やかな色彩の鳥ではなく褐色のちょっと地味な二羽の鳥だった。木版画も一旦はその色彩で摺られたのが、地味過ぎるということで版元の渡邊庄三郎の指摘で瑠璃鳥に変えられたとのことだった。
花鳥図としては原画も素晴らしいと思うが、確かに原画と比べるとこの瑠璃鳥版の方が色彩の対比も鮮やかで正月に相応しい吉祥の雰囲気もある。
固い事を言うと瑠璃鳥は夏の鳥で雪との取り合わせはあり得ないのかもしれないが、展覧会の解説では当時メーテルリンクの「青い鳥」が流行っていたこともあって、図柄の「南天」が「難を転じて福とする」ということと瑠璃鳥の「幸せを呼ぶ青い鳥」で新時代の吉祥図にふさわしい作品となった、とある。

小原古邨

†1945年(昭和20年)1月4日
雪中南天に瑠璃鳥

小原古邨(祥邨)
お正月になると小原古邨の祥邨時代の版画「雪中南天に瑠璃鳥」が大好きなので、それを飾るのだけれど、先年茅ケ崎市美術館で行われた「The新版画」展でこの作品の原画(下絵)を見てちょっと驚いた。
この絵は当初はタイトルも「雪中南天に鶫(つぐみ)」という題で、そこに描かれている鳥は今の瑠璃鳥のように鮮やかな色彩の鳥ではなく褐色のちょっと地味な二羽の鳥だった。木版画も一旦はその色彩で摺られたのが、地味過ぎるということで版元の渡邊庄三郎の指摘で瑠璃鳥に変えられたとのことだった。
花鳥図としては原画も素晴らしいと思うが、確かに原画と比べるとこの瑠璃鳥版の方が色彩の対比も鮮やかで正月に相応しい吉祥の雰囲気もある。
固い事を言うと瑠璃鳥は夏の鳥で雪との取り合わせはあり得ないのかもしれないが、展覧会の解説では当時メーテルリンクの「青い鳥」が流行っていたこともあって、図柄の「南天」が「難を転じて福とする」ということと瑠璃鳥の「幸せを呼ぶ青い鳥」で新時代の吉祥図にふさわしい作品となった、とある。

(Jan.2025/ org.Jan.2023)
gillman*s Choice Der Witz der Woche
Der Witz der Woche
今週のドイツ・ジョーク (4)

環境保護型トイレ
「分別にご協力ください」
・ビール
・ワイン
・レモネード
・水
ドイツは環境保護に熱心なのは有名だが、ここまで徹底しているとは(笑)。
もちろんこれはドイツ流のユーモアなのだけれど…よく考えてみると分別してどうしょうとするのだろうか。面白いジョークだと思っていたけれど、この秋ドイツでライン下りをしてその後、ライン川を見下ろす古城ホテルの「ライン・フェルス」のレストランで食事をしたら、そこの男性トイレがまさにこれだった。
まさか写真を撮るわけにはいかなかったけど…。分別はちょっと違って水、ビール、ワイン、高アルコール飲料の4種類になっていた。ジョークにまじめに取り組むドイツ人。
同ホテルのトイレの写真をやっと探し出したのがこれ…

(Dec.2024)
gillmn*s Choice Der Witz der Woche
Der Witz der Woche...
ドイツ・ジョーク 3

とあるセルフ給油所で…
M1「給油うまいねぇ!」
M2「ありがとう!」
ぼくは一コマ漫画が好きなのでドイツのカートゥーンもよく見る。ドイツ人は下ネタも好きだけれど時にはちょっと小じゃれた作品に出合うとうれしい。ドイツ語の勉強や文化理解にもなるかもしれない。
で、この作品の面白味のキモは"super"という言葉にある。"super"には素晴らしいという意味と別に"Super"でハイオクガソリンの意味もあるので、もうお分かりのように給油の男性がジーゼル車にガソリンを入れようとしているので、それを注意しているのだけれど、当の本人は褒められていると勘違いして…
「おい、それガソリンだぜ!」
「ありがとう!」
(Dec.2024)
ドイツ・ジョーク 3

とあるセルフ給油所で…
M1「給油うまいねぇ!」
M2「ありがとう!」
ぼくは一コマ漫画が好きなのでドイツのカートゥーンもよく見る。ドイツ人は下ネタも好きだけれど時にはちょっと小じゃれた作品に出合うとうれしい。ドイツ語の勉強や文化理解にもなるかもしれない。
で、この作品の面白味のキモは"super"という言葉にある。"super"には素晴らしいという意味と別に"Super"でハイオクガソリンの意味もあるので、もうお分かりのように給油の男性がジーゼル車にガソリンを入れようとしているので、それを注意しているのだけれど、当の本人は褒められていると勘違いして…
「おい、それガソリンだぜ!」
「ありがとう!」
(Dec.2024)
gillman*s Choice German Cinema Review Der Sommer des Samurai
ドイツ映画Review...

12月14日は忠臣蔵で有名な四十七士の赤穂浪士吉良邸討ち入りの日なのだけれど、母校の中学が吉良邸の近くだったこともあって関心もあり討ち入りの映画などはよく見たが、実はドイツの映画に「ベルリン忠臣蔵」という摩訶不思議な映画がある。
原題は"Der Sommer des Samurai(侍たちの夏)"なのだけれど「ベルリン忠臣蔵」という邦題がつけられている。外国映画の邦題にありがちななんちゃってタイトル的な気がするが内容的にはそれほどかけ離れてはいないような気もする。もっとも映画の舞台はハンブルクでベルリンじゃないけど…。
ストーリーはこうだ。(ネタバレあり) ハンブルクで地元の有力者が次々と襲われるが、首謀者は大石内蔵助と名乗る謎の男。その男のいでたちは怪傑ゾロのような覆面をして鉢巻には漢字で「大石」と書いてある。そして犯行現場には近松、木村、寺坂などの謎の文字が残されている。
それらの謎は忠臣蔵の四十七士のメンバーの名前だという事があかされる。その謎にたどり着いたのは新聞記者のクリスチアーネだったのだが、彼女は大石にもうこれ以上嗅ぎまわるなと脅される。
しかしクリスチアーネはついに大石の正体に辿り着き彼の本当の目的を知る。彼は大石内蔵助の末裔に侍魂を教えられて育てられた。今はハンブルクで資産家となっているクラールと友人たちが日本に居る時に家宝の「村正」を奪ったことを知り…。そろそろ頭が痛くなってきた。最後にはちゃんとニンジャもでてくる。
なんか言いながらこれはこれで結構楽しめた。タランティーノ監督の「キル・ビル」が流行ったのはずっとあとの2003年位なのだけれど、この作品はそれ以前に作られた奇想天外なキル・ビル的日本趣味の映画として貴重なものかもしれない。
元来ドイツはこの手の映画は得意なのだ。あまり知られていないけれどいわゆる「マカロニ・ウエスタン」同様1960年代のドイツのザワークラウト・ウェスタン(Sauerkraut Westerns)」はドイツで大人気だった。
一時代前の欧米人の日本観が見られて楽しいが、日本人はずっとそれに辟易していたかもしれない。そういう意味では時代考証などで妥協を許さない態度を貫き通して「将軍」でエミー賞を手にした真田広之の功績は素晴らしいと思う。
[Credit]
Year:1986
Director:Hans-Christoph Blumenberg
Writers:Hans-Christoph Blumenberg,Frederick Spindale,Carola Stern
Stars:
Cornelia Froboess
Hans Peter Hallwachs
Wojciech Pszoniak


*下記のYouTubeで観られるのでご関心のある方はどうぞ…
https://www.youtube.com/watch?v=PT77OPy-pZ8
~17~
ベルリン忠臣蔵
Der Sommer des Samurai
12月14日は忠臣蔵で有名な四十七士の赤穂浪士吉良邸討ち入りの日なのだけれど、母校の中学が吉良邸の近くだったこともあって関心もあり討ち入りの映画などはよく見たが、実はドイツの映画に「ベルリン忠臣蔵」という摩訶不思議な映画がある。
原題は"Der Sommer des Samurai(侍たちの夏)"なのだけれど「ベルリン忠臣蔵」という邦題がつけられている。外国映画の邦題にありがちななんちゃってタイトル的な気がするが内容的にはそれほどかけ離れてはいないような気もする。もっとも映画の舞台はハンブルクでベルリンじゃないけど…。
ストーリーはこうだ。(ネタバレあり) ハンブルクで地元の有力者が次々と襲われるが、首謀者は大石内蔵助と名乗る謎の男。その男のいでたちは怪傑ゾロのような覆面をして鉢巻には漢字で「大石」と書いてある。そして犯行現場には近松、木村、寺坂などの謎の文字が残されている。
それらの謎は忠臣蔵の四十七士のメンバーの名前だという事があかされる。その謎にたどり着いたのは新聞記者のクリスチアーネだったのだが、彼女は大石にもうこれ以上嗅ぎまわるなと脅される。
しかしクリスチアーネはついに大石の正体に辿り着き彼の本当の目的を知る。彼は大石内蔵助の末裔に侍魂を教えられて育てられた。今はハンブルクで資産家となっているクラールと友人たちが日本に居る時に家宝の「村正」を奪ったことを知り…。そろそろ頭が痛くなってきた。最後にはちゃんとニンジャもでてくる。
なんか言いながらこれはこれで結構楽しめた。タランティーノ監督の「キル・ビル」が流行ったのはずっとあとの2003年位なのだけれど、この作品はそれ以前に作られた奇想天外なキル・ビル的日本趣味の映画として貴重なものかもしれない。
元来ドイツはこの手の映画は得意なのだ。あまり知られていないけれどいわゆる「マカロニ・ウエスタン」同様1960年代のドイツのザワークラウト・ウェスタン(Sauerkraut Westerns)」はドイツで大人気だった。
一時代前の欧米人の日本観が見られて楽しいが、日本人はずっとそれに辟易していたかもしれない。そういう意味では時代考証などで妥協を許さない態度を貫き通して「将軍」でエミー賞を手にした真田広之の功績は素晴らしいと思う。
[Credit]
Year:1986
Director:Hans-Christoph Blumenberg
Writers:Hans-Christoph Blumenberg,Frederick Spindale,Carola Stern
Stars:
Cornelia Froboess
Hans Peter Hallwachs
Wojciech Pszoniak

*下記のYouTubeで観られるのでご関心のある方はどうぞ…
https://www.youtube.com/watch?v=PT77OPy-pZ8
(Dec.2024)
gillman*s Museum 田中一村展
Museum of the Month...
東京都美術館

2010年に千葉市美術館で行われた「田中一村展」を見逃した悔しさが忘れられなくて2020年に奄美大島の田中一村記念美術館に行った時のことは今でも良い想い出になっているが、彼の千葉時代の作品も含めてもっと全体を見てみたいという気持ちはさらに強くなってきたのでまたどこかで回顧展をやってくれないかと願っていた。
今回上野の東京都美術館での「田中一村展」を見て待った甲斐があったなぁ、と。今回の展覧会は千葉時代も含めて、また最近の新発見の作品まで展示されていてよくもまぁこれだけ集めたものだと、キュレーターの努力に頭が下がる。
彼の奄美時代の作品群はある程度奄美の記念美術館で目にしていたが、それ以前の作品はあまり観ていなかったし、正直言って一村は奄美時代に限るなぁと思い込んでいたのも確か。しかし今回の展示作品を見て生涯の画業を通じて一村の力量というものに驚きもし、感動もした。益々一村の作品が好きになったけれど、生前はさして見向きもされなかった彼の展覧会にこれだけの行列ができるということに、一瞬ゴッホの生涯が頭を過った。
蘭竹図/富貴図衝立(1929)

会場でも一際めだつ鮮やかな色彩の屏風。片面は墨絵の蘭竹図でもう片面は鮮やかな色彩で緻密に描かれた牡丹。画面には優雅に舞う蝶も描かれて題名のとおりいかにも富貴という豪華なつくりである。
椿図屏風(1931)

2013年に新たに発見された作品で、ある意味では一村の空白期間を埋める重要な作品である。20歳代半ばに描かれた作品とは思えないほど練達した画力と新鮮なエネルギーも感じる。同じつくりの金屏風が無地のまま遺されており、一村はここに何を描こうとしたのか想像が膨らむ。
岩上の磯鵯(1959)

大胆な構図である。画面の大半を占める黒々とした断崖の上にちょこんと磯鵯(イソヒヨドリ)がとまっている。発見されたのは比較的近年らしいが、奄美時代の初期の作品と思われ、縦長の画面に奄美の自然をダイナミックに描写する独特の構図もこの頃から定着し出したようだ。
枇榔樹の森(1973)

枇榔樹の葉が殆ど墨の濃淡だけで描かれておりそれだけでも奄美の光と湿潤な空気を感じ取ることができる。目を凝らすとアサギマダラチョウや僅かに色を載せられた草花がこの世界の神秘さを物語っている。今回の展覧会でも一番記憶に焼き付いた作品だった。
アダンの海辺(1969)

あまりにも有名となった彼の代表作と言われるものの一つ。彼自身も自分の代表作たり得ると自負していたようで「閻魔大王への土産物だ」と書簡に記しているようだ。陽の光を受けた熟したアダンの実は奄美のシンボルであり今日でも島のあちこちで見られる風景なのだが、一村はこれを見たものが生涯忘れられないような島のアイコンに昇華させたと思う。
[図録]

269頁、3500円。展覧会の図録もとうとう3000円をオーバーするのが珍しくはなくなった時代に入った。今までは図録は画集を買うよりは割安だし、実物を観た記憶を補強できるのでできるだけ買うようにはしていたけど、こう高額になるとこれからは吟味して買う必要がありそうだ。
好きな作家なので田中一村の画集は何冊か持っているが、今回の図録は、①展示点数の多さから他の画集を買わなくてもこれ一冊で彼の画業のかなりをカバーできる、②今までの画集には載っていない近年発見された作品も載っている、などの点で買う価値はあるかなと思った。
東京都美術館
田中一村展
(2024.09.19~12.01)
2010年に千葉市美術館で行われた「田中一村展」を見逃した悔しさが忘れられなくて2020年に奄美大島の田中一村記念美術館に行った時のことは今でも良い想い出になっているが、彼の千葉時代の作品も含めてもっと全体を見てみたいという気持ちはさらに強くなってきたのでまたどこかで回顧展をやってくれないかと願っていた。
今回上野の東京都美術館での「田中一村展」を見て待った甲斐があったなぁ、と。今回の展覧会は千葉時代も含めて、また最近の新発見の作品まで展示されていてよくもまぁこれだけ集めたものだと、キュレーターの努力に頭が下がる。
彼の奄美時代の作品群はある程度奄美の記念美術館で目にしていたが、それ以前の作品はあまり観ていなかったし、正直言って一村は奄美時代に限るなぁと思い込んでいたのも確か。しかし今回の展示作品を見て生涯の画業を通じて一村の力量というものに驚きもし、感動もした。益々一村の作品が好きになったけれど、生前はさして見向きもされなかった彼の展覧会にこれだけの行列ができるということに、一瞬ゴッホの生涯が頭を過った。
田中一村展
My Best 5
蘭竹図/富貴図衝立(1929)

会場でも一際めだつ鮮やかな色彩の屏風。片面は墨絵の蘭竹図でもう片面は鮮やかな色彩で緻密に描かれた牡丹。画面には優雅に舞う蝶も描かれて題名のとおりいかにも富貴という豪華なつくりである。
椿図屏風(1931)

2013年に新たに発見された作品で、ある意味では一村の空白期間を埋める重要な作品である。20歳代半ばに描かれた作品とは思えないほど練達した画力と新鮮なエネルギーも感じる。同じつくりの金屏風が無地のまま遺されており、一村はここに何を描こうとしたのか想像が膨らむ。
岩上の磯鵯(1959)

大胆な構図である。画面の大半を占める黒々とした断崖の上にちょこんと磯鵯(イソヒヨドリ)がとまっている。発見されたのは比較的近年らしいが、奄美時代の初期の作品と思われ、縦長の画面に奄美の自然をダイナミックに描写する独特の構図もこの頃から定着し出したようだ。
枇榔樹の森(1973)

枇榔樹の葉が殆ど墨の濃淡だけで描かれておりそれだけでも奄美の光と湿潤な空気を感じ取ることができる。目を凝らすとアサギマダラチョウや僅かに色を載せられた草花がこの世界の神秘さを物語っている。今回の展覧会でも一番記憶に焼き付いた作品だった。
アダンの海辺(1969)

あまりにも有名となった彼の代表作と言われるものの一つ。彼自身も自分の代表作たり得ると自負していたようで「閻魔大王への土産物だ」と書簡に記しているようだ。陽の光を受けた熟したアダンの実は奄美のシンボルであり今日でも島のあちこちで見られる風景なのだが、一村はこれを見たものが生涯忘れられないような島のアイコンに昇華させたと思う。
[図録]
269頁、3500円。展覧会の図録もとうとう3000円をオーバーするのが珍しくはなくなった時代に入った。今までは図録は画集を買うよりは割安だし、実物を観た記憶を補強できるのでできるだけ買うようにはしていたけど、こう高額になるとこれからは吟味して買う必要がありそうだ。
好きな作家なので田中一村の画集は何冊か持っているが、今回の図録は、①展示点数の多さから他の画集を買わなくてもこれ一冊で彼の画業のかなりをカバーできる、②今までの画集には載っていない近年発見された作品も載っている、などの点で買う価値はあるかなと思った。
(Nov.2024)
gillman*s Museum 田中一村記念美術館
My Museum...あの時の展覧会
奄美大島
田中一村記念美術館
常設展(2020)

田中一村の絵に興味を持ったのはそんなに昔の事ではなかった。2010年に千葉市美術館で彼の大規模な回顧展が開かれた際観に行きたかったのだけど叶わなかった。結局彼の作品の現物を初めて見たのは2018年に岡田美術館で一村展が開かれた時なのだが、その時は彼の代表作ともいえる「アダンの海辺」や「白花と赤翡翠」等を観ることができた。しかしその展覧会は一村本人の展示作品数はずいぶん少なかったので、いずれは奄美の田中一村記念美術館に行きたいと思っていた。
昨年、奄美大島に一週間の予定で友人と行くことになり念願の美術館を訪れることができた。美術館は島の一番北部に位置する空港の近くにある鹿児島県奄美パークの中にあり名前の通り田中一村の作品だけを所蔵展示している。
展示室は彼の東京時代・千葉時代・奄美時代など4つの部屋に分かれており最後の四番目に主に奄美時代の作品が展示されているが、順次見てゆくとやっぱり奄美との出会いが彼の作風や主題を大きく変えて才能を花開かせていったことが分かる。
常設展示は3か月づつ年四回入れ替え展示されているらしいのだけれど、そう何度も来られるところではないので奄美時代の作品をもう少し展示して欲しいなぁという感じはした。とはいえ展示されている奄美時代の作品はどれも力作でぼくが行ったときには、下の7点が展示されていた。
①パパイヤとゴムの木
②アダンと小舟
③奄美の海に蘇鉄とアダン
④初夏の海に赤翡翠
⑤不喰芋と蘇鉄
⑥榕樹に虎みみづく
⑦蘇残照図
(2020年3月17日まで)
田中一村美術館の
奄美の海に蘇鉄とアダン/1961年

奄美に本格定住する前に奄美を描いた作品で横長の画面いっぱいに蘇鉄の花とアダンの実が大きく描かれている。蘇鉄の花は以前石垣島で見たことがあるのだけど、独特の存在感があり香りも強い。その実は毒があるが島民は解毒して食料にするなど奄美、琉球のソウル・プランツだ。
色彩は奄美に本格的に移住してからの作品のように強烈ではなくデザイン性も高い。この作品は奄美の象徴的なファクターを千葉の人たちに見せる意味もあったのかもしれない。他の奄美時代の作品とはまた違った魅力を持っていると思う。
初夏の海に赤翡翠/1962年

一村の代表作の一つだと思う。画面いっぱいに奄美の植物であるビロウやアカミズキ、ハマユウなどに囲まれた画面の中央に舞台のような三角形のスリットが生じそこにアカショウビンがスーッと飛んできてとまっている。
一村がよくやったように繁みをかき分けて海辺にたどり着いた辺りでふっと出くわしそうな一瞬。南国のパラダイスのような光景。しかし、実際には繁みの中の足元には常にハブが潜んでいる危険がある。現地の人でもためらうような繁みに一村はいつも裸足にぞうり姿で平気で入っていったという。
不喰芋と蘇鉄/1973年

最晩年の方の作品だが一見するとルソーの作品のように見えたりもする。不喰芋(くわずいも)は島で最もポピュラーな植物でいたるところで見られる。中央に力強くその不喰芋が描かれ、そして画面の左右には蘇鉄の雄花と雌花が描かれておりそれは生命のサイクルを示しているようにも思える。
「奄美の海に蘇鉄とアダン」と同じように画面の向こうには立神(たちがみ)と呼ばれる沖合の大きな岩が描かれている。それはこの島にやってくる神の道しるべと言われて島民の信仰の対象にもなっている。一村は最後に南の島の神秘的な生命のサイクルについて描きたかったのかもしれない。
白い花/1947年

これは奄美での作品ではなくかなり初期の作品なのだが、美術館の展示の中でひときわ目を引いていた。形態は二曲一隻の屏風の形をとっている。内地の展覧会青龍社展で入選している。竹林の前に繁茂し咲き乱れるヤマボウシの枝ぶりの配置も絶妙で白い花と緑葉に覆われた画面全体に若い一村のみずみずしい感性が溢れている。この年彼は号を田中米邨から柳一村に替えている。
いまだに2010年に千葉市美術館で行われた田中一村展「田中一村 新たなる全貌」を観そこなってしまったのが悔やまれる。当分彼の大規模な回顧展はないだろうけど、没後30年にあたる2027年あたりがねらい目かもしれない…が、それまでこちらの寿命の方が持つかが問題だが。

奄美大島
田中一村記念美術館
常設展(2020)
田中一村の絵に興味を持ったのはそんなに昔の事ではなかった。2010年に千葉市美術館で彼の大規模な回顧展が開かれた際観に行きたかったのだけど叶わなかった。結局彼の作品の現物を初めて見たのは2018年に岡田美術館で一村展が開かれた時なのだが、その時は彼の代表作ともいえる「アダンの海辺」や「白花と赤翡翠」等を観ることができた。しかしその展覧会は一村本人の展示作品数はずいぶん少なかったので、いずれは奄美の田中一村記念美術館に行きたいと思っていた。
昨年、奄美大島に一週間の予定で友人と行くことになり念願の美術館を訪れることができた。美術館は島の一番北部に位置する空港の近くにある鹿児島県奄美パークの中にあり名前の通り田中一村の作品だけを所蔵展示している。
展示室は彼の東京時代・千葉時代・奄美時代など4つの部屋に分かれており最後の四番目に主に奄美時代の作品が展示されているが、順次見てゆくとやっぱり奄美との出会いが彼の作風や主題を大きく変えて才能を花開かせていったことが分かる。
常設展示は3か月づつ年四回入れ替え展示されているらしいのだけれど、そう何度も来られるところではないので奄美時代の作品をもう少し展示して欲しいなぁという感じはした。とはいえ展示されている奄美時代の作品はどれも力作でぼくが行ったときには、下の7点が展示されていた。
①パパイヤとゴムの木
②アダンと小舟
③奄美の海に蘇鉄とアダン
④初夏の海に赤翡翠
⑤不喰芋と蘇鉄
⑥榕樹に虎みみづく
⑦蘇残照図
(2020年3月17日まで)
田中一村美術館の
[奄美作品My Favorite 3+1]
奄美の海に蘇鉄とアダン/1961年

奄美に本格定住する前に奄美を描いた作品で横長の画面いっぱいに蘇鉄の花とアダンの実が大きく描かれている。蘇鉄の花は以前石垣島で見たことがあるのだけど、独特の存在感があり香りも強い。その実は毒があるが島民は解毒して食料にするなど奄美、琉球のソウル・プランツだ。
色彩は奄美に本格的に移住してからの作品のように強烈ではなくデザイン性も高い。この作品は奄美の象徴的なファクターを千葉の人たちに見せる意味もあったのかもしれない。他の奄美時代の作品とはまた違った魅力を持っていると思う。
初夏の海に赤翡翠/1962年

一村の代表作の一つだと思う。画面いっぱいに奄美の植物であるビロウやアカミズキ、ハマユウなどに囲まれた画面の中央に舞台のような三角形のスリットが生じそこにアカショウビンがスーッと飛んできてとまっている。
一村がよくやったように繁みをかき分けて海辺にたどり着いた辺りでふっと出くわしそうな一瞬。南国のパラダイスのような光景。しかし、実際には繁みの中の足元には常にハブが潜んでいる危険がある。現地の人でもためらうような繁みに一村はいつも裸足にぞうり姿で平気で入っていったという。
不喰芋と蘇鉄/1973年

最晩年の方の作品だが一見するとルソーの作品のように見えたりもする。不喰芋(くわずいも)は島で最もポピュラーな植物でいたるところで見られる。中央に力強くその不喰芋が描かれ、そして画面の左右には蘇鉄の雄花と雌花が描かれておりそれは生命のサイクルを示しているようにも思える。
「奄美の海に蘇鉄とアダン」と同じように画面の向こうには立神(たちがみ)と呼ばれる沖合の大きな岩が描かれている。それはこの島にやってくる神の道しるべと言われて島民の信仰の対象にもなっている。一村は最後に南の島の神秘的な生命のサイクルについて描きたかったのかもしれない。
白い花/1947年

これは奄美での作品ではなくかなり初期の作品なのだが、美術館の展示の中でひときわ目を引いていた。形態は二曲一隻の屏風の形をとっている。内地の展覧会青龍社展で入選している。竹林の前に繁茂し咲き乱れるヤマボウシの枝ぶりの配置も絶妙で白い花と緑葉に覆われた画面全体に若い一村のみずみずしい感性が溢れている。この年彼は号を田中米邨から柳一村に替えている。
いまだに2010年に千葉市美術館で行われた田中一村展「田中一村 新たなる全貌」を観そこなってしまったのが悔やまれる。当分彼の大規模な回顧展はないだろうけど、没後30年にあたる2027年あたりがねらい目かもしれない…が、それまでこちらの寿命の方が持つかが問題だが。
(Sept.2020)
Museum of hte Month Neue Pinakothek
Museum of the Month..
ミュンヘン

ピナコテーク(Pinakothek)とはドイツ語で絵画館のことだけれど、ミュンヘンにはルネサンス等古典的な絵画を展示するアルテ・ピナコテーク(Alte Pinakothek)と印象派など近代絵画を展示するノイエ・ピナコテーク(Neue Pinakothek)、それに現代美術を展示するピナコテーク・デア・モデルネ(Pinakothek der Moderne)の三種類の絵画館がある。
その内のノイエ・ピナコテークは残念ながら改修工事のため実に2029年まで長期間閉鎖されている。優れた収蔵作品を持つ美術館だけに残念なのだが、現在その一部だけアルテビナコテークのスペースを借りて常設展示されておりそれは観ることができる。本当に残念なのだが、そのかわり展示されているのは点数は多くはないが選りすぐりの名画ばかりという事も言える。そこに展示されている作品だけでも日本に持ってくれば立派に一つの展覧会が開けるのではないかな。
ノイエ・ピナコテーク
My Best 5+1
舟の中のアトリエで制作中のモネ(1874)

エドゥアール・マネ
マネは1871年から78年ごろまでパリっ子達が休暇を過ごすことが多いパリ北西の村アルジャントゥイユに住んでおりここで多くの作品を残している。この頃マネは小型のボートをアトリエとして使い、風景画やこのアトリエボート自体も描いている。
この絵には妻のカミーユが描かれているが彼女はこの二年後結核にかかり、さらに79年にはガンで亡くなっている。この絵はマネの幸せの残像のようにも思える。
織工(1884)

フィンセント・ファン・ゴッホ
1883年ゴッホはハーグから仕事の関係で父親が移り住んでいたニューネンの実家に戻りそこに二年ほど滞在する。そこでゴッホは近所の織工たちの家を訪れ織工たちや織機の絵を多く描いている。
この絵に描かれているのは男性の織工だが、2021年に東京都美術館で開かれた「ゴッホ展」では殆ど同じ構図で女性の織工が描かれているクレラーミュラー美術館所蔵の作品が展示されていたと思う。
この時代のゴッホは印象派ではなくバルビゾンン派の影響を強く受けており、この絵でも窓の外にはミレー風の風景が広がっているのが認めれられる。英語名での作品名はWeber in front of an open window with view the Tower of Nuenenとなっている。
耕作(1888)

ジョヴァンニ・セガンティーニ
セガンティーニの絵には筆触分割特有の濁りのない色の世界が広がっている。特にアルプスを題材にした彼の絵からは澄み切って清浄でちょっとひんやりとした空気が伝わってくる。
ぼくはセガンティーニの絵が大好きで西洋美術館の常設展に展示されている彼の作品「羊の剪毛 The Sheepshearing(1884)」の前に立つといつも暫くの間みとれてしまう。ピナコテークではあまり見ている人はいなかったが、ぼくはこの絵にくぎ付けになってしばらく離れられなかった。大きさも116x227cmと見ごたえのある大作だ。
ひまわり(1888)

フィンセント・ファン・ゴッホ
ノイエピナコテークの看板作品の一つだったゴッホの「ひまわり」も展示されていた。ゴッホは7点のひまわりを描いているが、実際に目の前のひまわりを見ながら描いたのは3点で、一点は個人臓で二点目は日本にあったが空襲で焼失、そして3点目がこのピナコテークにあるひまわりということで、三点の内現在ぼくらが実際に見られるのはこの一点のみということになる。
現在SOMPO美術館やロンドンのナショナルギャラリーなどにあるゴッホのひまわりは主にノイエピナコテークにあるこのひまわりの絵を見ながらゴッホ自身が制作したものとみられる。
マルガレーテ・ストンボロー・ヴィトゲンシュタインの肖像(1905)

グスタフ・クリムト
クリムトは映画化もされた「アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像」をはじめとしてウィーン社交界の女性の肖像画を多く描いているがこの肖像画もそういった一連の肖像画の一つだ。
彼女はウィーンの大富豪ヴィトゲンシュタイン家の娘で弟には哲学者のルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインがいる。この肖像画は有名な「エミール・フレーゲの肖像(1902)」同様クリムトが女性の肖像画に好んで使う縦長の画面に様式化された表現で描かれている。
苦悩(1912)

エゴン・シーレ
エゴン・シーレを観るなら本命はウィーンのレオポルド美術館なのだけれど、ここで彼の作品にお目にかかるとは思っていなかったので嬉しい誤算。この絵の描かれた1912年といえばシーレが14歳の少女を自宅に泊めたことで警察に逮捕されるという事件が起きた年だが、それ以外にも自宅の庭で女性を裸にして絵を描くなど村の住人といざこざが絶えなかった時期だ。
英語の題名はAgony (The Death Struggle)「苦悩、死のもがき」となっており画面には死者を看取る僧らしき人物が描かれており第一次世界大戦の足音が迫っていた時代も感じさせる。
ミュンヘン
ノイエピナコテーク

ピナコテーク(Pinakothek)とはドイツ語で絵画館のことだけれど、ミュンヘンにはルネサンス等古典的な絵画を展示するアルテ・ピナコテーク(Alte Pinakothek)と印象派など近代絵画を展示するノイエ・ピナコテーク(Neue Pinakothek)、それに現代美術を展示するピナコテーク・デア・モデルネ(Pinakothek der Moderne)の三種類の絵画館がある。
その内のノイエ・ピナコテークは残念ながら改修工事のため実に2029年まで長期間閉鎖されている。優れた収蔵作品を持つ美術館だけに残念なのだが、現在その一部だけアルテビナコテークのスペースを借りて常設展示されておりそれは観ることができる。本当に残念なのだが、そのかわり展示されているのは点数は多くはないが選りすぐりの名画ばかりという事も言える。そこに展示されている作品だけでも日本に持ってくれば立派に一つの展覧会が開けるのではないかな。
ノイエ・ピナコテーク
My Best 5+1
舟の中のアトリエで制作中のモネ(1874)

エドゥアール・マネ
マネは1871年から78年ごろまでパリっ子達が休暇を過ごすことが多いパリ北西の村アルジャントゥイユに住んでおりここで多くの作品を残している。この頃マネは小型のボートをアトリエとして使い、風景画やこのアトリエボート自体も描いている。
この絵には妻のカミーユが描かれているが彼女はこの二年後結核にかかり、さらに79年にはガンで亡くなっている。この絵はマネの幸せの残像のようにも思える。
織工(1884)

フィンセント・ファン・ゴッホ
1883年ゴッホはハーグから仕事の関係で父親が移り住んでいたニューネンの実家に戻りそこに二年ほど滞在する。そこでゴッホは近所の織工たちの家を訪れ織工たちや織機の絵を多く描いている。
この絵に描かれているのは男性の織工だが、2021年に東京都美術館で開かれた「ゴッホ展」では殆ど同じ構図で女性の織工が描かれているクレラーミュラー美術館所蔵の作品が展示されていたと思う。
この時代のゴッホは印象派ではなくバルビゾンン派の影響を強く受けており、この絵でも窓の外にはミレー風の風景が広がっているのが認めれられる。英語名での作品名はWeber in front of an open window with view the Tower of Nuenenとなっている。
耕作(1888)

ジョヴァンニ・セガンティーニ
セガンティーニの絵には筆触分割特有の濁りのない色の世界が広がっている。特にアルプスを題材にした彼の絵からは澄み切って清浄でちょっとひんやりとした空気が伝わってくる。
ぼくはセガンティーニの絵が大好きで西洋美術館の常設展に展示されている彼の作品「羊の剪毛 The Sheepshearing(1884)」の前に立つといつも暫くの間みとれてしまう。ピナコテークではあまり見ている人はいなかったが、ぼくはこの絵にくぎ付けになってしばらく離れられなかった。大きさも116x227cmと見ごたえのある大作だ。
ひまわり(1888)

フィンセント・ファン・ゴッホ
ノイエピナコテークの看板作品の一つだったゴッホの「ひまわり」も展示されていた。ゴッホは7点のひまわりを描いているが、実際に目の前のひまわりを見ながら描いたのは3点で、一点は個人臓で二点目は日本にあったが空襲で焼失、そして3点目がこのピナコテークにあるひまわりということで、三点の内現在ぼくらが実際に見られるのはこの一点のみということになる。
現在SOMPO美術館やロンドンのナショナルギャラリーなどにあるゴッホのひまわりは主にノイエピナコテークにあるこのひまわりの絵を見ながらゴッホ自身が制作したものとみられる。
マルガレーテ・ストンボロー・ヴィトゲンシュタインの肖像(1905)

グスタフ・クリムト
クリムトは映画化もされた「アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像」をはじめとしてウィーン社交界の女性の肖像画を多く描いているがこの肖像画もそういった一連の肖像画の一つだ。
彼女はウィーンの大富豪ヴィトゲンシュタイン家の娘で弟には哲学者のルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインがいる。この肖像画は有名な「エミール・フレーゲの肖像(1902)」同様クリムトが女性の肖像画に好んで使う縦長の画面に様式化された表現で描かれている。
苦悩(1912)

エゴン・シーレ
エゴン・シーレを観るなら本命はウィーンのレオポルド美術館なのだけれど、ここで彼の作品にお目にかかるとは思っていなかったので嬉しい誤算。この絵の描かれた1912年といえばシーレが14歳の少女を自宅に泊めたことで警察に逮捕されるという事件が起きた年だが、それ以外にも自宅の庭で女性を裸にして絵を描くなど村の住人といざこざが絶えなかった時期だ。
英語の題名はAgony (The Death Struggle)「苦悩、死のもがき」となっており画面には死者を看取る僧らしき人物が描かれており第一次世界大戦の足音が迫っていた時代も感じさせる。
(Nov.2024)
Museum of hte Month Alte Pinakothek
Museum of the Month...
ミュンヘン


ミュンヘンにはウィーンと同じように音楽と酒とそして美術館の楽しみが待っている。その中でもこのアルテピナコテークはウィーンの美術史美術館と同様の質の高い作品を所蔵している事でも知られている。
ウィーンがハプスブルグ家の収蔵品であるのに対しこちらミュンヘンはヴィッテルスバッハ家の収蔵品とどちらもかつて栄華を誇った貴族のコレクションだということも共通している。美術館の建物はウィーンの場合はネオ・ルネサンス様式の建物自体が素晴らしく、特に中の大理石に囲まれたカフェはぼくの大好きなスペースだ。
そこへいくとアルテピナコテークの建物はシンプルで機能的だが派手さはない。実は建物が建てられたのはウィーンが1881年なのに対しミュンヘンは1836年とこちらの方が古い。それなのにウィーンの方が歴史がありそうなのはウィーンの他の主要な建築物同様にこの美術館もいわゆるネオ・クラシック様式で建てられているからで、そこら辺は街造りの点でウィーンの戦略勝ちというところかもしれない。
アルテピナコテークの収蔵作品の中ではデューラーやクラナハ、アルトドルファーなどのドイツの画家の作品が充実しているが、他にもルーベンスのコレクションも凄いし、世界に数少ないダヴィンチの作品もある。とてもワクワクする美術館であることは確かだ。
アルテビナコテークの
自画像(1500)

A.デューラー
デューラー28歳の時に描いた自画像。当時の自画像は普通少し斜めを向いた格好のものが多いらしいのだが、この絵は真っすぐに見るものを見据えている。
見方によってはキリスト像とも見えるが若きデューラーの中にはそういう意識もあったのではないか。ここには他にも「四人の使途」を始め数点のデューラーの宗教画が収められている。
キリストの哀悼(1490)

S.ボッティチェリ
もとはフィレンツェのパオリーノ修道院にあったものを19世紀に当時のルートヴィッヒ皇太子が購入したとされる。キリストをめぐる人々が哀しみを表す荘厳な群像として描かれており彼の作品「春」等とはかなり異なった傾向がある。色彩は実に鮮やかで15世紀には描かれたとは思えないほどで図録や印刷物で観た印象とはかなり違っていた。
レーゲンスブルク近郊のヴェルト城を望むドナウ風景(1529)

A.アルトドルファー
アルトドルファーの描く大スペクタクル戦争画。画題はアレクサンダー大王のイッソスでのペルシャ軍撃退でかなり精緻な地勢図にもなっている。この絵の中には2000人以上の人間が描かれており仔細に観るとアレクサンダー大王や逃げてゆくダレイオス王の姿も認められる。
撮影が許される場合は好きな絵はできるだけデジタルカメラで撮っておくことが多いが、図録ではできない後で拡大してみるということができるのはありがたい。(添付した写真はアップする際に縮小されているのであまり拡大は出来ませんが)
カーネーションの聖母(1473)

L.ダヴィンチ
ダヴィンチは残されている作品自体が少ないのでこれも貴重な作品。聖母マリアが手に赤いカーネーションを持っているのでこう呼ばれている。
ダヴィンチ20歳代の初期の作品。赤いカーネーションはキリストの受難を示している。聖母の胸元のブローチはルーブルならびにロンドンのナショナルギャラリーにある彼の「岩窟の聖母」のものと共通しているとされている。
カニジャーニ家の聖家族(1505)

ラファエロ
聖母子に加えて、聖ヨゼフ、聖アンナそして幼い洗礼者ヨハネが三角構図の安定した画面に収められている。画面上部の天使は18世紀に塗りつぶされてしまったが、20世紀の修復で再び姿を現した。当館にはラファエロの聖母子像が何点かあって見比べてみるとダヴィンチの端正さに対してラファエロの聖母子像の温かさが際立って見える。
レウキッポスの娘たちの略奪(1618)

P.ルーベンス
当館は売りの一つにルーベンスコレクションがある。大画面に展開されるバロックの色鮮やかなスペクタクルは観ていて圧巻である。ほぼ正方形の画面に男女四人の姿がダイナミックに描かれており、女性が裸であることからこれが神話の一場面であることがわかる。

.JPG)
ミュンヘン
アルテピナコテーク


ミュンヘンにはウィーンと同じように音楽と酒とそして美術館の楽しみが待っている。その中でもこのアルテピナコテークはウィーンの美術史美術館と同様の質の高い作品を所蔵している事でも知られている。
ウィーンがハプスブルグ家の収蔵品であるのに対しこちらミュンヘンはヴィッテルスバッハ家の収蔵品とどちらもかつて栄華を誇った貴族のコレクションだということも共通している。美術館の建物はウィーンの場合はネオ・ルネサンス様式の建物自体が素晴らしく、特に中の大理石に囲まれたカフェはぼくの大好きなスペースだ。
そこへいくとアルテピナコテークの建物はシンプルで機能的だが派手さはない。実は建物が建てられたのはウィーンが1881年なのに対しミュンヘンは1836年とこちらの方が古い。それなのにウィーンの方が歴史がありそうなのはウィーンの他の主要な建築物同様にこの美術館もいわゆるネオ・クラシック様式で建てられているからで、そこら辺は街造りの点でウィーンの戦略勝ちというところかもしれない。
アルテピナコテークの収蔵作品の中ではデューラーやクラナハ、アルトドルファーなどのドイツの画家の作品が充実しているが、他にもルーベンスのコレクションも凄いし、世界に数少ないダヴィンチの作品もある。とてもワクワクする美術館であることは確かだ。
アルテビナコテークの
My Best 5+1
自画像(1500)

A.デューラー
デューラー28歳の時に描いた自画像。当時の自画像は普通少し斜めを向いた格好のものが多いらしいのだが、この絵は真っすぐに見るものを見据えている。
見方によってはキリスト像とも見えるが若きデューラーの中にはそういう意識もあったのではないか。ここには他にも「四人の使途」を始め数点のデューラーの宗教画が収められている。
キリストの哀悼(1490)

S.ボッティチェリ
もとはフィレンツェのパオリーノ修道院にあったものを19世紀に当時のルートヴィッヒ皇太子が購入したとされる。キリストをめぐる人々が哀しみを表す荘厳な群像として描かれており彼の作品「春」等とはかなり異なった傾向がある。色彩は実に鮮やかで15世紀には描かれたとは思えないほどで図録や印刷物で観た印象とはかなり違っていた。
レーゲンスブルク近郊のヴェルト城を望むドナウ風景(1529)

A.アルトドルファー
アルトドルファーの描く大スペクタクル戦争画。画題はアレクサンダー大王のイッソスでのペルシャ軍撃退でかなり精緻な地勢図にもなっている。この絵の中には2000人以上の人間が描かれており仔細に観るとアレクサンダー大王や逃げてゆくダレイオス王の姿も認められる。
撮影が許される場合は好きな絵はできるだけデジタルカメラで撮っておくことが多いが、図録ではできない後で拡大してみるということができるのはありがたい。(添付した写真はアップする際に縮小されているのであまり拡大は出来ませんが)
カーネーションの聖母(1473)

L.ダヴィンチ
ダヴィンチは残されている作品自体が少ないのでこれも貴重な作品。聖母マリアが手に赤いカーネーションを持っているのでこう呼ばれている。
ダヴィンチ20歳代の初期の作品。赤いカーネーションはキリストの受難を示している。聖母の胸元のブローチはルーブルならびにロンドンのナショナルギャラリーにある彼の「岩窟の聖母」のものと共通しているとされている。
カニジャーニ家の聖家族(1505)

ラファエロ
聖母子に加えて、聖ヨゼフ、聖アンナそして幼い洗礼者ヨハネが三角構図の安定した画面に収められている。画面上部の天使は18世紀に塗りつぶされてしまったが、20世紀の修復で再び姿を現した。当館にはラファエロの聖母子像が何点かあって見比べてみるとダヴィンチの端正さに対してラファエロの聖母子像の温かさが際立って見える。
レウキッポスの娘たちの略奪(1618)

P.ルーベンス
当館は売りの一つにルーベンスコレクションがある。大画面に展開されるバロックの色鮮やかなスペクタクルは観ていて圧巻である。ほぼ正方形の画面に男女四人の姿がダイナミックに描かれており、女性が裸であることからこれが神話の一場面であることがわかる。

(Nov.2024)
gillman*s Memories Lucia Berlin
I remember...

もともと何のきっかけで彼女の小説を読み出したのかは忘れてしまった。ルシア・ベルリン(Lucia Berlin)という名に惹かれて何人だろうと思って調べたらアメリカ人だったので、だったらベルリンじゃなくてバーリンなんじゃないかと。「ホワイトクリスマス」を作曲したアーヴィング・バーリン(Irving Berlin)はバーリンなのに…。
そんなことはどうでもいいのだけれど、それよりこの作家の生きざまが凄いのに驚いた。子供の頃は脊椎に障害があるため体育の時間は教室で待機、飛び級するほど頭は良いのに他の子とコミュニケーションがとれないで、どう話しかけて良いかも分からずいきなり「私の叔父さん、片目が義眼なの」とか「顔にウジがたかったアラスカヒグマの死体を見たことがあるよ」などと話しかけて「バ~カ」と罵られたり。
けっこう美人で、三十歳までに3度結婚、離婚。シングルマザーで4人の子供を抱えて色々な職業を転々とする。その上祖父や母や叔父同様アル中でも苦しんだ。彼女の作品がブレークしたのは死後大分たってかららしいが、晩年は(68歳没)大学で創作指導をするなどして准教授にまでなっている。
彼女は生涯に76の物語を6つの短編集で発表しているが、現在日本語で読むことのできる彼女の作品は二冊の短編集に収められたものだけ。一冊目は「掃除婦のための手引き書(A Manual for Cleaning Women)」で二冊目が今年リリースされた「すべての月、すべての年(Tode Luna,Toda Ano)」で、もともとは英語では一冊の短編集に収められていたのだけれど、日本ではまだ未知数の作家なので瀬踏みもあってか最初は半分の量で出したのかもしれない。

翻訳はどちらも岸本佐知子氏でこの翻訳がほんとに素晴らしい。彼女の名訳もあってベルリンの人気に火がついて多くのファンが生まれた。ぼくもあまり素晴らしいので元はどんな文章なのだろうとKindle英語版を買ってみたら、会話が多くしかも動詞のない短いフレーズが散りばめられており、それがリズムを作っている一因でもある。短編なのでKindleのバンドル辞書やWord Wise機能を使えばぼく程度の英語力でも何とか読み続けられる。(もちろん、既に翻訳を読んでいるからだけど…)
短編集の内容はどうやら殆どが彼女自身の体験した事実に基づいたところが多いらしい。いわば文学的な自叙伝に近いものだけれど、凡庸なぼくら常識人からするとどれもぶっ飛んだルシア・ワールドが展開される。

例えば「虎に噛まれて」という作品の中では、クリスマスに彼女の身内や大勢の親戚が集まる機会があって、そこにルシアも加わるのだが、先に来ていた従姉妹が迎えに来てくれて、こんな事を言った。
…「はじめに言っとくけど、クリスマスおめでとうってな感じの楽しい雰囲気にはとてもなりそうにないわよ。ジョン叔父が来るのはあさってだって、クリスマスの前の日よ、まったくやんなっちゃう。あんたのママのメアリとうちのママは飲みだしたと思ったらたちまち大ゲンカ。うちの ママはガレージの屋根に上がったっきり降りてこないし、あんたのママ は手首切るし」「ああ、もう」…
普通ならそのどれ一つをとっても人生に暗く影をさし立ち上がれないような出来事が、まるで小石にちょいと躓いた位の軽さで記述されて、尚且つその中になんか苦笑い的な要素まであって凄い。喧嘩した女がガレージの屋根に上って降りてこないなんて、猫じゃないんだから…。何かと言うとすぐに手首を切るママもすごいけど。
この時ルシアには小さな子供が一人いたのだけれど、彫刻家の夫はグッゲンハイムの奨励金が出たと知るや女とイタリアに逃げて住所も知らせず養育費もくれない。その直後にルシアは彼の子を妊娠していることに気づき、しかもその時、彼女はクリスマス休暇をくれないという理由で勤め先を辞めたばかり…。怒涛のように"不幸"が襲って来る。
テンポの良い短い文章の連続。鋭く本質を射抜くような観察眼に基づいた歯に衣着せぬ率直な言葉の直撃弾。それはもちろん彼女自身にも向けられている。読んでいるうちに自分の中で不幸とか幸福とか、常識とか非常識とかのグレード感覚が麻痺してくるような気がするが、不思議と暗澹たる気持ちには襲われない。それどころかその混沌の中からしぶとく「生きる」という言葉が浮かび上がってくるような不思議な気持ちにさせてくれる作品集である。

[電子書籍版](翻訳版と英語版あり)

*Kindleバンドル辞書…電子書籍リーダーのKindleには英和辞書、英独辞書など各国語辞書が無料でダウンロードできるようになっており、分からない単語があればそこを長押しすると辞書がその単語の訳を表示してくれる機能がある。またその単語をマークしておけば、読後に単語帳ができる機能もある。
*Word Wise…この機能をオンにすると例えば英語の本であれば、難しい単語にはその上にルビのように小さな字で平易な英語で意味が説明されている。その頻度もかなり難しい単語のみにするなど、調整ができるようになっているが、行が乱れたり文章が見にくくなることがあるので、ぼくは辞書の方を使っている。
Lucia Berlin
(†2004年11月12日)

もともと何のきっかけで彼女の小説を読み出したのかは忘れてしまった。ルシア・ベルリン(Lucia Berlin)という名に惹かれて何人だろうと思って調べたらアメリカ人だったので、だったらベルリンじゃなくてバーリンなんじゃないかと。「ホワイトクリスマス」を作曲したアーヴィング・バーリン(Irving Berlin)はバーリンなのに…。
そんなことはどうでもいいのだけれど、それよりこの作家の生きざまが凄いのに驚いた。子供の頃は脊椎に障害があるため体育の時間は教室で待機、飛び級するほど頭は良いのに他の子とコミュニケーションがとれないで、どう話しかけて良いかも分からずいきなり「私の叔父さん、片目が義眼なの」とか「顔にウジがたかったアラスカヒグマの死体を見たことがあるよ」などと話しかけて「バ~カ」と罵られたり。
けっこう美人で、三十歳までに3度結婚、離婚。シングルマザーで4人の子供を抱えて色々な職業を転々とする。その上祖父や母や叔父同様アル中でも苦しんだ。彼女の作品がブレークしたのは死後大分たってかららしいが、晩年は(68歳没)大学で創作指導をするなどして准教授にまでなっている。
彼女は生涯に76の物語を6つの短編集で発表しているが、現在日本語で読むことのできる彼女の作品は二冊の短編集に収められたものだけ。一冊目は「掃除婦のための手引き書(A Manual for Cleaning Women)」で二冊目が今年リリースされた「すべての月、すべての年(Tode Luna,Toda Ano)」で、もともとは英語では一冊の短編集に収められていたのだけれど、日本ではまだ未知数の作家なので瀬踏みもあってか最初は半分の量で出したのかもしれない。

翻訳はどちらも岸本佐知子氏でこの翻訳がほんとに素晴らしい。彼女の名訳もあってベルリンの人気に火がついて多くのファンが生まれた。ぼくもあまり素晴らしいので元はどんな文章なのだろうとKindle英語版を買ってみたら、会話が多くしかも動詞のない短いフレーズが散りばめられており、それがリズムを作っている一因でもある。短編なのでKindleのバンドル辞書やWord Wise機能を使えばぼく程度の英語力でも何とか読み続けられる。(もちろん、既に翻訳を読んでいるからだけど…)
短編集の内容はどうやら殆どが彼女自身の体験した事実に基づいたところが多いらしい。いわば文学的な自叙伝に近いものだけれど、凡庸なぼくら常識人からするとどれもぶっ飛んだルシア・ワールドが展開される。

例えば「虎に噛まれて」という作品の中では、クリスマスに彼女の身内や大勢の親戚が集まる機会があって、そこにルシアも加わるのだが、先に来ていた従姉妹が迎えに来てくれて、こんな事を言った。
…「はじめに言っとくけど、クリスマスおめでとうってな感じの楽しい雰囲気にはとてもなりそうにないわよ。ジョン叔父が来るのはあさってだって、クリスマスの前の日よ、まったくやんなっちゃう。あんたのママのメアリとうちのママは飲みだしたと思ったらたちまち大ゲンカ。うちの ママはガレージの屋根に上がったっきり降りてこないし、あんたのママ は手首切るし」「ああ、もう」…
普通ならそのどれ一つをとっても人生に暗く影をさし立ち上がれないような出来事が、まるで小石にちょいと躓いた位の軽さで記述されて、尚且つその中になんか苦笑い的な要素まであって凄い。喧嘩した女がガレージの屋根に上って降りてこないなんて、猫じゃないんだから…。何かと言うとすぐに手首を切るママもすごいけど。
この時ルシアには小さな子供が一人いたのだけれど、彫刻家の夫はグッゲンハイムの奨励金が出たと知るや女とイタリアに逃げて住所も知らせず養育費もくれない。その直後にルシアは彼の子を妊娠していることに気づき、しかもその時、彼女はクリスマス休暇をくれないという理由で勤め先を辞めたばかり…。怒涛のように"不幸"が襲って来る。
テンポの良い短い文章の連続。鋭く本質を射抜くような観察眼に基づいた歯に衣着せぬ率直な言葉の直撃弾。それはもちろん彼女自身にも向けられている。読んでいるうちに自分の中で不幸とか幸福とか、常識とか非常識とかのグレード感覚が麻痺してくるような気がするが、不思議と暗澹たる気持ちには襲われない。それどころかその混沌の中からしぶとく「生きる」という言葉が浮かび上がってくるような不思議な気持ちにさせてくれる作品集である。

[電子書籍版](翻訳版と英語版あり)

*Kindleバンドル辞書…電子書籍リーダーのKindleには英和辞書、英独辞書など各国語辞書が無料でダウンロードできるようになっており、分からない単語があればそこを長押しすると辞書がその単語の訳を表示してくれる機能がある。またその単語をマークしておけば、読後に単語帳ができる機能もある。
*Word Wise…この機能をオンにすると例えば英語の本であれば、難しい単語にはその上にルビのように小さな字で平易な英語で意味が説明されている。その頻度もかなり難しい単語のみにするなど、調整ができるようになっているが、行が乱れたり文章が見にくくなることがあるので、ぼくは辞書の方を使っている。
(Nov.2022)
gillman*s Gellery On the Hill シルエットの頃
gillman*s gallery...
At the Park
境界、境目というものは独特の雰囲気を持っている。国の境目とか、季節の境目とか時代の境目とか、少年時代と大人の境目とか…。どこか不安定でそれでいて何かドラマチック。
一日の昼と夜の境目もそんな危うさと妖しさと美しさを持っている。昼の光が力を失いシルエットへと映り込んだ世界。それもまた美しい。
語らい



丘に夕暮れが迫るころ、段々と空気の色が変わりそのうち色の世界から輪郭だけをのこしたシルエットの世界が訪れる。夜という別の世界への入り口。
スカイラインに立つ

微妙な光を受けてシルエットになるのは人影だけじゃない。陽が傾き始めた頃、遠くの山々や街並みのスカイラインがくっきりとシルエットになる時がある。まるで舞台の書き割りの背景のようにドラマチックだ。
未知との遭遇


夕暮れが迫る頃、丘の上で数人の人が空を指さして見上げている。ぼくの方からは声も聞こえないし、見上げても彼らが何を指しているのかわからない。一瞬、映画「未知との遭遇」のワンシーンを思い浮かべた。
ザ・キング・オブ・シルエット


天気の良い日にはこの丘から富士山、筑波山、東京スカイツリーそして遥か彼方に新宿の高層ビル群が見渡せる。その中でも夕焼け空をバックにした富士山のシルエットは圧巻だ。ぼくの子供の頃は東京の至る所から富士山を望むことができたのだけれど、今では貴重な眺めだ。
自動点灯


自分の家の門灯もそうだけど、公園の街灯も薄暗くなると自動的に点く自動点灯になっている。点き始める時間は季節や天候によっても違うけれど、冬の曇天だと四時過ぎにはちらほらと点き始める。人工的な灯点し頃だけれども、頃合いを見計らって街灯がポッ、ポッとあちこちで点き始める光景は好きな瞬間だ。
月はいたかい?

一年を通して公園を散歩していると、林の木々の隙間や雲の間などに月があるのを見つけて、こんな時間にこんな処に…、と思うことがよくある。昼間の月は実に神出鬼没だ。
At the Park
On the Hill
~シルエットの頃~
境界、境目というものは独特の雰囲気を持っている。国の境目とか、季節の境目とか時代の境目とか、少年時代と大人の境目とか…。どこか不安定でそれでいて何かドラマチック。
一日の昼と夜の境目もそんな危うさと妖しさと美しさを持っている。昼の光が力を失いシルエットへと映り込んだ世界。それもまた美しい。
語らい
丘に夕暮れが迫るころ、段々と空気の色が変わりそのうち色の世界から輪郭だけをのこしたシルエットの世界が訪れる。夜という別の世界への入り口。
スカイラインに立つ
微妙な光を受けてシルエットになるのは人影だけじゃない。陽が傾き始めた頃、遠くの山々や街並みのスカイラインがくっきりとシルエットになる時がある。まるで舞台の書き割りの背景のようにドラマチックだ。
未知との遭遇
夕暮れが迫る頃、丘の上で数人の人が空を指さして見上げている。ぼくの方からは声も聞こえないし、見上げても彼らが何を指しているのかわからない。一瞬、映画「未知との遭遇」のワンシーンを思い浮かべた。
ザ・キング・オブ・シルエット
天気の良い日にはこの丘から富士山、筑波山、東京スカイツリーそして遥か彼方に新宿の高層ビル群が見渡せる。その中でも夕焼け空をバックにした富士山のシルエットは圧巻だ。ぼくの子供の頃は東京の至る所から富士山を望むことができたのだけれど、今では貴重な眺めだ。
自動点灯

自分の家の門灯もそうだけど、公園の街灯も薄暗くなると自動的に点く自動点灯になっている。点き始める時間は季節や天候によっても違うけれど、冬の曇天だと四時過ぎにはちらほらと点き始める。人工的な灯点し頃だけれども、頃合いを見計らって街灯がポッ、ポッとあちこちで点き始める光景は好きな瞬間だ。
月はいたかい?

一年を通して公園を散歩していると、林の木々の隙間や雲の間などに月があるのを見つけて、こんな時間にこんな処に…、と思うことがよくある。昼間の月は実に神出鬼没だ。
(rev.Aug.2024)
gillman*s Choice Der Witz der Woche
Der Witz der Woche
今週のドイツ・ジョーク
Police「生年月日は?」
Driver「7月3日よ」
P「何年の?」
D「毎年よ!」
日本語でも生年月日と誕生日は使い分けていると思うけど、ドイツ語でもGeburtsdatum(Date of Birth)とGeturtstag(Birthday)は使い分けていて普通はGeburtsdatumといえば生年月日だから何年生まれという情報が入ってくるんだけど、女性は生年を言いたくないのでわざと誕生日を言ったというところ。この答えは絶妙。
女性に生年を聞かないのは万国共通になっている感じがあるが、留学生と付き合っていると、年長者を尊ぶ儒教思想の盛んだった韓国では人間関係を円滑にするためにも相手の年齢を知る必要があるため比較的気軽に女性の年齢も聞いていた感じだけれど段々変わってきたかもしれない。
(AUg.2024)
gillman*s Choice Ernst Haas
gillman*s Choice...
New York in Color
1952-1962
Ernst Haas

カメラ雑誌の「アサヒカメラ」が事実上の廃刊になって大分時が経った。ぼくは同誌に毎月載っている写真家の少しまとまった作品群を楽しみにしていて、いわば月刊の写真集のように思っていた。本当は写真集を買うのが良いのだけれど、それは結構高いので年1冊か2冊位しか買えない。それがなくなってしまったのでとても寂しい。季刊でもいいから出してほしいなぁ。
で、今年の購入写真集はErnst Haas (エルンスト・ハース)の写真集「New York in Color1952-1962」だ。ハースはウィーン生まれでその後パリ、アメリカで活躍した写真家で初期カラーの時代を経てカラー写真のパイオニアの一人だと思う。彼の写真集では1971年に出版された「The Creation天地創造」が有名で雄大なネイチャーフォトなのだけれどそれは中古でも結構高いので…。でも、今回の写真集もそれに劣らず素晴らしい。

タイトルのNew York in Color 1952-1962でもわかるようにその時代のニューヨークを撮ったストリート写真集だ。ぼくも持っているソール・ライターの写真集「Early Color」が1948年-1960年なので被っている時代もある。一方Vivian Maiyerの「The Color Work」はもうちょっと時代の幅が広く1950年代の後半から1970年代まで広がっているが、それぞれが時代の色を持っているような気がする。
ハースは戦争で荒廃したヨーロッパから1951年にニューヨークに移り住んだ。彼の眼の底に焼き付いた灰色のヨーロッパから色に満ちたニューヨークにワープした彼にとって、カラー表現は必然的だったのかもしれない。その彼の目に輝いていたニューヨークの光景はコダクロームを通じて今のぼくらには懐かしさをおびた光として蘇ってくる。


ぼくの好きな写真集
New York in Color
1952-1962
Ernst Haas

カメラ雑誌の「アサヒカメラ」が事実上の廃刊になって大分時が経った。ぼくは同誌に毎月載っている写真家の少しまとまった作品群を楽しみにしていて、いわば月刊の写真集のように思っていた。本当は写真集を買うのが良いのだけれど、それは結構高いので年1冊か2冊位しか買えない。それがなくなってしまったのでとても寂しい。季刊でもいいから出してほしいなぁ。
で、今年の購入写真集はErnst Haas (エルンスト・ハース)の写真集「New York in Color1952-1962」だ。ハースはウィーン生まれでその後パリ、アメリカで活躍した写真家で初期カラーの時代を経てカラー写真のパイオニアの一人だと思う。彼の写真集では1971年に出版された「The Creation天地創造」が有名で雄大なネイチャーフォトなのだけれどそれは中古でも結構高いので…。でも、今回の写真集もそれに劣らず素晴らしい。
タイトルのNew York in Color 1952-1962でもわかるようにその時代のニューヨークを撮ったストリート写真集だ。ぼくも持っているソール・ライターの写真集「Early Color」が1948年-1960年なので被っている時代もある。一方Vivian Maiyerの「The Color Work」はもうちょっと時代の幅が広く1950年代の後半から1970年代まで広がっているが、それぞれが時代の色を持っているような気がする。
ハースは戦争で荒廃したヨーロッパから1951年にニューヨークに移り住んだ。彼の眼の底に焼き付いた灰色のヨーロッパから色に満ちたニューヨークにワープした彼にとって、カラー表現は必然的だったのかもしれない。その彼の目に輝いていたニューヨークの光景はコダクロームを通じて今のぼくらには懐かしさをおびた光として蘇ってくる。
(Jul.2024)
gillman*s Choice Der Witz der Woche
Der Witz der Woche
今週のドイツ・ジョーク
妻「ねぇ、ダーリン。もしも、誰かがあたしとお義母さんを誘拐したら、あなたは誰の事を一番心配するのかしら?」
夫「誘拐したヤツだね」
どこの国のジョークでもよくあるスタイル。ドイツも核家族だから姑と同居というのは少ないと思うけど、それでも女性の「あたしと〇〇とどっちが大事なのよ」という天秤思考は健在なのかも。
〇〇には仕事や子供や趣味やどこかの女性など色々なものが入りえるけれど、お義母さんもその候補の一つ。亭主はもしかしたら同じようなことを母親にも言われているのかも…。誘拐犯は二人の女性にやいのやいの責められて…可哀そうに。亭主の答えに何となくそんな匂いが。
つづく…
gillaman*s Gellery. At the Park/On the Hill
gillman*s gallery...
At the Park
公園の丘の上は360度の視界。街並みを見下ろすのも良いけど、遮るもののない空を見上げて忘れていた空の広さ、刻々と変化するその表情に魅せられる楽しさに浸るのもいい。
雲に向かって

公園の丘の最大の魅力は何と言っても見渡す限りの大空。空と言う自由なキャンバスに雲と言う絵具を使って描かれた壮大な空模様はいつまで見ていても飽きることがない。
白い太陽

雲の向こうからこちらをじっと見つめているような冬の白い太陽が好きだ。他の季節では眩しくて見ることができない太陽の存在が、雲の向こうから優しく語りかけてくる。
大空を駆ける

大空をバックに晩夏の丘をひたすら駆ける。気持ちいいんだろうなぁ。羨んでいても仕方ない。今はまずそこまでたどり着くことだ。
夢の中の空

よく空の夢を見る。空一面に雲が広がっていて青い空が少し顔をのぞかせている。少し風が吹いてきてパラソルを微かに揺らす。この先荒れ模様になるのではと夢の中で心配している。
空の蓋

いつもは丘の上の空には蓋がないけれど、真冬のどんよりとした昼間、まるで空に蓋がされたように雲が低く覆いかぶさってくる日がある。まぁ、それはそれでまた趣かあるんだけれども…。
Tokyo Blue Sky

雲は大空の彩だけれど、雲一つない真冬の東京の青空も好きだ。変化もなくて単調な気もするが見ていると吸い込まれそうになるこのTokyo Blue Skyが好きだ。
At the Park
On the Hill
~空よ、雲よ~
公園の丘の上は360度の視界。街並みを見下ろすのも良いけど、遮るもののない空を見上げて忘れていた空の広さ、刻々と変化するその表情に魅せられる楽しさに浸るのもいい。
雲に向かって
公園の丘の最大の魅力は何と言っても見渡す限りの大空。空と言う自由なキャンバスに雲と言う絵具を使って描かれた壮大な空模様はいつまで見ていても飽きることがない。
白い太陽

雲の向こうからこちらをじっと見つめているような冬の白い太陽が好きだ。他の季節では眩しくて見ることができない太陽の存在が、雲の向こうから優しく語りかけてくる。
大空を駆ける

大空をバックに晩夏の丘をひたすら駆ける。気持ちいいんだろうなぁ。羨んでいても仕方ない。今はまずそこまでたどり着くことだ。
夢の中の空

よく空の夢を見る。空一面に雲が広がっていて青い空が少し顔をのぞかせている。少し風が吹いてきてパラソルを微かに揺らす。この先荒れ模様になるのではと夢の中で心配している。
空の蓋
いつもは丘の上の空には蓋がないけれど、真冬のどんよりとした昼間、まるで空に蓋がされたように雲が低く覆いかぶさってくる日がある。まぁ、それはそれでまた趣かあるんだけれども…。
Tokyo Blue Sky
雲は大空の彩だけれど、雲一つない真冬の東京の青空も好きだ。変化もなくて単調な気もするが見ていると吸い込まれそうになるこのTokyo Blue Skyが好きだ。
(Apr.2024)
gillman*s Gallery At the Park/On the Hill
gillman*s gallery...
At the Park
お天気の良い日には家の前を保母さんに連れられた保育園の子供たちが賑やかに通りすぎてゆく。
みんなで手をつないで歩いたり、時には数人が乗れる小さなトロッコのような手押し車に載せられて。
園児たちは公園の広い芝生の野原につくと先生の一声で解き放たれて勢いよくあちこちに散らばってゆく。まるで牧草地に一斉に解き放たれは子羊たちのように。
Green Angels

良く晴れた日の午前中、公園の丘にはかわいい天使たちが姿をみせる。一列になって街を見晴らす。このまま飛んで行ってしまうのかと…。
Blue Angels

がらにもなく時々平和って何だろうか、なんて小難しい事を考えることもないでは無いけど、そんな時にもぼくにはこういう光景しか頭に浮かんでこないんだ。
じじばば固まる、子供は動く

寒さの盛り吹きさらしの丘の上は結構寒い。孫連れて散歩に来たらしいじじばばは寒さに固まるけれど子供は元気に動きまわる。
どこでも遊園地

子供にとってはどこでもが遊園地だ。ジェットコースターやシンデレラ城がなくても天使たちが降り立ったところが遊園地になる。
アンドリュー・ワイエスの言葉 「…このひとつの丘が私にとっては何千の丘と同じ意味を持つ。このひとつの対象の中に私は世界を見出す」また「…題材を変えることは私にとってそれほど重要なことではない。なぜなら、ひとつの題材からいつも新しい発見があるからだ」(「アンドリュー・ワイエス 創造への道程」/Bunkamura) この身近な公園の丘がぼくにとって生涯そういう丘であり続けることを願って…。
At the Park
On the Hill
~丘の上の天使たち~
お天気の良い日には家の前を保母さんに連れられた保育園の子供たちが賑やかに通りすぎてゆく。
みんなで手をつないで歩いたり、時には数人が乗れる小さなトロッコのような手押し車に載せられて。
園児たちは公園の広い芝生の野原につくと先生の一声で解き放たれて勢いよくあちこちに散らばってゆく。まるで牧草地に一斉に解き放たれは子羊たちのように。
Green Angels

良く晴れた日の午前中、公園の丘にはかわいい天使たちが姿をみせる。一列になって街を見晴らす。このまま飛んで行ってしまうのかと…。
Blue Angels
がらにもなく時々平和って何だろうか、なんて小難しい事を考えることもないでは無いけど、そんな時にもぼくにはこういう光景しか頭に浮かんでこないんだ。
じじばば固まる、子供は動く
寒さの盛り吹きさらしの丘の上は結構寒い。孫連れて散歩に来たらしいじじばばは寒さに固まるけれど子供は元気に動きまわる。
どこでも遊園地

子供にとってはどこでもが遊園地だ。ジェットコースターやシンデレラ城がなくても天使たちが降り立ったところが遊園地になる。
アンドリュー・ワイエスの言葉 「…このひとつの丘が私にとっては何千の丘と同じ意味を持つ。このひとつの対象の中に私は世界を見出す」また「…題材を変えることは私にとってそれほど重要なことではない。なぜなら、ひとつの題材からいつも新しい発見があるからだ」(「アンドリュー・ワイエス 創造への道程」/Bunkamura) この身近な公園の丘がぼくにとって生涯そういう丘であり続けることを願って…。
(Mar.2024)
gillman*s Gallery At the Park/On the Hill
gillman*s gallery...
At the Park
丘の上の広々とした世界はそこを訪れる人の心も晴れやかにするようだ。踊りたい気持ちの表し方は人それぞれ…。
鼻歌ダンス


若いってだけで、それだけで楽しいって時代あったなぁ。ここは何だか青春広場みたいな…。そんな気持ちすっかり忘れていたなぁ。
身体も踊る、心も踊る


広々とした丘の上はホッとするけど、若者はそれだけじゃ済まないらしく鼻歌まじりに踊り出した。彼女たちにはここは街を見下ろす格好のステージなんだ。見ているぼくまでなんだか楽しくなる。でも、じいさまも踊りたいけど、今じゃスキップさえムリ。
最初は鼻歌を交えた軽いノリのダンスだったけど、次第に動きの激しいくるくるダンスに。なんだかコロナで溜まりに溜まったうっぷんを晴らすように…。ストレスとんでけ、コロナといっしょに。
やったぁ~

皆で自転車でやってきた中高生らしい男女のグループ。一人の男の子が大きくジャンプするのをみんなで写メしている。何か良いことあったのかな。目立ちたい年頃。
日暮れサーカス

一本のレールが続いている丘のフェンスは格好の遊び道具になっている。みんなその上を綱渡りのように歩く衝動にかられるらしい。日も傾き始めたころ二人の男の子が飽かずにその綱渡りにチャレンジしている。が、中々先に行かない。日暮れサーカスの綱渡りダンス。
*子供の頃夏休みになると夏祭りで西新井大師の境内にやってくるサーカスを観るのが楽しかった。やってくるのは木下大サーカスかキグレサーカスのどちらか。親に手を引かれてサーカスの巨大なテントを見上げるとその向こうに真っ青な夜空が広がっていたのをうっすらと覚えている。キグレサーカスは残念ながら2010に廃業しているが、「日暮れサーカス」はこのキグレサーカスのもじり。
アンドリュー・ワイエスの言葉 「…このひとつの丘が私にとっては何千の丘と同じ意味を持つ。このひとつの対象の中に私は世界を見出す」また「…題材を変えることは私にとってそれほど重要なことではない。なぜなら、ひとつの題材からいつも新しい発見があるからだ」(「アンドリュー・ワイエス 創造への道程」/Bunkamura) この身近な公園の丘がぼくにとって生涯そういう丘であり続けることを願って…。
At the Park
On the Hill
~踊りたい気持ち~
丘の上の広々とした世界はそこを訪れる人の心も晴れやかにするようだ。踊りたい気持ちの表し方は人それぞれ…。
鼻歌ダンス

若いってだけで、それだけで楽しいって時代あったなぁ。ここは何だか青春広場みたいな…。そんな気持ちすっかり忘れていたなぁ。
身体も踊る、心も踊る

広々とした丘の上はホッとするけど、若者はそれだけじゃ済まないらしく鼻歌まじりに踊り出した。彼女たちにはここは街を見下ろす格好のステージなんだ。見ているぼくまでなんだか楽しくなる。でも、じいさまも踊りたいけど、今じゃスキップさえムリ。
最初は鼻歌を交えた軽いノリのダンスだったけど、次第に動きの激しいくるくるダンスに。なんだかコロナで溜まりに溜まったうっぷんを晴らすように…。ストレスとんでけ、コロナといっしょに。
やったぁ~

皆で自転車でやってきた中高生らしい男女のグループ。一人の男の子が大きくジャンプするのをみんなで写メしている。何か良いことあったのかな。目立ちたい年頃。
日暮れサーカス

一本のレールが続いている丘のフェンスは格好の遊び道具になっている。みんなその上を綱渡りのように歩く衝動にかられるらしい。日も傾き始めたころ二人の男の子が飽かずにその綱渡りにチャレンジしている。が、中々先に行かない。日暮れサーカスの綱渡りダンス。
*子供の頃夏休みになると夏祭りで西新井大師の境内にやってくるサーカスを観るのが楽しかった。やってくるのは木下大サーカスかキグレサーカスのどちらか。親に手を引かれてサーカスの巨大なテントを見上げるとその向こうに真っ青な夜空が広がっていたのをうっすらと覚えている。キグレサーカスは残念ながら2010に廃業しているが、「日暮れサーカス」はこのキグレサーカスのもじり。
アンドリュー・ワイエスの言葉 「…このひとつの丘が私にとっては何千の丘と同じ意味を持つ。このひとつの対象の中に私は世界を見出す」また「…題材を変えることは私にとってそれほど重要なことではない。なぜなら、ひとつの題材からいつも新しい発見があるからだ」(「アンドリュー・ワイエス 創造への道程」/Bunkamura) この身近な公園の丘がぼくにとって生涯そういう丘であり続けることを願って…。
(Feb.2024)
gillman*s Choice 名画の背中
■gillman*s choice

「父の背中を見て育つ」など日本人には昔から後ろ姿への独特の思い入れのようなものがあると思っている。それは寡黙なことが良いとされた日本的風土の中で相手の心を言葉以外のものでも読み解こうとする伝統のようなものがあったのかもしれない。
西洋絵画においては肖像画は宗教画と並んで早くから発達していたけれど、それは誰が描かれたかわかることが大事で、ステイタス等をあらわすものであったということもあるが古典の中にはごく例外的なものを除いては人物の後ろ姿が描かれるというのはそう頻繁にあることではなかったようだ。
しかし世紀末あたりから絵画にも心理的側面の絵画への反映やモチーフの自由度が高まることによって後ろ姿にその作家なりの思入れを込めた作品も出始めてきたように思う。同じ後ろ姿を描くにもその意図するところは必ずしも同じではないようだ。人の背中は時に顔の表情に劣らず多くの事を語ってくれる。また時として顔の表情は人を欺くが、背中は正直である。ぼくもいつか東京の街なかで見かける「都会の背中」を撮って歩きたいと思っている。
背中は語る [My Best 5+1]
①ピアノを弾く妻イーダのいる室内(1910)/ヴィルヘルム・ハンマースホイ…
西洋美術館での「ハンマースホイ展」の図録やドイツのPrestel 社の画集「Hammershoi und Europa 」で確認できるだけでもハンマースホイは20点近くの妻を始めとする女性の室内での後ろ姿の絵を描いている。彼はコペンハーゲンの自宅内を多く描いているが、現在国立西洋美術館に展示されている彼の作品「ピアノを弾く妻イーダのいる室内」もそのような絵の一枚だ。
白い扉の向こうで妻のイーダがピアノを弾いている後ろ姿。しかし、イーダはピアノの前には座っているけれど本当にピアノを弾いているようには見えない。画面を静寂が支配していてぼくにはピアノの音は聞こえてこない。言わば静謐だがどこか不安な空気が画面を覆っている。国立西洋美術館は2008年のハンマースホイ展の直前にこの絵を購入したと思われる。今では西洋美術館の目玉作品の一つだ。

②クリスチーナの世界(1948)/アンドリュー・ワイエス…ワイエスの代表作ともいえる作品。クリスチーナはワイエスが長年描き続けたオルソン家の女主人だが、脚が不自由なため車椅子か這って移動しなればならない。そのクリスチーナがはるか遠くの自宅を目指して草原をゆく後姿を描いている。
この秋丸沼芸術の森で開かれたワイエス展でこの絵の初期スケッチを観て分かったのだが、ワイエスは最初正面から彼女を描くつもりだったようだ。絵の発端はある日ワイエスがオルソン家の二階から牧場の方を見ていたら、遥か彼方からクリスチーナが草原を這っている姿が見えた。その崇高ともいえる光景をワイエスは結局クリスチーナの側から遥か彼方の家を見上げるという構図に切り替えた。それにより絵を観る者もクリスチーナと同じ目線になり、彼女の背中が多くのことを語り始める。

③雲海のうえの旅人(1818)/カスパー・ダーフィド・フリードリヒ…フリードリヒの絵は自然への畏怖、畏敬を表すものが多いが、中でも大自然を前に立ち尽くす人物の絵が目につくけれどその場合大抵その人物はこちら側に背中を向けて立っている。
この絵も山上の雲海を前にして一人の男が立っている。フリードリヒは絵の中の人物を背後から描くことによって絵を観る者が画中の人物の視線を通じて大自然に対峙している状況を作り出しているのだと思う。つまり、画中の人物の視線と感慨を今の言葉でいえば鑑賞者と「同期」させようとしているのだと思う。

④赤毛の女[身づくろい](1896)/トゥールーズ・ロートレック…この絵は厚紙に油彩で描かれているため一見パステルのように見える。原題はLa Toiletteでここは娼館だろうか画面の左奥にバスタブが見える。客の来る前に湯あみして着衣する前のひととき。虚脱したような、物思うような複雑な背中の表情。彼女たちからの信頼篤い、そして速描きが得意なロートレックならではの作品だと思う。
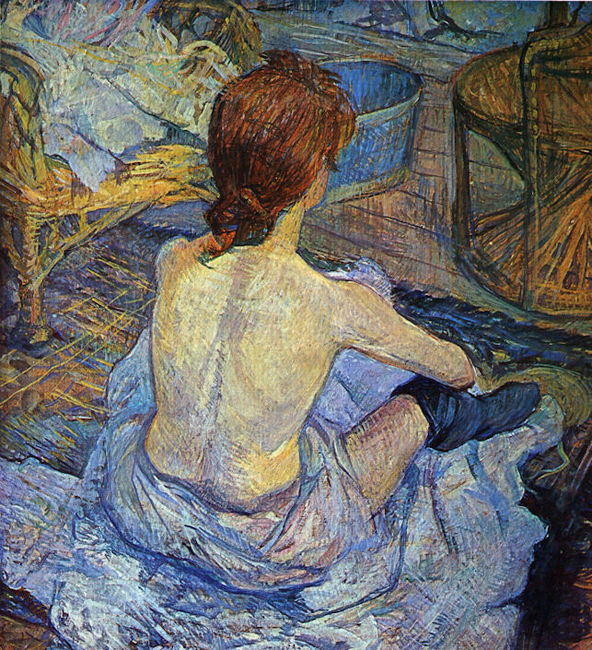
⑤夕食、ランプの光(1899)/フェリックス・ヴァロットン…ヴァロットンは代表作の「ボール」を始め不思議な雰囲気の絵が多いのだけれど、この絵もなんとも不思議な感覚の絵だ。ヴァロットンは裕福な画商の娘と結婚したが、その雰囲気にも妻の連れ子たちとも馴染めなかったようだ。この絵は妻と二人の連れ子との食卓を描いていると思うのだけど、シルエットになっているヴァロットンの背中がいかにも家庭の中にあって浮いているような、孤独な感じが伝わってくる。

⑤あやめの衣/岡田三郎助(1927)…この絵はつい最近ポーラ美術館で観たばかり。第一印象は端正で綺麗という感じで、油彩でありながら「和」の感触が伝わってい来るのは単にアヤメ柄の和服を着ているということだけでなく、女性の背中自体から滲み出てくるもののように思う。その美しい「うなじ」や恐らく恥ずかしさのためか耳がほんのりと赤くなっている佇まいからもそれが伝わってくる。

上記以外にも
・ドガ/背中をふく女
・ムンク/海辺に立つ娘_孤独なる者
・アングル/ヴァルパンソンの浴女
など多くの画家が後ろ姿を描いている。美術館でまたどんな新たな「後ろ姿」に出会えるか、楽しみではある。
背中は語る
~後ろ姿の名画~
「父の背中を見て育つ」など日本人には昔から後ろ姿への独特の思い入れのようなものがあると思っている。それは寡黙なことが良いとされた日本的風土の中で相手の心を言葉以外のものでも読み解こうとする伝統のようなものがあったのかもしれない。
西洋絵画においては肖像画は宗教画と並んで早くから発達していたけれど、それは誰が描かれたかわかることが大事で、ステイタス等をあらわすものであったということもあるが古典の中にはごく例外的なものを除いては人物の後ろ姿が描かれるというのはそう頻繁にあることではなかったようだ。
しかし世紀末あたりから絵画にも心理的側面の絵画への反映やモチーフの自由度が高まることによって後ろ姿にその作家なりの思入れを込めた作品も出始めてきたように思う。同じ後ろ姿を描くにもその意図するところは必ずしも同じではないようだ。人の背中は時に顔の表情に劣らず多くの事を語ってくれる。また時として顔の表情は人を欺くが、背中は正直である。ぼくもいつか東京の街なかで見かける「都会の背中」を撮って歩きたいと思っている。
背中は語る [My Best 5+1]
①ピアノを弾く妻イーダのいる室内(1910)/ヴィルヘルム・ハンマースホイ…
西洋美術館での「ハンマースホイ展」の図録やドイツのPrestel 社の画集「Hammershoi und Europa 」で確認できるだけでもハンマースホイは20点近くの妻を始めとする女性の室内での後ろ姿の絵を描いている。彼はコペンハーゲンの自宅内を多く描いているが、現在国立西洋美術館に展示されている彼の作品「ピアノを弾く妻イーダのいる室内」もそのような絵の一枚だ。
白い扉の向こうで妻のイーダがピアノを弾いている後ろ姿。しかし、イーダはピアノの前には座っているけれど本当にピアノを弾いているようには見えない。画面を静寂が支配していてぼくにはピアノの音は聞こえてこない。言わば静謐だがどこか不安な空気が画面を覆っている。国立西洋美術館は2008年のハンマースホイ展の直前にこの絵を購入したと思われる。今では西洋美術館の目玉作品の一つだ。

②クリスチーナの世界(1948)/アンドリュー・ワイエス…ワイエスの代表作ともいえる作品。クリスチーナはワイエスが長年描き続けたオルソン家の女主人だが、脚が不自由なため車椅子か這って移動しなればならない。そのクリスチーナがはるか遠くの自宅を目指して草原をゆく後姿を描いている。
この秋丸沼芸術の森で開かれたワイエス展でこの絵の初期スケッチを観て分かったのだが、ワイエスは最初正面から彼女を描くつもりだったようだ。絵の発端はある日ワイエスがオルソン家の二階から牧場の方を見ていたら、遥か彼方からクリスチーナが草原を這っている姿が見えた。その崇高ともいえる光景をワイエスは結局クリスチーナの側から遥か彼方の家を見上げるという構図に切り替えた。それにより絵を観る者もクリスチーナと同じ目線になり、彼女の背中が多くのことを語り始める。

③雲海のうえの旅人(1818)/カスパー・ダーフィド・フリードリヒ…フリードリヒの絵は自然への畏怖、畏敬を表すものが多いが、中でも大自然を前に立ち尽くす人物の絵が目につくけれどその場合大抵その人物はこちら側に背中を向けて立っている。
この絵も山上の雲海を前にして一人の男が立っている。フリードリヒは絵の中の人物を背後から描くことによって絵を観る者が画中の人物の視線を通じて大自然に対峙している状況を作り出しているのだと思う。つまり、画中の人物の視線と感慨を今の言葉でいえば鑑賞者と「同期」させようとしているのだと思う。

④赤毛の女[身づくろい](1896)/トゥールーズ・ロートレック…この絵は厚紙に油彩で描かれているため一見パステルのように見える。原題はLa Toiletteでここは娼館だろうか画面の左奥にバスタブが見える。客の来る前に湯あみして着衣する前のひととき。虚脱したような、物思うような複雑な背中の表情。彼女たちからの信頼篤い、そして速描きが得意なロートレックならではの作品だと思う。
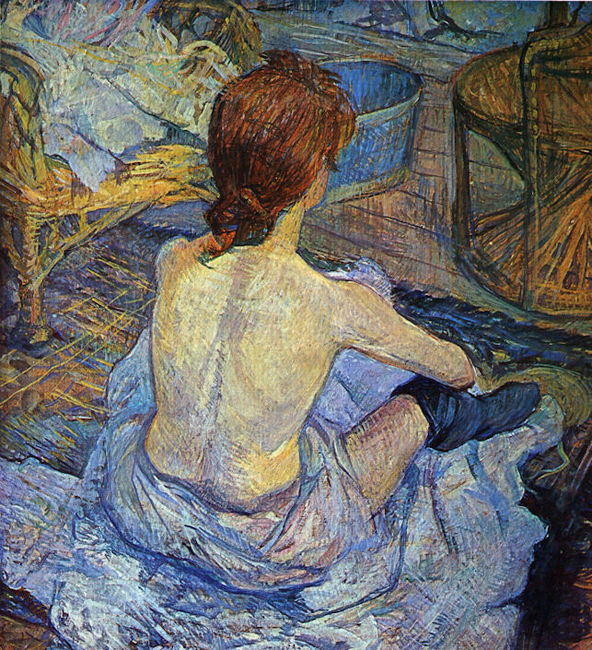
⑤夕食、ランプの光(1899)/フェリックス・ヴァロットン…ヴァロットンは代表作の「ボール」を始め不思議な雰囲気の絵が多いのだけれど、この絵もなんとも不思議な感覚の絵だ。ヴァロットンは裕福な画商の娘と結婚したが、その雰囲気にも妻の連れ子たちとも馴染めなかったようだ。この絵は妻と二人の連れ子との食卓を描いていると思うのだけど、シルエットになっているヴァロットンの背中がいかにも家庭の中にあって浮いているような、孤独な感じが伝わってくる。

⑤あやめの衣/岡田三郎助(1927)…この絵はつい最近ポーラ美術館で観たばかり。第一印象は端正で綺麗という感じで、油彩でありながら「和」の感触が伝わってい来るのは単にアヤメ柄の和服を着ているということだけでなく、女性の背中自体から滲み出てくるもののように思う。その美しい「うなじ」や恐らく恥ずかしさのためか耳がほんのりと赤くなっている佇まいからもそれが伝わってくる。

上記以外にも
・ドガ/背中をふく女
・ムンク/海辺に立つ娘_孤独なる者
・アングル/ヴァルパンソンの浴女
など多くの画家が後ろ姿を描いている。美術館でまたどんな新たな「後ろ姿」に出会えるか、楽しみではある。
(rev.Dec.2023/Dec.2017)
gillaman*s Gellery. At hte Park/On the Hill
gillaman*s gellery...
At the Park
散歩の途中で街を見下ろす公園の丘の上に来るとなんだかホッとする。それはどうもぼくだけではないようで、色々な人がそういう感じの表情になる。
時には丘のはるか下の方からでもそんな雰囲気がみてとれる時もあるのだ。そういう意味では丘の上はホッとスポットであり、そこでのひとときは貴重なホッとタイムなのだ。
えっ、な~に。

丘の上の蓋のない広々とした空の下に来ると誰もが伸びをしたくなる。そのうちホッとして心がほぐれてくる。
はぁ~っ

丘のベンチにここではあまり見かけないスーツ姿の男性が座っている。缶コーヒーを手に眼下に広がる街並みを見下ろしている。何だか缶コーヒーのコマーシャルのシーンみたいだ。「ただ、この惑星の住人は、なぜか上を向くだけで元気になれる」 BOSSコーヒーでの宇宙人ジョーンズの言葉。*2011年放送 第28弾「とある老人編」
・・・

よく見かける丘の常連さん。特徴はベンチに反対向きに座って背もたれに両肘をついて街並みを眺めていること。一人のこともペアのこともある。言葉を交わさなくてもじっと街並みを見つめることで何か通じ合っているのかもしれないなぁ。
天空カウチ

長閑な昼前、丘の上から大きな声が聞こえてきた。誰かが電話しているらしいのだが日本語ではないらしい。タガログ語かな。階段を昇ると、丘の上のベンチに横になって携帯で電話している女性が見えた。どこに電話しているのかな、故国かな。丘の上の天空カウチでホッとタイムしているんだな。
火点し頃

火点し頃(ひともしごろ/ひとぼしごろ)は好きな言葉だけれど、夕暮れがせまる時刻の感じが良く出ていると思う。夕暮れ時に丘の上のベンチに座っていると、下から聞こえてくる街の喧騒が次第に変わってくるのがわかる。下町の工場の機械の音が止まり、やがて公園から子供たちの声が遠ざかってゆく。街灯が少しづつ灯りはじめる。
ホっとドッグ

休日の朝夕は公園は犬を散歩させる人でさながらドッグショウみたいな様相を呈する。朝方といっても真夏の散歩はアスファルトで舗装された地表に近い犬にとってはきつい時もあるのでは…と思ったりもする。この日も丘の上にやっとたどり着いて人も犬もホッと一息。ホッとドッグだね。
小さな幸せ

ホッとタイムは小さな幸せ。丘の上に小さく豆粒のように見えるホッとタイムな人影。とても眩しく、大切なもののように見える。他人の幸せそうな姿が疎ましく思える時は、自分の心が病んでいるのかもしれない。今の自分にはどう見えているか、心のリトマス試験紙。
アンドリュー・ワイエスの言葉 「…このひとつの丘が私にとっては何千の丘と同じ意味を持つ。このひとつの対象の中に私は世界を見出す」また「…題材を変えることは私にとってそれほど重要なことではない。なぜなら、ひとつの題材からいつも新しい発見があるからだ」(「アンドリュー・ワイエス 創造への道程」/Bunkamura) この身近な公園の丘がぼくにとって生涯そういう丘であり続けることを願って…。
At the Park
On the Hill
~ホッとタイム~
散歩の途中で街を見下ろす公園の丘の上に来るとなんだかホッとする。それはどうもぼくだけではないようで、色々な人がそういう感じの表情になる。
時には丘のはるか下の方からでもそんな雰囲気がみてとれる時もあるのだ。そういう意味では丘の上はホッとスポットであり、そこでのひとときは貴重なホッとタイムなのだ。
えっ、な~に。
丘の上の蓋のない広々とした空の下に来ると誰もが伸びをしたくなる。そのうちホッとして心がほぐれてくる。
はぁ~っ
丘のベンチにここではあまり見かけないスーツ姿の男性が座っている。缶コーヒーを手に眼下に広がる街並みを見下ろしている。何だか缶コーヒーのコマーシャルのシーンみたいだ。「ただ、この惑星の住人は、なぜか上を向くだけで元気になれる」 BOSSコーヒーでの宇宙人ジョーンズの言葉。*2011年放送 第28弾「とある老人編」
・・・

よく見かける丘の常連さん。特徴はベンチに反対向きに座って背もたれに両肘をついて街並みを眺めていること。一人のこともペアのこともある。言葉を交わさなくてもじっと街並みを見つめることで何か通じ合っているのかもしれないなぁ。
天空カウチ
長閑な昼前、丘の上から大きな声が聞こえてきた。誰かが電話しているらしいのだが日本語ではないらしい。タガログ語かな。階段を昇ると、丘の上のベンチに横になって携帯で電話している女性が見えた。どこに電話しているのかな、故国かな。丘の上の天空カウチでホッとタイムしているんだな。
火点し頃
火点し頃(ひともしごろ/ひとぼしごろ)は好きな言葉だけれど、夕暮れがせまる時刻の感じが良く出ていると思う。夕暮れ時に丘の上のベンチに座っていると、下から聞こえてくる街の喧騒が次第に変わってくるのがわかる。下町の工場の機械の音が止まり、やがて公園から子供たちの声が遠ざかってゆく。街灯が少しづつ灯りはじめる。
ホっとドッグ
休日の朝夕は公園は犬を散歩させる人でさながらドッグショウみたいな様相を呈する。朝方といっても真夏の散歩はアスファルトで舗装された地表に近い犬にとってはきつい時もあるのでは…と思ったりもする。この日も丘の上にやっとたどり着いて人も犬もホッと一息。ホッとドッグだね。
小さな幸せ

ホッとタイムは小さな幸せ。丘の上に小さく豆粒のように見えるホッとタイムな人影。とても眩しく、大切なもののように見える。他人の幸せそうな姿が疎ましく思える時は、自分の心が病んでいるのかもしれない。今の自分にはどう見えているか、心のリトマス試験紙。
アンドリュー・ワイエスの言葉 「…このひとつの丘が私にとっては何千の丘と同じ意味を持つ。このひとつの対象の中に私は世界を見出す」また「…題材を変えることは私にとってそれほど重要なことではない。なぜなら、ひとつの題材からいつも新しい発見があるからだ」(「アンドリュー・ワイエス 創造への道程」/Bunkamura) この身近な公園の丘がぼくにとって生涯そういう丘であり続けることを願って…。
(Jan.2024)
gillman*s Gallery At the Park/On the Hill
gillman*s gallery...
At the Park
公園の丘に昇る階段が好きなのだけれど、階段くらい年齢を感じさせるものはないと思う。高齢になればマラソンに参加をするなどどんなに健脚を誇っていても歳をとれば階段を駆け上がったり、駆け降りたりはできない。
気が付けば階段ではしゃいで汗かきながら昇り降りしている子供や、ファッションショウのランウェイのように颯爽と降りてくる若者の姿を眩しそうに見ている自分が居る。
Red&White

丘に登る階段を空をバックに下から見上げる構図が好きで…。この日は荒天を予想させるような空をバックに赤と白のジャケットを着たペアが目に入った。カメラを持って街にでると赤い色に何となく条件反射してしまう自分がいる。小津安二郎のカラー作品を観ていると、画面のどこかにワンポイント赤が入っていることが多いような気がするのだけれど、あのアグファの赤い色が素敵だなぁ。
冬のイナヅマ

日も傾き始めた真冬の四時過ぎ頃になると、西から差し込んだ陽が作り出す影が丁度丘の階段の真ん中あたりに来て、なにやら階段をはしるイナヅマのように見えることがある。ぼくはこの影が好きでそのイナヅマが階段の中央に来るまで下の東屋で待つこともある。この時はイナヅマのはしる階段の上の親子がまるで歌舞伎の見栄をきっているように見えて面白かった。
冬のイナヅマ2 (ねじ式)

子供を真ん中に親子が手をつないで階段を降りてくる。ありふれた、そして微笑ましい日常の散歩風景。しかしその前には風雲急を告げるイナヅマが待ち受けている…ような。階段途中の踊り場で親子を待ち受けているような坊主頭の男の存在が不気味で…。昔、漫画雑誌の「ガロ」で見たつげ義春の「ねじ式」のワンシーンを思い浮かべた。
Across

公園の丘へはこの一直線の石段の他にも急な坂道や地面に丸木で土留めをしただけの階段や緩やかなスロープの道などあってそれぞれ趣も異なっている。この石段の中間の踊り場のところを緩やかなスロープが横切っている。長い石段を昇る人が入道雲が湧きたつ夏空に引き込まれてゆくような視界の中をスロープを下る人がゆっくりと横切っていった。どこかでカラスが鳴いている。
辿り着く

同じ階段でも、子供たちは跳ねるように、学生さんは大股で二段おきに、家族連れは子供の手を取って、そして歳を取るにつれて手すりのお世話になって時にはステッキを持って…。でも、階段くらい年齢を感じさせるものはないと思う。段々そこに辿り着くことが大変になってくるけれど、それでもそこに行こうとするのはそこに行かねば見られない世界があるからだろう。
At the Park
On the Hill
~空につづく階段~
公園の丘に昇る階段が好きなのだけれど、階段くらい年齢を感じさせるものはないと思う。高齢になればマラソンに参加をするなどどんなに健脚を誇っていても歳をとれば階段を駆け上がったり、駆け降りたりはできない。
気が付けば階段ではしゃいで汗かきながら昇り降りしている子供や、ファッションショウのランウェイのように颯爽と降りてくる若者の姿を眩しそうに見ている自分が居る。
Red&White

丘に登る階段を空をバックに下から見上げる構図が好きで…。この日は荒天を予想させるような空をバックに赤と白のジャケットを着たペアが目に入った。カメラを持って街にでると赤い色に何となく条件反射してしまう自分がいる。小津安二郎のカラー作品を観ていると、画面のどこかにワンポイント赤が入っていることが多いような気がするのだけれど、あのアグファの赤い色が素敵だなぁ。
冬のイナヅマ

日も傾き始めた真冬の四時過ぎ頃になると、西から差し込んだ陽が作り出す影が丁度丘の階段の真ん中あたりに来て、なにやら階段をはしるイナヅマのように見えることがある。ぼくはこの影が好きでそのイナヅマが階段の中央に来るまで下の東屋で待つこともある。この時はイナヅマのはしる階段の上の親子がまるで歌舞伎の見栄をきっているように見えて面白かった。
冬のイナヅマ2 (ねじ式)

子供を真ん中に親子が手をつないで階段を降りてくる。ありふれた、そして微笑ましい日常の散歩風景。しかしその前には風雲急を告げるイナヅマが待ち受けている…ような。階段途中の踊り場で親子を待ち受けているような坊主頭の男の存在が不気味で…。昔、漫画雑誌の「ガロ」で見たつげ義春の「ねじ式」のワンシーンを思い浮かべた。
Across

公園の丘へはこの一直線の石段の他にも急な坂道や地面に丸木で土留めをしただけの階段や緩やかなスロープの道などあってそれぞれ趣も異なっている。この石段の中間の踊り場のところを緩やかなスロープが横切っている。長い石段を昇る人が入道雲が湧きたつ夏空に引き込まれてゆくような視界の中をスロープを下る人がゆっくりと横切っていった。どこかでカラスが鳴いている。
辿り着く
同じ階段でも、子供たちは跳ねるように、学生さんは大股で二段おきに、家族連れは子供の手を取って、そして歳を取るにつれて手すりのお世話になって時にはステッキを持って…。でも、階段くらい年齢を感じさせるものはないと思う。段々そこに辿り着くことが大変になってくるけれど、それでもそこに行こうとするのはそこに行かねば見られない世界があるからだろう。
(Dec.2023)
gillman*s Gellery On the Hill
gillman*s gallery...
At the Park
もう長いこと公園の丘に行けていない。以前は公園の丘がぼくの散歩の目的地のひとつなのだけれど、その丘の上で季節や時間や天候ごとに展開されるシーンはぼくにとってまるで人生の舞台を見るように興味深い。今のリハビリの当面の目標もあの丘に戻ること。その日まで丘の上の撮りためた写真をあの丘へのオマージュとして…。
少年時代

夕暮れが訪れようとする時間帯、丘の上で少年が一人自転車にまたがり眼下の街並みをじっと見つめていた。その刹那、井上陽水の歌「少年時代」のメロディーが耳をかすめた。
ぼくも彼くらいの子供の頃、夏休みはここら辺を駆け回っていた。その頃はここには公園も丘もなく一面の畑や田んぼが広がっていた。もう一度、あの頃に戻ってこの丘に登ってみたいと思った。
青春時代

学校の帰りじゃないな。一旦家に帰ってからか、休みかなんかで皆で誘い合って自転車でここに来たような。女の子たちは丘の柵に腰を掛けている。一段下の方から男子たちが話しかけている。とても楽しそうな、でもどこか照れくさそうで…。もう、すっかり忘れてしまったけれどこんな気持ちがあったなぁ。
Sundown Dancers

夕暮れが迫る中、丘の上では下校途中に公園の丘に来たらしい男女学生が三人。鼻歌を口ずさみながらダンス。風は冷たい。なんか楽しいことがあったのかな、ぐるぐる回っている。いいなぁ。
アンドリュー・ワイエスの言葉 「…このひとつの丘が私にとっては何千の丘と同じ意味を持つ。このひとつの対象の中に私は世界を見出す」また「…題材を変えることは私にとってそれほど重要なことではない。なぜなら、ひとつの題材からいつも新しい発見があるからだ」(「アンドリュー・ワイエス 創造への道程」/Bunkamura) この身近な公園の丘がぼくにとって生涯そういう丘であり続けることを願って…。
At the Park
On the Hill
~若いっていいなぁ~
もう長いこと公園の丘に行けていない。以前は公園の丘がぼくの散歩の目的地のひとつなのだけれど、その丘の上で季節や時間や天候ごとに展開されるシーンはぼくにとってまるで人生の舞台を見るように興味深い。今のリハビリの当面の目標もあの丘に戻ること。その日まで丘の上の撮りためた写真をあの丘へのオマージュとして…。
少年時代

夕暮れが訪れようとする時間帯、丘の上で少年が一人自転車にまたがり眼下の街並みをじっと見つめていた。その刹那、井上陽水の歌「少年時代」のメロディーが耳をかすめた。
ぼくも彼くらいの子供の頃、夏休みはここら辺を駆け回っていた。その頃はここには公園も丘もなく一面の畑や田んぼが広がっていた。もう一度、あの頃に戻ってこの丘に登ってみたいと思った。
青春時代
学校の帰りじゃないな。一旦家に帰ってからか、休みかなんかで皆で誘い合って自転車でここに来たような。女の子たちは丘の柵に腰を掛けている。一段下の方から男子たちが話しかけている。とても楽しそうな、でもどこか照れくさそうで…。もう、すっかり忘れてしまったけれどこんな気持ちがあったなぁ。
Sundown Dancers
夕暮れが迫る中、丘の上では下校途中に公園の丘に来たらしい男女学生が三人。鼻歌を口ずさみながらダンス。風は冷たい。なんか楽しいことがあったのかな、ぐるぐる回っている。いいなぁ。
アンドリュー・ワイエスの言葉 「…このひとつの丘が私にとっては何千の丘と同じ意味を持つ。このひとつの対象の中に私は世界を見出す」また「…題材を変えることは私にとってそれほど重要なことではない。なぜなら、ひとつの題材からいつも新しい発見があるからだ」(「アンドリュー・ワイエス 創造への道程」/Bunkamura) この身近な公園の丘がぼくにとって生涯そういう丘であり続けることを願って…。
(Dec.2023)
カテゴリー
- 新隠居主義(433)
- 猫と暮らせば(185)
- gillman*s park(295)
- gillman*s Lands(109)
- Ansicht Tokio(61)
- German Jokes(1)
- 下町の時間(40)
- NOSTALGIA(12)
- Déjà-vu(15)
- Music Scene(12)
- Column Ansicht(27)
- にほんご(20)
- あの時の文春(9)
- ドイツの目(4)
- Retro-Kino(5)
- TV-Eye(8)
- 落語(2)
gillman*s Choice Tod und Mädchen
ドイツ映画View
~3~
エゴン・シーレ
死と乙女
Egon Schiele: Tod und Mädchen

2018年はこのエゴン・シーレとグスタフ・クリムトの没後100年にあたり、翌年には日本でもこの二人の作品が大分紹介されたけど、周知のようにこの二人は当時世界を席巻したスペイン風邪で命を落としている。新型コロナウイルスに世界が震撼している今、急にこの時代が目の前に迫ってくるような気になる。
この映画は厳密にいえばオーストリアとルクセンブルクの合作映画なのだが言語はドイツ語だしドイツ語文化圏の映画ということでここに入れた。映画はエゴン・シーレの伝記には違いないが、物語は彼をとりまく女性たち特に恋人ヴァリ・ノイツィルとの関係を軸に回り始める。全編極めて抒情的に描かれているけど、その中身は実にやりきれない感じだ。
ヴァリとシーレの関係を中心にシーレの芸術に対する純粋さと表裏一体の狡さ。シーレはクリムトのモデルであったヴァリとの出会いによって近親相姦的な愛の関係にもあった妹ゲルティとの関係が変化してゆく。続いてヴァリとの同棲生活、そしてシーレの幼女との性愛疑惑の裁判。

その後シーレはアデーレとエーディト姉妹に目を付けて結局生活のためにエーディトと結婚、ヴァリとは画家とモデルの関係以上の関係を続けたいというエゴまるだしのシーレ。捨てられた形のヴァリは戦地の前線看護婦に志願しそこで病死してしまう。
妻となった良家育ちのエーディトは世間体をはばかりの性愛テーマの絵をやめて欲しいと願ったが、シーレは売れる絵だからやめられないという。終盤、スペイン風邪で身重のエーディトが亡くなる。シーレも罹患して重体に。結局妹が世話をするが医者は、闇市で宝石と交換で特効薬のキニーネを手に入れれば助かるとも。妹はエーディトの実家の姉アディーレに散々懇願した末に彼女が保有していたダイヤモンドを貰い受けやっと闇市でキニーネを手に入れるが、既にシーレは亡くなっていた。

映画の中の随所にシーレの作品を思わせるシーンが登場する。特に妻のエーディトと二人だけの会話のシーンで彼女が着ていた縞のドレスは、ぼくがシーレの人物画の中でも好きな一枚のうちの「縞のドレスを着て座るエーディト・シーレ(1915)/レオポルド美術館」そのまま、その場にいたように胸が熱くなった。

こういう映画を観ると人物としての芸術家とその作品についていつも考えされられる。シーレがもし絵を描かなかったらただの女たらしのクズだが…、芸術はそれを正当化させてくれるのだろうか。それは音楽家のリヒャルト・ワグナーなどにも言えることなのだけれども、ぼくは今その答えは持っていない。
観終わった後ヴァリ役のValerie Pachner(ヴァレリー・パフナー)の好演と彼女が演じたヴァリという女性の人物像の愛しさが深く心に残った。彼女はオーストリアの女優でこの作品で同国の主演女優賞をとり、さらに他の作品でも昨年ドイツ映画賞の女優賞も獲得している。これからが楽しみな女優だ。
[CREDIT]
Year:2016
Director: Dieter Berner
Writers: Hilde Berger, Dieter Berner
Stars:
Noah Saavedra-Egon Schiele
Maresi Riegner-sister Gerti Schiele
Valerie Pachner-Wally Neuzil
(May 2020)
Museum of the Month ピカソとその時代
Museum of the Month...

[感想メモ]
ベルリンの美術館の名称はややこしくて行くたびに面食らうのだけれど、例えばベルリン美術館(Staatliche Museen zu Berlin)という名の美術館は実際は無くて、それは15位いの美術館・博物館群を総称して言うのであって、その中にナショナルギャラリー(国立美術館)もある。そのナショナルギャラリーもアルテ(旧)とノイエ(新)があるって…。
ドイツ語のStaatlichというのが曲者で国立とも州立もとれる。日本では「国立」と称されるバイエルン国立歌劇場(Bayerische Staatsoper)もドレスデン国立歌劇場(Sächsischen Staatsoper Dresden)も実は州立である。
まぁ、そんなことはどうでも良いのだけれど、そのナショナルギャラリーの一つのベルクグリューン美術館の改装を機会に同館所蔵のピカソなどの作品がごっそり展示されるということで、これはめったにない機会に違いない。
考えてみたらピカソの作品をまとめて観たという記憶は余りない。パリやバルセロナにピカソ美術館というのがあるが、ピカソ自体多作なので色々な処で観ることは出来るけれど、それ以外ではこれほどまとまって観られることは少ないかもしれない。
今回はぼくの好きな青の時代の作品は少なかったけれど、展覧会のタイトルにもあるようにピカソと同時にクレーやマチスの多くの作品にも触れることが出来たのが嬉しかった。尚、今回はごく一部の作品を除いて撮影可だった。ぼくが撮ってきたのが下の6点。会場での撮影は後で詳細にまた観たいものに限ってすることにしている。

座るアルルカン/ピカソ

(1905)
どんなアーチストも時と共に作風は変わるのだろうが、中でもピカソほど生涯で作風が変わっていった作家も珍しいと思う。例えば以前見たヘレン・シャルフベックも生涯作風が変わり続けた人だったけれど、ピカソの変化幅は桁が違うと感じた。このアルルカンの絵も青の時代から抜け出てバラ色の時代へと変貌していった時期の作品。この頃は道化師や旅芸人の作品が多い。
座って足を拭く裸婦/ピカソ

(1921)
ピカソの新古典主義時代と称されるこの時期の作品がぼくは青の時代と並んで好きだ。手足が異常に大きいのだが奇異な感じはなくどちらかと言えば裸婦の豊饒さが伝わって来る。第一次世界大戦の混乱から抜け出た時代の古典的調和への憧憬もあるのだろうか。
サーカスの馬/ピカソ

(1937)
この馬を見ると「ゲルニカ」の中央で叫んでいるようなあの馬を想起する。この悲壮な表情をした馬は屈強な男にまさにサーカス会場に引き出されようとしている。このパステル画はゲルニカが描かれた数か月後に制作されたことから何らかの関連したモチーフを持っていると思う。画面は小さかったのだけれど撮ってきた写真を拡大してみると背後の観客のグロテスクな表情も明確に分かって会場とはまた違った鑑賞が出来る。
緑色のマニキュアをつけたドラ・マール/ピカソ

(1936)
今回の展覧会のポスターや図録の表紙にも使われている作品。ドラ・マールは当時新進気鋭の女流写真家でピカソのパートナーになった。この絵からは彼女の都会的な雰囲気と才能あふれる自信みたいなものが伝わって来る。ピカソから彼女に贈られ彼女は生涯その手元に置いていたという。
夢の都市/クレー

(1921)
今回の展覧会は「ピカソと…」と銘打っているけれど、クレーの作品もピカソに劣らず多数展示されていた。(ピカソの作品展示が55点に対しクレーの作品も33点という充実ぶり)そのクレーの作品の中でもぼくが一番惹かれたのがこの作品。バウハウス時代の作品だが別名フーガと呼ばれるように色と形がフーガのようにズレながら移行してゆくそのリズム感が素晴らしかった。
室内、エトルタ/マティス

(1920)
マチスの作品も素晴らしいものが多かった。マティスといえばその赤色が印象的だが、この作品の青系統の色彩も捨てがたい。エトルタとは印象派の画家たちが愛した北フランスの海辺の町。開いた窓の向こうに広がる港と海。青い光に囲まれた静謐な時間。
[図録]

358頁、2800円。殆ど全ての展示作品に丁寧な解説もついて標準的な図録になっているが最後に掲載されているクレー、ピカソ、マティスとジャコメッティに関する論文が興味深かった。
[蛇足]

西美で特別展がある時には混雑して待ち時間があるのでレストラン「CAFÉすいれん」には中々寄ることはないのだけれど、常設展だけの時には昔からよく寄っていた。この時は特別展が行われていたけれど時間がズレていたからか空いていたので久しぶりによって遅い昼食をとった。その時食べたのがこのオムライスだけど、フワトロの卵とビーフシチューが絶妙なハーモニーでとても美味しかった。
ピカソとその時代展

国立西洋美術館
2022年10月8日~2023年1月22日[感想メモ]
ベルリンの美術館の名称はややこしくて行くたびに面食らうのだけれど、例えばベルリン美術館(Staatliche Museen zu Berlin)という名の美術館は実際は無くて、それは15位いの美術館・博物館群を総称して言うのであって、その中にナショナルギャラリー(国立美術館)もある。そのナショナルギャラリーもアルテ(旧)とノイエ(新)があるって…。
ドイツ語のStaatlichというのが曲者で国立とも州立もとれる。日本では「国立」と称されるバイエルン国立歌劇場(Bayerische Staatsoper)もドレスデン国立歌劇場(Sächsischen Staatsoper Dresden)も実は州立である。
まぁ、そんなことはどうでも良いのだけれど、そのナショナルギャラリーの一つのベルクグリューン美術館の改装を機会に同館所蔵のピカソなどの作品がごっそり展示されるということで、これはめったにない機会に違いない。
考えてみたらピカソの作品をまとめて観たという記憶は余りない。パリやバルセロナにピカソ美術館というのがあるが、ピカソ自体多作なので色々な処で観ることは出来るけれど、それ以外ではこれほどまとまって観られることは少ないかもしれない。
今回はぼくの好きな青の時代の作品は少なかったけれど、展覧会のタイトルにもあるようにピカソと同時にクレーやマチスの多くの作品にも触れることが出来たのが嬉しかった。尚、今回はごく一部の作品を除いて撮影可だった。ぼくが撮ってきたのが下の6点。会場での撮影は後で詳細にまた観たいものに限ってすることにしている。
ピカソとその時代展
My Best 5+1
座るアルルカン/ピカソ
(1905)
どんなアーチストも時と共に作風は変わるのだろうが、中でもピカソほど生涯で作風が変わっていった作家も珍しいと思う。例えば以前見たヘレン・シャルフベックも生涯作風が変わり続けた人だったけれど、ピカソの変化幅は桁が違うと感じた。このアルルカンの絵も青の時代から抜け出てバラ色の時代へと変貌していった時期の作品。この頃は道化師や旅芸人の作品が多い。
座って足を拭く裸婦/ピカソ
(1921)
ピカソの新古典主義時代と称されるこの時期の作品がぼくは青の時代と並んで好きだ。手足が異常に大きいのだが奇異な感じはなくどちらかと言えば裸婦の豊饒さが伝わって来る。第一次世界大戦の混乱から抜け出た時代の古典的調和への憧憬もあるのだろうか。
サーカスの馬/ピカソ
(1937)
この馬を見ると「ゲルニカ」の中央で叫んでいるようなあの馬を想起する。この悲壮な表情をした馬は屈強な男にまさにサーカス会場に引き出されようとしている。このパステル画はゲルニカが描かれた数か月後に制作されたことから何らかの関連したモチーフを持っていると思う。画面は小さかったのだけれど撮ってきた写真を拡大してみると背後の観客のグロテスクな表情も明確に分かって会場とはまた違った鑑賞が出来る。
緑色のマニキュアをつけたドラ・マール/ピカソ

(1936)
今回の展覧会のポスターや図録の表紙にも使われている作品。ドラ・マールは当時新進気鋭の女流写真家でピカソのパートナーになった。この絵からは彼女の都会的な雰囲気と才能あふれる自信みたいなものが伝わって来る。ピカソから彼女に贈られ彼女は生涯その手元に置いていたという。
夢の都市/クレー
(1921)
今回の展覧会は「ピカソと…」と銘打っているけれど、クレーの作品もピカソに劣らず多数展示されていた。(ピカソの作品展示が55点に対しクレーの作品も33点という充実ぶり)そのクレーの作品の中でもぼくが一番惹かれたのがこの作品。バウハウス時代の作品だが別名フーガと呼ばれるように色と形がフーガのようにズレながら移行してゆくそのリズム感が素晴らしかった。
室内、エトルタ/マティス
(1920)
マチスの作品も素晴らしいものが多かった。マティスといえばその赤色が印象的だが、この作品の青系統の色彩も捨てがたい。エトルタとは印象派の画家たちが愛した北フランスの海辺の町。開いた窓の向こうに広がる港と海。青い光に囲まれた静謐な時間。
[図録]
358頁、2800円。殆ど全ての展示作品に丁寧な解説もついて標準的な図録になっているが最後に掲載されているクレー、ピカソ、マティスとジャコメッティに関する論文が興味深かった。
[蛇足]
西美で特別展がある時には混雑して待ち時間があるのでレストラン「CAFÉすいれん」には中々寄ることはないのだけれど、常設展だけの時には昔からよく寄っていた。この時は特別展が行われていたけれど時間がズレていたからか空いていたので久しぶりによって遅い昼食をとった。その時食べたのがこのオムライスだけど、フワトロの卵とビーフシチューが絶妙なハーモニーでとても美味しかった。
(Jan.202)
Museu of the Month Vallotton版画展
Museum of the Month...
ヴァロットン

[感想メモ]
日本で初のヴァロットンの本格的な回顧展が三菱一号館美術館で開かれたのは確か2014年の事だったと思う。それはオルセー美術館から始まった世界巡回の回顧展の一環だった。その時も三菱一号館美術館の所有するヴァロットンの版画の多くが展示されていたけれど、当時は謎に満ちた油彩作品の「ボール(1899)」が世間の耳目を集めミステリアスな画家という側面に光が当てられていたように感じた。
その時ぼくはヴァロットンの黒と白の世界に魅せられて展覧会の図録とは別にヴァロットンの版画集を買った。今回の展覧会ではその黒と白の世界を堪能できた。グレーという中間的なモノクロ諧調を排して、黒と白の両極端に集約された光と影の世界の中で人々の揺れ動く心が炙り出される。世紀末のジャポニズムに触発された彼の版画は黒と白という領域で新たな表現に発展していったのだと思う。奇しくも今日12月29日はヴァロットンの命日である。

嘘/アンティミテ

(1897)
アンティミテというのは親密なという意味で男女関係の微妙な駆け引きや心理の揺れが白黒の極端なコントラストの中に浮かび上がる。アンティミテでは10の場面が描かれているがどれも甲乙つけがたい傑作と思う。このポストカードをもう長いこと自分の部屋に飾っている。
怠惰

(1896)
この構図を一目見て思い起こされるのがマネやセザンヌのオランピアで、この作品もそういう横たわる裸婦という範疇に入ると思うけれど、それにしても何と美しいモノクロの世界か。黒と白だけで素材の質感の違いまで伝わって来るような。ヴァロットンの中でもとりわけ美しい作品だ。
暗殺

(1893)
ヴァロットンは死をテーマにした作品をいくつか残しているけれど、これは何とも恐ろしい場面。直接的に描いてはいないが暗殺者の足元のズレたラグに勢い込んで襲いかかった形跡が見られるし、開かれたのドアノブに差し込まれた鍵の束らしいもの、暗殺者を抑える手、何があったのか、これを見た鑑賞者の中で新しいストーリーが動き出しそうな作品。
可愛い天使たち

(1894)
ヴァロットンには子供の版画も多い。暗殺や不倫など緊張する場面から屈託のない子供たちの姿にほっとさせるかと思いきや、子供たちが囃し立てているのは警官に連行される男。犯罪人というよりはホームレスのような格好の男を子供たちが寄ってたかって…、中には笑っている子もいる。可愛い天使たちの無邪気な残酷さ。
祖国を讃える歌

(1893)
ヴァロットンの作品を支えている一つの要素は透徹した観察眼。タイトルからすると台頭しつつあったナショナリズムに燃える群衆のようだが、よく見ると退屈そうにしている男や冷ややかに見ている者もいて…それもヴァロットンは見逃さない。前の作品もそうだけれど、絵を観るとタイトルが多分に皮肉であることに気づく。

[図録など]
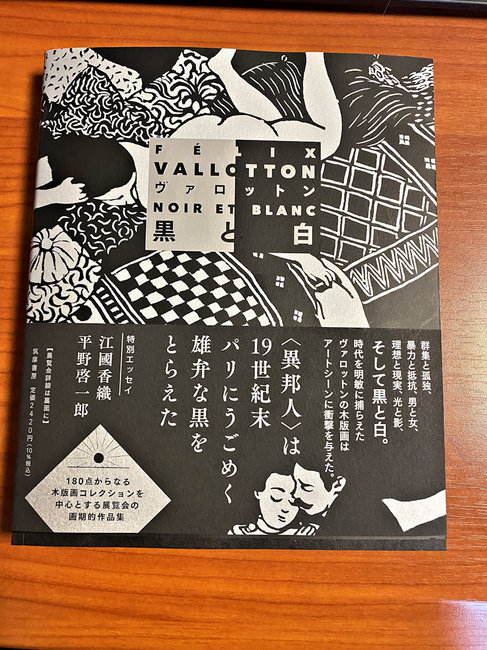
238頁。2200円+税。ぼくはヴァロットンの版画集を持っていたので迷ったけれど、版画集には載っていない彩色リトグラフの作品や蔵書票などの小粋な作品も載っていたので買うことにした。これ一冊あれば彼の版画の世界を十分楽しむことが出来ると思う。
*会場では撮影可の展示室もあり、小さな版画は撮影してあとで拡大して細部を鑑賞できるのでありがたい。
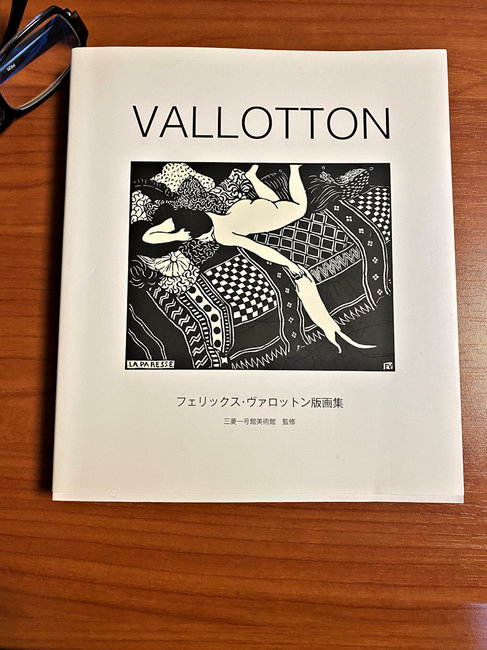
ヴァロットン版画集

ヴァロットン
「黒と白」展
三菱一号館美術館
2022年10月21日~2023年1月29日
[感想メモ]
日本で初のヴァロットンの本格的な回顧展が三菱一号館美術館で開かれたのは確か2014年の事だったと思う。それはオルセー美術館から始まった世界巡回の回顧展の一環だった。その時も三菱一号館美術館の所有するヴァロットンの版画の多くが展示されていたけれど、当時は謎に満ちた油彩作品の「ボール(1899)」が世間の耳目を集めミステリアスな画家という側面に光が当てられていたように感じた。
その時ぼくはヴァロットンの黒と白の世界に魅せられて展覧会の図録とは別にヴァロットンの版画集を買った。今回の展覧会ではその黒と白の世界を堪能できた。グレーという中間的なモノクロ諧調を排して、黒と白の両極端に集約された光と影の世界の中で人々の揺れ動く心が炙り出される。世紀末のジャポニズムに触発された彼の版画は黒と白という領域で新たな表現に発展していったのだと思う。奇しくも今日12月29日はヴァロットンの命日である。
Vallotton版画
My Best 5
嘘/アンティミテ

(1897)
アンティミテというのは親密なという意味で男女関係の微妙な駆け引きや心理の揺れが白黒の極端なコントラストの中に浮かび上がる。アンティミテでは10の場面が描かれているがどれも甲乙つけがたい傑作と思う。このポストカードをもう長いこと自分の部屋に飾っている。
怠惰

(1896)
この構図を一目見て思い起こされるのがマネやセザンヌのオランピアで、この作品もそういう横たわる裸婦という範疇に入ると思うけれど、それにしても何と美しいモノクロの世界か。黒と白だけで素材の質感の違いまで伝わって来るような。ヴァロットンの中でもとりわけ美しい作品だ。
暗殺
(1893)
ヴァロットンは死をテーマにした作品をいくつか残しているけれど、これは何とも恐ろしい場面。直接的に描いてはいないが暗殺者の足元のズレたラグに勢い込んで襲いかかった形跡が見られるし、開かれたのドアノブに差し込まれた鍵の束らしいもの、暗殺者を抑える手、何があったのか、これを見た鑑賞者の中で新しいストーリーが動き出しそうな作品。
可愛い天使たち
(1894)
ヴァロットンには子供の版画も多い。暗殺や不倫など緊張する場面から屈託のない子供たちの姿にほっとさせるかと思いきや、子供たちが囃し立てているのは警官に連行される男。犯罪人というよりはホームレスのような格好の男を子供たちが寄ってたかって…、中には笑っている子もいる。可愛い天使たちの無邪気な残酷さ。
祖国を讃える歌
(1893)
ヴァロットンの作品を支えている一つの要素は透徹した観察眼。タイトルからすると台頭しつつあったナショナリズムに燃える群衆のようだが、よく見ると退屈そうにしている男や冷ややかに見ている者もいて…それもヴァロットンは見逃さない。前の作品もそうだけれど、絵を観るとタイトルが多分に皮肉であることに気づく。
[図録など]
238頁。2200円+税。ぼくはヴァロットンの版画集を持っていたので迷ったけれど、版画集には載っていない彩色リトグラフの作品や蔵書票などの小粋な作品も載っていたので買うことにした。これ一冊あれば彼の版画の世界を十分楽しむことが出来ると思う。
*会場では撮影可の展示室もあり、小さな版画は撮影してあとで拡大して細部を鑑賞できるのでありがたい。
ヴァロットン版画集
(Dec/2022)
gillman*s Art 青木繁「海の幸」の家
gillman*s Art...
青木繁「海の幸」の家

実に数年ぶりに二泊三日で房総に温泉旅行に行った。二日目、養老渓谷から次の温泉地である千倉に行く前に海岸沿いに車を走らせている内にコーヒーが飲みたくなりたまたま見つけた喫茶店に入った。
入ってみると客はいない。人懐っこそうなマスターが出てきて注文をする前から何か話したくてか外の景色の説明を始める、…めったに客が来ないのかしら。頼んだコーヒーが来てここら辺に何かないかとスマホで地図をみていたら、近くに青木繁があの名作「海の幸」を描いた時に滞在していた家が残っていると出ていた。
気づいていなかったけど、そう言えばここはあの名作の舞台になった布良(めら)の海岸だ。マスターにその場所を聞くと案内するという。コーヒーがまだ来たばかりなので暫らく飲んでいると、彼がそわそわして身体中から早く案内したい光線みたいなのが発せられている。で、コーヒータイム終了。

その青木繁「海の幸」の家は海岸に向かって少し坂を下ったすぐそばにあった。そこには一軒の古民家が建っていてマスターがその前にある住宅の玄関の戸を叩くと男性が出てきた。その人がこの古民家の現在の主の小谷さんで案内をしてくれる。古民家は市の文化財で記念館にもなっているので入館料300円を払う。

青木繁は東京美術学校(現東京藝大)を卒業した年の夏、東京美術学校の仲間でもあり画塾「不同舎」の仲間であった坂本繁二郎・森田恒友・福田たねと制作旅行で布良に来ていたのだけれど、宿代がなくなって旅館を追い出されたところを当時の漁師頭をしていた小谷家にいわば居候することが許されて二月近くも滞在した。その時にここで「海の幸」が制作されたということらしい。

部屋は多分二間続きの奥の座敷を使っていたと思われるのだけれど、さして広くないこの座敷で四人の若者が日本の黎明期の西洋画を巡り熱い芸術論議を戦わせていたかと思うと感慨深かった。絵画には直接関係ないが、青木繁は28歳の若さで亡くなってしまうが、妻となった福田たねとの間に子供が出来ていて、その子は後に音楽家、尺八奏者の第一人者となった福田蘭堂氏でその長男が往年のクレージーキャッツのメンバーであり、料理家でもあった石橋エータロー氏ということであった。つまりエータロー氏は青木繁の孫だったのだということを初めて知った。

*小谷さんの話では、ここらへんの事情が12月26日(月)にNHK BSプレミアムの「ぐるっと海道3万キロ~海の幸の生まれた浜、房州布良の三代の訪問者~」というタイトルで18時半から放映されるということだった。
また余談になるがこの小谷家は漁師頭だったためいつも水産伝習所の伝習生の訓練の受け入れをしていたのだが、その訓練生をいつも引率してきていたのが当時伝習所の教師をしていた内村鑑三だった。
以前から鑑三の話をよく聞いてくれていた漁師で村の役場の収入役でもあった神田吉右衛門という人物にある日、自分が漁法の改良などいろいろ頑張っても中々漁師の生活は良くはならないとこぼしたところ、「内村さん、改良も良いけれど、何よりも先に漁師を改良しなければ駄目ですよ」と言われて、以前から迷っていたキリスト者としての道を目指すことに決めたという。鑑三はすぐに水産伝道所を辞しキリスト教伝道者の道を歩み始める。
偶然コーヒーを飲みに寄った喫茶店がきっかけで色々な歴史上の人物の接点に触れることになって布良という場所の当時の奥深さも知ることができた。これも縁というものかもしれない。
「日本重要水産動植物圖」
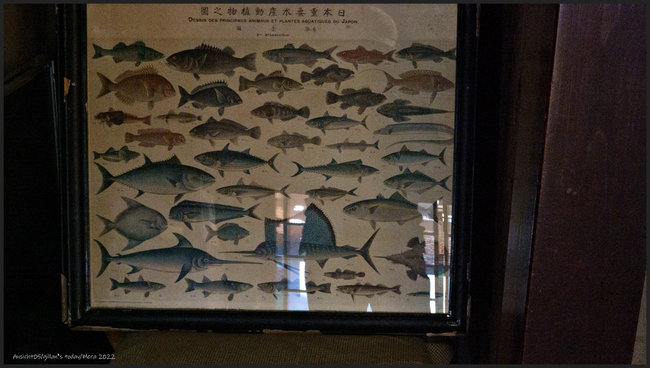
水産伝習所から伝習生を受け入れているお礼として三枚が小谷家に贈られたもので、それがまだ残されていた。それは実は日本最初の本格的な図鑑とされるものらしい。当時、青木繁もこれを見て魚の表現の参考にしたらしい。これの原画100枚が大日本水産会の資料室で発見され以前テレビの「なんでも鑑定団」に出され超高額査定がされていたのをぼくも覚えている。
これが「日本重要水産動植物圖」として大蔵省印刷局の印刷で出版されたのが明治23年(1890)でそのタイトルに英語がついているが、小谷家に贈られたものを見るとそれがフランス語のタイトルになっているので、これはおそらくその2年前の明治21年にパリ万博に出展されたものと同じ版と思われる。英語版とは魚の向きなども異なっているので分かる。
「日本水産動植物図集」としては昭和6-7年(1931-32年)に大日本水産会創立50周年事業として当時の知識・技術を集結させて上下巻で出版された。(当時45円)。52㎝×37㎝の大きさで、600種類以上、805図が収録されている。
青木繁「海の幸」の家

実に数年ぶりに二泊三日で房総に温泉旅行に行った。二日目、養老渓谷から次の温泉地である千倉に行く前に海岸沿いに車を走らせている内にコーヒーが飲みたくなりたまたま見つけた喫茶店に入った。
入ってみると客はいない。人懐っこそうなマスターが出てきて注文をする前から何か話したくてか外の景色の説明を始める、…めったに客が来ないのかしら。頼んだコーヒーが来てここら辺に何かないかとスマホで地図をみていたら、近くに青木繁があの名作「海の幸」を描いた時に滞在していた家が残っていると出ていた。
気づいていなかったけど、そう言えばここはあの名作の舞台になった布良(めら)の海岸だ。マスターにその場所を聞くと案内するという。コーヒーがまだ来たばかりなので暫らく飲んでいると、彼がそわそわして身体中から早く案内したい光線みたいなのが発せられている。で、コーヒータイム終了。

その青木繁「海の幸」の家は海岸に向かって少し坂を下ったすぐそばにあった。そこには一軒の古民家が建っていてマスターがその前にある住宅の玄関の戸を叩くと男性が出てきた。その人がこの古民家の現在の主の小谷さんで案内をしてくれる。古民家は市の文化財で記念館にもなっているので入館料300円を払う。

青木繁は東京美術学校(現東京藝大)を卒業した年の夏、東京美術学校の仲間でもあり画塾「不同舎」の仲間であった坂本繁二郎・森田恒友・福田たねと制作旅行で布良に来ていたのだけれど、宿代がなくなって旅館を追い出されたところを当時の漁師頭をしていた小谷家にいわば居候することが許されて二月近くも滞在した。その時にここで「海の幸」が制作されたということらしい。

部屋は多分二間続きの奥の座敷を使っていたと思われるのだけれど、さして広くないこの座敷で四人の若者が日本の黎明期の西洋画を巡り熱い芸術論議を戦わせていたかと思うと感慨深かった。絵画には直接関係ないが、青木繁は28歳の若さで亡くなってしまうが、妻となった福田たねとの間に子供が出来ていて、その子は後に音楽家、尺八奏者の第一人者となった福田蘭堂氏でその長男が往年のクレージーキャッツのメンバーであり、料理家でもあった石橋エータロー氏ということであった。つまりエータロー氏は青木繁の孫だったのだということを初めて知った。

*小谷さんの話では、ここらへんの事情が12月26日(月)にNHK BSプレミアムの「ぐるっと海道3万キロ~海の幸の生まれた浜、房州布良の三代の訪問者~」というタイトルで18時半から放映されるということだった。
また余談になるがこの小谷家は漁師頭だったためいつも水産伝習所の伝習生の訓練の受け入れをしていたのだが、その訓練生をいつも引率してきていたのが当時伝習所の教師をしていた内村鑑三だった。
以前から鑑三の話をよく聞いてくれていた漁師で村の役場の収入役でもあった神田吉右衛門という人物にある日、自分が漁法の改良などいろいろ頑張っても中々漁師の生活は良くはならないとこぼしたところ、「内村さん、改良も良いけれど、何よりも先に漁師を改良しなければ駄目ですよ」と言われて、以前から迷っていたキリスト者としての道を目指すことに決めたという。鑑三はすぐに水産伝道所を辞しキリスト教伝道者の道を歩み始める。
偶然コーヒーを飲みに寄った喫茶店がきっかけで色々な歴史上の人物の接点に触れることになって布良という場所の当時の奥深さも知ることができた。これも縁というものかもしれない。
「日本重要水産動植物圖」
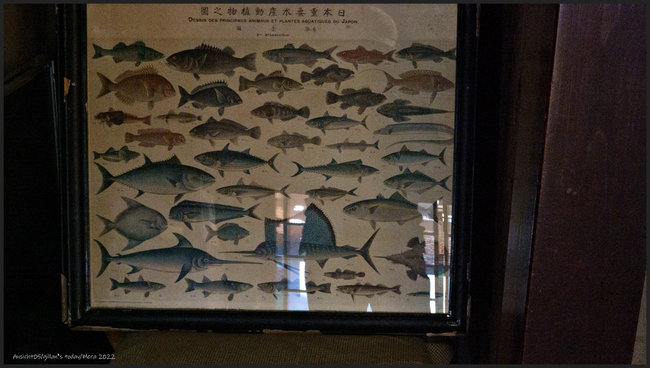
水産伝習所から伝習生を受け入れているお礼として三枚が小谷家に贈られたもので、それがまだ残されていた。それは実は日本最初の本格的な図鑑とされるものらしい。当時、青木繁もこれを見て魚の表現の参考にしたらしい。これの原画100枚が大日本水産会の資料室で発見され以前テレビの「なんでも鑑定団」に出され超高額査定がされていたのをぼくも覚えている。
これが「日本重要水産動植物圖」として大蔵省印刷局の印刷で出版されたのが明治23年(1890)でそのタイトルに英語がついているが、小谷家に贈られたものを見るとそれがフランス語のタイトルになっているので、これはおそらくその2年前の明治21年にパリ万博に出展されたものと同じ版と思われる。英語版とは魚の向きなども異なっているので分かる。
「日本水産動植物図集」としては昭和6-7年(1931-32年)に大日本水産会創立50周年事業として当時の知識・技術を集結させて上下巻で出版された。(当時45円)。52㎝×37㎝の大きさで、600種類以上、805図が収録されている。
(Dec.2022)
gillman*s Choice うたたね
gillman*s Choice...

写真集や画集は好きだけれど高いし場所をとるので基本的には美術展や写真展の図録以外は買わないようにしているのだけれど、それでもどうしても手元に置いておきたくなるものがあると年に一、二冊は買うことがある。
今年は川内倫子の写真集「うたたね」を買った。今までぼくが買った写真集とは大分傾向が異なる。彼女独特の色合いと視線。日常の何気ないシーンが主にスクエアーの画面の中に展開されている。
写真集の帯には「うたたね」というタイトルの上に「死んでしまうということ」と書いてある。見開いたページの左右に一枚づつの写真。丁寧に日常を見つめた何気ないシーンに少しづつ死の匂いが漂い始める。

何気ない日常こそが死と隣り合わせにあるのだと言いたいのか。それともそうだからこそ何気ない日常が愛おしいというのか。それとも…。どう解釈しようともそれは美術史家のゴンブリッジの言う「鑑賞者の取り分」の範疇なのだろうが、見るたびに感ずるところがある。この写真集には「うたたね」というタイトル以外に文字は一切ない。

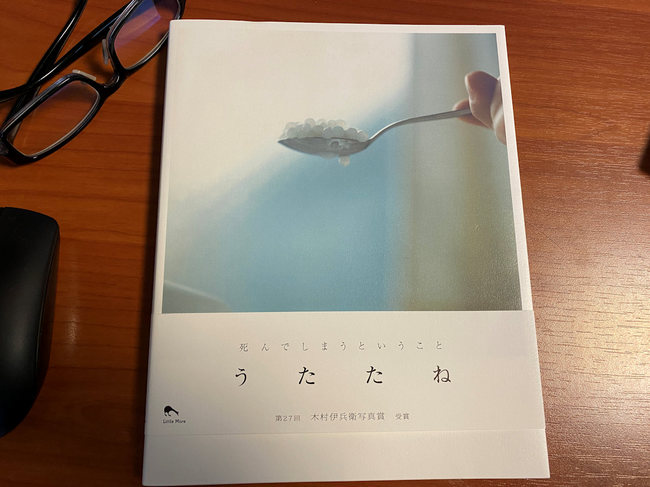
My Favorite Photobooks

写真集「うたたね」
川内倫子
写真集や画集は好きだけれど高いし場所をとるので基本的には美術展や写真展の図録以外は買わないようにしているのだけれど、それでもどうしても手元に置いておきたくなるものがあると年に一、二冊は買うことがある。
今年は川内倫子の写真集「うたたね」を買った。今までぼくが買った写真集とは大分傾向が異なる。彼女独特の色合いと視線。日常の何気ないシーンが主にスクエアーの画面の中に展開されている。
写真集の帯には「うたたね」というタイトルの上に「死んでしまうということ」と書いてある。見開いたページの左右に一枚づつの写真。丁寧に日常を見つめた何気ないシーンに少しづつ死の匂いが漂い始める。

何気ない日常こそが死と隣り合わせにあるのだと言いたいのか。それともそうだからこそ何気ない日常が愛おしいというのか。それとも…。どう解釈しようともそれは美術史家のゴンブリッジの言う「鑑賞者の取り分」の範疇なのだろうが、見るたびに感ずるところがある。この写真集には「うたたね」というタイトル以外に文字は一切ない。

(Dec.2022)
Museum of the Month 新版画 進化系UKIYO-Eの美
Museum of the Month...
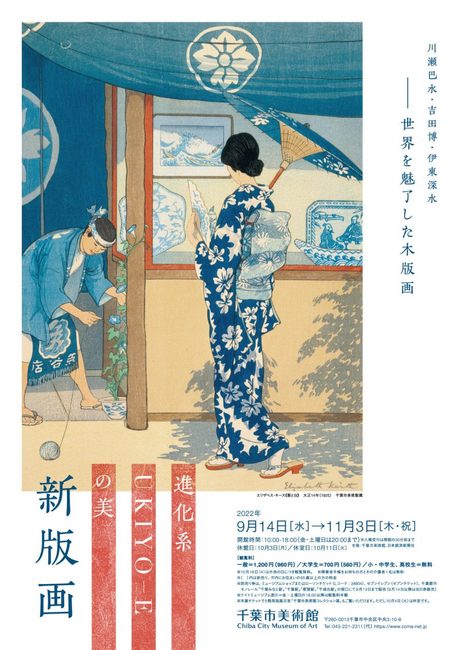
[印象メモ]
コロナ禍でいくつもの気になっていた展覧会を見逃したけれど流石にそろそろ我慢の限界に来た。ということで予約制が解けた美術展も多くなって来たからこちらも動き始めた。
手始めに千葉市美術館の新版画展に行くことにした。ここはまず混んでいることはないのと、昨年の1月に開かれた「田中一村展 ―千葉市美術館収蔵全作品展」を見損なったリベンジみたいな気持ちがあった。
結果、行ってみて大正解。川瀬巴水、伊藤深水から吉田博そしてフリッツ・カペラリやヘレン・ハイドそしてバーサ・ラム等往年の外国人による新版画など実に多岐にわたり、かつ膨大な作品数の展示が素晴らしかった。
千葉市美術館の新版画の所蔵も凄いし、加えて学芸員の西山さんの的確な審美眼もこの美術館の活動を支えていると感じた。それにしてもいつも感じるのは今回の美術展もそうなのだけれど、素晴らしい内容なのに当日も会場で見かけたのはほんの数名の人影。平日だったからかもしれないが、落ち着いてゆっくり見られるのは嬉しいけれど、何とももったいない気がした。
新版画展
東京十二か月三十間堀の暮雪

川瀬巴水(1920)
巴水の意欲作として有名な作品。場所は今の銀座あたりらしいが川を挟んで向かい側にある建物が東京にしては珍しい吹雪のような激しい雪でかすんでいる。雪の激しさを表すために版木を砥石やタワシでこすって凹凸をつけたと言われる。当時革新的だった版元の渡邉庄三郎の下での意欲的な取り組みと思う。
新美人十二姿 虫の音

伊東深水(1923)
日本画で中々芽が出ない川瀬巴水に版画を薦めたのは伊東深水と言われるように深水は早くから日本画と同時に版画に取り組んでいた。その作風は彼の美人画にあるように女性の楚々とした姿が印象的。このシリーズは渡邉版画店の予約会員に毎月一枚づつリリースされたようだ。それまでの版画の美人図とは異なりとても現代的に感じられる。
五位鷺

小原古邨(1912)
古邨は鷺が好きらしく色々な鷺を描いている。ぼくも小原祥邨時代に渡邊庄三郎のところで出した春先の鷺を描いたものの後摺りを持っているけど清々しい感じがする。それに対してこの五位鷺はどこかドスがきいている。三日月の輝く葦の原でじっと瞑想しているような。構図も決まっている。
今戸夏月

小林清親(1881)
小林清親は浮世絵に西洋的な技巧、視点を取り入れて新版画の先駆的な作家だと思う。清親の時代の浮世絵は洋紅と呼ばれる毒々しい赤色を使った開花絵が多いが、ぼくはそれは余り好きではない。清親の絵は当時としてはどちらかと言えば色は抑え目でパースペクティブな構図などに重きを置いていた。この絵では芸者がひとつのお座敷が終わってランプのともる部屋でこれからのお座敷のために三味線の調子を調べているような情景に見える。
入浴

ヘレン・ハイド(1905)
会場には別コーナーとしてヘレン・ハイドそしてバーサ・ラムのかなり充実した展示がなされていた。ヘレンはアメリカの版画家で1899年に来日しフェノロサや狩野友信やバーナード・リーチなどの教えも受けていたらしい。このヘレンやバーサ・ラムなどの版画は日本人の版画家の作品に比べて色彩が全体に淡いのが印象的だった。彼女は母子の情景を描いた浮世絵が好きだったようで、同じ嗜好を持っていたメアリー・カサットの影響もあるようだ。

[関連書籍]
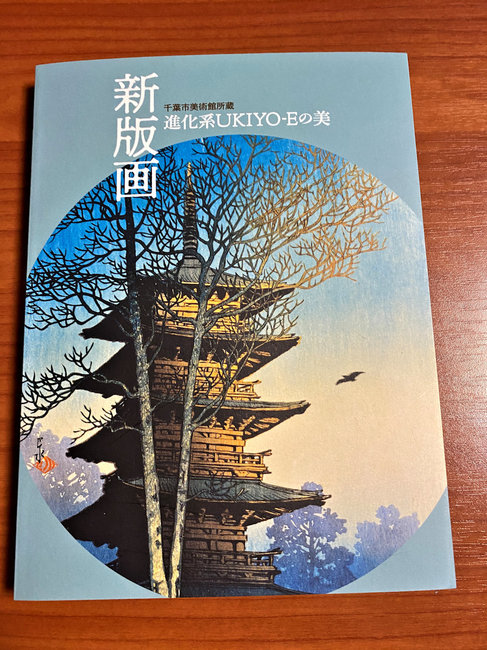
新版画/進化系UKIYO-Eの美
169頁、2300円。今回の展覧会の図録にもなっているが同時に別枠で展示されていたヘレン・ハイドそしてバーサ・ラムの作品は収録されていない。図録のタイトルには千葉市美術館所蔵と銘打ってあるところはいかにも版画作品の充実した所蔵を有している当美術館の誇りのようなものが感じられる。
東京人No.451 新版画と東京

今回の展覧会とは直接関連はないが、ぼくの好きな雑誌である「東京人」の今年の三月号がまさに新版画と東京という特集だったので、この展覧会と合わせて読むと興味深い。記事の中には川瀬巴水等の版画のコレクターとしても有名だったスティーブ・ジョブズのエピソードなども載っていて楽しい。
新版画 進化系UKIYO-Eの美
千葉市美術館
2022年9月14日~11月3日
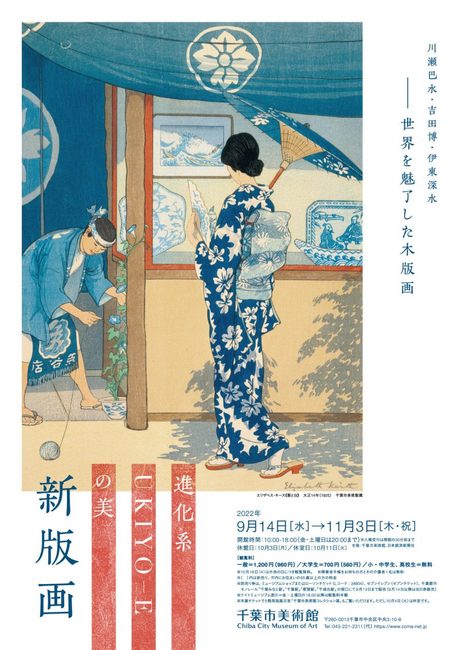
[印象メモ]
コロナ禍でいくつもの気になっていた展覧会を見逃したけれど流石にそろそろ我慢の限界に来た。ということで予約制が解けた美術展も多くなって来たからこちらも動き始めた。
手始めに千葉市美術館の新版画展に行くことにした。ここはまず混んでいることはないのと、昨年の1月に開かれた「田中一村展 ―千葉市美術館収蔵全作品展」を見損なったリベンジみたいな気持ちがあった。
結果、行ってみて大正解。川瀬巴水、伊藤深水から吉田博そしてフリッツ・カペラリやヘレン・ハイドそしてバーサ・ラム等往年の外国人による新版画など実に多岐にわたり、かつ膨大な作品数の展示が素晴らしかった。
千葉市美術館の新版画の所蔵も凄いし、加えて学芸員の西山さんの的確な審美眼もこの美術館の活動を支えていると感じた。それにしてもいつも感じるのは今回の美術展もそうなのだけれど、素晴らしい内容なのに当日も会場で見かけたのはほんの数名の人影。平日だったからかもしれないが、落ち着いてゆっくり見られるのは嬉しいけれど、何とももったいない気がした。
新版画展
My Best 5
東京十二か月三十間堀の暮雪
川瀬巴水(1920)
巴水の意欲作として有名な作品。場所は今の銀座あたりらしいが川を挟んで向かい側にある建物が東京にしては珍しい吹雪のような激しい雪でかすんでいる。雪の激しさを表すために版木を砥石やタワシでこすって凹凸をつけたと言われる。当時革新的だった版元の渡邉庄三郎の下での意欲的な取り組みと思う。
新美人十二姿 虫の音
伊東深水(1923)
日本画で中々芽が出ない川瀬巴水に版画を薦めたのは伊東深水と言われるように深水は早くから日本画と同時に版画に取り組んでいた。その作風は彼の美人画にあるように女性の楚々とした姿が印象的。このシリーズは渡邉版画店の予約会員に毎月一枚づつリリースされたようだ。それまでの版画の美人図とは異なりとても現代的に感じられる。
五位鷺
小原古邨(1912)
古邨は鷺が好きらしく色々な鷺を描いている。ぼくも小原祥邨時代に渡邊庄三郎のところで出した春先の鷺を描いたものの後摺りを持っているけど清々しい感じがする。それに対してこの五位鷺はどこかドスがきいている。三日月の輝く葦の原でじっと瞑想しているような。構図も決まっている。
今戸夏月
小林清親(1881)
小林清親は浮世絵に西洋的な技巧、視点を取り入れて新版画の先駆的な作家だと思う。清親の時代の浮世絵は洋紅と呼ばれる毒々しい赤色を使った開花絵が多いが、ぼくはそれは余り好きではない。清親の絵は当時としてはどちらかと言えば色は抑え目でパースペクティブな構図などに重きを置いていた。この絵では芸者がひとつのお座敷が終わってランプのともる部屋でこれからのお座敷のために三味線の調子を調べているような情景に見える。
入浴
ヘレン・ハイド(1905)
会場には別コーナーとしてヘレン・ハイドそしてバーサ・ラムのかなり充実した展示がなされていた。ヘレンはアメリカの版画家で1899年に来日しフェノロサや狩野友信やバーナード・リーチなどの教えも受けていたらしい。このヘレンやバーサ・ラムなどの版画は日本人の版画家の作品に比べて色彩が全体に淡いのが印象的だった。彼女は母子の情景を描いた浮世絵が好きだったようで、同じ嗜好を持っていたメアリー・カサットの影響もあるようだ。
[関連書籍]
新版画/進化系UKIYO-Eの美
169頁、2300円。今回の展覧会の図録にもなっているが同時に別枠で展示されていたヘレン・ハイドそしてバーサ・ラムの作品は収録されていない。図録のタイトルには千葉市美術館所蔵と銘打ってあるところはいかにも版画作品の充実した所蔵を有している当美術館の誇りのようなものが感じられる。
東京人No.451 新版画と東京
今回の展覧会とは直接関連はないが、ぼくの好きな雑誌である「東京人」の今年の三月号がまさに新版画と東京という特集だったので、この展覧会と合わせて読むと興味深い。記事の中には川瀬巴水等の版画のコレクターとしても有名だったスティーブ・ジョブズのエピソードなども載っていて楽しい。
(Oct.2022)
Museum of the Month THE新版画
Museum of the Month...

[感想メモ]
茅ケ崎市美術館は、原安三郎のコレクションから新たに発見されたものも含めて240点が一斉に公開された2018年の「小原古邨展」以来の久しぶりの訪問なのだけれど、今回は版元、渡邊庄三郎の挑戦と銘打った「THE 新版画」展だった。
先月行った千葉市美術館での「新版画 進化系UKIYO-Eの美」展と合わせると今年はちょっと集中的に版画展を観ていることになるのだけれど、コロナ明け(まだそうは言えないとは思うが)の美術館訪問再開の皮切りとしては悪くない。内容は重複している所もあるが、今回は新版画を世に送った版元、渡邊庄三郎を中心に組み立てているのでまた一味違ったものになっている。
先の「小原古邨展」では新発見の作品が多数公開されるということでここも最終日には1時間待ちの行列ができたけれど、今回は会場には平日ということもあってまばらな観客が居たのみで閑散としていた。ここは原安三郎の別荘跡ということもあって(それ以前は川上音二郎と貞奴の邸宅)版画にはゆかりの地なのだが…。
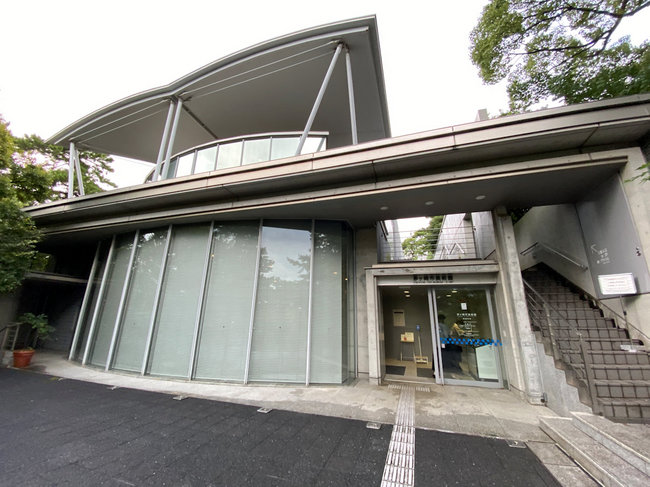
THE新版画展
ホノルル波乗り(1919)
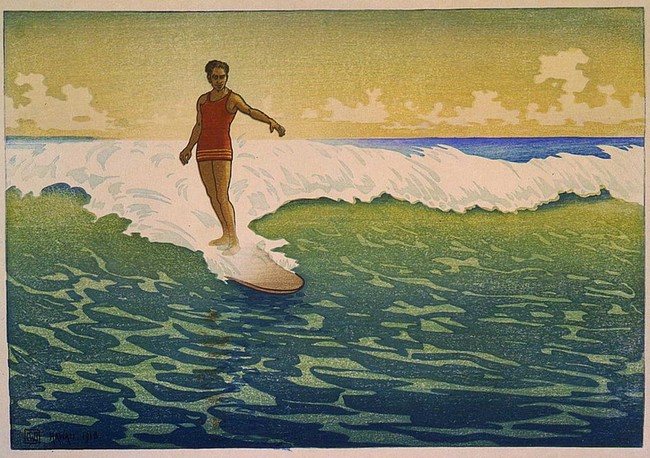
チャールズ・W・バートレット
イギリス人バートレットは来日して渡邊庄三郎のところで浮世絵や版画の技法を活かして当時の日本の様子やアジアなどの風景を浮世絵版画で制作していた。その後イギリスへの帰国途中で立ち寄ったハワイが気に入り永住することに。この版画はハワイの伝説的サーファー、デューク・カハナモクがサーフィンをしているシーンなのだが、もう浮世絵の模倣ではなく新版画の技法が完全に彼の表現手段として成り立っているように思う。本展覧会のパンフレットにも載っているように彼にはサーフィンの連作がある。バートレットは後にホノルル美術館の創設者になる。
猟師の話(1922)

吉田博
本展には吉田博の作品も展示されていたがその中でもこの作品は異彩を放っていた。彼はこの作品で洋画の筆致や題材を版画で表現しようとしたらしいが、確かに一見して他の新版画の作品とは異なっている。もともと吉田は洋画家出身でこの作品は庄三郎の下で最初期に取り組んだ作品で、これはその試し刷りのようだ。吉田はその後庄三郎の下を離れて自分の新版画の道を行くことになる。
吹雪(1932)

伊東深水
深水は版画の世界では川瀬巴水の先輩にあたる。会場には何点か深水の風景版画も展示されていたが、やはり深水の美人画は版画の世界でも白眉であることは間違いない。この作品は現代美人集第二輯に収められた作品で、このタイトル「吹雪」では多分同じような構図の別の作品の方が知られていると思うけど、ぼくはこちらの方が好きだ。降りしきる雪を傘で除けながら歩む女性が何かの拍子にふと足元に目をやる、日本舞踊のような仕草が歌舞伎の見栄を切った一瞬のように決まっている。
雪中群鷺(昭和初期)

小原祥邨
小原古邨は版元渡邊庄三郎のところでは小原祥邨と名乗っていた。古邨は鷺が好きらしく庄三郎のもとでも多くの鷺の作品を残している。柳の新芽が芽吹いた春先、二羽の鷺が飛び立つ「柳に白鷺」はぼくも後刷りをもっている好きな作品だけれども、この「雪中群鷺」はそうした鷺を扱った作品の中でも一番好きな作品だ。五羽の鷺の配置と全体の構図が雪中で寒さに耐える鷺の凛とした姿を的確に表している。
湯宿の朝(塩原新湯)(1946)

川瀬巴水
巴水に縁の深い塩原の温泉宿の窓外風景なのだが、この作品に初めて触れたのは2013年に大田区立郷土博物館で行われた「川瀬巴水展」だったと思う。今回はこの一枚だけが飾られているが、大田区郷土博物館では山や空そして障子の色合いが微妙に異なる薄刷版、濃刷版などが展示されていた。川瀬巴水や吉田博は一つの版木で色などを変えることで、同じ場所の季節や時間などの変化を付けた複数の作品を作るという手法を使うことがあるが、これはもう少し微妙な変化をつけたいくつかの作品があるということなのかもしれない。
[図録]
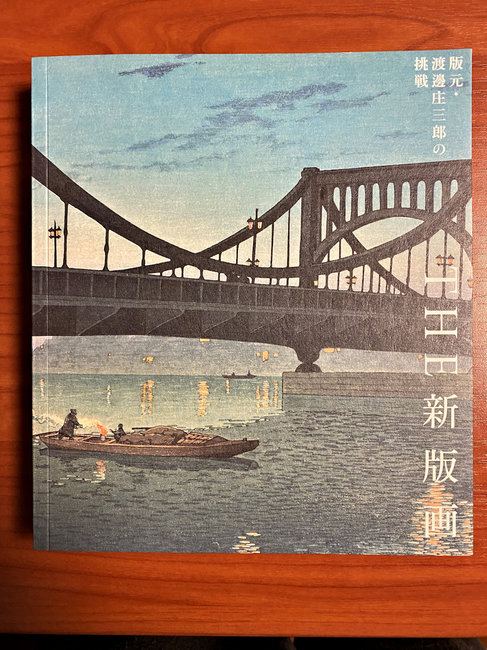
264頁、2500円。大変見やすい図録になっている。版元、渡邊庄三郎を軸とした新版画の流れが作品と解説で分かりやすく構成されている。展示作品の何所かにも表示されていた庄三郎マークのついた庄三郎目線の口語体の解説も図録にも載っていてこれも楽しめる。
THE 新版画
版元 渡邊庄三郎の挑戦
茅ケ崎市美術館
2022年9月10日~11月6日
[感想メモ]
茅ケ崎市美術館は、原安三郎のコレクションから新たに発見されたものも含めて240点が一斉に公開された2018年の「小原古邨展」以来の久しぶりの訪問なのだけれど、今回は版元、渡邊庄三郎の挑戦と銘打った「THE 新版画」展だった。
先月行った千葉市美術館での「新版画 進化系UKIYO-Eの美」展と合わせると今年はちょっと集中的に版画展を観ていることになるのだけれど、コロナ明け(まだそうは言えないとは思うが)の美術館訪問再開の皮切りとしては悪くない。内容は重複している所もあるが、今回は新版画を世に送った版元、渡邊庄三郎を中心に組み立てているのでまた一味違ったものになっている。
先の「小原古邨展」では新発見の作品が多数公開されるということでここも最終日には1時間待ちの行列ができたけれど、今回は会場には平日ということもあってまばらな観客が居たのみで閑散としていた。ここは原安三郎の別荘跡ということもあって(それ以前は川上音二郎と貞奴の邸宅)版画にはゆかりの地なのだが…。
THE新版画展
My Best5
ホノルル波乗り(1919)
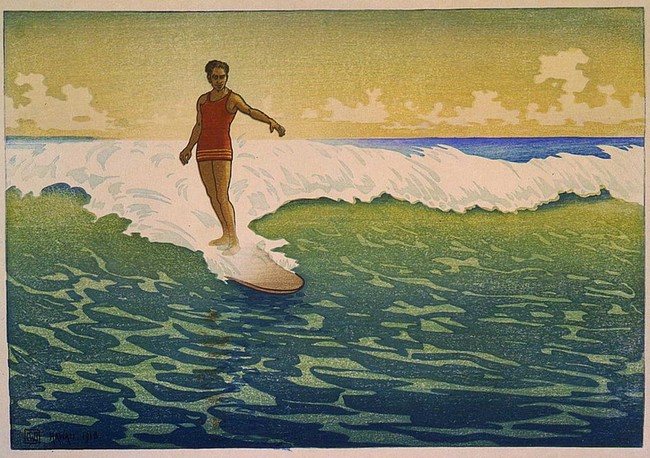
チャールズ・W・バートレット
イギリス人バートレットは来日して渡邊庄三郎のところで浮世絵や版画の技法を活かして当時の日本の様子やアジアなどの風景を浮世絵版画で制作していた。その後イギリスへの帰国途中で立ち寄ったハワイが気に入り永住することに。この版画はハワイの伝説的サーファー、デューク・カハナモクがサーフィンをしているシーンなのだが、もう浮世絵の模倣ではなく新版画の技法が完全に彼の表現手段として成り立っているように思う。本展覧会のパンフレットにも載っているように彼にはサーフィンの連作がある。バートレットは後にホノルル美術館の創設者になる。
猟師の話(1922)

吉田博
本展には吉田博の作品も展示されていたがその中でもこの作品は異彩を放っていた。彼はこの作品で洋画の筆致や題材を版画で表現しようとしたらしいが、確かに一見して他の新版画の作品とは異なっている。もともと吉田は洋画家出身でこの作品は庄三郎の下で最初期に取り組んだ作品で、これはその試し刷りのようだ。吉田はその後庄三郎の下を離れて自分の新版画の道を行くことになる。
吹雪(1932)

伊東深水
深水は版画の世界では川瀬巴水の先輩にあたる。会場には何点か深水の風景版画も展示されていたが、やはり深水の美人画は版画の世界でも白眉であることは間違いない。この作品は現代美人集第二輯に収められた作品で、このタイトル「吹雪」では多分同じような構図の別の作品の方が知られていると思うけど、ぼくはこちらの方が好きだ。降りしきる雪を傘で除けながら歩む女性が何かの拍子にふと足元に目をやる、日本舞踊のような仕草が歌舞伎の見栄を切った一瞬のように決まっている。
雪中群鷺(昭和初期)

小原祥邨
小原古邨は版元渡邊庄三郎のところでは小原祥邨と名乗っていた。古邨は鷺が好きらしく庄三郎のもとでも多くの鷺の作品を残している。柳の新芽が芽吹いた春先、二羽の鷺が飛び立つ「柳に白鷺」はぼくも後刷りをもっている好きな作品だけれども、この「雪中群鷺」はそうした鷺を扱った作品の中でも一番好きな作品だ。五羽の鷺の配置と全体の構図が雪中で寒さに耐える鷺の凛とした姿を的確に表している。
湯宿の朝(塩原新湯)(1946)

川瀬巴水
巴水に縁の深い塩原の温泉宿の窓外風景なのだが、この作品に初めて触れたのは2013年に大田区立郷土博物館で行われた「川瀬巴水展」だったと思う。今回はこの一枚だけが飾られているが、大田区郷土博物館では山や空そして障子の色合いが微妙に異なる薄刷版、濃刷版などが展示されていた。川瀬巴水や吉田博は一つの版木で色などを変えることで、同じ場所の季節や時間などの変化を付けた複数の作品を作るという手法を使うことがあるが、これはもう少し微妙な変化をつけたいくつかの作品があるということなのかもしれない。
[図録]
264頁、2500円。大変見やすい図録になっている。版元、渡邊庄三郎を軸とした新版画の流れが作品と解説で分かりやすく構成されている。展示作品の何所かにも表示されていた庄三郎マークのついた庄三郎目線の口語体の解説も図録にも載っていてこれも楽しめる。
(Oct.2022)
gillman*s Museums 本城直季展
Museum of the Month...
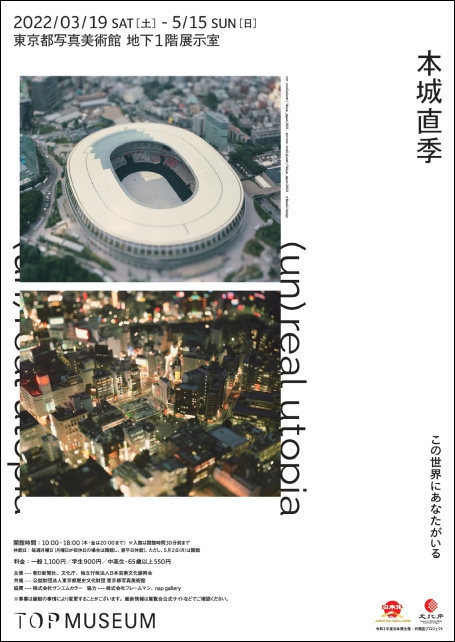
本城直季の写真を初めて見たのは20年くらい前だと思う。当時彼のブログに載っている写真を見てとても不思議な気持ちになったのを覚えている。それ以来彼の写真が気になっていた。高い視線からカメラの「あおり」を使ってまるでジオラマのような、おもちゃの街のような不思議な写真を撮る。

人によってはそれを「神の視線」と呼ぶ人もいるけど、彼に言わせればそれは逆に人の視線そのものでもある。全体を見渡す広い視角の中で彼の写真はごく狭い一点だけに焦点があっている。それ以外の場所はぼけて詳細な姿は描かれていない。実は人間の視覚もそうだという。というのは人間の視角はとても広いのだけれど、実際に脳が詳細に把握するのはその中の関心が向いている狭い領域で、そこは細部まで見えているけれどもそれ以外の所はボケたイメージになっているという。
高い視点からの写真と言うのはドローンの普及した現在で言えば決して珍しいものではないかもしれないけれど、彼の写真は単に俯瞰ということだけではないと思う。彼の写真では例え見慣れた場所であってもまるで異界の世界のように感じられる。それはいわゆる客観的視点というものとも違う。少なくともどこかにはフォーカスがあたっており、そこは主観の匂いがする。そういう意味ではアンドレアス・グルスキーの透徹した俯瞰ともまた違っている。
写真展は予約制になっていたけどネットで見ると当日分のチケットは満杯だったので直接会場に行ったら人もまばらで、しかもネットでは一般料金しかないのだけれどシニア料金で入ることができた。聞けばネットのチケットはかなり数を絞っているみたいだった。会場では一枚一枚の写真を寄って観たり、離れて観たりゆったりと本城ジオラマの世界を楽しむことができた。
■Small Planet
ぼくの一番好きな写真集Small Planetからの展示写真。
東京タワー、プール、千葉競馬場そしてストックホルム郊外の草原。特に最後のストックホルム郊外の写真が好きだ。
緑の草原の中に一本の道が通っている。そこに一台の赤い車。フォーカスはその車の居る一本の道に沿ってあてられている。現実的でそして夢のような世界。




■Ginza Six建設現場の壁面写真
銀座松坂屋の跡地に建設されたGinza Sixの建設現場に建てられた仮設の壁面には本城直季氏の写真が使われていた。建設中の2015年の冬、銀座に行った時に何度かその壁面を撮りに行った。彼の写真が銀座の道を行く人ととてもいい感じでマッチしていて、いずれ撤去されてしまうのがもったいないと思った。
写真のユニークな新しい使い方として今でも思い出に残っている。自分でも何度かジオラマ風の写真を撮ってみたけれど様にならない。下手なこともあるけど自分の中から出た表現でないからだなぁ。
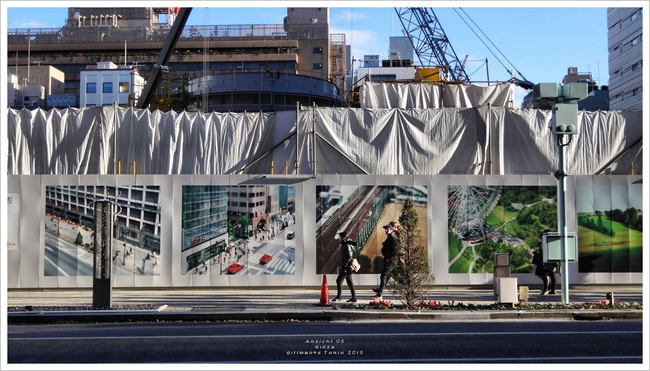



[図録写真集]

3300円。構成はSmall Planet~Daily Photosまで展示構成に従って出展作品の写真が掲載されているので、今まで彼が出した写真集のエッセンスが詰まっているともいえるけれど、作品の写真がそのまま出ているというより、細部をアップにしたものも多い。さらに全体の写真が載せられている場合でもページ跨りで載っていることが多くそれもちょっと気になる。
出来ればこの図録のように縦長ではなくて彼の写真集Small Planetのように横長の体裁にしてほしかったのだけれど、それは個々の写真集を買って見てくれという事かもしれないし、それは展示会場でじっくりと味わってほしいという事なのだろうと思うが、高い写真集をそう何冊も買うわけにはいかないぼくのような者にとってはこの図録を買うか、気に入った写真集の方を買うか迷うところだ。

(un)real utopia
本城直季 写真展東京都写真美術館
2022年3月19日~5月15日
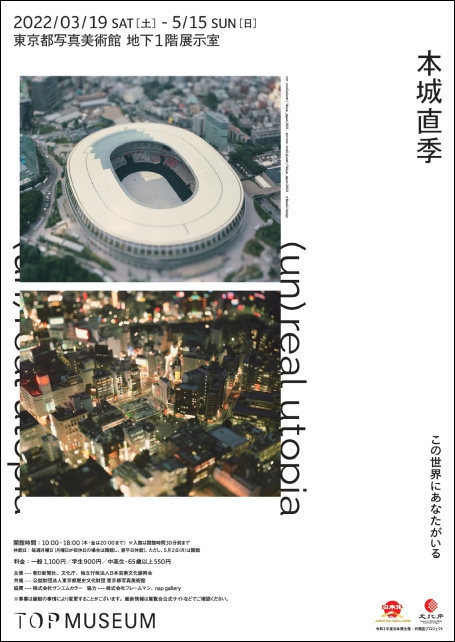
本城直季の写真を初めて見たのは20年くらい前だと思う。当時彼のブログに載っている写真を見てとても不思議な気持ちになったのを覚えている。それ以来彼の写真が気になっていた。高い視線からカメラの「あおり」を使ってまるでジオラマのような、おもちゃの街のような不思議な写真を撮る。
人によってはそれを「神の視線」と呼ぶ人もいるけど、彼に言わせればそれは逆に人の視線そのものでもある。全体を見渡す広い視角の中で彼の写真はごく狭い一点だけに焦点があっている。それ以外の場所はぼけて詳細な姿は描かれていない。実は人間の視覚もそうだという。というのは人間の視角はとても広いのだけれど、実際に脳が詳細に把握するのはその中の関心が向いている狭い領域で、そこは細部まで見えているけれどもそれ以外の所はボケたイメージになっているという。
高い視点からの写真と言うのはドローンの普及した現在で言えば決して珍しいものではないかもしれないけれど、彼の写真は単に俯瞰ということだけではないと思う。彼の写真では例え見慣れた場所であってもまるで異界の世界のように感じられる。それはいわゆる客観的視点というものとも違う。少なくともどこかにはフォーカスがあたっており、そこは主観の匂いがする。そういう意味ではアンドレアス・グルスキーの透徹した俯瞰ともまた違っている。
写真展は予約制になっていたけどネットで見ると当日分のチケットは満杯だったので直接会場に行ったら人もまばらで、しかもネットでは一般料金しかないのだけれどシニア料金で入ることができた。聞けばネットのチケットはかなり数を絞っているみたいだった。会場では一枚一枚の写真を寄って観たり、離れて観たりゆったりと本城ジオラマの世界を楽しむことができた。
■Small Planet
ぼくの一番好きな写真集Small Planetからの展示写真。
東京タワー、プール、千葉競馬場そしてストックホルム郊外の草原。特に最後のストックホルム郊外の写真が好きだ。
緑の草原の中に一本の道が通っている。そこに一台の赤い車。フォーカスはその車の居る一本の道に沿ってあてられている。現実的でそして夢のような世界。
■Ginza Six建設現場の壁面写真
銀座松坂屋の跡地に建設されたGinza Sixの建設現場に建てられた仮設の壁面には本城直季氏の写真が使われていた。建設中の2015年の冬、銀座に行った時に何度かその壁面を撮りに行った。彼の写真が銀座の道を行く人ととてもいい感じでマッチしていて、いずれ撤去されてしまうのがもったいないと思った。
写真のユニークな新しい使い方として今でも思い出に残っている。自分でも何度かジオラマ風の写真を撮ってみたけれど様にならない。下手なこともあるけど自分の中から出た表現でないからだなぁ。

[図録写真集]
3300円。構成はSmall Planet~Daily Photosまで展示構成に従って出展作品の写真が掲載されているので、今まで彼が出した写真集のエッセンスが詰まっているともいえるけれど、作品の写真がそのまま出ているというより、細部をアップにしたものも多い。さらに全体の写真が載せられている場合でもページ跨りで載っていることが多くそれもちょっと気になる。
出来ればこの図録のように縦長ではなくて彼の写真集Small Planetのように横長の体裁にしてほしかったのだけれど、それは個々の写真集を買って見てくれという事かもしれないし、それは展示会場でじっくりと味わってほしいという事なのだろうと思うが、高い写真集をそう何冊も買うわけにはいかないぼくのような者にとってはこの図録を買うか、気に入った写真集の方を買うか迷うところだ。
(May 2022)
Museum of the Month メトロポリタン美術館展
Museum of the Month...


[感想メモ]
ヨーロッパの美術館は昔から比較的よく見ている方だと思っていたけど、アメリカの美術館は見たことがないし、考えてみたらアメリカにも行ったことがなかった。ということでこのまま行くと本当に行かずじまいになってしまうと思って、2年前に思い切ってアメリカの美術館を巡るツアーを申し込んだ。
主要な目的はヨーロッパの美術館では殆ど観ることができないエドワード・ホッパーやアンドリュー・ワイエスの絵だったのだけれど、他にはもちろんこのメトロポリタン美術館も含まれていた。けど…、全てはこのコロナ禍でキャンセルになってしまった。
そんな時に国立新美術館での「メトロポリタン美術館展」が開催されたのは嬉しい限り。500年の西洋絵画史を駆け足でというのもすごいけど、実際に大美術館に足を運んで行ってみるとじっくりと見られる点数は意外と少ないことを想うと、充分にありがたい。同美術館の展示改修が無かったらこれほどの作品も見られなかったというのも幸運だったかもしれない。
玉座の聖母子と二人の天使/フラ・フィリッポ・リッピ(ca.1440)

この絵は元はトリプティーク(三連画)の中央部分であったらしい。この聖母子像も伝統にのっとって安定した三角構図によって描かれているが、その表現はより現実的で生身の人間ぽくなっていると思う。特に幼子キリストの表情は今までの紋切り型の子供顔ではなく観るものを睨みつけるような威厳と迫力がある。
リッピはフラと名前についているように元来修道士なのだけれど、50歳の時に23歳の修道女と駆け落ちし子供をつくるなど破天荒なところがある人物だったらしい。ここら辺はカラヴァッジョと相通じるものがあるかもしれないが、絵に関しては優れた才能を示しなによりもあのボッティチェリの師匠としても後世に名を残している。
ベネディクト・フォン・ヘルテンシュタイン/ハンス・ホルバイン(1517)

ホルバインの肖像画を見るとその人物の息遣いまで伝わってきそうで、これが16世紀初頭の作品だとは思えないほどのリアリティーに驚かされる。ホルバインは南ドイツで生まれたが活動はスイスやまた特にイギリスで活動した時期が長い。
この肖像画のベネディクト・フォン・ヘルテンシュタインは当時のルツェルンの市長の息子で、まだ22歳だが学業を終えて州議会のメンバーになったばかりのようだ。肖像画はその記念という事もあるのかもしれない。(実はこれを描いているホルバイン自身もまだ20歳前後だったと思われる) フォン・ヘルテンシュタイン家の才気ある後継者としての輝きと、その期待を背負っている照れのようなものまで感じさせる。しかしこの数年後彼はイタリア戦争の戦いで命を落とすことになるのだけれど…。
音楽家たち/カラヴァッジョ(1597)

展覧会場の遠目からもすぐ分かる、どこからどう見てもカラヴァッジョの絵である。この絵の中央のヌメッとした感じの美少年は2016年に国立西洋美術館で行われた「カラヴァッジョ展」に展示されていた「トカゲに噛まれる少年(ca.1596)」や「バッカス(ca.1597)」に描かれている美少年群の一人だろうと思われる。
カラヴァッジョのパトロンであったデル・モンテ枢機卿のもとに集められていた美少年達を描いたもので後ろでこちらを向いているのはカラヴァッジョ自身と言われているらしい。彼の画力から言えば描かれた姿はカラヴァッジョ本人にそっくりなはずで、ということはこの雰囲気に難なく馴染んでいた人物のような気がして、乱暴で無頼漢の彼のイメージとはまた違った印象を持った。一説によるとカラヴァッジョはバイセクシャルだったという話もあるので、それもあるかもしれない。
信仰の寓意/ヨハネス・フェルメール(ca.1670)

フェルメールの作品は比較的小さなものが多いけど、これは彼にしてはかなり大きい方の作品に属すると思う。以前ウィーンで観た「絵画芸術」も大きいけれどそれよりも少し大きいかもしれない。でも、正直言ってあまりフェルメールっぽくはない。
勿論よく見ると球体のガラスに写り込む室内の様子だったり、ドレスに現れる光の玉だったり、画面左のカーテンだったり彼らしい表現はそこここに散見されるけどどうも全体が…。というのもこの絵の発注主がカソリック教徒だったらしく、恐らくはそのリクエストでタイトルのように宗教的寓意がそこここに込められているのだ。(フェルメール自身もプロテスタントからカソリックに改宗しているが、宗教的な理由だけだったのかは疑問が残るような…)
当時はオランダはプロテスタント国家で絵画界の顧客は既に教会から市民に移っていたのだけれど数少ないカソリック信者が家の中にカソリック的世界を作るために宗教的寓意に満ちたものを頼んだらしい。女性が地球儀を踏んずけているのはカソリック教が世界を広く支配する事の寓意らしいが、ここら辺はもしかしたら当時のオランダでも既にアナクロだったのではないかとぼくは邪推したりしている。
テラスの陽気な集い/ヤン・ステーン(ca.1670)

ステーンはライデン生まれの画家で風俗画を多く描いている。絵に寓意が込められていることもあるけれど、当時の風俗を見たり想像したりするだけでも楽しいし、観察眼の鋭いステーンは観るものが退屈しないように細かい所に仕掛けをしていたりもする。
猥雑な感じのするこの絵も、登場人物の一人一人を見てその台詞なんかを考えてみると退屈しない。そうこうしている内に視線はどうしても中央の女将の胸元に…吸いつけられる。ステーンもそのつもりで描いている。彼女にじっと見つめられて、エプロンをはだけて「ねぇ…」と。 うっ、と戸惑って固まっているこちらを、画面左にいるでっぷりと太ったステーン自身がそれを見て大笑いをしている。
ガルダンヌ/ポール・セザンヌ(ca.1885)

正直言ってセザンヌの本当の良さはぼくには分かっていないと思う。ぼくの頭の中ではセザンヌはあのアンリ・ルソーと同じような位置にいると言ったら、大半の人が異を唱えて、しかしほんの少しの人が頷くかもしれない。ぼくの中では彼はそういうような立ち位置にある。ついでにアンリ・ルソーはぼくの大好きな画家であることも言っておかないといけないかもしれないが…。
このカルダンヌ村はセザンヌのいたエクスの南にある小さな村だ。この絵を観ているとセザンヌが風景を忠実に描こうというより、この風景を四角や三角のエレメントに再構成して全体としての風景を構成してゆこうとしている感じが、ぼくにでも比較的容易に感じられるという点で気に入っている。


[図録]

228頁、2900円。ここのところ図録の値段がじわりと上がってきている。コロナ禍で入場者も見込めず印刷部数が減れば一冊当たりの制作費用がかさんでくることもあるのかもしれない。
構成は展示に従って①信仰とルネサンス、②絶対主義と啓蒙主義の時代、③革命と人々のための芸術、の3部に分かれている。内容は典型的な図録で全ての作品に図と解説がついているのはありがたいが、折角3部に分けたのだから会場にあったように、各部の最初にその時代の概観的な解説を載せておいてほしかった。
会場の展示では目ぼしい作品には短い解説がこまめに書かれていたのでオーディオガイドがなくてもスムーズに流れを追うことができたように思う。
[蛇足]
国立新美術館にいくといつも必ず寄る美術館のすぐそばの中華料理屋に久しぶりに行った。昼時を少し外したのでちょっと待たされたけど意外と速く入店できた。そこは二階席もあるのだけれど、店員さんに聞くと客足とか、バイトさんの確保とか先行きが見通せないので二階は閉めているという。好きなお店なのでなんとか切り抜けて欲しいなと思った。


メトロポリタン
美術館展
国立新美術館
2022年2月9日~5月30日


[感想メモ]
ヨーロッパの美術館は昔から比較的よく見ている方だと思っていたけど、アメリカの美術館は見たことがないし、考えてみたらアメリカにも行ったことがなかった。ということでこのまま行くと本当に行かずじまいになってしまうと思って、2年前に思い切ってアメリカの美術館を巡るツアーを申し込んだ。
主要な目的はヨーロッパの美術館では殆ど観ることができないエドワード・ホッパーやアンドリュー・ワイエスの絵だったのだけれど、他にはもちろんこのメトロポリタン美術館も含まれていた。けど…、全てはこのコロナ禍でキャンセルになってしまった。
そんな時に国立新美術館での「メトロポリタン美術館展」が開催されたのは嬉しい限り。500年の西洋絵画史を駆け足でというのもすごいけど、実際に大美術館に足を運んで行ってみるとじっくりと見られる点数は意外と少ないことを想うと、充分にありがたい。同美術館の展示改修が無かったらこれほどの作品も見られなかったというのも幸運だったかもしれない。
MY BEST 5+1
玉座の聖母子と二人の天使/フラ・フィリッポ・リッピ(ca.1440)

この絵は元はトリプティーク(三連画)の中央部分であったらしい。この聖母子像も伝統にのっとって安定した三角構図によって描かれているが、その表現はより現実的で生身の人間ぽくなっていると思う。特に幼子キリストの表情は今までの紋切り型の子供顔ではなく観るものを睨みつけるような威厳と迫力がある。
リッピはフラと名前についているように元来修道士なのだけれど、50歳の時に23歳の修道女と駆け落ちし子供をつくるなど破天荒なところがある人物だったらしい。ここら辺はカラヴァッジョと相通じるものがあるかもしれないが、絵に関しては優れた才能を示しなによりもあのボッティチェリの師匠としても後世に名を残している。
ベネディクト・フォン・ヘルテンシュタイン/ハンス・ホルバイン(1517)

ホルバインの肖像画を見るとその人物の息遣いまで伝わってきそうで、これが16世紀初頭の作品だとは思えないほどのリアリティーに驚かされる。ホルバインは南ドイツで生まれたが活動はスイスやまた特にイギリスで活動した時期が長い。
この肖像画のベネディクト・フォン・ヘルテンシュタインは当時のルツェルンの市長の息子で、まだ22歳だが学業を終えて州議会のメンバーになったばかりのようだ。肖像画はその記念という事もあるのかもしれない。(実はこれを描いているホルバイン自身もまだ20歳前後だったと思われる) フォン・ヘルテンシュタイン家の才気ある後継者としての輝きと、その期待を背負っている照れのようなものまで感じさせる。しかしこの数年後彼はイタリア戦争の戦いで命を落とすことになるのだけれど…。
音楽家たち/カラヴァッジョ(1597)

展覧会場の遠目からもすぐ分かる、どこからどう見てもカラヴァッジョの絵である。この絵の中央のヌメッとした感じの美少年は2016年に国立西洋美術館で行われた「カラヴァッジョ展」に展示されていた「トカゲに噛まれる少年(ca.1596)」や「バッカス(ca.1597)」に描かれている美少年群の一人だろうと思われる。
カラヴァッジョのパトロンであったデル・モンテ枢機卿のもとに集められていた美少年達を描いたもので後ろでこちらを向いているのはカラヴァッジョ自身と言われているらしい。彼の画力から言えば描かれた姿はカラヴァッジョ本人にそっくりなはずで、ということはこの雰囲気に難なく馴染んでいた人物のような気がして、乱暴で無頼漢の彼のイメージとはまた違った印象を持った。一説によるとカラヴァッジョはバイセクシャルだったという話もあるので、それもあるかもしれない。
信仰の寓意/ヨハネス・フェルメール(ca.1670)

フェルメールの作品は比較的小さなものが多いけど、これは彼にしてはかなり大きい方の作品に属すると思う。以前ウィーンで観た「絵画芸術」も大きいけれどそれよりも少し大きいかもしれない。でも、正直言ってあまりフェルメールっぽくはない。
勿論よく見ると球体のガラスに写り込む室内の様子だったり、ドレスに現れる光の玉だったり、画面左のカーテンだったり彼らしい表現はそこここに散見されるけどどうも全体が…。というのもこの絵の発注主がカソリック教徒だったらしく、恐らくはそのリクエストでタイトルのように宗教的寓意がそこここに込められているのだ。(フェルメール自身もプロテスタントからカソリックに改宗しているが、宗教的な理由だけだったのかは疑問が残るような…)
当時はオランダはプロテスタント国家で絵画界の顧客は既に教会から市民に移っていたのだけれど数少ないカソリック信者が家の中にカソリック的世界を作るために宗教的寓意に満ちたものを頼んだらしい。女性が地球儀を踏んずけているのはカソリック教が世界を広く支配する事の寓意らしいが、ここら辺はもしかしたら当時のオランダでも既にアナクロだったのではないかとぼくは邪推したりしている。
テラスの陽気な集い/ヤン・ステーン(ca.1670)

ステーンはライデン生まれの画家で風俗画を多く描いている。絵に寓意が込められていることもあるけれど、当時の風俗を見たり想像したりするだけでも楽しいし、観察眼の鋭いステーンは観るものが退屈しないように細かい所に仕掛けをしていたりもする。
猥雑な感じのするこの絵も、登場人物の一人一人を見てその台詞なんかを考えてみると退屈しない。そうこうしている内に視線はどうしても中央の女将の胸元に…吸いつけられる。ステーンもそのつもりで描いている。彼女にじっと見つめられて、エプロンをはだけて「ねぇ…」と。 うっ、と戸惑って固まっているこちらを、画面左にいるでっぷりと太ったステーン自身がそれを見て大笑いをしている。
ガルダンヌ/ポール・セザンヌ(ca.1885)

正直言ってセザンヌの本当の良さはぼくには分かっていないと思う。ぼくの頭の中ではセザンヌはあのアンリ・ルソーと同じような位置にいると言ったら、大半の人が異を唱えて、しかしほんの少しの人が頷くかもしれない。ぼくの中では彼はそういうような立ち位置にある。ついでにアンリ・ルソーはぼくの大好きな画家であることも言っておかないといけないかもしれないが…。
このカルダンヌ村はセザンヌのいたエクスの南にある小さな村だ。この絵を観ているとセザンヌが風景を忠実に描こうというより、この風景を四角や三角のエレメントに再構成して全体としての風景を構成してゆこうとしている感じが、ぼくにでも比較的容易に感じられるという点で気に入っている。


[図録]

228頁、2900円。ここのところ図録の値段がじわりと上がってきている。コロナ禍で入場者も見込めず印刷部数が減れば一冊当たりの制作費用がかさんでくることもあるのかもしれない。
構成は展示に従って①信仰とルネサンス、②絶対主義と啓蒙主義の時代、③革命と人々のための芸術、の3部に分かれている。内容は典型的な図録で全ての作品に図と解説がついているのはありがたいが、折角3部に分けたのだから会場にあったように、各部の最初にその時代の概観的な解説を載せておいてほしかった。
会場の展示では目ぼしい作品には短い解説がこまめに書かれていたのでオーディオガイドがなくてもスムーズに流れを追うことができたように思う。
[蛇足]
国立新美術館にいくといつも必ず寄る美術館のすぐそばの中華料理屋に久しぶりに行った。昼時を少し外したのでちょっと待たされたけど意外と速く入店できた。そこは二階席もあるのだけれど、店員さんに聞くと客足とか、バイトさんの確保とか先行きが見通せないので二階は閉めているという。好きなお店なのでなんとか切り抜けて欲しいなと思った。


(April 2022)
gillman*s Choice Michael Kenna Photobook
My Favorite Photobooks...
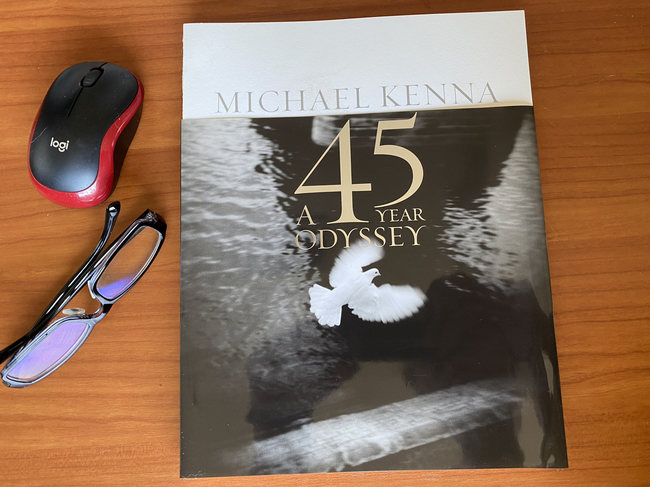
マイケル・ケンナはイギリス出身で今はアメリカで活躍している写真家だ。彼の写真は殆どがモノクロそして正方形の画面と言うのが作品の定番になっている。
彼の深いモノクロの世界はその独特の余白の使い方や、微妙で繊細な白黒の濃淡表現など日本人を含めてぼくたち東洋人の美意識と相通じるものがあるとぼくは勝手に思っている。
2018年彼の写真展が東京都写真美術館で行われたのだけれど、その時観た数々の写真は忘れられないものとなった。植田正治写真美術館の展示と同じように一つひとつの写真はとても小さく、今流行りのような大画面はないのだけれど、それを観た者の心の中でそれは大きなスペースを占めることになる。
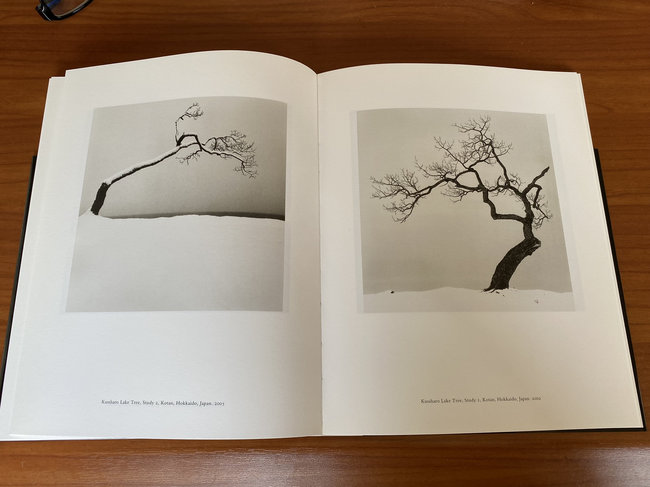
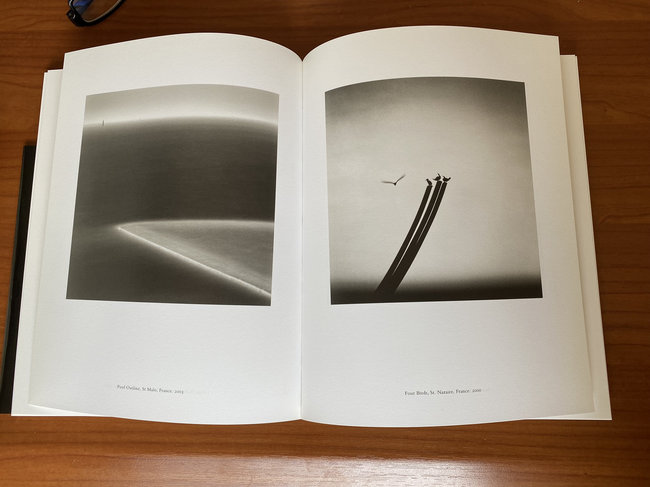
彼の一連の写真の中で何枚かの北海道の原野で撮られたものがある。荒涼とした雪原に一本の樹が立っている。時にはのたうつように、時には空に向かって毛細血管のような枝を拡げて…。
この写真を見てぼくはウィーンのオーストリア美術館で観たセガンティーニの「悪しき母たち(Die bösen Mütter)」を思い浮かべた。セガンティーニは母性なき生の荒涼さをその樹で表しているのだと思うけれど、それに対してケンナのこれらの樹は冬を耐え抜く強さのようなものを感じさせる。フォルムは似ていてもその違いは大きい。

ぼくも好きな彼の写真でフランスで撮った三羽の鳥の写真があるのだけれど、実はその写真が村上春樹の短編集「女のいない男たち」の文庫本の表紙に使われている。先日アカデミー賞をとった映画「ドライブ・マイ・カー」の原作はこの短編集の中に収められていて、先日ケンナは自分のFacebookでその映画の受賞を祝うとともに、この原作の本の表紙に自分の写真が使われていることが誇らしいと語っていた。
彼のキャリア45年を記念して出されたこの写真集を見ていると世界のいたるところに美しい静謐な時間が流れていたことが思い起こされて癒されるが、一方彼は今自分のFBに何度か彼がかつてウクライナで撮った平和で静謐な時間の作品を載せている。静かなプロテストだと思う。
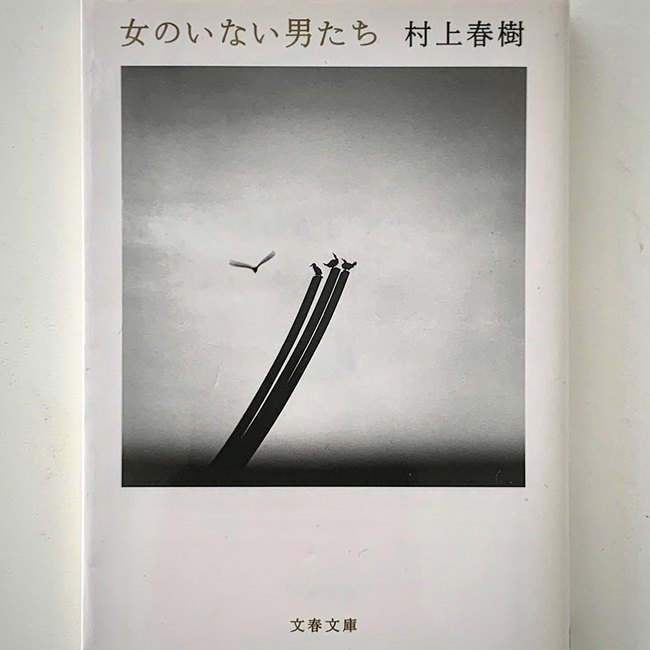
A 45 Year Odyssey
Michael Kenna
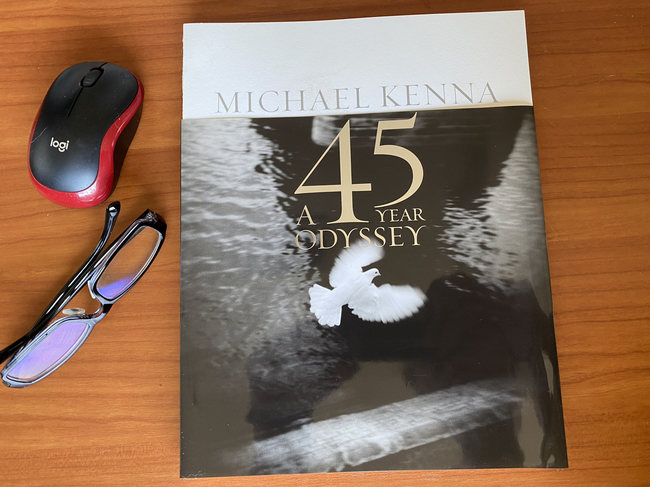
マイケル・ケンナはイギリス出身で今はアメリカで活躍している写真家だ。彼の写真は殆どがモノクロそして正方形の画面と言うのが作品の定番になっている。
彼の深いモノクロの世界はその独特の余白の使い方や、微妙で繊細な白黒の濃淡表現など日本人を含めてぼくたち東洋人の美意識と相通じるものがあるとぼくは勝手に思っている。
2018年彼の写真展が東京都写真美術館で行われたのだけれど、その時観た数々の写真は忘れられないものとなった。植田正治写真美術館の展示と同じように一つひとつの写真はとても小さく、今流行りのような大画面はないのだけれど、それを観た者の心の中でそれは大きなスペースを占めることになる。
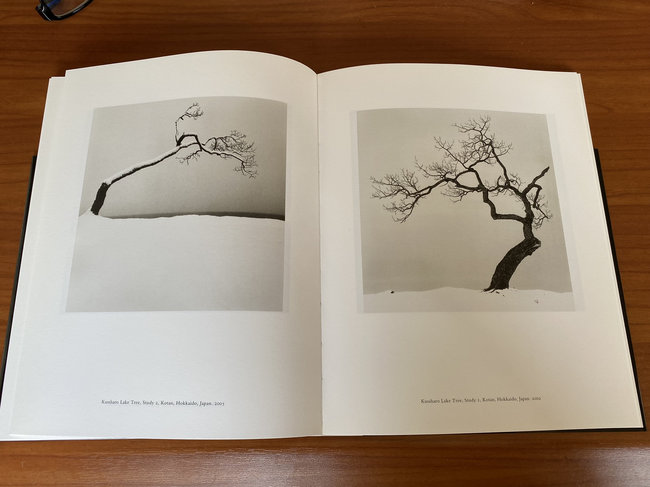
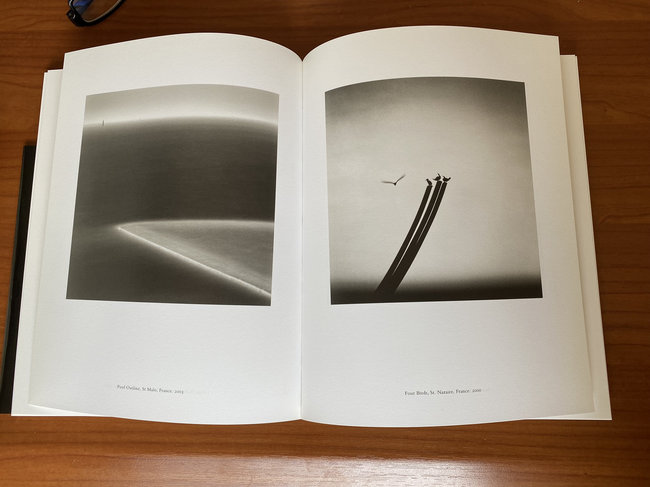
彼の一連の写真の中で何枚かの北海道の原野で撮られたものがある。荒涼とした雪原に一本の樹が立っている。時にはのたうつように、時には空に向かって毛細血管のような枝を拡げて…。
この写真を見てぼくはウィーンのオーストリア美術館で観たセガンティーニの「悪しき母たち(Die bösen Mütter)」を思い浮かべた。セガンティーニは母性なき生の荒涼さをその樹で表しているのだと思うけれど、それに対してケンナのこれらの樹は冬を耐え抜く強さのようなものを感じさせる。フォルムは似ていてもその違いは大きい。

ぼくも好きな彼の写真でフランスで撮った三羽の鳥の写真があるのだけれど、実はその写真が村上春樹の短編集「女のいない男たち」の文庫本の表紙に使われている。先日アカデミー賞をとった映画「ドライブ・マイ・カー」の原作はこの短編集の中に収められていて、先日ケンナは自分のFacebookでその映画の受賞を祝うとともに、この原作の本の表紙に自分の写真が使われていることが誇らしいと語っていた。
彼のキャリア45年を記念して出されたこの写真集を見ていると世界のいたるところに美しい静謐な時間が流れていたことが思い起こされて癒されるが、一方彼は今自分のFBに何度か彼がかつてウクライナで撮った平和で静謐な時間の作品を載せている。静かなプロテストだと思う。
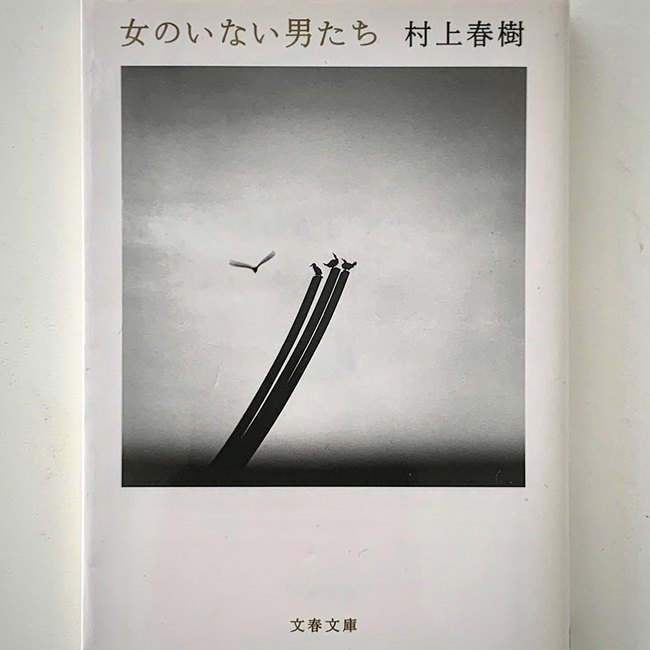
(April 2022)
Momory of the past Exhibitions Michael Kenna
回顧展回顧
.マイケル・ケンナ展
MICHAEL KENNA A 45 Year Odyssey 1973-2018 Retrospective 東京都写真美術館
2018年12月1日~2019年1月27日

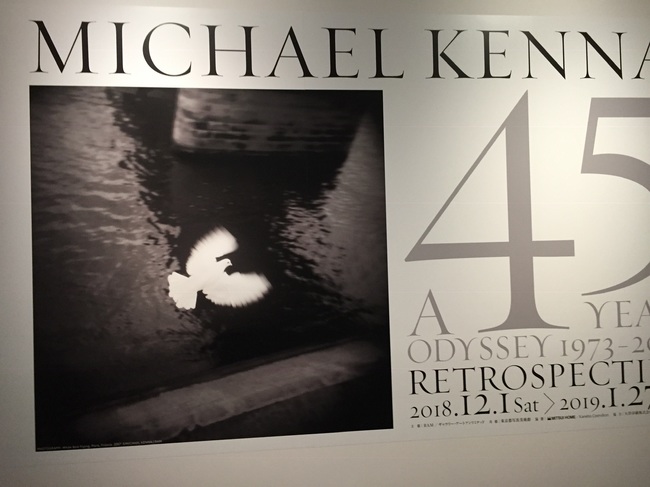
[感想メモ]
マイケル・ケンナはソール・ライターやセバスチャン・サルガドそして植田正治等と並んでぼくの好きな写真家の一人だ。ケンナは6x6版のハッセルブラッドを使って独特のモノクロの色調で知られている。
今回のマイケル・ケンナ写真展はサブタイトルに「MICHAEL KENNA A 45 Year Odyssey 1973-2018 Retrospective」とうたわれているように、彼の45年間の作品を振り返って行われた日本では初めての彼の本格的な回顧展だ。
会場では条件付きではあるけど作品の撮影も許可されている。ただし会場には2つの別のブースがあって、そちらの方は撮影が禁止されている。
その一つは「Impossible to Forget」と題された50年後のナチス強制収容所のシリーズ、そしてもう一つは「RAFU」と題された10年間にわたって日本で撮りためた裸婦のシリーズ。
メインの写真展の方には人物は写っていない、荒涼とした平原や霧にかすむ並木道など、言わば幽玄ともいえるモノクロの世界が広がっている。
その多くは正方形のアングルで対象物をコンポジション的に捉えており、画面は西欧的な画面を埋め尽くす、というより引き算的な画面構成が印象的だ。ここら辺は、引き算の美意識を根底に持っている日本人の感性に訴えることが多いと思う。彼の作品が日本で評価されている一つの理由でもあるかもしれない。
最近の写真展は引き延ばした巨大な写真やマルチアングルの画面があったりして、それはそれで迫力はあるのだけれど、風景写真で言えばときにはこれでもかという絶景写真のオンパレードの写真展もあったりして…。ぼくにとっては絶景写真は5分で飽きるが、マイケル・ケンナの写真は何度見ても飽きることがないし、観るたびに新しい発見がある。それは水墨画がそうであるのと似ているかもしれない。期間中にもう一度来たいと思っている。

[印象に残った作品について少し…]
■Deckchairs,Bournemouth,Darset,England 1983

正方形ではなく横長の画面。海岸につきでたテラスに畳まれたデッキチェアーが置かれている。シーズンオフなのかそれともシーズン中だがこれから人の来る前の朝だろうか、あたりを静謐な空気が支配している。
ぼくはこれに似た状況を冬の沖縄の離島の海岸で感じたことがある。海に突き出た木製のデッキに置かれた木製のテーブルの腋に椅子が重ねられていた。見渡す限り海岸にも人影はない。静謐、安堵、寂寥いくつもの思いが重なってくる。ハンマースホイの感性を思い起こした。
■Kussharo Lake,Tree Study 1.Kotan,Hokkaido,Japan.2002


正方形の画面に雪の中に身をよじらすように立っている一本の木。ケンナが通いつめた冬の北海道で撮った一枚で、同じところで撮った他の木の写真も展示されていた。
この写真にある屈斜路湖にあったこの木は「ケンナの木」として親しまれていたみたいだが、倒壊の恐れがあるとして伐採されてしまった。尤も切ったほうは「そういう木」だとは知らなかったらしいのだが…。
この写真を見たとき、ぼくはとっさに一枚の絵を想いうかべた。それはウィーンのベルベデーレの美術館で観たセガンティーニの「Evil Mothers(邪悪な母たち)」だった。子供をないがしろにして自らの快楽におぼれる母の心を荒涼とした雪中にさらされる一本の古木になぞらえている。
ケンナの写真の木に絡みつく女の姿がぼくの頭の中でダブる。ケンナは風雪に耐える木のフォルムに惹かれたのだと思うが、観る者によってそれぞれの感慨があるという例かもしれない。
■Ten and a Half Trees,Peterhof,Russia.2000

ケンナの風景写真は基本的には静謐な雰囲気の写真が多いのだけれど、それは画面に動きがないということではない。例えば木立や杭や石像や電灯など同じものを繰り返し一つの画面に入れることによってリズムを生み出している作品は意外と多い。抽象絵画を観るような楽しさも味あわせてくれる。
■Avonmouth Docks,Study 7,Avon,England.1987

ケンナの写真には純粋にコンポジションの表現を狙ったような大胆な作品も多い。もちろんそれでも風景写真には違いないのだけれど、この写真はタイトルからすると多分造船所のドライドックの下から撮った写真だと思う。以前横浜のドライドックの底から見上げた空がこんなシルエットだった。
一見するとコントラストの強いまるでデ・キリコの絵のようだけど、空の星の動きやシャープで明快なスカイラインなどみるといろんな撮影テクニックが入っているんだろうなぁと想像できる。彼は時には10時間くらいかけて露光することもあるというから、それだけでも大変なことだ。
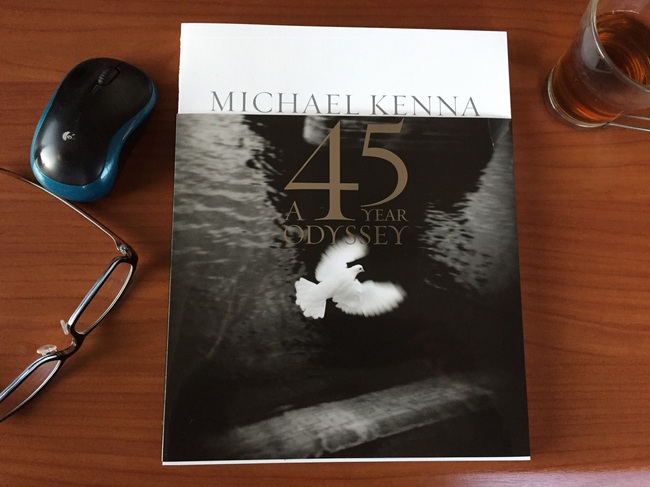
(Dec.2018)
gillman*s Choice 通達/謁見
Book Review...

ヴァーツラフ・ハヴェル著
チェコの劇作家ヴァーツラフ・ハヴェル(V´aclav Havel)の作品は日本では「反政治のすすめ」(1991)「ジェブラーツカー・オペラ〈乞食オペラ〉(2002)」や「力なき者たちの力(2019)」など数編が翻訳されているがこの度、彼の戯曲「通達」と「謁見」が翻訳され出版された。
ハヴェルといえば劇作家であると同時にチェコスロバキアの最後の大統領であり、かつチェコ共和国の初代大統領でもある。彼は裕福な実業家の家に生まれたが共産主義体制によって全財産を没収されその後アルバイトなどで働きながら勉学をつづけるとともに劇団を組織し俳優としても活動していた。

*Prague Morningより
彼の戯曲や政治活動は反体制という言葉で象徴されるようにソ連時代をはじめとして抑圧する力に対して抵抗するという点に向けられている。本編の「通達」は役所という官僚組織に人工言語「プティテベ」が導入されそれに翻弄される人物を描いており、「謁見」は上司が部下に奇妙な提案をするというビール工場が舞台の話なのだが、ここら辺はハヴェルは実際にビール工場で働いたこともありその時の経験も活かされているのかもしれない。
両編とも一見コミカルではあるが登場人物の会話は最初はとことんかみ合っていない。クスッとしながらも、観るものにも少しづつ不条理なこの状況に割り切れないものが心の中に溜まってゆく。翻訳の巧さもあって読んでいくうちにプラハの小劇場の舞台が彷彿としてくる。この出版記念を兼ねて訳者である阿部賢一氏のオンライン講義をぼくも会員である日本チェコ友好協会のイベントで聴くことができた。とても分かりやすく、興味深い講義だった。
そこで感じるのはやはり「言葉の力」ということになる。言葉を武器に反体制の活動を続けて来たハヴェルの姿におもわずゼレンスキーの姿を重ね合わせてしまうのはぼくだけではないかもしれない。彼が最初に話題になりかけた頃日本のマスコミでコメディアンと紹介されテレビでいかにもふやけたコメントを発する類の人と見られていたのを想うと、今はまるでヒーローのような扱いでマスコミの節操のなさにあきれもする。
彼の政治的手腕の結果も未知数で今は何とも言えないが、彼は言葉の力を持っていること、そして長い間抑圧された東欧の底流に流れているハヴェルのような反骨の精神を持っていそうだという事は言えると思う。長引くコロナ禍や世界の紛争など不条理に囲まれている今、読み進めてゆくうちに色々なことが心に引っかかってきて忘れられない一冊になった。

オストラヴァのアレーナ劇場での「通達」公演(2017)
*阿部賢一氏講演資料より
本書籍は
版元ドットコム
より購入できます。
チェコの戯曲
通達/謁見
ヴァーツラフ・ハヴェル著
チェコの劇作家ヴァーツラフ・ハヴェル(V´aclav Havel)の作品は日本では「反政治のすすめ」(1991)「ジェブラーツカー・オペラ〈乞食オペラ〉(2002)」や「力なき者たちの力(2019)」など数編が翻訳されているがこの度、彼の戯曲「通達」と「謁見」が翻訳され出版された。
ハヴェルといえば劇作家であると同時にチェコスロバキアの最後の大統領であり、かつチェコ共和国の初代大統領でもある。彼は裕福な実業家の家に生まれたが共産主義体制によって全財産を没収されその後アルバイトなどで働きながら勉学をつづけるとともに劇団を組織し俳優としても活動していた。

*Prague Morningより
彼の戯曲や政治活動は反体制という言葉で象徴されるようにソ連時代をはじめとして抑圧する力に対して抵抗するという点に向けられている。本編の「通達」は役所という官僚組織に人工言語「プティテベ」が導入されそれに翻弄される人物を描いており、「謁見」は上司が部下に奇妙な提案をするというビール工場が舞台の話なのだが、ここら辺はハヴェルは実際にビール工場で働いたこともありその時の経験も活かされているのかもしれない。
両編とも一見コミカルではあるが登場人物の会話は最初はとことんかみ合っていない。クスッとしながらも、観るものにも少しづつ不条理なこの状況に割り切れないものが心の中に溜まってゆく。翻訳の巧さもあって読んでいくうちにプラハの小劇場の舞台が彷彿としてくる。この出版記念を兼ねて訳者である阿部賢一氏のオンライン講義をぼくも会員である日本チェコ友好協会のイベントで聴くことができた。とても分かりやすく、興味深い講義だった。
そこで感じるのはやはり「言葉の力」ということになる。言葉を武器に反体制の活動を続けて来たハヴェルの姿におもわずゼレンスキーの姿を重ね合わせてしまうのはぼくだけではないかもしれない。彼が最初に話題になりかけた頃日本のマスコミでコメディアンと紹介されテレビでいかにもふやけたコメントを発する類の人と見られていたのを想うと、今はまるでヒーローのような扱いでマスコミの節操のなさにあきれもする。
彼の政治的手腕の結果も未知数で今は何とも言えないが、彼は言葉の力を持っていること、そして長い間抑圧された東欧の底流に流れているハヴェルのような反骨の精神を持っていそうだという事は言えると思う。長引くコロナ禍や世界の紛争など不条理に囲まれている今、読み進めてゆくうちに色々なことが心に引っかかってきて忘れられない一冊になった。

オストラヴァのアレーナ劇場での「通達」公演(2017)
*阿部賢一氏講演資料より
本書籍は
版元ドットコム
より購入できます。
(March 2022)
gillman*s Choice Red & Blue Mitchell
gillman*s Choice...
赤と青のミッチェル

いろいろなジャズのアルバムを聴いていると意味なく頭の中で勝手に関連付けてしまう時がある。例えば以前にも書いたBeverly KellyとBeverly Kenneyのように二人のBeverlyが頭の中に入ってくると、どうしてもその二人を聴き比べてみたくなってしまう。何の意味もないのだけれど…。
同じようなことがこのベーシストのRed MitchellとトランぺッターBlue Mitchellの二人にも「赤と青」ということだけでそれが起こってしまって、ここ二週間くらいこの二人のアルバムばかり聴きなおしていた。活躍時期も少しずれている二人だし、もちろんそれで何かが分かったという事でもないけど、コロナ禍のお籠りの気晴らしになったことだけは確かなことだ。
Presenting Red Mitchell

(1957)
レッド・ミッチェルの演奏を聴くようになったのはこの猫ジャケのアルバムに出会ってからだ。レッドのベースは最初聴くと弾きが弱いのかな、と少し物足りなさを感じていたのだけれどそのうちにその軽やかさに魅せられるようになって、それはそれでまた良いなぁと思うようになった。
全体を通じてジェームス・クレイのテナーとフルートを持ち換えてのワンホーン構成なのも気楽に聴いていられる雰囲気を出している。このアルバムの中に"Out of the Blue"という曲が入っていて、考えてみたらBlue Mitchellが同じタイトルのアルバムを出している。偶然だけど面白い。ロレイン・ゲラーのピアノもレッドに優しくよりそう彼女の姿が目に浮かびそうな好感の持てる演奏。一瞬、対極にあるような女性ピアニストPat Moranのギンギンのピアノを思い浮かべてしまった。
蛇足だけど、このOut of the Blueというフレーズはぼくは勝手に「藍は青より出でて…」かなと思っていたけど、実はOut of the blue skyつまり青空からいきない雷が落ちてくる、要はまさに「青天の霹靂」唐突に、という意味らしい。辞書はひいてみるもんだ。
When I'm Singing

(1982)
アルバムタイトルにある「ぼくが歌う時」というように、このアルバムはちょっと気だるそうなおじさんの歌で始まる。歌っているのはベーシストのレッド・ミッチェル。そればかりかこのアルバムではベースはもちろんピアノも彼一人による多重録音で出来ている。聴きこんでいくと実に味のある声だ。
たぶん基本はベースを弾きながらの弾き語りに後からピアノを被せたのだろうと思うのだけれど、さすがに自分で弾いているだけあってピアノも実に好いタイミングで入って来る。ベースの弾き語りというと最近はベースギターの弾き語りを言うことが多いらしいけれど、こっちはコントラバスの弾き語りの方。それで言えば近年ではニッキ・パロットがやっているけど、レッドがもっとずっと昔にやっていたんだ。
Out Of The Blue

(1959)
このアルバムタイトルを見ればBlueNoteファンなら、若いミュージシャンを推したあれ"OTB"(Out of the Blue)のことかと思うかもしれないけれど、こちらはRiversideのレーベルでそれとは無関係だと思う。
一見地味なアルバムだけれど、ぼくはブルー・ミッチェルのアルバムの中では一番好きだ。選曲も良いしメンバーも最高。ピアノはウィントン・ケリー、ドラムスにアート・ブレイキーそしてテナーサックスのベニー・ゴルソンなどそうそうたる面子。
1曲目のBlues on my mindはフランス映画「殺られる」(1959)のテーマソングに使われたものでこの映画の音楽担当はアート・ブレーキーで、この曲はこのアルバムの演奏にも参加しているゴルソン作曲によるもの。緊張感のある雰囲気が良い。他にも死刑台のエレベーターなどこの頃のフランス映画にはジャズがとても粋で効果的に使われている映画が多かった。
残念なのはジャケットがちょっとしょぼ過ぎ、黒いボルトの大写しで何だか不明だけれども地味。誰のデザインかと思って調べてみたらあの大御所Paul Baconのデザインではないか。ベーコンはBlueNoteのジャケットもデザインしているし、このRiversideでもメインでデザインしており200枚以上のアルバムジャケットのデザインもしているし本の装丁家としても著名である。。
彼のデザインはタイポグラフィーを活かしてあか抜けたものが多く、中でもBILL EVANSのアルバム"Everybody Digs BILL EVANS"のジャケットはその種のデザインでは傑作だと思うのだけれど、このジャケットのタイポグラフィーの何か投げやりな感じは謎だ。でもアルバムの内容は素晴らしい。
Blue's Moods
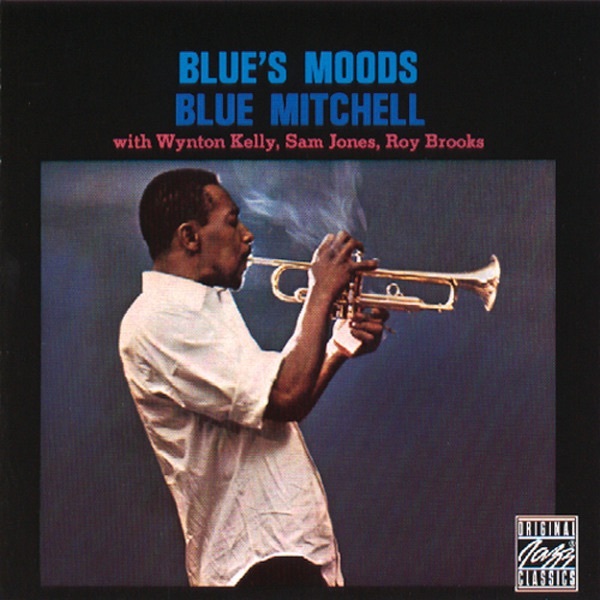
(1960)
こちらはブルー・ミッチェルのペット一本のワンホーンのアルバム。ぼくはジャズでは小編成のしかもどちらかと言えばホーンが入るならワンホーンの編成が好きだ。このアルバムではブルーの軽快なテンポにウイントン・ケリーのピアノが絶妙に絡み合っている。
トランぺッターといえば何といってもマイルスに尽きるのだろうけど、幸いジャズは録音技術の進展とともに歩んできて、いまだに多くの昔の名演が音源資産として残っている。少し振り返ってブルーのようなハードパップ時代の演奏を振り返ると、少しも古さを感じない。ジャズの歴史は進化ではなく変化なんだなぁとつくづく想う。8曲42分間の至福の時。
(Feb.2022)
赤と青のミッチェル
Red & Blue Mitchell

いろいろなジャズのアルバムを聴いていると意味なく頭の中で勝手に関連付けてしまう時がある。例えば以前にも書いたBeverly KellyとBeverly Kenneyのように二人のBeverlyが頭の中に入ってくると、どうしてもその二人を聴き比べてみたくなってしまう。何の意味もないのだけれど…。
同じようなことがこのベーシストのRed MitchellとトランぺッターBlue Mitchellの二人にも「赤と青」ということだけでそれが起こってしまって、ここ二週間くらいこの二人のアルバムばかり聴きなおしていた。活躍時期も少しずれている二人だし、もちろんそれで何かが分かったという事でもないけど、コロナ禍のお籠りの気晴らしになったことだけは確かなことだ。
Red Mitchel
Presenting Red Mitchell

(1957)
レッド・ミッチェルの演奏を聴くようになったのはこの猫ジャケのアルバムに出会ってからだ。レッドのベースは最初聴くと弾きが弱いのかな、と少し物足りなさを感じていたのだけれどそのうちにその軽やかさに魅せられるようになって、それはそれでまた良いなぁと思うようになった。
全体を通じてジェームス・クレイのテナーとフルートを持ち換えてのワンホーン構成なのも気楽に聴いていられる雰囲気を出している。このアルバムの中に"Out of the Blue"という曲が入っていて、考えてみたらBlue Mitchellが同じタイトルのアルバムを出している。偶然だけど面白い。ロレイン・ゲラーのピアノもレッドに優しくよりそう彼女の姿が目に浮かびそうな好感の持てる演奏。一瞬、対極にあるような女性ピアニストPat Moranのギンギンのピアノを思い浮かべてしまった。
蛇足だけど、このOut of the Blueというフレーズはぼくは勝手に「藍は青より出でて…」かなと思っていたけど、実はOut of the blue skyつまり青空からいきない雷が落ちてくる、要はまさに「青天の霹靂」唐突に、という意味らしい。辞書はひいてみるもんだ。
When I'm Singing

(1982)
アルバムタイトルにある「ぼくが歌う時」というように、このアルバムはちょっと気だるそうなおじさんの歌で始まる。歌っているのはベーシストのレッド・ミッチェル。そればかりかこのアルバムではベースはもちろんピアノも彼一人による多重録音で出来ている。聴きこんでいくと実に味のある声だ。
たぶん基本はベースを弾きながらの弾き語りに後からピアノを被せたのだろうと思うのだけれど、さすがに自分で弾いているだけあってピアノも実に好いタイミングで入って来る。ベースの弾き語りというと最近はベースギターの弾き語りを言うことが多いらしいけれど、こっちはコントラバスの弾き語りの方。それで言えば近年ではニッキ・パロットがやっているけど、レッドがもっとずっと昔にやっていたんだ。
Blue Mitchell
Out Of The Blue

(1959)
このアルバムタイトルを見ればBlueNoteファンなら、若いミュージシャンを推したあれ"OTB"(Out of the Blue)のことかと思うかもしれないけれど、こちらはRiversideのレーベルでそれとは無関係だと思う。
一見地味なアルバムだけれど、ぼくはブルー・ミッチェルのアルバムの中では一番好きだ。選曲も良いしメンバーも最高。ピアノはウィントン・ケリー、ドラムスにアート・ブレイキーそしてテナーサックスのベニー・ゴルソンなどそうそうたる面子。
1曲目のBlues on my mindはフランス映画「殺られる」(1959)のテーマソングに使われたものでこの映画の音楽担当はアート・ブレーキーで、この曲はこのアルバムの演奏にも参加しているゴルソン作曲によるもの。緊張感のある雰囲気が良い。他にも死刑台のエレベーターなどこの頃のフランス映画にはジャズがとても粋で効果的に使われている映画が多かった。
残念なのはジャケットがちょっとしょぼ過ぎ、黒いボルトの大写しで何だか不明だけれども地味。誰のデザインかと思って調べてみたらあの大御所Paul Baconのデザインではないか。ベーコンはBlueNoteのジャケットもデザインしているし、このRiversideでもメインでデザインしており200枚以上のアルバムジャケットのデザインもしているし本の装丁家としても著名である。。
彼のデザインはタイポグラフィーを活かしてあか抜けたものが多く、中でもBILL EVANSのアルバム"Everybody Digs BILL EVANS"のジャケットはその種のデザインでは傑作だと思うのだけれど、このジャケットのタイポグラフィーの何か投げやりな感じは謎だ。でもアルバムの内容は素晴らしい。
Blue's Moods
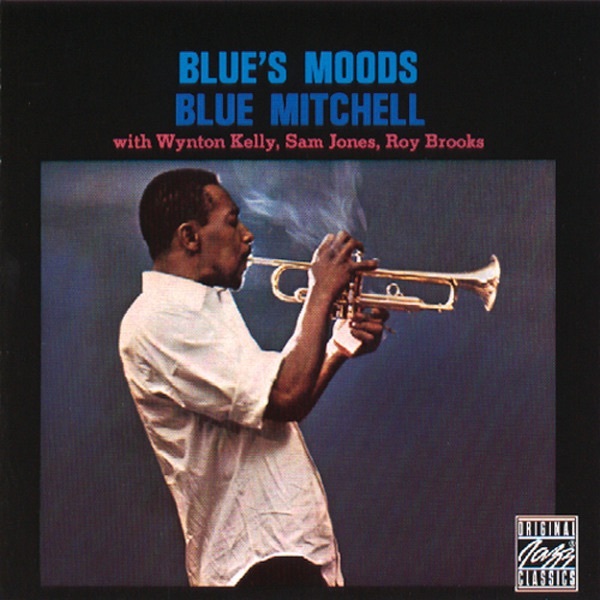
(1960)
こちらはブルー・ミッチェルのペット一本のワンホーンのアルバム。ぼくはジャズでは小編成のしかもどちらかと言えばホーンが入るならワンホーンの編成が好きだ。このアルバムではブルーの軽快なテンポにウイントン・ケリーのピアノが絶妙に絡み合っている。
トランぺッターといえば何といってもマイルスに尽きるのだろうけど、幸いジャズは録音技術の進展とともに歩んできて、いまだに多くの昔の名演が音源資産として残っている。少し振り返ってブルーのようなハードパップ時代の演奏を振り返ると、少しも古さを感じない。ジャズの歴史は進化ではなく変化なんだなぁとつくづく想う。8曲42分間の至福の時。
(Feb.2022)
gillman*s Museums 和田誠展
gillman*s Museuns...

[感想メモ]
初台のオペラシティのアートギャラリーで行われている「和田誠展」の会期終了が近づいているので、やっぱり観たくなってのこのこ出だした。この間意を決してやっと買った和田さんの画集「表紙はうたう」を見ていてやっぱりどうしても行かなきゃ、という気になった。コンサートには良く来たけどアートギャラリーの方は初めて。予約なしで大丈夫なので気楽に行ったら行列が出来ていて30分待ち。ひとりで直行、展覧会後軽いランチだけで直帰。
天才和田誠なのだけれど、どうしても和田さんと呼びたくなるのだが、その彼の画業の殆んどがポスターや本の表紙、絵本そしてエッセイなどいわゆるマスプロダクトとしての作品なのでその原画も展示されているが、大半は圧倒するまでの量の印刷物だ。それらが主に時系列もしくはジャンル別に展示されているがその幅の広さにも圧倒される。
天才には二つのタイプがあって、ピカソのようにまるで別人のように変化し続ける天才と和田さんのように美大の頃から既に和田誠として完成されているようなタイプとがあるような気がする。シンプルな線で構成される平面的な表現と独特の色彩感覚、それは彼の中で早くから完成されていたような気がする。
ぼくは特に彼の線が好きだ。その描く線はぼくの好きな人に、南伸坊や内田春菊、浦沢直樹そして上村一夫がいるのだけれど、彼らの線のように削っていって最後に残った線に命が宿っている、そういう力を和田誠の線も持っていると思う。


レコードジャケット

(1958)
和田さんはレコードやCDのジャケットも多くデザインしているけど、会場にはその原点ともいえる大学4年の時にデザインした架空のLPレコードのジャケットデザインが展示されていた。日宣美展に出品して奨励賞を受賞したのだけれど今見ても洗練されて垢抜けしている。ジャケットに登場するアーチストもジャズに造詣の深い彼らしいし、当時の大学生としては渋いなぁ。
「核実験を即時中止せよ」ポスター

(1958)
これも制作年代からいって美大時代の課題制作みたいなものだと思うのだけれど、強烈なメッセージが伝わってくる。この手のポスターではオリーブを咥えた鳩を描いたピカソののが有名だけれど、こちらのポスターからは平和への危機感がストレートに伝わってくる。
絵本「猫のしじみ」
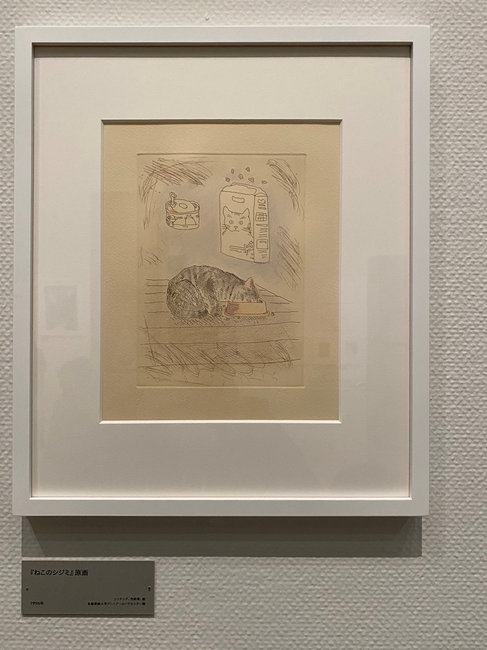
(1996)
和田さんは数々の絵本も作っているが、これはその一冊。公園に捨てられていた猫しじみがくれた何気ない日常の幸せがしみじみとしたタッチの銅版画で描かれている。塗りつぶしの平面的ないつものスタイルとはまた一味違った良さがある。
シェルブールの雨傘

(2002)
ぼくにとっては和田さんの絵に一番触れたのは映画に関する本なのだけれど、和田さんのイラストは見ているだけでその俳優の雰囲気が、そして映画のシーンが目の前に彷彿としてくる。絵がシンプルなだけに見る人の想像力を刺激してくれる。この原画は色の組み合わせも素敵だ。
似顔絵ハンフリー・ボガート

(2010)
これは会場の入り口に展示されていて、脇の画面では和田さんがこのイラストを描いている作業の動画が流されていた。会場には和田さんが手がけた有名人などの似顔絵が多数展示されているが、どれもこんなにシンプルな線なのにここまで似ているのか不思議でならない。

[図録]
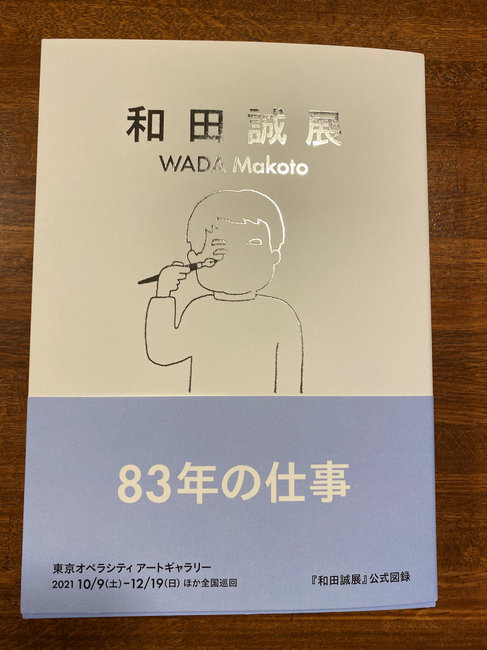
518頁、4400円。図録というには高すぎる感じがするけど、膨大な和田誠作品のインデックス的な存在ととらえた方が良いような気がする。もちろん展覧会に展示されている作品が網羅されているので彼の画業を俯瞰することができるし、作品の存在が分かればマスプロダクトが多い彼の作品の特性からネットなどでさらに詳細を知ることが出来るかもしれない。
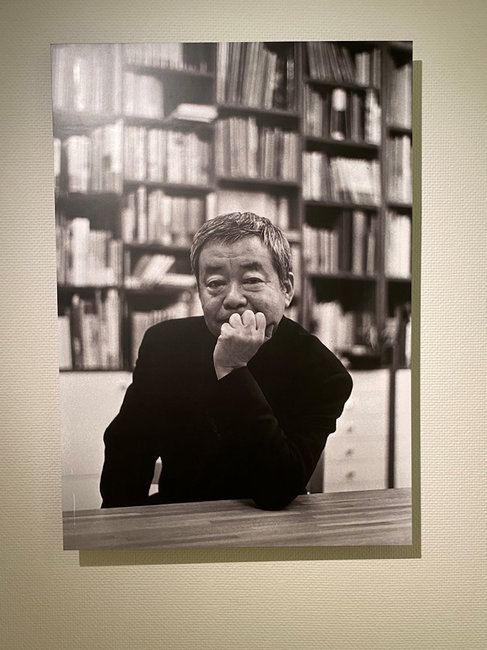
ありがとう、和田さん...
和田誠展
東京オペラシティ
アートギャラリー
[感想メモ]
初台のオペラシティのアートギャラリーで行われている「和田誠展」の会期終了が近づいているので、やっぱり観たくなってのこのこ出だした。この間意を決してやっと買った和田さんの画集「表紙はうたう」を見ていてやっぱりどうしても行かなきゃ、という気になった。コンサートには良く来たけどアートギャラリーの方は初めて。予約なしで大丈夫なので気楽に行ったら行列が出来ていて30分待ち。ひとりで直行、展覧会後軽いランチだけで直帰。
天才和田誠なのだけれど、どうしても和田さんと呼びたくなるのだが、その彼の画業の殆んどがポスターや本の表紙、絵本そしてエッセイなどいわゆるマスプロダクトとしての作品なのでその原画も展示されているが、大半は圧倒するまでの量の印刷物だ。それらが主に時系列もしくはジャンル別に展示されているがその幅の広さにも圧倒される。
天才には二つのタイプがあって、ピカソのようにまるで別人のように変化し続ける天才と和田さんのように美大の頃から既に和田誠として完成されているようなタイプとがあるような気がする。シンプルな線で構成される平面的な表現と独特の色彩感覚、それは彼の中で早くから完成されていたような気がする。
ぼくは特に彼の線が好きだ。その描く線はぼくの好きな人に、南伸坊や内田春菊、浦沢直樹そして上村一夫がいるのだけれど、彼らの線のように削っていって最後に残った線に命が宿っている、そういう力を和田誠の線も持っていると思う。
印象的だった原画
レコードジャケット
(1958)
和田さんはレコードやCDのジャケットも多くデザインしているけど、会場にはその原点ともいえる大学4年の時にデザインした架空のLPレコードのジャケットデザインが展示されていた。日宣美展に出品して奨励賞を受賞したのだけれど今見ても洗練されて垢抜けしている。ジャケットに登場するアーチストもジャズに造詣の深い彼らしいし、当時の大学生としては渋いなぁ。
「核実験を即時中止せよ」ポスター
(1958)
これも制作年代からいって美大時代の課題制作みたいなものだと思うのだけれど、強烈なメッセージが伝わってくる。この手のポスターではオリーブを咥えた鳩を描いたピカソののが有名だけれど、こちらのポスターからは平和への危機感がストレートに伝わってくる。
絵本「猫のしじみ」
(1996)
和田さんは数々の絵本も作っているが、これはその一冊。公園に捨てられていた猫しじみがくれた何気ない日常の幸せがしみじみとしたタッチの銅版画で描かれている。塗りつぶしの平面的ないつものスタイルとはまた一味違った良さがある。
シェルブールの雨傘
(2002)
ぼくにとっては和田さんの絵に一番触れたのは映画に関する本なのだけれど、和田さんのイラストは見ているだけでその俳優の雰囲気が、そして映画のシーンが目の前に彷彿としてくる。絵がシンプルなだけに見る人の想像力を刺激してくれる。この原画は色の組み合わせも素敵だ。
似顔絵ハンフリー・ボガート
(2010)
これは会場の入り口に展示されていて、脇の画面では和田さんがこのイラストを描いている作業の動画が流されていた。会場には和田さんが手がけた有名人などの似顔絵が多数展示されているが、どれもこんなにシンプルな線なのにここまで似ているのか不思議でならない。
[図録]
518頁、4400円。図録というには高すぎる感じがするけど、膨大な和田誠作品のインデックス的な存在ととらえた方が良いような気がする。もちろん展覧会に展示されている作品が網羅されているので彼の画業を俯瞰することができるし、作品の存在が分かればマスプロダクトが多い彼の作品の特性からネットなどでさらに詳細を知ることが出来るかもしれない。
ありがとう、和田さん...
(Dec.2021)
gillman*s Museum 川瀬巴水展
Museum of the Month...

コロナ禍以前は毎月のように美術館に行っていたのだけれどコロナ禍でそれが年に数度ということになってしまった。でもワクチンのお陰かここのところ感染者の数が低水準で推移しているので木曜日にカミさんとSOMPO美術館で行われている「川瀬巴水展」に行ってきた。もちろん寄り道せず直行直帰で。
SOMPO美術館は新館がオープンしてから初めて行ったのだけれど、展示スペースもかなり広くなったし高所恐怖症のぼくにとっては以前のように高層階ではなく5階建ての建物ということも嬉しい。今回の展覧会は前期と後期に分かれていて両方合わせれば今までの川瀬巴水展の中でも本格的な展覧会と言っていい。。
ぼくが巴水の絵に本格的に触れたのは平成5年(2013)に大田区立郷土博物館で開かれた「生誕130年 川瀬巴水展」だった。大田区は巴水が戦前は馬込に、戦後は池上に住んでいた縁もあって特に巴水のスケッチブックのコレクションなどの収蔵品も所有しており、この展覧会はまさに総力を挙げた企画だったと思う。
三期に分けて500点の作品が展示され、制作された図録も巴水の画業を記すにふさわしい充実したものだった。それまでも巴水の作品は好きだったのだけれど、展覧会で彼の多くの作品の実物に触れて自分の中でも忘れられない作家になった。当時どうしても欲しくて後刷りの作品を何点か手に入れたけれど、今ではその後刷りも中々手に入りにくくなってしまった。
今回のSOMPO美術館での展覧会はその時と並ぶ大規模なもので出品作はほぼ全てが巴水の作品の版元でありプロデューサーでもあった渡邊庄三郎の渡邊木版美術画舗の所有によるもので版画の状態もすばらしい。展示点数は前期・後期併せて300点であるけれど、今回は「旅みやげ」や「東京二十景」などシリーズものの作品がまとめて観られるということの意義は大きいと思う。観客もまだまだ少なく余裕をもって観ることができたのも嬉しい。なお、前期と後期では色々と作品の入れ替えが行われるが、一番の大きい入れ替えは以下のシリーズ作品となる。東海道風景選集…前期、風景画集・東日本編…前期、旅みやげ第二集…後期。

ベスト5と言ったって、実際には目移りして選ぶこともできないのだけれど…。今回は巴水の版画家へのきっかけを作った盟友でもある伊藤深水が巴水のことを「旅情詩人」と称したのに倣って、展示作品の中から詩情あふれる巴水の得意とする5つのテーマの観点から勝手に好きなものを選んでみた。
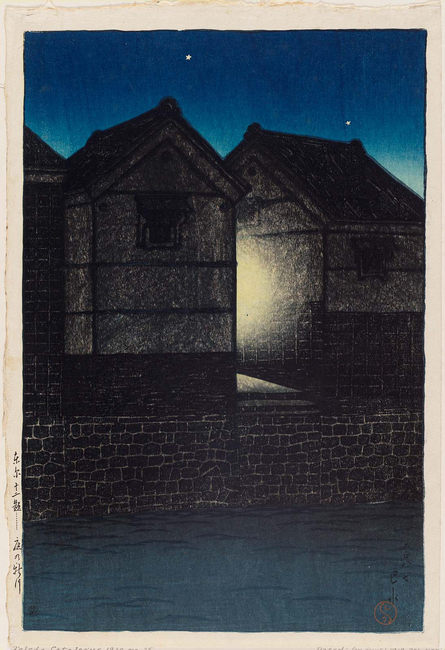
(1919)
詩情を表すには点景としての人物が有効で巴水もその手の使い方をよくしているけれど、この作品には人物はおろかその影さえも登場しない。しんとした夜更けの川べりの倉庫街の一角にガス灯の明かりがぼーっと光っている。
きっと何も音はしていないのだろうけど、ぼくら日本人にはなんか「し~ん」という音にならない音が聞こえてくるような気配さえする。すごくモダンな構図にも見えるし、古いウィーンの路地裏の雰囲気をも思わせるような不思議な絵だ。

(1926)
雨も巴水の詩情の重要な要素だと思う。その雨もいつも同じではない。横殴りの雨からシトシトと降る雨まで。その描き方も黒い線の雨から、白い線で表現される雨まで…。この作品は都会の篠突く雨の中を一台の人力車が急いでいる。橋の外灯の明かりが路面電車の軌道のある路を照らしている。
会場にはこの作品のラフスケッチが描かれたスケッチブックが展示されている。隅田川にかかるこの新大橋は大正元年に新たな鉄製の橋として架け替えられたもので、この数年前に起きた関東大震災を生き残った象徴として巴水の目には映ったのではないか。巴水自身は大震災で自宅ばかりか書き溜めたスケッチ帖188冊をはじめ彼の画業の殆ど全てを失ってしまった。
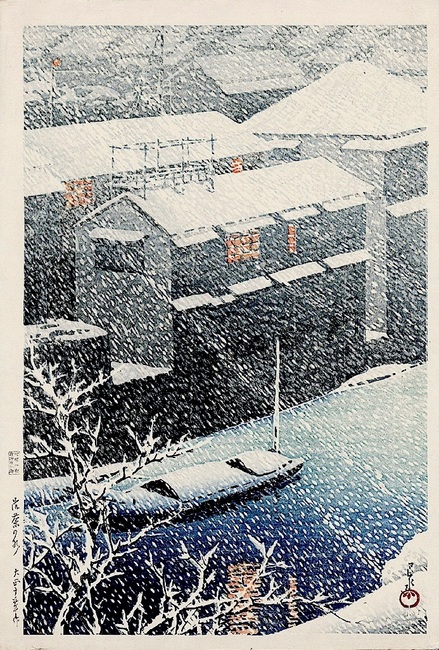
(1926)
雪は作品を選ぶのに雨以上に迷いに迷った。巴水はある意味では雨以上に雪の表現に苦心した。夜しんしんと降り積もる雪。ふんわりと落ちてくる牡丹雪、そして「三十軒堀の暮雪(1920)」での実験的な横殴りに吹き付ける雪の表現、など。ぼく自身は彼の絶筆になった「平泉金色堂(1957)」の雪景色が忘れられないのだけれど、これは別格。
迷った末に選んだのがこの御茶ノ水の雪景色でこれはぼく自身が慣れ親しんできた景色でもあるのだけれど、何よりもその横殴りに降る雪の描き方が雪を運んでくる気まぐれな風の動きまで見えそうな動的な雪の表現が珍しく、そして効果的だなぁと思った。

(1919)
月といえばもちろん彼の代表作である「馬込の月」なのだろうけど、この作品は彼のまだ三十代半ばの若い頃の作品だけれども、既に彼の詩情性に溢れていて、もうしっかりと川瀬巴水の世界が出来ている。
青森県八戸にある海辺の湧き水は住民にとって貴重な水源となっており、その三嶌の湧き水を夜分に汲みに来た親子を玉子の黄身のような満月がじっと見下ろしている。池の淵に建つあばら家の向こうに広がる夜の海から波音が聞こえてきそうだ。巴水の詩情性は画面から聞こえてくる微かな音を伴っている。
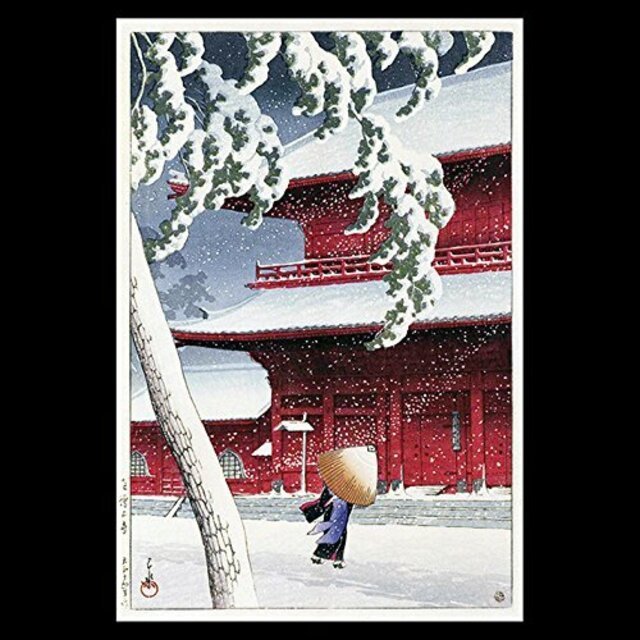
(1925)
ここまで挙げてきた彼の詩情性の要素と「東京」というのにはなんか大きな隔たりがあるように思えるけど、東京生まれの巴水にとっては東京と言う都会の色々な場面に詩情を感じるのは、故郷の山河に思いをはせる思いとなんら変わらないことだったのじゃないかと勝手に思っている。ぼく自身も下町の路地に同じような気持ちをもっているから。
この作品「芝増上寺」はまさに彼の代表作でここで挙げるには余りにベタじゃないかとも思うのだけれど、改めて今回すごいなぁと惚れ直したので…。展示されていたのは初刷りだと思うのだけれど、その赤というか朱というか、その色の深みとインパクトが同じ作品は今まで何回か観たはずなのだが、改めて心に沁みてきた。
構図と言い、色合いと言い完璧に調和のとれた作品で、巴水は似たような構図、状況を各地でも何点か描いているけど、やはりこれに尽きる。ぼくにとって巴水のこの「東京二十景」は歌川広重の「江戸百景」と並んで忘れることのできない作品に満ちている。
[図録]
260頁、2500円。巴水の画集は何種類か出ているけれど、それに比しても全く見劣りのしない画集と言えるし、その割には他の画集よりもコスパが良いのではないか。2013年に大田区立郷土博物館で開催された「生誕130年 川瀬巴水展」の図録に収録されているのが500点で、巴水は生涯で700図を制作したと言われているので、500点というのはすごいことだと思う。
今回の展覧会の図録には300点あまりが掲載されているので、もちろん重複はあるけれど、この二冊の図録で巴水の画業のかなりの部分が見られると思う。と言っておきながら矛盾しているようだけれど、やっぱり一度は実物を観ておくことが肝心だと思う。その上で図録を見れば図版に加えてそれだけでは伝わりにくい部分を記憶が補ってくれるような気がする。


川瀬巴水展
SOMPO美術館
2021年10月2日~12月26日

コロナ禍以前は毎月のように美術館に行っていたのだけれどコロナ禍でそれが年に数度ということになってしまった。でもワクチンのお陰かここのところ感染者の数が低水準で推移しているので木曜日にカミさんとSOMPO美術館で行われている「川瀬巴水展」に行ってきた。もちろん寄り道せず直行直帰で。
SOMPO美術館は新館がオープンしてから初めて行ったのだけれど、展示スペースもかなり広くなったし高所恐怖症のぼくにとっては以前のように高層階ではなく5階建ての建物ということも嬉しい。今回の展覧会は前期と後期に分かれていて両方合わせれば今までの川瀬巴水展の中でも本格的な展覧会と言っていい。。
ぼくが巴水の絵に本格的に触れたのは平成5年(2013)に大田区立郷土博物館で開かれた「生誕130年 川瀬巴水展」だった。大田区は巴水が戦前は馬込に、戦後は池上に住んでいた縁もあって特に巴水のスケッチブックのコレクションなどの収蔵品も所有しており、この展覧会はまさに総力を挙げた企画だったと思う。
三期に分けて500点の作品が展示され、制作された図録も巴水の画業を記すにふさわしい充実したものだった。それまでも巴水の作品は好きだったのだけれど、展覧会で彼の多くの作品の実物に触れて自分の中でも忘れられない作家になった。当時どうしても欲しくて後刷りの作品を何点か手に入れたけれど、今ではその後刷りも中々手に入りにくくなってしまった。
今回のSOMPO美術館での展覧会はその時と並ぶ大規模なもので出品作はほぼ全てが巴水の作品の版元でありプロデューサーでもあった渡邊庄三郎の渡邊木版美術画舗の所有によるもので版画の状態もすばらしい。展示点数は前期・後期併せて300点であるけれど、今回は「旅みやげ」や「東京二十景」などシリーズものの作品がまとめて観られるということの意義は大きいと思う。観客もまだまだ少なく余裕をもって観ることができたのも嬉しい。なお、前期と後期では色々と作品の入れ替えが行われるが、一番の大きい入れ替えは以下のシリーズ作品となる。東海道風景選集…前期、風景画集・東日本編…前期、旅みやげ第二集…後期。
川瀬巴水展
My Best 5
ベスト5と言ったって、実際には目移りして選ぶこともできないのだけれど…。今回は巴水の版画家へのきっかけを作った盟友でもある伊藤深水が巴水のことを「旅情詩人」と称したのに倣って、展示作品の中から詩情あふれる巴水の得意とする5つのテーマの観点から勝手に好きなものを選んでみた。
夜/夜の新川
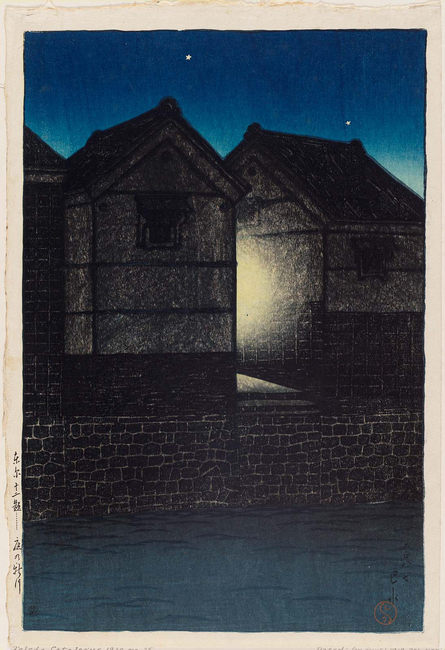
(1919)
詩情を表すには点景としての人物が有効で巴水もその手の使い方をよくしているけれど、この作品には人物はおろかその影さえも登場しない。しんとした夜更けの川べりの倉庫街の一角にガス灯の明かりがぼーっと光っている。
きっと何も音はしていないのだろうけど、ぼくら日本人にはなんか「し~ん」という音にならない音が聞こえてくるような気配さえする。すごくモダンな構図にも見えるし、古いウィーンの路地裏の雰囲気をも思わせるような不思議な絵だ。
雨/新大橋

(1926)
雨も巴水の詩情の重要な要素だと思う。その雨もいつも同じではない。横殴りの雨からシトシトと降る雨まで。その描き方も黒い線の雨から、白い線で表現される雨まで…。この作品は都会の篠突く雨の中を一台の人力車が急いでいる。橋の外灯の明かりが路面電車の軌道のある路を照らしている。
会場にはこの作品のラフスケッチが描かれたスケッチブックが展示されている。隅田川にかかるこの新大橋は大正元年に新たな鉄製の橋として架け替えられたもので、この数年前に起きた関東大震災を生き残った象徴として巴水の目には映ったのではないか。巴水自身は大震災で自宅ばかりか書き溜めたスケッチ帖188冊をはじめ彼の画業の殆ど全てを失ってしまった。
雪/御茶ノ水
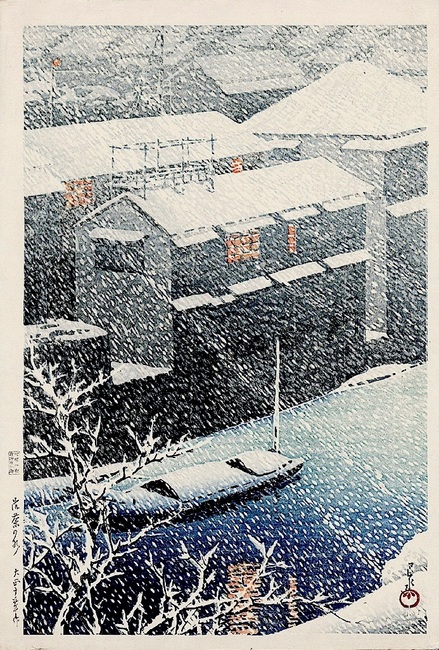
(1926)
雪は作品を選ぶのに雨以上に迷いに迷った。巴水はある意味では雨以上に雪の表現に苦心した。夜しんしんと降り積もる雪。ふんわりと落ちてくる牡丹雪、そして「三十軒堀の暮雪(1920)」での実験的な横殴りに吹き付ける雪の表現、など。ぼく自身は彼の絶筆になった「平泉金色堂(1957)」の雪景色が忘れられないのだけれど、これは別格。
迷った末に選んだのがこの御茶ノ水の雪景色でこれはぼく自身が慣れ親しんできた景色でもあるのだけれど、何よりもその横殴りに降る雪の描き方が雪を運んでくる気まぐれな風の動きまで見えそうな動的な雪の表現が珍しく、そして効果的だなぁと思った。
月/陸奥三嶌川

(1919)
月といえばもちろん彼の代表作である「馬込の月」なのだろうけど、この作品は彼のまだ三十代半ばの若い頃の作品だけれども、既に彼の詩情性に溢れていて、もうしっかりと川瀬巴水の世界が出来ている。
青森県八戸にある海辺の湧き水は住民にとって貴重な水源となっており、その三嶌の湧き水を夜分に汲みに来た親子を玉子の黄身のような満月がじっと見下ろしている。池の淵に建つあばら家の向こうに広がる夜の海から波音が聞こえてきそうだ。巴水の詩情性は画面から聞こえてくる微かな音を伴っている。
東京/芝増上寺
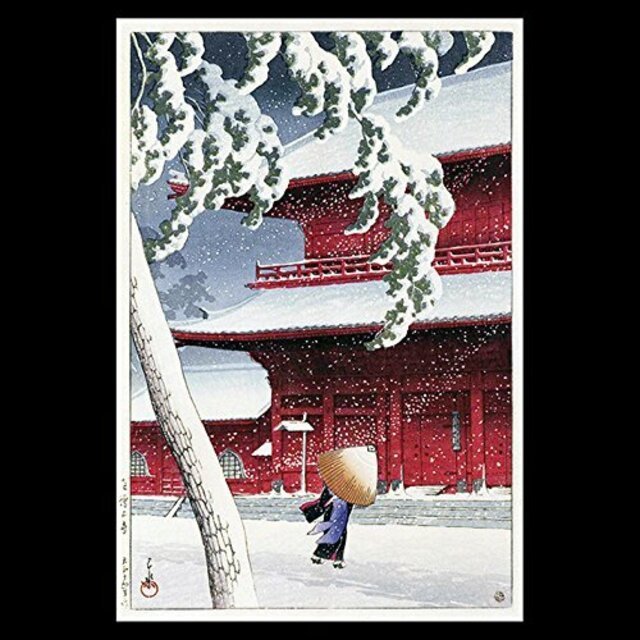
(1925)
ここまで挙げてきた彼の詩情性の要素と「東京」というのにはなんか大きな隔たりがあるように思えるけど、東京生まれの巴水にとっては東京と言う都会の色々な場面に詩情を感じるのは、故郷の山河に思いをはせる思いとなんら変わらないことだったのじゃないかと勝手に思っている。ぼく自身も下町の路地に同じような気持ちをもっているから。
この作品「芝増上寺」はまさに彼の代表作でここで挙げるには余りにベタじゃないかとも思うのだけれど、改めて今回すごいなぁと惚れ直したので…。展示されていたのは初刷りだと思うのだけれど、その赤というか朱というか、その色の深みとインパクトが同じ作品は今まで何回か観たはずなのだが、改めて心に沁みてきた。
構図と言い、色合いと言い完璧に調和のとれた作品で、巴水は似たような構図、状況を各地でも何点か描いているけど、やはりこれに尽きる。ぼくにとって巴水のこの「東京二十景」は歌川広重の「江戸百景」と並んで忘れることのできない作品に満ちている。
[図録]
260頁、2500円。巴水の画集は何種類か出ているけれど、それに比しても全く見劣りのしない画集と言えるし、その割には他の画集よりもコスパが良いのではないか。2013年に大田区立郷土博物館で開催された「生誕130年 川瀬巴水展」の図録に収録されているのが500点で、巴水は生涯で700図を制作したと言われているので、500点というのはすごいことだと思う。
今回の展覧会の図録には300点あまりが掲載されているので、もちろん重複はあるけれど、この二冊の図録で巴水の画業のかなりの部分が見られると思う。と言っておきながら矛盾しているようだけれど、やっぱり一度は実物を観ておくことが肝心だと思う。その上で図録を見れば図版に加えてそれだけでは伝わりにくい部分を記憶が補ってくれるような気がする。
(Oct.2021)
gillman*s Choice Jazzの猫ジャケ
gillman*s Choice...

LPレコードの時代はジャケットは新しいアルバムを手にするときの楽しみの一つでもあったし、そのアルバムを聴いていない時でも好きなジャケットを部屋の見えるところに飾っておくというのも楽しかった。
それがCDになっていきなり小さくなってジャケットの楽しみも大幅に減ってしまったのだけれど、それでもその楽しみが無くなってしまったわけではない。好きなジャケットを机の上に並べてみたり、PCの画面でプレイリストの画面に色々なアルバムのジャケットが並んだ時などはそれはそれで新しい楽しみではあると感じる。
という訳で聴いているジャズのアルバムの中に猫のデザインのあるジャケットが時々目についたのでググッてみたら、それらは「猫ジャケ」といってかなりの数があるらしい。我が家にも猫が三匹いるので手持ちのジャズアルバムの中から猫ジャケを探してみたら結構あるではないか。試しにここに並べてみた。
■The Cat/Jimmy Smith

(1964)
猫ジャケといえば鮮烈な赤色を背景に黒猫がこちらに忍び寄ってくる写真のジャケットでまずこのアルバムを思い浮かべる。LP時代の最初のジャケ買いかもしれない。ジャケットに惹かれて買ったけど中身の音楽はもっと良かった。
メインテーマの曲The Catはスミスの小気味いいオルガンが冴えわたる。今でもこの曲を聴くとワクワクする。3曲目のBasin Street Bluesもスリリングで良い。アルバムに満ちている都会の雰囲気がとても新しく感じられたのを覚えている。今でもよく聴きなおすアルバムだ。
■Charlie Haden-Jim Hall/Charlie Haden & Jim Hall

(2014)
エジプトの猫の像のような猫が二匹シルエットで向かい合っている。シンメトリーな構図と言い、配色と言い実に洗練されたデザインだと思う。1990年7月2日にモントリオール・インターナショナル・ジャズ・フェスティバルで録音されたライブ録音盤。
ベーシストのヘイデンもギターのホールもどちらかと言うグイグイと攻めてくるというよりは玄人好みのスタイルなんだけども、このアルバムでは各々のソロの素晴らしさと、二人のスウィンギーなシンクロがまた何とも言えない。聴けばきくほど味が出てくるアルバムだと思う。
■Paris Blues/Gil Evans,Steve Lacy
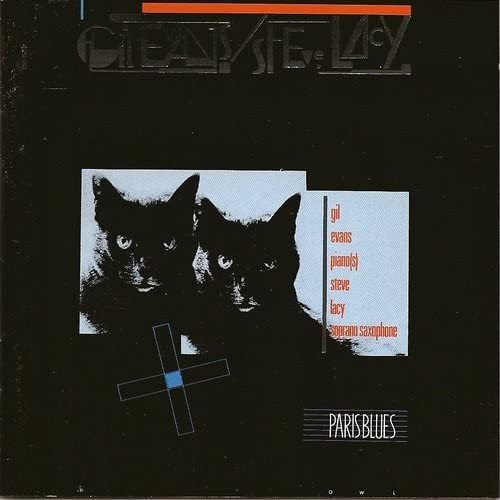
(1988)
ジャケットには二匹の黒猫が寄り添っている(ジャズは黒猫が好きそうだ。もっとも白い可愛い子猫ではジャズとイマイチ雰囲気が…)がこれはもちろんギル・エバンスとスティーブ・レイシーを表しているのだろうけど、ジャケット上の二人の名前を示すタイポグラフィーが凝り過ぎていて殆ど読めないのが残念。
ギル・エバンスはアレンジ界では大御所でぼくも何枚もアルバムを持っているけど、正直言ってぼくの場合ビッグバンドが余り肌に合わないので持っている彼のアルバムはピアニストとしての彼のものが多い。そういう意味ではエバンスのピアノやエレピとスティーヴ・レイシーのソプラノ・サックスだけというこのアルバムは二人の魅力を味わい尽くせるという点でぼくにはありがたい。
アルバムはエバンスの好きなチャールズ・ミンガス作曲の曲の他にエリントンの曲やレイシー自身の曲も入っている。このアルバムは1987年11月30日~12月1日にパリで録音されているけど、翌年の3月にはエバンスが亡くなっているので、もしかしたらこれが彼の最後のアルバムかもしれない。
■The Pat Moran Quartet/Pat Moran

(1956)
これまた漫画チックな猫のカルテット。よく見ると雌猫が二匹とワニみたいなのが二匹。歌っている雌猫はBev Kellyでピアノを弾いている雌猫はPat Moranということになるだろう。モランといえばベツレヘム・レコードのもう一枚のアルバム、美脚アルバムの方が有名なのでこちらはちょっとかすんでいるかもしれない。
パット・モラン・カルテットはパット・モラン・トリオに歌手のベブ・ケリーを加えた4人でこのアルバムでは演奏するとともに全員で歌っているのが面白い。コーラスも良いけどぼくは3曲目のベブが歌っているWhat a difference a day makesが気に入っている。ベブ・ケリー(正式にはベブリー・ケリー)については一度ちゃんと振り返ってみたい。全曲がスタンダードといっていい程お馴染みの曲ばかりで楽しいこと請け合い。
[Personnel]
Pat Moran-piano & Vocals
John Doling-bass & Vacals
Johnny Whited-drums & Vacals
Bev Kelly-Vocals
Recorded Hollywood, CA, May, 1956.
■The Cats/Tommy Flanagan,John Coltrane,Kenny Burrell,Idrees Sulieman

(1957)
全面どぎつい紫色のジャケットに二匹の強面の猫が何かを要求しているような素振りで右のタイトルの方に詰め寄っている。フラナガンもコルトレーンも若い時の録音でそんなつっぱらかった雰囲気に合っていて好きなジャケットなんだけど、リマスター版のCDのジャケットは確かに猫ジャケなんだけど写真が替えられていて4匹の子猫の写真でちょっと可愛すぎ。
このメンバーで悪いわけがないけどぼくは特に2曲目のHow Long Has This Been Going On?(この曲だけトリオ)がフラナガンのピアノがリリカルで好きだ。このアルバムは形的にはトミー・フラナガントリオにコルトレーンとスリーマンの二管とバレルのギターが加わったもので、もちろん全員参加のEclypsoなども小気味いい演奏で好きだ。
曲にはないのになんで"Cats"なのかと思ったけど、当時はジャズマンのことをCATと言っていたらしくて、そういう意味らしい。
[personnel]
Tommy Flanagan-piano
Doug Watkins-bass
Louis Hayes-drums
Kenny Burrell-guitar
John Coltrane-tenor saxophone
Idrees Sulieman-trumpet
■More Swinging Sounds/Shelly Manne&His Men

(1957)
シャンデリアにぶる下がっている猫のイラストのジャケットがシャレている。ぼくの持ってるのはCDだけどLPはコンテンポラリーのレーベルででておりジャケットにはVol.5の文字が入っているのでShelly Manne & His Menでシリーズ化されていたのかもしれない。
シェリー・マンのアルバムでは"My Fair Lady"が一番好きだけどこのアルバムのスウィング感は捨てがたい。
[Personnel]
Shelly Manne (drums)
Charlie Mariano (alto sax)
Stu Williamson (trumpet)
Russ Freeman (piano)
Leroy Vinnegar (bass)
■Presenting...Jackie Mclean/Jackie Mclean

(1956)
ジャケットはこれも黒猫のイラスト、どうもジャズと黒猫は相性が良いようだ。黒猫の手前にモアレ模様の女性の顔がデザインされていてこれがアルバムがリリースされた50年代のものだとしたら、こういうサイケデリックなデザインが流行ったのが60年代後半だから先進的なものだと思う。
アルバムはマクリーンの最初のリーダー作にしてなんか既に完成している感じ。陰影の濃いウォルドロンのピアノと透明感のあるジャクリーンのサックスが微妙にマッチしている。
[personnel]
Jackie Mclean-alto sax
Donald Byrd-trumpet
Doug Watkins-bass
Mal Waldron-piano
Ronald Tucker-drums
■MY CAT ARNOLD/KAREN MANTLER

(1989)
これは完全なジャケ買い。カレン・マントラーというシンガーは知らなかったけど、ジャケットとアルバムタイトルのMY CAT ARNOLDに興味をひかれてどんな曲か聴いてみたいと思った。このタイトル曲はふんわりしていい感じだけどジャズと言うよりぼくにはバックはヒュージョンっぽく響いたし歌の方はより奔放に感じた。
調べてみるとカレン・マントラーの母親はジャズ作曲家、歌手のカーラ・ブレイでマントラーはカーラ・ブレイが前夫ポール・ブレイと別れた後再婚したミュージシャンの姓らしい。カーラ・ブレイの曲はコンセプチャルな感じでポール・ブレイがカーラの作曲した曲ばかりを演奏しているアルバム「Paul Plays Carla」はぼくも持っているけど、曲の奔放さは娘のカレンに繋がっているかもしれないなと思った。
JAZZの猫ジャケ

LPレコードの時代はジャケットは新しいアルバムを手にするときの楽しみの一つでもあったし、そのアルバムを聴いていない時でも好きなジャケットを部屋の見えるところに飾っておくというのも楽しかった。
それがCDになっていきなり小さくなってジャケットの楽しみも大幅に減ってしまったのだけれど、それでもその楽しみが無くなってしまったわけではない。好きなジャケットを机の上に並べてみたり、PCの画面でプレイリストの画面に色々なアルバムのジャケットが並んだ時などはそれはそれで新しい楽しみではあると感じる。
という訳で聴いているジャズのアルバムの中に猫のデザインのあるジャケットが時々目についたのでググッてみたら、それらは「猫ジャケ」といってかなりの数があるらしい。我が家にも猫が三匹いるので手持ちのジャズアルバムの中から猫ジャケを探してみたら結構あるではないか。試しにここに並べてみた。
■The Cat/Jimmy Smith

(1964)
猫ジャケといえば鮮烈な赤色を背景に黒猫がこちらに忍び寄ってくる写真のジャケットでまずこのアルバムを思い浮かべる。LP時代の最初のジャケ買いかもしれない。ジャケットに惹かれて買ったけど中身の音楽はもっと良かった。
メインテーマの曲The Catはスミスの小気味いいオルガンが冴えわたる。今でもこの曲を聴くとワクワクする。3曲目のBasin Street Bluesもスリリングで良い。アルバムに満ちている都会の雰囲気がとても新しく感じられたのを覚えている。今でもよく聴きなおすアルバムだ。
■Charlie Haden-Jim Hall/Charlie Haden & Jim Hall

(2014)
エジプトの猫の像のような猫が二匹シルエットで向かい合っている。シンメトリーな構図と言い、配色と言い実に洗練されたデザインだと思う。1990年7月2日にモントリオール・インターナショナル・ジャズ・フェスティバルで録音されたライブ録音盤。
ベーシストのヘイデンもギターのホールもどちらかと言うグイグイと攻めてくるというよりは玄人好みのスタイルなんだけども、このアルバムでは各々のソロの素晴らしさと、二人のスウィンギーなシンクロがまた何とも言えない。聴けばきくほど味が出てくるアルバムだと思う。
■Paris Blues/Gil Evans,Steve Lacy
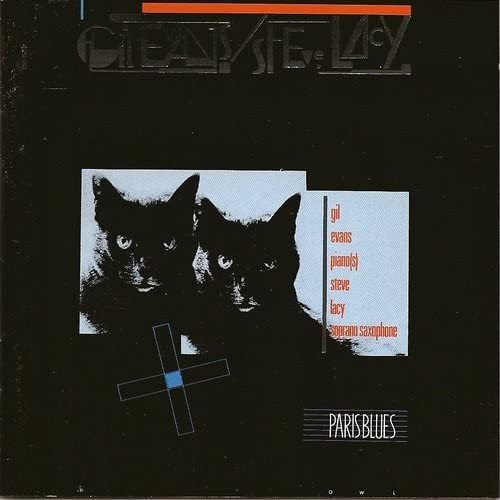
(1988)
ジャケットには二匹の黒猫が寄り添っている(ジャズは黒猫が好きそうだ。もっとも白い可愛い子猫ではジャズとイマイチ雰囲気が…)がこれはもちろんギル・エバンスとスティーブ・レイシーを表しているのだろうけど、ジャケット上の二人の名前を示すタイポグラフィーが凝り過ぎていて殆ど読めないのが残念。
ギル・エバンスはアレンジ界では大御所でぼくも何枚もアルバムを持っているけど、正直言ってぼくの場合ビッグバンドが余り肌に合わないので持っている彼のアルバムはピアニストとしての彼のものが多い。そういう意味ではエバンスのピアノやエレピとスティーヴ・レイシーのソプラノ・サックスだけというこのアルバムは二人の魅力を味わい尽くせるという点でぼくにはありがたい。
アルバムはエバンスの好きなチャールズ・ミンガス作曲の曲の他にエリントンの曲やレイシー自身の曲も入っている。このアルバムは1987年11月30日~12月1日にパリで録音されているけど、翌年の3月にはエバンスが亡くなっているので、もしかしたらこれが彼の最後のアルバムかもしれない。
■The Pat Moran Quartet/Pat Moran

(1956)
これまた漫画チックな猫のカルテット。よく見ると雌猫が二匹とワニみたいなのが二匹。歌っている雌猫はBev Kellyでピアノを弾いている雌猫はPat Moranということになるだろう。モランといえばベツレヘム・レコードのもう一枚のアルバム、美脚アルバムの方が有名なのでこちらはちょっとかすんでいるかもしれない。
パット・モラン・カルテットはパット・モラン・トリオに歌手のベブ・ケリーを加えた4人でこのアルバムでは演奏するとともに全員で歌っているのが面白い。コーラスも良いけどぼくは3曲目のベブが歌っているWhat a difference a day makesが気に入っている。ベブ・ケリー(正式にはベブリー・ケリー)については一度ちゃんと振り返ってみたい。全曲がスタンダードといっていい程お馴染みの曲ばかりで楽しいこと請け合い。
[Personnel]
Pat Moran-piano & Vocals
John Doling-bass & Vacals
Johnny Whited-drums & Vacals
Bev Kelly-Vocals
Recorded Hollywood, CA, May, 1956.
■The Cats/Tommy Flanagan,John Coltrane,Kenny Burrell,Idrees Sulieman

(1957)
全面どぎつい紫色のジャケットに二匹の強面の猫が何かを要求しているような素振りで右のタイトルの方に詰め寄っている。フラナガンもコルトレーンも若い時の録音でそんなつっぱらかった雰囲気に合っていて好きなジャケットなんだけど、リマスター版のCDのジャケットは確かに猫ジャケなんだけど写真が替えられていて4匹の子猫の写真でちょっと可愛すぎ。
このメンバーで悪いわけがないけどぼくは特に2曲目のHow Long Has This Been Going On?(この曲だけトリオ)がフラナガンのピアノがリリカルで好きだ。このアルバムは形的にはトミー・フラナガントリオにコルトレーンとスリーマンの二管とバレルのギターが加わったもので、もちろん全員参加のEclypsoなども小気味いい演奏で好きだ。
曲にはないのになんで"Cats"なのかと思ったけど、当時はジャズマンのことをCATと言っていたらしくて、そういう意味らしい。
[personnel]
Tommy Flanagan-piano
Doug Watkins-bass
Louis Hayes-drums
Kenny Burrell-guitar
John Coltrane-tenor saxophone
Idrees Sulieman-trumpet
■More Swinging Sounds/Shelly Manne&His Men

(1957)
シャンデリアにぶる下がっている猫のイラストのジャケットがシャレている。ぼくの持ってるのはCDだけどLPはコンテンポラリーのレーベルででておりジャケットにはVol.5の文字が入っているのでShelly Manne & His Menでシリーズ化されていたのかもしれない。
シェリー・マンのアルバムでは"My Fair Lady"が一番好きだけどこのアルバムのスウィング感は捨てがたい。
[Personnel]
Shelly Manne (drums)
Charlie Mariano (alto sax)
Stu Williamson (trumpet)
Russ Freeman (piano)
Leroy Vinnegar (bass)
■Presenting...Jackie Mclean/Jackie Mclean

(1956)
ジャケットはこれも黒猫のイラスト、どうもジャズと黒猫は相性が良いようだ。黒猫の手前にモアレ模様の女性の顔がデザインされていてこれがアルバムがリリースされた50年代のものだとしたら、こういうサイケデリックなデザインが流行ったのが60年代後半だから先進的なものだと思う。
アルバムはマクリーンの最初のリーダー作にしてなんか既に完成している感じ。陰影の濃いウォルドロンのピアノと透明感のあるジャクリーンのサックスが微妙にマッチしている。
[personnel]
Jackie Mclean-alto sax
Donald Byrd-trumpet
Doug Watkins-bass
Mal Waldron-piano
Ronald Tucker-drums
■MY CAT ARNOLD/KAREN MANTLER

(1989)
これは完全なジャケ買い。カレン・マントラーというシンガーは知らなかったけど、ジャケットとアルバムタイトルのMY CAT ARNOLDに興味をひかれてどんな曲か聴いてみたいと思った。このタイトル曲はふんわりしていい感じだけどジャズと言うよりぼくにはバックはヒュージョンっぽく響いたし歌の方はより奔放に感じた。
調べてみるとカレン・マントラーの母親はジャズ作曲家、歌手のカーラ・ブレイでマントラーはカーラ・ブレイが前夫ポール・ブレイと別れた後再婚したミュージシャンの姓らしい。カーラ・ブレイの曲はコンセプチャルな感じでポール・ブレイがカーラの作曲した曲ばかりを演奏しているアルバム「Paul Plays Carla」はぼくも持っているけど、曲の奔放さは娘のカレンに繋がっているかもしれないなと思った。
(Aug.2021)
gillman*s Choice Venus Records
gillman*s Choide...
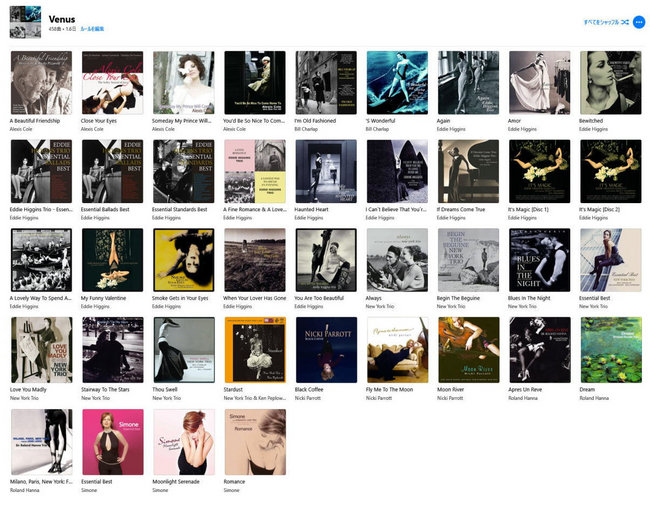
またジャケットの話で恐縮だけれど、レーベルによってジャケットの傾向が変わってくるということもあってレーベルを少し整理しておこうと思って、手持ちのCDのデータベースにレーベルの登録を始めたのだけれど結構手間がかかってまだ2割くらいしか手が付いていない。
その作業の中で比較的新しいレーベルなのだけれどVenus Recordsのジャケットはスタイリッシュな写真を意識的にジャケットにしている戦略なんだと再認識した。もちろんこれは有名な話なんだけれど、こうして並べてみると、これは原さんの趣味なのかもしれないと思った。
ヴィーナスレコードは1992年、日本ビクターでプロデューサーだった原哲夫氏が設立した日本のジャズ専門レーベルとして30年近い歴史を持っている。主に米国やヨーロッパで活躍するジャズミュージシャンの演奏を録音したりしている。
ぼくの手元の登録済みのCDではEddie Higgins、Alexis Cole、Bill Charlap、New York Trio、Nicki Parrott、Roland HannaやSimoneといったところだけれど、例えばNew York Trioと言っても海外では誰も知らないかもしれないが、これはVenus Recordが日本のマーケットだけに向けてBill Charlapをリーダーに据えて組んだトリオなのらしい。
よく見ると同じ写真でもスタイリッシュなものと艶っぽい路線のとがあって、スタイリッシュな方ではEddie Higgins Trioの「Again」とか「Haunted Heart」なんかが好きだ。Alexis Coleの「You'd Be So Nice To Come Home To」なんかもあか抜けていて良い。


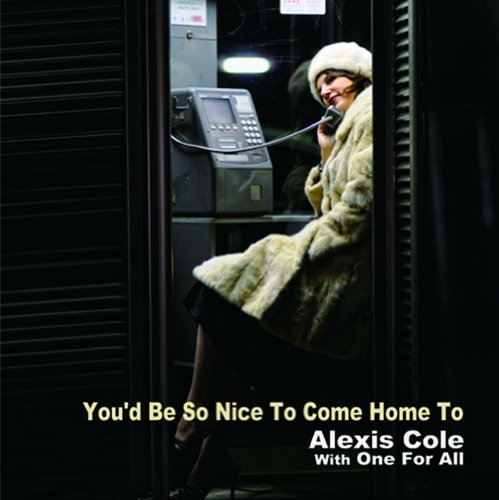
それに対してやはりEddie Higinsの「It's Magic」やRoland Hannaの「Apres Un Reve」はいかにも艶っぽい。ここら辺になると評判でも賛否両論で嫌いだという人も結構いたりする。まぁ、それだけで中身の音楽自体を決めつけられるのは勘弁だけれど、ジャケ買いというのもあるから大事な要素ではあるかも。


Venus Records
のジャケット
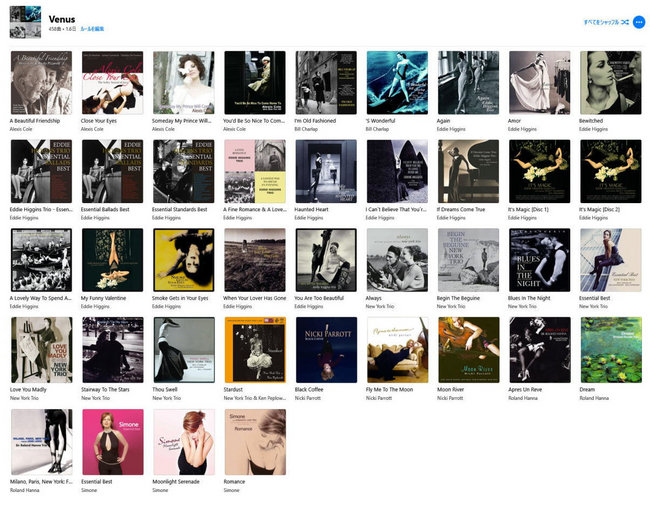
またジャケットの話で恐縮だけれど、レーベルによってジャケットの傾向が変わってくるということもあってレーベルを少し整理しておこうと思って、手持ちのCDのデータベースにレーベルの登録を始めたのだけれど結構手間がかかってまだ2割くらいしか手が付いていない。
その作業の中で比較的新しいレーベルなのだけれどVenus Recordsのジャケットはスタイリッシュな写真を意識的にジャケットにしている戦略なんだと再認識した。もちろんこれは有名な話なんだけれど、こうして並べてみると、これは原さんの趣味なのかもしれないと思った。
ヴィーナスレコードは1992年、日本ビクターでプロデューサーだった原哲夫氏が設立した日本のジャズ専門レーベルとして30年近い歴史を持っている。主に米国やヨーロッパで活躍するジャズミュージシャンの演奏を録音したりしている。
ぼくの手元の登録済みのCDではEddie Higgins、Alexis Cole、Bill Charlap、New York Trio、Nicki Parrott、Roland HannaやSimoneといったところだけれど、例えばNew York Trioと言っても海外では誰も知らないかもしれないが、これはVenus Recordが日本のマーケットだけに向けてBill Charlapをリーダーに据えて組んだトリオなのらしい。
よく見ると同じ写真でもスタイリッシュなものと艶っぽい路線のとがあって、スタイリッシュな方ではEddie Higgins Trioの「Again」とか「Haunted Heart」なんかが好きだ。Alexis Coleの「You'd Be So Nice To Come Home To」なんかもあか抜けていて良い。


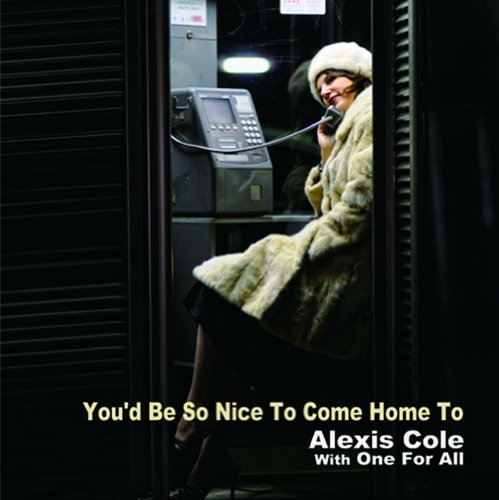
それに対してやはりEddie Higinsの「It's Magic」やRoland Hannaの「Apres Un Reve」はいかにも艶っぽい。ここら辺になると評判でも賛否両論で嫌いだという人も結構いたりする。まぁ、それだけで中身の音楽自体を決めつけられるのは勘弁だけれど、ジャケ買いというのもあるから大事な要素ではあるかも。


(Nov.2021)
gillman*s Choice California Cool
Book Review...
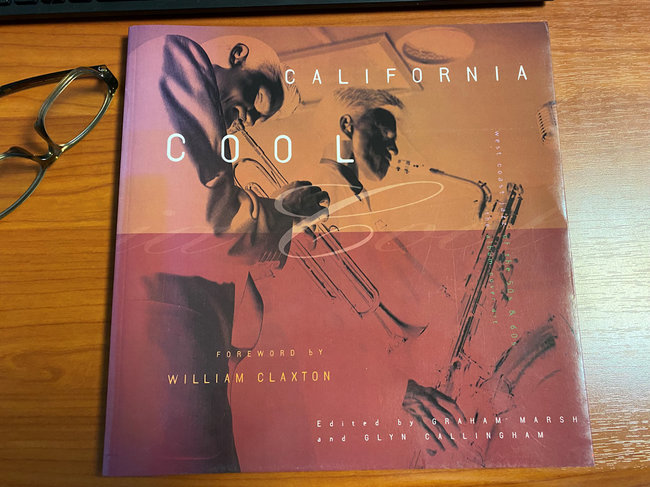
Jazzのレコード・ジャケットの写真集も第三弾になってしまったが、これも前の二冊同様グラハム・マーシュの編集によるものだけれど、一冊目がBlue Noteの特集、そして二冊目がAtlantic、PrestigeそしてRiversideというレーベル別に構成されていたのに対し、これはジャケットのデザイン別に構成されている。

即ち、Studio、Drawings、Girls、Abstract/Graphics、Hats(この分け方は面白い)、Paintings、Location、Moviesそして最後にPhoto Galleryという構成になっている。レーベル別も良いけどこういう分け方も楽しい。写真の大きさは見開きで右が実物大のジャケット、左には縮小されたジャケットの写真が2~4枚という構成。
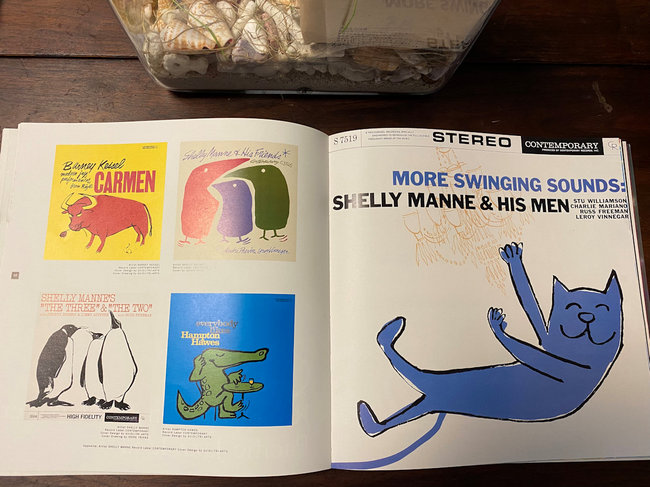

もう一つの違いは、タイトルにCalifornia Coolとあるように、こちらは西海岸つまりウエストコースト・ジャズのシーンを中心に構成されている。サブタイトルには50年代、62年代のウエストコースト・ジャズのアルバム・カバー・アートとなっている。
そしてさらに特徴的なことはこの写真集は広範なジャズシーンを撮り続けた写真家ウイリアム・クラックストン(William Claxton)の写真を多く載せているということだ。彼のスタジオ撮影や最後の方のフォト・ギャラリーにも多くの彼の作品が載せられている。
中でも彼が頻繁に撮影したのがチェット・ベイカーとアート・ペッパーで、彼らのLPのジャケット写真の中ではクラックストンの撮影になるものも多い。(ジャズ以外にも俳優の中ではクラックストンは頻繁にスティーブ・マックイーンを撮っていた)

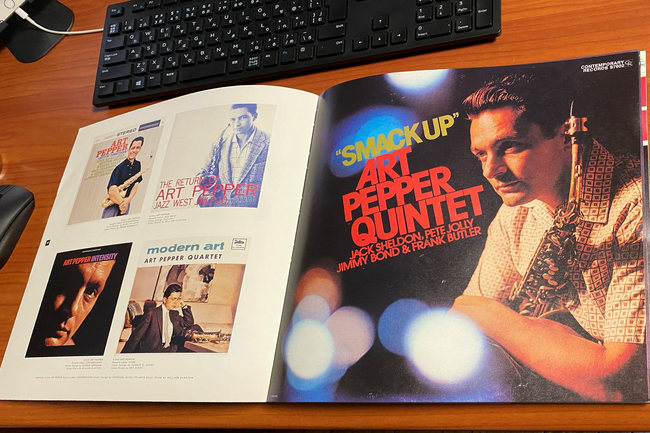
このクラックストンの伝記的な映画がドイツで作成された「Jazz Seen」でこの中には色々なインタビューや数多くのジャズ・ミュージシャンの話なども出てきて興味深い。(写真とジャズに興味のない人には全くつまらない映画だとおもうけど…)
今ではCDに乗りえてしまったので手元にジャケットはないけど、お陰で雰囲気だけでもジャケットの楽しみに浸れるし、気に入ったジャケットのLPがCDで出ていないか探すのも新たな楽しみになった。
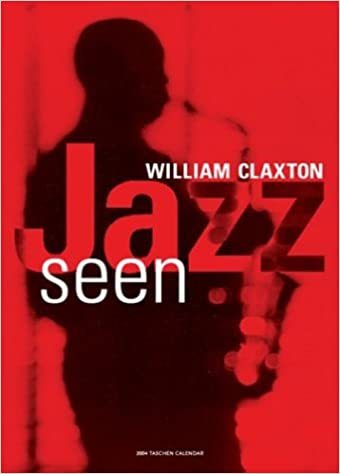
California Cool
West Coast Jazz
of the 50s & 60s
The Album Cover Art
Jazzのレコード・ジャケットの写真集も第三弾になってしまったが、これも前の二冊同様グラハム・マーシュの編集によるものだけれど、一冊目がBlue Noteの特集、そして二冊目がAtlantic、PrestigeそしてRiversideというレーベル別に構成されていたのに対し、これはジャケットのデザイン別に構成されている。
即ち、Studio、Drawings、Girls、Abstract/Graphics、Hats(この分け方は面白い)、Paintings、Location、Moviesそして最後にPhoto Galleryという構成になっている。レーベル別も良いけどこういう分け方も楽しい。写真の大きさは見開きで右が実物大のジャケット、左には縮小されたジャケットの写真が2~4枚という構成。
もう一つの違いは、タイトルにCalifornia Coolとあるように、こちらは西海岸つまりウエストコースト・ジャズのシーンを中心に構成されている。サブタイトルには50年代、62年代のウエストコースト・ジャズのアルバム・カバー・アートとなっている。
そしてさらに特徴的なことはこの写真集は広範なジャズシーンを撮り続けた写真家ウイリアム・クラックストン(William Claxton)の写真を多く載せているということだ。彼のスタジオ撮影や最後の方のフォト・ギャラリーにも多くの彼の作品が載せられている。
中でも彼が頻繁に撮影したのがチェット・ベイカーとアート・ペッパーで、彼らのLPのジャケット写真の中ではクラックストンの撮影になるものも多い。(ジャズ以外にも俳優の中ではクラックストンは頻繁にスティーブ・マックイーンを撮っていた)
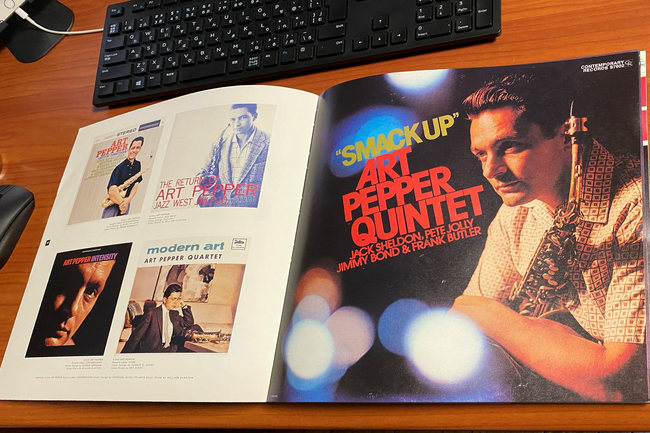
このクラックストンの伝記的な映画がドイツで作成された「Jazz Seen」でこの中には色々なインタビューや数多くのジャズ・ミュージシャンの話なども出てきて興味深い。(写真とジャズに興味のない人には全くつまらない映画だとおもうけど…)
今ではCDに乗りえてしまったので手元にジャケットはないけど、お陰で雰囲気だけでもジャケットの楽しみに浸れるし、気に入ったジャケットのLPがCDで出ていないか探すのも新たな楽しみになった。
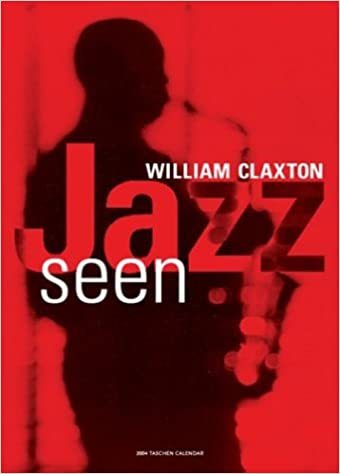
(Oct.2021)
gillman*s Choice East Coasting
Book Review...
By GRaham Marsh and Glyn Callingham
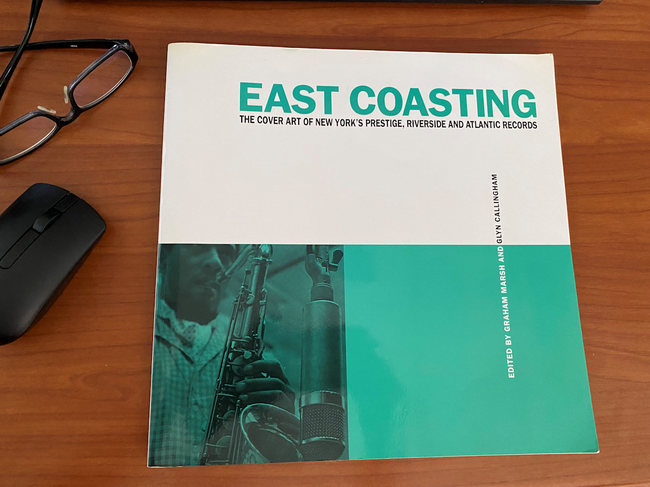
この間紹介したレコードのジャケットデザインを載せた「THE COLLECTION/BLUE NOTE RECORDS」と同じ著者グラハム・マーシュによるジャケットデザインの本だけど、あちらがBlue Noteのジャケット専門だったのに対して、こちらはBlue Noteとジャズの三大レーベルと言われたPrestige、AtlanticとRiversideのレコードジャケットの特集だ。
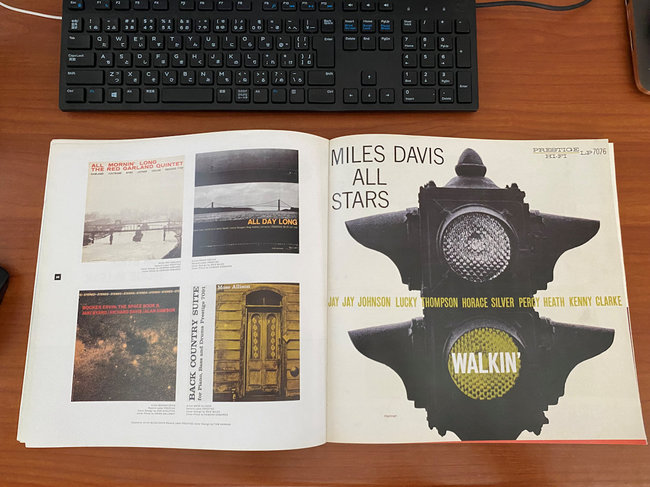
一番の違いはBlue Note版が実際のLPレコードより一回り小さい版だったのに対して、こちらは実物大の大きさでジャケットデザインが載せられている。但し、全てがその大きさではなくて先のBlue Note版と同じように見開きで右のページには実物大のジャケットが左の頁には縮小したジャケットの写真が4枚載っているという構成になっている。

タイトルのEast Coastingとはこの本にも載っているビル・エヴァンスも参加しているチャーリー・ミンガスのアルバムのタイトルでもあり曲名でもあるが、もちろんそれはWest Coastジャズに対する、50年代と60年代に東海岸から出てきたEast Coastジャズの主張でもある。
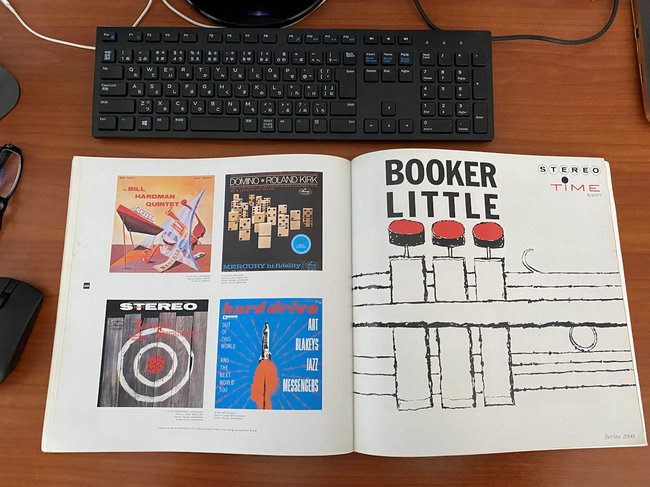
冒頭でこの本ではPrestigeとRiversideのレーベルのレコードを扱っていると言ったけれど、それ以外のレーベルのジャケットも掲載されている。先のミンガスのEast CoastingもレーベルはBethlehem Recordである。他にもImpulseレーベル等も載っている。
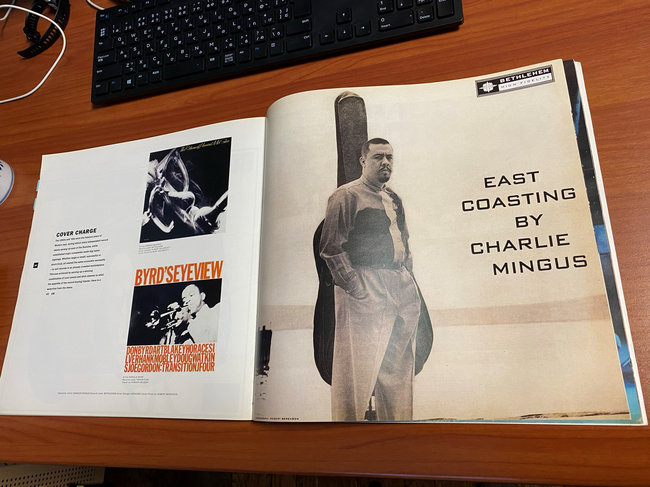
色々なレーベルのデザインも混在しているため一概には言えないけど、タイポグラフィーの扱い方や写真の質はBlue Noteの方が上質に思えるのはやっぱりリード・マイルズ達のセンスの賜物かも知れない。しかし、Prestigeのジャケットで良いなと思うやつのキャプションを見るとリード・マイルズのデザインのが何点かあったので彼はBlue Note以外のレーベルのデザインもしていたようだ。
いずれにしてもこの原寸大のジャケットはそれはそれで楽しめる。古書で探したので結構安く手に入った。
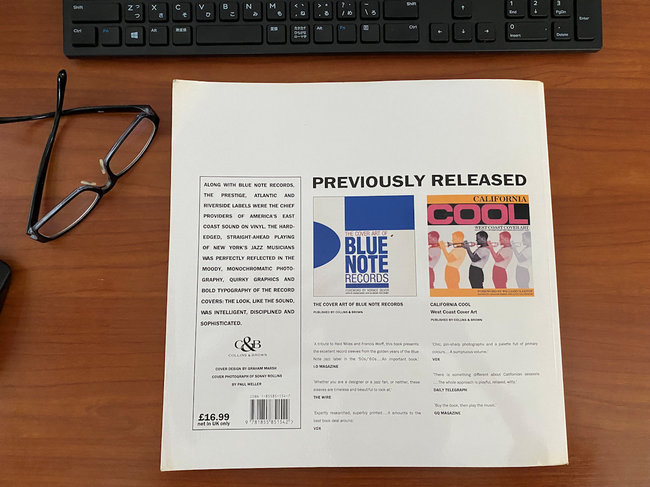
East Coasting
The Cover Art of New York's
PRESTIGE,RIVERSIDE AND ATLANTIC RECORDS
By GRaham Marsh and Glyn Callingham
この間紹介したレコードのジャケットデザインを載せた「THE COLLECTION/BLUE NOTE RECORDS」と同じ著者グラハム・マーシュによるジャケットデザインの本だけど、あちらがBlue Noteのジャケット専門だったのに対して、こちらはBlue Noteとジャズの三大レーベルと言われたPrestige、AtlanticとRiversideのレコードジャケットの特集だ。
一番の違いはBlue Note版が実際のLPレコードより一回り小さい版だったのに対して、こちらは実物大の大きさでジャケットデザインが載せられている。但し、全てがその大きさではなくて先のBlue Note版と同じように見開きで右のページには実物大のジャケットが左の頁には縮小したジャケットの写真が4枚載っているという構成になっている。
タイトルのEast Coastingとはこの本にも載っているビル・エヴァンスも参加しているチャーリー・ミンガスのアルバムのタイトルでもあり曲名でもあるが、もちろんそれはWest Coastジャズに対する、50年代と60年代に東海岸から出てきたEast Coastジャズの主張でもある。
冒頭でこの本ではPrestigeとRiversideのレーベルのレコードを扱っていると言ったけれど、それ以外のレーベルのジャケットも掲載されている。先のミンガスのEast CoastingもレーベルはBethlehem Recordである。他にもImpulseレーベル等も載っている。
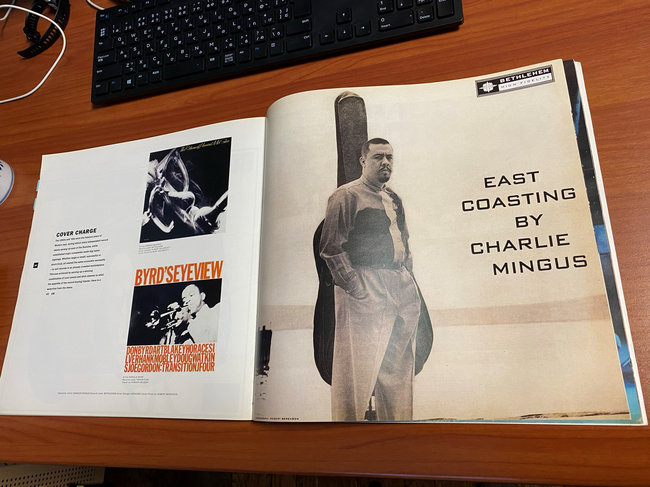
色々なレーベルのデザインも混在しているため一概には言えないけど、タイポグラフィーの扱い方や写真の質はBlue Noteの方が上質に思えるのはやっぱりリード・マイルズ達のセンスの賜物かも知れない。しかし、Prestigeのジャケットで良いなと思うやつのキャプションを見るとリード・マイルズのデザインのが何点かあったので彼はBlue Note以外のレーベルのデザインもしていたようだ。
いずれにしてもこの原寸大のジャケットはそれはそれで楽しめる。古書で探したので結構安く手に入った。
(Oct.2021)
gillman*s Choice Portrait in Jazz
Book Review...
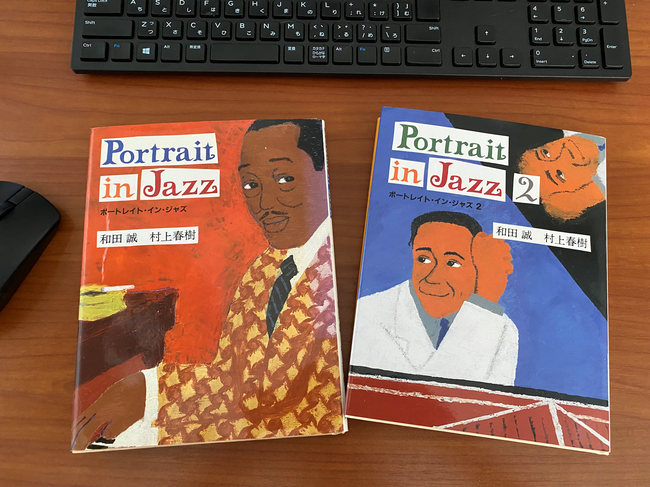
イラスト:和田誠
エッセイ:村上春樹
10月7日は和田誠さんの命日で今年は三回忌に当たると思うのだけど、その日は以前手に入れた「週刊文春」のカヴァー・イラストレーションを網羅した画集「表紙はうたう完全版」をまたじっくりと眺めた。

その時一緒に読んだというか、ページをめくったのがこの「Protrait in Jazz」と「Protrait in Jazz 2」だった。映画とともにジャズ通としても知られていた和田さんだが、この本のきっかけは和田氏が1992年に20人の名ジャズプレイヤーのイラストの個展を開いたのだけれど、そのイラストを小説家の村上春樹氏が気に入ってジャズプレイヤーそれぞれのイラストに村上氏がエッセイを付けたのが初めらしい。
ということなので、まず和田氏が選んだプレイヤーのイラストを描き、それに村上氏がエッセイを付けるという形で「Protrait in Jazz」で26人、その2で25人のジャズプレーヤーのイラストが揃った。殆どが1940年代から60年代にかけての往年のプレーヤーだけど、どのイラストをとっても唸るほど特徴が良くとらえられていて、しかもその人物を見る和田氏の暖かい眼差しが感じられる。
村上氏のエッセイはそのプレーヤーに対する彼の想いと、選ばれた一枚のLPレコードで成り立っている。ぼくが今まで読んだ村上氏の文章は殆どが音楽か酒にまつわるもので、不届きにも彼の小説は未だに読んだことがないのだけれども…。彼のエッセイは日本のジャズファンのまさに黎明期の熱を含んでいる。和田さんのイラストと村上氏の文章でそのプレーヤーの姿が立体的に浮かび上がってくる。主にネット配信で聴く今の若いファンには新鮮だろうし、ジャズ喫茶でモダンジャズを聴いていた世代は頷くことが多いかもしれない。

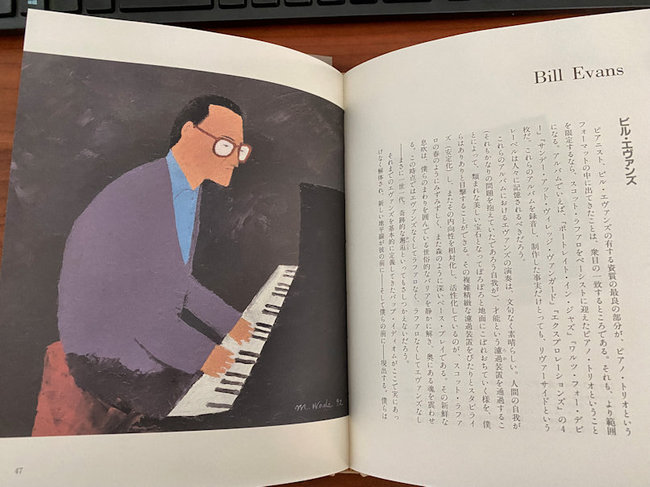
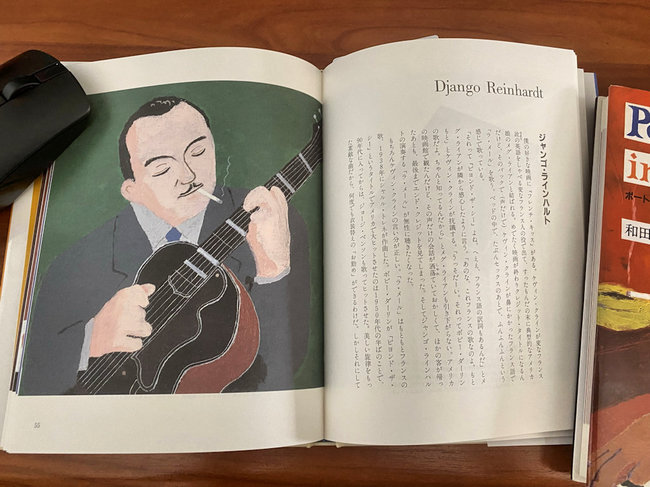
どのページのイラストも文章も好きなのだけれど、特にビリー・ホリデー、ビル・エヴァンスそしてジャンゴ・ラインハルトのイラストが特に素敵だ。凛としたホリデー、ガラスのように繊細なエヴァンスそして慈しむようにギターを抱えるジャンゴの優しい眼差し。どれも素敵だ。
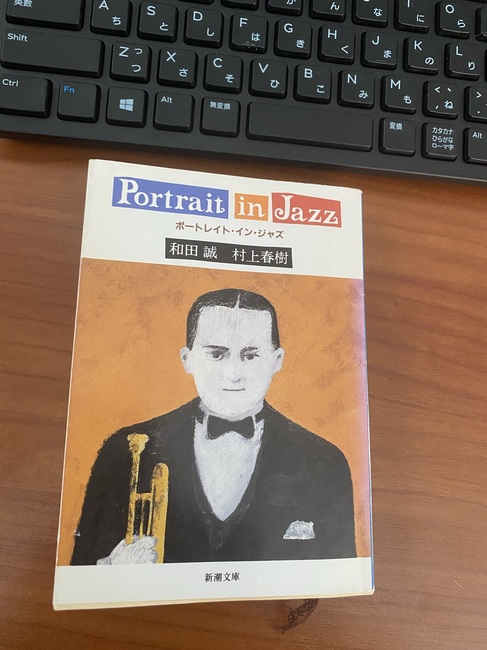
二冊を合本した文庫版も出ているけど、大型の方には絵本的な楽しさもある。
またそれぞれの著書の中で村上春樹氏が選んだミュージシャンの曲を10曲強収録したCDアルバムが異なるレコード会社から出されている。
■ポートレイト・イン・ジャズ 和田誠・村上春樹セレクション(ソニー・ミュージックレコーズ)

[収録ミュージシャン]
ビリー・ホリデイ、マイルス・デイビス、ベニー・グッドマン、ビックス・バイダーベック、ジェリー・マリガン、デクスター・ゴードン、チュー・ベリー、ルイ・アームストロング、チャーリー・クリスチャンなど11曲。
■ポートレイト・イン・ジャズ 和田誠・村上春樹セレクション(ポリドール)
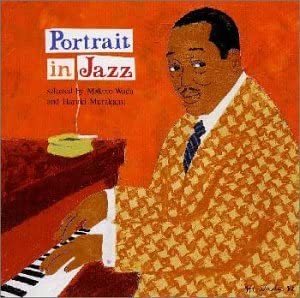
[収録ミュージシャン]
チャーリー・パーカー、ハーブ・ゲラー、アート・ブレイキー、スタン・ゲッツ、ビル・エヴァンス、デューク・エリントン、エラ・フィッツジェラルド、エリック・ドルフィー、カウント・ベイシー、ナット・キング・コール、ディジー・ガレスピー、セロニアス・モンク、レスター・ヤングなど13曲。
Protrait in Jazz
Protrait in Jazz2
イラスト:和田誠
エッセイ:村上春樹
10月7日は和田誠さんの命日で今年は三回忌に当たると思うのだけど、その日は以前手に入れた「週刊文春」のカヴァー・イラストレーションを網羅した画集「表紙はうたう完全版」をまたじっくりと眺めた。

その時一緒に読んだというか、ページをめくったのがこの「Protrait in Jazz」と「Protrait in Jazz 2」だった。映画とともにジャズ通としても知られていた和田さんだが、この本のきっかけは和田氏が1992年に20人の名ジャズプレイヤーのイラストの個展を開いたのだけれど、そのイラストを小説家の村上春樹氏が気に入ってジャズプレイヤーそれぞれのイラストに村上氏がエッセイを付けたのが初めらしい。
ということなので、まず和田氏が選んだプレイヤーのイラストを描き、それに村上氏がエッセイを付けるという形で「Protrait in Jazz」で26人、その2で25人のジャズプレーヤーのイラストが揃った。殆どが1940年代から60年代にかけての往年のプレーヤーだけど、どのイラストをとっても唸るほど特徴が良くとらえられていて、しかもその人物を見る和田氏の暖かい眼差しが感じられる。
村上氏のエッセイはそのプレーヤーに対する彼の想いと、選ばれた一枚のLPレコードで成り立っている。ぼくが今まで読んだ村上氏の文章は殆どが音楽か酒にまつわるもので、不届きにも彼の小説は未だに読んだことがないのだけれども…。彼のエッセイは日本のジャズファンのまさに黎明期の熱を含んでいる。和田さんのイラストと村上氏の文章でそのプレーヤーの姿が立体的に浮かび上がってくる。主にネット配信で聴く今の若いファンには新鮮だろうし、ジャズ喫茶でモダンジャズを聴いていた世代は頷くことが多いかもしれない。
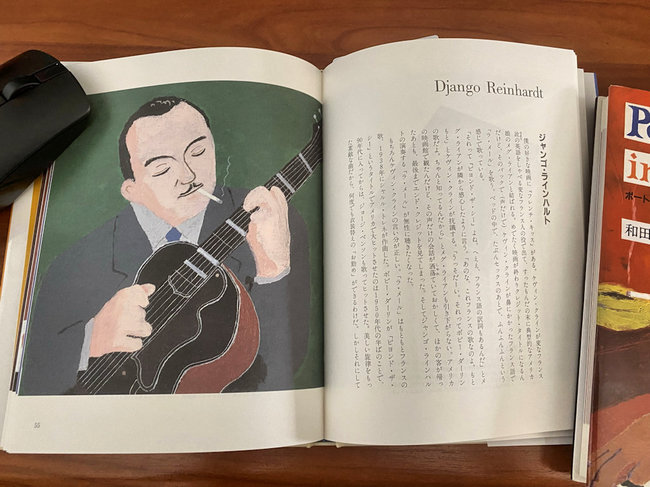
どのページのイラストも文章も好きなのだけれど、特にビリー・ホリデー、ビル・エヴァンスそしてジャンゴ・ラインハルトのイラストが特に素敵だ。凛としたホリデー、ガラスのように繊細なエヴァンスそして慈しむようにギターを抱えるジャンゴの優しい眼差し。どれも素敵だ。
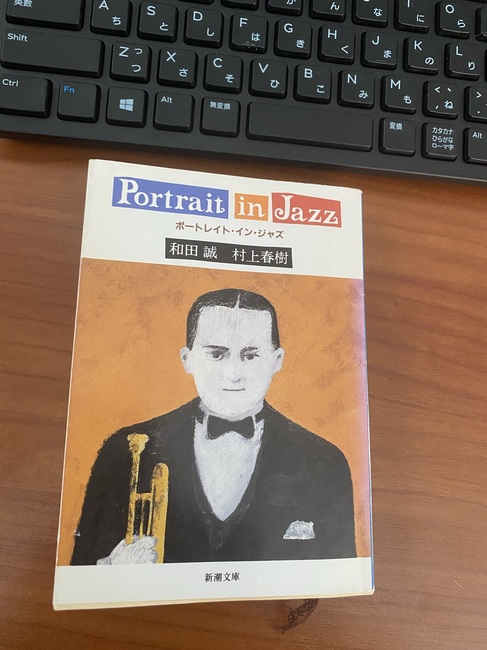
二冊を合本した文庫版も出ているけど、大型の方には絵本的な楽しさもある。
またそれぞれの著書の中で村上春樹氏が選んだミュージシャンの曲を10曲強収録したCDアルバムが異なるレコード会社から出されている。
■ポートレイト・イン・ジャズ 和田誠・村上春樹セレクション(ソニー・ミュージックレコーズ)

[収録ミュージシャン]
ビリー・ホリデイ、マイルス・デイビス、ベニー・グッドマン、ビックス・バイダーベック、ジェリー・マリガン、デクスター・ゴードン、チュー・ベリー、ルイ・アームストロング、チャーリー・クリスチャンなど11曲。
■ポートレイト・イン・ジャズ 和田誠・村上春樹セレクション(ポリドール)
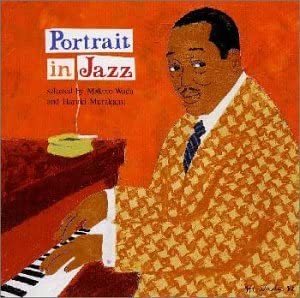
[収録ミュージシャン]
チャーリー・パーカー、ハーブ・ゲラー、アート・ブレイキー、スタン・ゲッツ、ビル・エヴァンス、デューク・エリントン、エラ・フィッツジェラルド、エリック・ドルフィー、カウント・ベイシー、ナット・キング・コール、ディジー・ガレスピー、セロニアス・モンク、レスター・ヤングなど13曲。
(Oct.2021)
gillman*s Choice BLUE NOTE RECORDS
Book Review...
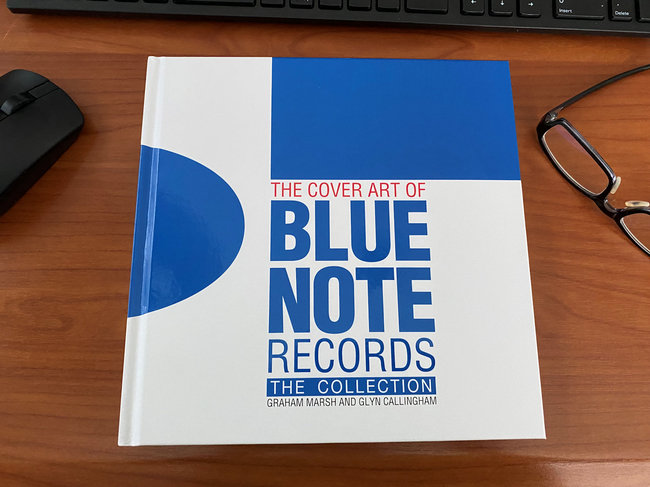
音楽界では今やネット配信が主流になってCD自体もある意味では過去のものになりつつある感がある。方やLPが息を吹き返して巷では中古レコード市場が活気づいていると聞いている。
ぼく自身は今はCD中心にそれとCDからPCのハードディスに落とした4万曲弱の音楽の海の中を楽しく漂っている。昔はオーディオファンの端くれとしてLPもLPの再生装置もそれなりに持ってはいたけれど仕事のリタイアを機に全てをCDに切り替えた。それにはいくつかの理由があるけど、今でもそのことに後悔はしていない。

とは言いつつ、LPを離れたことに一つだけちょっと残念に思っていることがある。それはジャケットがCD化ですごく小さくなってしまったことだ。買ってきたLPに心ときめかせ、盤をクリーナーで綺麗に撫でまわし、そっと針を落とす。スピーカーの前に陣取りジャケットを眺めつつライナーノーツに目を通す。この時間が何といっても至福の時間だった。
もちろん今なりのジャケットの楽しみ方はあって、ぼくは良く自分で作ったプレイリストのアルバムジャケットをPCの画面に並べて一人悦に入ることもあるけど…。

前置きが長くなったけど、そんなジャズのジャケット好きにはたまらない写真集が出た。BLUE NOTEのジャケットばかり400点以上の写真が載っている。大きさはLP盤より小さいのがちょっと不満ではあるけどジャケットを一つの作品として楽しむには充分だ。以前にも国内外でBLUE NOTEのジャケット本は何冊かは出ていたけど結構お値段も高かった。それが今年になって英語版だけど3千円以下で出版されたので手に入れて楽しんでいる。

BLUE NOTE RECORDSは言うまでもなくドイツ出身のアルフレッド・ライオン等によって1939年にニューヨークで設立されたのだけれど、彼の幼なじみのプロの写真家フランシス・ウォルフは1939年末にアメリカに移住してすぐにライオンと協力して会社を盛り立てていった。つまりBLUE NOTEの創成期はこのライオン(Lion)と狼(Wolf名前のスペルはWolffだが)のコンビで推進されていたわけだ。

そのウォルフはジャケットの写真を担当、そしてタイポグラフィーなどのデザインを担当したのがリード・マイルズだ。この二人が作り出したジャケットの傑作が日本人にも最も好まれているアルバムの一つSonny Clearkの「Cool Struttin'」でこの本の巻頭も飾っている。
BLUE NOTEのジャケットも後年になるとカラー写真が多くなってそれなりに今風になっているのだけれど、ぼく自身はやっぱりブルーの写真にシンプルなタイポグラフィーのジャケットが好きだ。それらのデザインは時を経た今でも少しも古さを感じさせないと思う。
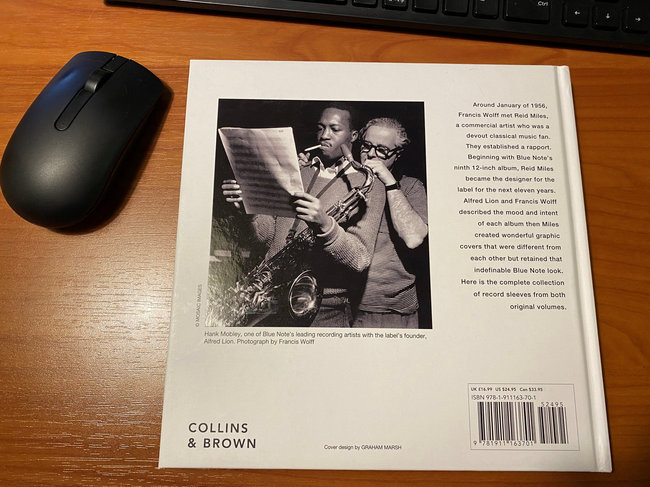
THE COLLECTION
BLUE NOTE RECORDS
音楽界では今やネット配信が主流になってCD自体もある意味では過去のものになりつつある感がある。方やLPが息を吹き返して巷では中古レコード市場が活気づいていると聞いている。
ぼく自身は今はCD中心にそれとCDからPCのハードディスに落とした4万曲弱の音楽の海の中を楽しく漂っている。昔はオーディオファンの端くれとしてLPもLPの再生装置もそれなりに持ってはいたけれど仕事のリタイアを機に全てをCDに切り替えた。それにはいくつかの理由があるけど、今でもそのことに後悔はしていない。
とは言いつつ、LPを離れたことに一つだけちょっと残念に思っていることがある。それはジャケットがCD化ですごく小さくなってしまったことだ。買ってきたLPに心ときめかせ、盤をクリーナーで綺麗に撫でまわし、そっと針を落とす。スピーカーの前に陣取りジャケットを眺めつつライナーノーツに目を通す。この時間が何といっても至福の時間だった。
もちろん今なりのジャケットの楽しみ方はあって、ぼくは良く自分で作ったプレイリストのアルバムジャケットをPCの画面に並べて一人悦に入ることもあるけど…。

前置きが長くなったけど、そんなジャズのジャケット好きにはたまらない写真集が出た。BLUE NOTEのジャケットばかり400点以上の写真が載っている。大きさはLP盤より小さいのがちょっと不満ではあるけどジャケットを一つの作品として楽しむには充分だ。以前にも国内外でBLUE NOTEのジャケット本は何冊かは出ていたけど結構お値段も高かった。それが今年になって英語版だけど3千円以下で出版されたので手に入れて楽しんでいる。
BLUE NOTE RECORDSは言うまでもなくドイツ出身のアルフレッド・ライオン等によって1939年にニューヨークで設立されたのだけれど、彼の幼なじみのプロの写真家フランシス・ウォルフは1939年末にアメリカに移住してすぐにライオンと協力して会社を盛り立てていった。つまりBLUE NOTEの創成期はこのライオン(Lion)と狼(Wolf名前のスペルはWolffだが)のコンビで推進されていたわけだ。
そのウォルフはジャケットの写真を担当、そしてタイポグラフィーなどのデザインを担当したのがリード・マイルズだ。この二人が作り出したジャケットの傑作が日本人にも最も好まれているアルバムの一つSonny Clearkの「Cool Struttin'」でこの本の巻頭も飾っている。
BLUE NOTEのジャケットも後年になるとカラー写真が多くなってそれなりに今風になっているのだけれど、ぼく自身はやっぱりブルーの写真にシンプルなタイポグラフィーのジャケットが好きだ。それらのデザインは時を経た今でも少しも古さを感じさせないと思う。
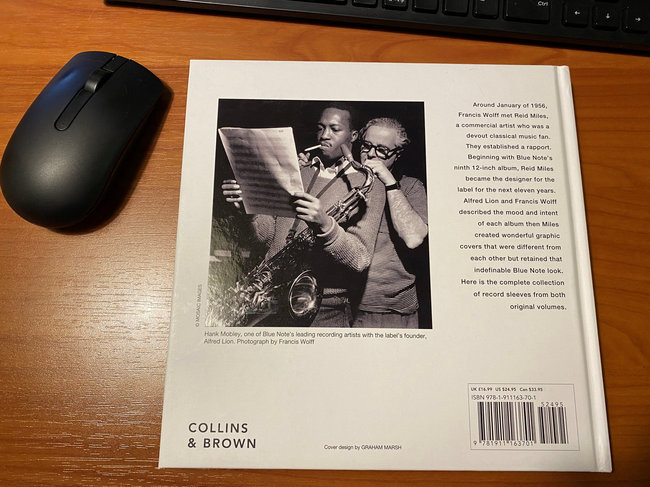
(Sept.2021)
gillman*s Choice Life & Death with Bill Evans
Book Review...
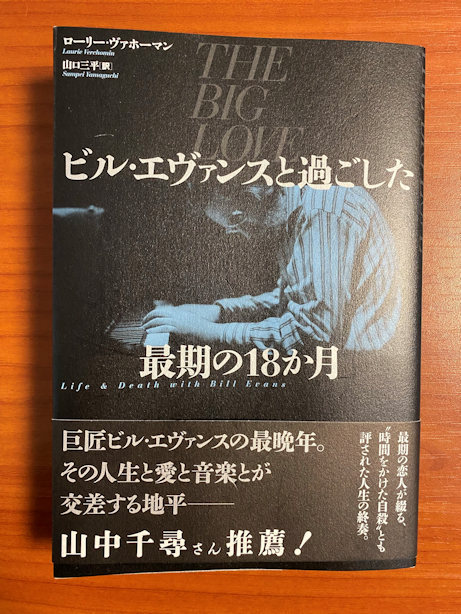
今年のエヴァンスの命日である9月15日に、彼に関する新しい本が出版された。エヴァンスの傍らには亡くなった前妻エレインをはじめ色々な女性がいたけれど、この著者のローリー・ヴァホーマンはエヴァンス最晩年(と言っても51歳だが)の恋人として最後に傍にいた女性だ。
エヴァンスの晩年は緩やかな自殺と称されるごとく薬と鬱と音楽の間を揺れている。本の最初に出てくるビル最後の日の出来事は壮絶だがあまりにあっけない幕切れに驚く。
二十二歳の女性から、若い愛人から見たエヴァンスの像に今までのファンは反発を覚えるかもしれない。煮えたぎるような若さの女性と50代とは言え人生の全てを出し尽くし枯れてゆこうとしている男とのアンバランスな生活。救いはローリーに宛てた数々の手紙の中にまだ消えていない彼の音楽への炎が垣間見られることだ。
この本を読んだ後でもぼくのエヴァンスに対する想いは変わらない。
ビル・エヴァンスと過ごした最期の 18か月
Life & Death with Bill Evans
ローリー・ヴァホーマン著
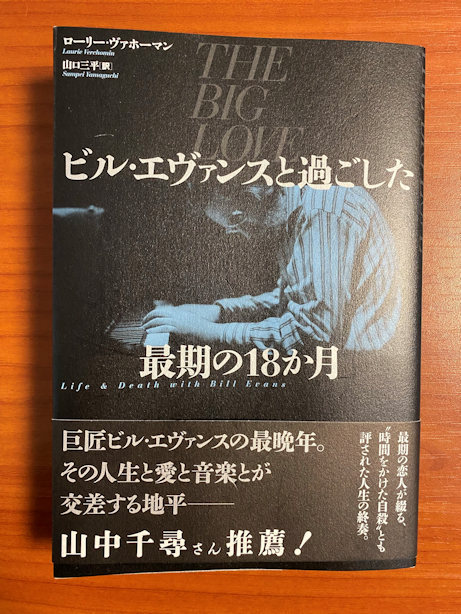
今年のエヴァンスの命日である9月15日に、彼に関する新しい本が出版された。エヴァンスの傍らには亡くなった前妻エレインをはじめ色々な女性がいたけれど、この著者のローリー・ヴァホーマンはエヴァンス最晩年(と言っても51歳だが)の恋人として最後に傍にいた女性だ。
エヴァンスの晩年は緩やかな自殺と称されるごとく薬と鬱と音楽の間を揺れている。本の最初に出てくるビル最後の日の出来事は壮絶だがあまりにあっけない幕切れに驚く。
二十二歳の女性から、若い愛人から見たエヴァンスの像に今までのファンは反発を覚えるかもしれない。煮えたぎるような若さの女性と50代とは言え人生の全てを出し尽くし枯れてゆこうとしている男とのアンバランスな生活。救いはローリーに宛てた数々の手紙の中にまだ消えていない彼の音楽への炎が垣間見られることだ。
この本を読んだ後でもぼくのエヴァンスに対する想いは変わらない。
(Sept.2021)
gillman*s Choice 贅沢な子守唄
gillman*s choice...

難しいことは分からないけど、ジャズだって色んな聴き方があって良いと思う。コロナ禍のお籠りでストレスのせいか中々寝付かれない晩もある。そんな時はBlossom Dearieに子守唄を歌ってもらう。
昨日はDearieの8枚のアルバムをシャッフルして枕もとのiPadで再生した。真っ暗な寝室の中に小さな画面が浮き上がって静かに歌いだす。タイマーは30分にしてあるけど大体その前に寝入る。
ぼくがナイトキャップ代わりに寝室で聴くのは自分でLullaby Ladiesと名前をつけたプレイリストに入れた6枚のアルバム。全部で66曲あるからそれをシャッフルして聴くと毎日違う歌が楽しめるし、タイマーの途中で寝入ってしまうから飽きることはない。
■Beverly Kenney/Snuggled On Your Shoulder
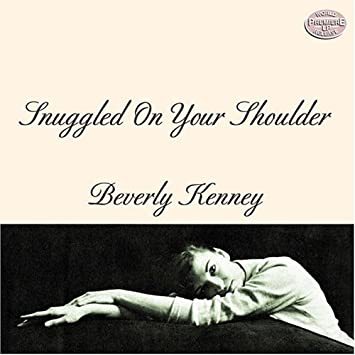
(1954)
1曲目のTea for Twoを聴いて最初に頭に浮かんだ言葉は「キュート」だった。ジャズボーカルでは中々浮かんでこない言葉だけれど、かといって甘ったるいだけのいやらしさはなく、逆に「巧いなぁ」という言葉もでてくる。
ピアノ伴奏だけというのもぼくが好きなところだ。CDは2006年リリースだが、音源はレコーディングのためのデモテープとして録音されたものらしい。ピアノの伴奏はトニー・タンブレロ。気負いもなくて彼女が伸び伸びと歌っているのがいい。
■Blossom Dearie/Blossom Dearie
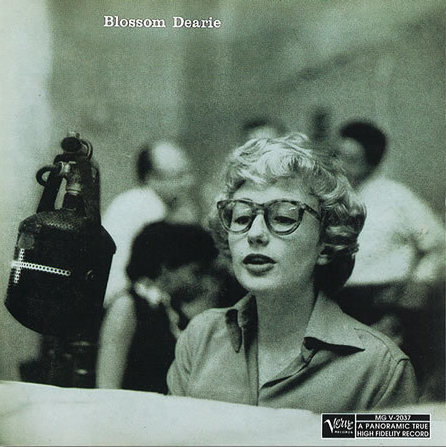
(1957)
彼女の名前を冠したこのアルバムがヴァーヴレコードでの最初のアルバムとなった。その前年にバークレーレコードから出したアルバム「April in Paris」はピアニストとしての参加だから、ジャズシンガーしての初のアルバムでもある。
ジャケットの写真も好いなぁ。彼女をクールなジャズシンガーとして売り出そうとしていたヴァーヴの意気込みが垣間見られるかも。この頃の彼女はアメリカとフランスを行き来していたこともあって、このアルバムには4曲目のComment Allez-Vousや7曲目のIt might as well be spring、8曲目のTout Documentなどフランス語で歌っている曲も入っている。
最後の曲「A Fine Spring Morning」なんかは歌詞の韻を踏んだリフレインの部分がとても心地よくて好きだ。Personnelは以下のようにこれもゴージャス。
[Personnel]
Blossom Dearie(piano, vocals)
Herb Ellis(guitar)
Ray Brown(double bass)
Jo Jones(drums)
■Dinah Shore/Dinah Sings and Previn Plays

(1960)
実はジャズ・シンガーとしての彼女の歌を聴くようになったのは最近になってのことだ。それはこのDinah sings and Previn plays(1960)というアルバムに出会ってからのことだ。アンドレ・プレヴィンのピアノでダイナがスタンダード・ナンバーを歌っている。このアルバムは1960年の録音、ダイナが44歳の時の作品だから歳を重ねていい味が出ている。
か細くて、ちょっとヴィブラートのかかった彼女の声は昔のままだけれど、プレヴィンのピアノと一つに溶け合った彼女の歌声はBlue Canaryの頃とは全く違う大人の世界を創り出している。どの曲も心に響く出来だけれど、特にI'll be seeing youは聴いていて胸が苦しくなる程の情感をもって迫ってくる。
この曲自体ぼくは大好きで今まではBilli Holidayのものがベストと思っていたけれど、それにも引けを取らない。と言うか、全く雰囲気も違うのだ。ビリー・ホリデーの歌が闇の向こうから聴こえてくるとすれば、ダイナ・ショアの歌は背中から懇願するように聴こえてくる感じなのだ。切なくて身をよじるような哀感がある。この一曲を聴くだけでこのアルバムを手に入れる価値はあると思う。
[Pasonnel]
Dinah Shore(vocals)
Red Mitchell(double bass)
Andre Previn(piano)
Frank Capp(drums)
■Ann Burton/Blue Burton

(1967)
2曲目の「Go Away Little Boy」がとてもいい。元はCarole King & Gerry Goffinのコンビの曲らしいのだけれど、キャロル・キングは「Go Away Little Girl」で作っており、1971年に少年ダニー・オズモンドが歌ってヒットした曲なのだが、それはお子様ソングでバートンのそれとは比ぶべくもない。バートンのはほんとに大人の情感が詰まった素晴らしい歌となっている。
その次の「He Was Too Good To Me」もしっとりとして聴きほれてしまう。バートンの繊細な歌声に寄り添うようなルイス・ヴァン・ダイクのピアノがこれまた渋い。バートンのバッキングをするときのヴァン・ダイクのピアノは彼女の歌に影のように寄り添い、出過ぎることなく歌を引き立てている。クラシックでいえば、名伴奏家のジェラール・ムーアかイェルク・デムスと言ったら言い過ぎだろうか。でも本当に良い。
[Personnel]
Piet Noordijk(Alto Saxophone)
Jacques Schols(Bass)
John Engels(Drums)
Ann Burton(Lead Vocals)
Louis Van Dyke(Piano)
■Rosemary Clooney/Sings Ballads

(1985)
ぼくが最初に手にした彼女のアルバムで今でもおそらく一番よく聴くジャズ・ボーカルのアルバムの一つだ。彼女の声はちょっとかすれ気味の声で、だからと言って決して濁った声ではない。
曲の雰囲気は白人系のジャズボーカルも聴いてきたぼくには何の抵抗も無く耳になじんだ。このアルバムのバックの演奏がフルバンドでなく小編成の手堅いプレーヤーというところも気に入っている。
1曲目のThanks for the memoryなどではRosieの歌に寄り添うようなエド・ビカートのギターが何とも言えず好い味を出している。この一曲でいきなり好きになってしまった。彼女の歌い方は歌自体にはあまり大げさな陰影はついていないけれど、何回も聴くうちに次第に心に沁みて來るし、聴き飽きることが無い。
ここら辺の彼女の曲の解釈の仕方がとても好くて、今や女性ジャズボーカル界の大アネゴの感があるダイアナ・クラルがRosieを評価しているところかもしれない。それにRosieの英語はとても分かりやすい。(ジャズ歌手ではアン・バートンの英語がとても分かりやすいけど、彼女はオランダ人だから英語は外国語にあたるからかもしれないが…) これはぼくにとっての永久保存版だ。
[Personnel]
Rosemary Clooney (vocal)
Scott Hamilton (tenor saxophone)
Warrn Vache (cornet)
John Oddo (piano)
Ed Bickert (guitar)
Chuck Israels (bass)
Jake Hanna (drums)
■手嶌葵/La Vie En Rose ~I Love Cinemas~

(2009)
La Vie En Roseという曲に関しては、ぼくの好きなエディット・ピアフ、マレーネ・ディートリそして美空ひばりの歌う3つのLa Vie en Roseは人生の時を積み重ねて幸せだったバラ色の時に想いを馳せている歌であり、歌手自体の人生の重みが歌に表れて胸を打つという点で共通したものがある。
一方この手嶌葵のLa Vie En Roseはそれらとはまったく異なる。溜息のような、囁くような彼女の声は少女がこれから迎える人生のバラ色の時を前にして胸をときめかせている雰囲気がある。ちょっとけだるい雰囲気が期待だけでなく漠とした不安さえも匂わせているような不思議な世界だ。日本人もこんな風に歌えるようになったんだと感激。
贅沢な子守唄
~穏やかに眠りにつくために~
難しいことは分からないけど、ジャズだって色んな聴き方があって良いと思う。コロナ禍のお籠りでストレスのせいか中々寝付かれない晩もある。そんな時はBlossom Dearieに子守唄を歌ってもらう。
昨日はDearieの8枚のアルバムをシャッフルして枕もとのiPadで再生した。真っ暗な寝室の中に小さな画面が浮き上がって静かに歌いだす。タイマーは30分にしてあるけど大体その前に寝入る。
ぼくがナイトキャップ代わりに寝室で聴くのは自分でLullaby Ladiesと名前をつけたプレイリストに入れた6枚のアルバム。全部で66曲あるからそれをシャッフルして聴くと毎日違う歌が楽しめるし、タイマーの途中で寝入ってしまうから飽きることはない。
穏やかに眠りにつくための
ぼくの6枚のアルバム
■Beverly Kenney/Snuggled On Your Shoulder
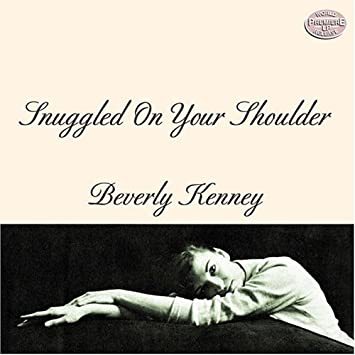
(1954)
1曲目のTea for Twoを聴いて最初に頭に浮かんだ言葉は「キュート」だった。ジャズボーカルでは中々浮かんでこない言葉だけれど、かといって甘ったるいだけのいやらしさはなく、逆に「巧いなぁ」という言葉もでてくる。
ピアノ伴奏だけというのもぼくが好きなところだ。CDは2006年リリースだが、音源はレコーディングのためのデモテープとして録音されたものらしい。ピアノの伴奏はトニー・タンブレロ。気負いもなくて彼女が伸び伸びと歌っているのがいい。
■Blossom Dearie/Blossom Dearie
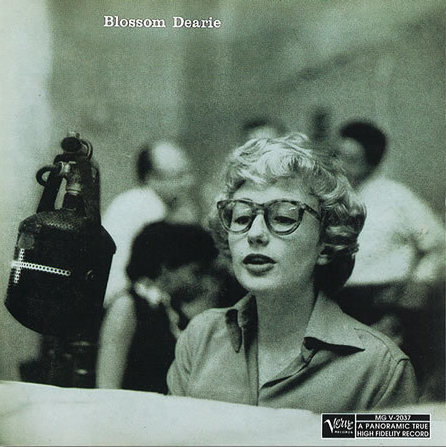
(1957)
彼女の名前を冠したこのアルバムがヴァーヴレコードでの最初のアルバムとなった。その前年にバークレーレコードから出したアルバム「April in Paris」はピアニストとしての参加だから、ジャズシンガーしての初のアルバムでもある。
ジャケットの写真も好いなぁ。彼女をクールなジャズシンガーとして売り出そうとしていたヴァーヴの意気込みが垣間見られるかも。この頃の彼女はアメリカとフランスを行き来していたこともあって、このアルバムには4曲目のComment Allez-Vousや7曲目のIt might as well be spring、8曲目のTout Documentなどフランス語で歌っている曲も入っている。
最後の曲「A Fine Spring Morning」なんかは歌詞の韻を踏んだリフレインの部分がとても心地よくて好きだ。Personnelは以下のようにこれもゴージャス。
[Personnel]
Blossom Dearie(piano, vocals)
Herb Ellis(guitar)
Ray Brown(double bass)
Jo Jones(drums)
■Dinah Shore/Dinah Sings and Previn Plays

(1960)
実はジャズ・シンガーとしての彼女の歌を聴くようになったのは最近になってのことだ。それはこのDinah sings and Previn plays(1960)というアルバムに出会ってからのことだ。アンドレ・プレヴィンのピアノでダイナがスタンダード・ナンバーを歌っている。このアルバムは1960年の録音、ダイナが44歳の時の作品だから歳を重ねていい味が出ている。
か細くて、ちょっとヴィブラートのかかった彼女の声は昔のままだけれど、プレヴィンのピアノと一つに溶け合った彼女の歌声はBlue Canaryの頃とは全く違う大人の世界を創り出している。どの曲も心に響く出来だけれど、特にI'll be seeing youは聴いていて胸が苦しくなる程の情感をもって迫ってくる。
この曲自体ぼくは大好きで今まではBilli Holidayのものがベストと思っていたけれど、それにも引けを取らない。と言うか、全く雰囲気も違うのだ。ビリー・ホリデーの歌が闇の向こうから聴こえてくるとすれば、ダイナ・ショアの歌は背中から懇願するように聴こえてくる感じなのだ。切なくて身をよじるような哀感がある。この一曲を聴くだけでこのアルバムを手に入れる価値はあると思う。
[Pasonnel]
Dinah Shore(vocals)
Red Mitchell(double bass)
Andre Previn(piano)
Frank Capp(drums)
■Ann Burton/Blue Burton

(1967)
2曲目の「Go Away Little Boy」がとてもいい。元はCarole King & Gerry Goffinのコンビの曲らしいのだけれど、キャロル・キングは「Go Away Little Girl」で作っており、1971年に少年ダニー・オズモンドが歌ってヒットした曲なのだが、それはお子様ソングでバートンのそれとは比ぶべくもない。バートンのはほんとに大人の情感が詰まった素晴らしい歌となっている。
その次の「He Was Too Good To Me」もしっとりとして聴きほれてしまう。バートンの繊細な歌声に寄り添うようなルイス・ヴァン・ダイクのピアノがこれまた渋い。バートンのバッキングをするときのヴァン・ダイクのピアノは彼女の歌に影のように寄り添い、出過ぎることなく歌を引き立てている。クラシックでいえば、名伴奏家のジェラール・ムーアかイェルク・デムスと言ったら言い過ぎだろうか。でも本当に良い。
[Personnel]
Piet Noordijk(Alto Saxophone)
Jacques Schols(Bass)
John Engels(Drums)
Ann Burton(Lead Vocals)
Louis Van Dyke(Piano)
■Rosemary Clooney/Sings Ballads

(1985)
ぼくが最初に手にした彼女のアルバムで今でもおそらく一番よく聴くジャズ・ボーカルのアルバムの一つだ。彼女の声はちょっとかすれ気味の声で、だからと言って決して濁った声ではない。
曲の雰囲気は白人系のジャズボーカルも聴いてきたぼくには何の抵抗も無く耳になじんだ。このアルバムのバックの演奏がフルバンドでなく小編成の手堅いプレーヤーというところも気に入っている。
1曲目のThanks for the memoryなどではRosieの歌に寄り添うようなエド・ビカートのギターが何とも言えず好い味を出している。この一曲でいきなり好きになってしまった。彼女の歌い方は歌自体にはあまり大げさな陰影はついていないけれど、何回も聴くうちに次第に心に沁みて來るし、聴き飽きることが無い。
ここら辺の彼女の曲の解釈の仕方がとても好くて、今や女性ジャズボーカル界の大アネゴの感があるダイアナ・クラルがRosieを評価しているところかもしれない。それにRosieの英語はとても分かりやすい。(ジャズ歌手ではアン・バートンの英語がとても分かりやすいけど、彼女はオランダ人だから英語は外国語にあたるからかもしれないが…) これはぼくにとっての永久保存版だ。
[Personnel]
Rosemary Clooney (vocal)
Scott Hamilton (tenor saxophone)
Warrn Vache (cornet)
John Oddo (piano)
Ed Bickert (guitar)
Chuck Israels (bass)
Jake Hanna (drums)
■手嶌葵/La Vie En Rose ~I Love Cinemas~

(2009)
La Vie En Roseという曲に関しては、ぼくの好きなエディット・ピアフ、マレーネ・ディートリそして美空ひばりの歌う3つのLa Vie en Roseは人生の時を積み重ねて幸せだったバラ色の時に想いを馳せている歌であり、歌手自体の人生の重みが歌に表れて胸を打つという点で共通したものがある。
一方この手嶌葵のLa Vie En Roseはそれらとはまったく異なる。溜息のような、囁くような彼女の声は少女がこれから迎える人生のバラ色の時を前にして胸をときめかせている雰囲気がある。ちょっとけだるい雰囲気が期待だけでなく漠とした不安さえも匂わせているような不思議な世界だ。日本人もこんな風に歌えるようになったんだと感激。
(Sept.2021)
gillman*s Choice Two Beverlys
gillman*s Choice...


Beverly Kenneyベブリー・ケニー(1932-1960)とBeverly Kellyベブリー・ケリー(1934)とはどちらも同時代に生まれたアメリカの女性ジャズシンガーだけど、ケニーは多くのアルバムを残しているが28歳の若さで自死をとげている。一方後者のケリーは一度引退したが、後にカムバックして今も存命みたいだ。
ぼくが最初に聴くようになったのはベブリー・ケニーの方で少し甘い声で、かと言ってぼくがやはり好きなブロッサム・ディアリーほど甘くはなくてジュリー・ロンドンほどウエットでもない。
彼女の歌を聴いているとぼくなんかは体験したことはないのだけれど、50年代のアメリカが彼女の背後から立ち上がってくるような不思議な懐かしさを感じる。
日本には彼女の熱狂的なファンがいるみたいで、ぼくが持っているのは10枚のアルバムだけれど彼女の全てのアルバムが日本ではリリースされているようだ。
一方、ベブリー・ケリーの方だけど、混同をさけるためか愛称としてベブ・ケリー(Bev Kelly)と呼ばれることが多いようだがぼくは最初彼女のことは知らなくて、夭折の天才ベーシストのスコット・ラファロの作品を追っているうちにピアニストのパット・モランそして彼女と組んで歌っていたベブ・ケリーに辿り着いた。
ググってみると、この二人のBeverlyがいることはジャズファンの間ではどうも有名な話ではあるようだ。ベブ・ケリーの歌声は少しハスキー気味でスウィンギーな曲などはどこかアニタ・オデイに似た感じもするが時々彼女独特のフェイクも入れたりまた違った魅力がある。ぼくの持っている彼女のアルバムは殆どがスタンダードナンバーで構成されていることも親しみを感じる。
My Favourite Albums
[Beverly Kenney]

■Snuggled On Your Shoulder
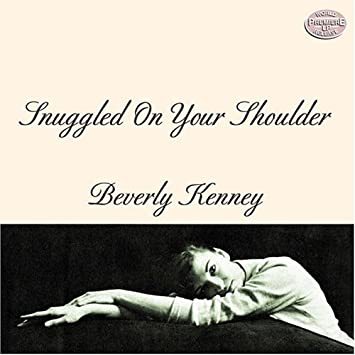
(1954)
1曲目のTea for Twoを聴いて最初に頭に浮かんだ言葉は「キュート」だった。ジャズボーカルでは中々浮かんでこない言葉だけれど、かといって甘ったるいだけのいやらしさはなく、逆に「巧いなぁ」という言葉もでてくる。
ピアノ伴奏だけというのもぼくが好きなところだ。CDは2006年リリースだが、音源はレコーディングのためのデモテープとして録音されたものらしい。ピアノの伴奏はトニー・タンブレロ。気負いもなくて彼女が伸び伸びと歌っているのがいい。
■Like Yesterday
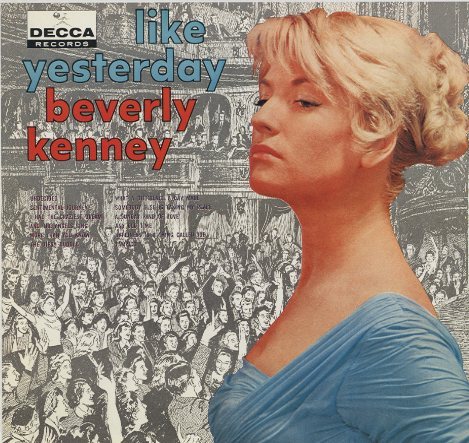
(1959)
2曲目のSENTIMENTAL JOURNEYなんか聴いていると本当にほっこりとしてしまうし、7曲目のWHAT A DIFFERENCE A DAY MADEを聴くとそのフレージングやさらっと流すところなど粋な歌い方だなぁと感心してしまうのだけれど、残念なことにこれが彼女の遺作のアルバムとなってしまった。
ジャズ歌手としては決して音域が広くはないので無理しない歌い方がどこかボサノバ的な雰囲気も醸し出して結果として気軽に聴いていられるものになっているけど、もちろんそれは彼女の巧みなフレージングや音程の確かさなどに裏打ちされて初めて可能な世界だということも確かだと思う。
[Personnel]
Beverly Kenney(vo)
Jerome Richardson(woodwinds)
Ed Shaughnessy(ds)
Bill Pemberton(b)
Chuck Wayne(g)
Stan Free(p,tp)
Johnny Rae(vibes,per)
Eddie Bert(tb)
Al Klink(ts)
曲により編成は異なる
Recorded in New York City, July 1959.
Originally issued on Decca D78948.
[Berverly Kelly]

■Beverly Kelly Sings

(1957)
彼女のアルバムは3枚しか持っていないのだけれど、ここに挙げた二枚はいずれもほぼ全曲がスタンダードナンバーなので聴く頻度は高い。このアルバムはパット・モラン・トリオがバックをつとめているがその中のベースはあのスコット・ラファロだ。
2曲目のThe Man I Loveはラファロの小気味のいいベースで始まりそれに乗るようなベブのハスキーボイスが光っている。ピアノを担当しているパット・モランは他のアルバムも持っているがぼく自身はバッキングとしては彼女の演奏は余り好きではない。目立ちすぎるし時にはうるさ過ぎるように感じる。ビル・エバンスのような上品な伴奏を期待するのは酷かもしれないけど…。
なおこのアルバムではBev Kellyではなく正式なBeverly Kelly名で出ている。最後の曲Spring is Hereはクリス・コナーそしてローズマリー・クルーニーと並んでぼくの中ではベスト・スリー。
[Personnel]
Beverly Kelly(vo)
Pat Moran(p)
Scott LaFaro(b)
Johnny Whited(ds)
■In Person

(1960)
録音はジャニス・ジョプリンもよく使っていたサンフランシスコのクラブCoffee Galleryでの録音。音質的には先のアルバムの方が良いけどクラブの雰囲気は満点。彼女自身での曲の紹介なども入って、こうやって聞くと彼女は生粋のクラブ歌手なんだなぁと思える。
全曲スタンダードナンバーだが、というかスタンダードナンバーナンバーだからこそ彼女の得意とするフレージングやフェイクを十分楽しめるのだと思う。彼女のハスキーなビブラートは先のアルバムではそれほど目につかなかったけれど、このアルバムではアーサー・キットを思い起こすほど全開だ。
8曲目のLove Lettersも素晴らしいし、最後のリクエストMy Funny Valentineまでジャズクラブの雰囲気に浸れるアルバムだ。後年アニー・ロスともアルバム録音しているポインデクスターのアルトサックスが光っている。
[Personnel]
Bev Kelly(vo)
Pony Poindexter(as)
Flip Nunez(p)
Johnny Allen(b)
Tony Johnson(ds)
recorded 10/14/1960
二人のBeverly


Beverly Kenneyベブリー・ケニー(1932-1960)とBeverly Kellyベブリー・ケリー(1934)とはどちらも同時代に生まれたアメリカの女性ジャズシンガーだけど、ケニーは多くのアルバムを残しているが28歳の若さで自死をとげている。一方後者のケリーは一度引退したが、後にカムバックして今も存命みたいだ。
ぼくが最初に聴くようになったのはベブリー・ケニーの方で少し甘い声で、かと言ってぼくがやはり好きなブロッサム・ディアリーほど甘くはなくてジュリー・ロンドンほどウエットでもない。
彼女の歌を聴いているとぼくなんかは体験したことはないのだけれど、50年代のアメリカが彼女の背後から立ち上がってくるような不思議な懐かしさを感じる。
日本には彼女の熱狂的なファンがいるみたいで、ぼくが持っているのは10枚のアルバムだけれど彼女の全てのアルバムが日本ではリリースされているようだ。
一方、ベブリー・ケリーの方だけど、混同をさけるためか愛称としてベブ・ケリー(Bev Kelly)と呼ばれることが多いようだがぼくは最初彼女のことは知らなくて、夭折の天才ベーシストのスコット・ラファロの作品を追っているうちにピアニストのパット・モランそして彼女と組んで歌っていたベブ・ケリーに辿り着いた。
ググってみると、この二人のBeverlyがいることはジャズファンの間ではどうも有名な話ではあるようだ。ベブ・ケリーの歌声は少しハスキー気味でスウィンギーな曲などはどこかアニタ・オデイに似た感じもするが時々彼女独特のフェイクも入れたりまた違った魅力がある。ぼくの持っている彼女のアルバムは殆どがスタンダードナンバーで構成されていることも親しみを感じる。
My Favourite Albums
[Beverly Kenney]

■Snuggled On Your Shoulder
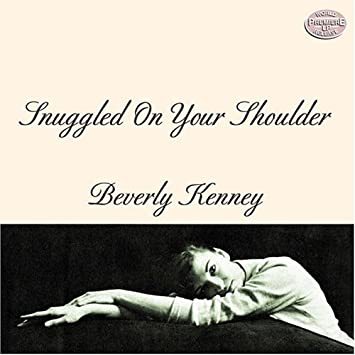
(1954)
1曲目のTea for Twoを聴いて最初に頭に浮かんだ言葉は「キュート」だった。ジャズボーカルでは中々浮かんでこない言葉だけれど、かといって甘ったるいだけのいやらしさはなく、逆に「巧いなぁ」という言葉もでてくる。
ピアノ伴奏だけというのもぼくが好きなところだ。CDは2006年リリースだが、音源はレコーディングのためのデモテープとして録音されたものらしい。ピアノの伴奏はトニー・タンブレロ。気負いもなくて彼女が伸び伸びと歌っているのがいい。
■Like Yesterday
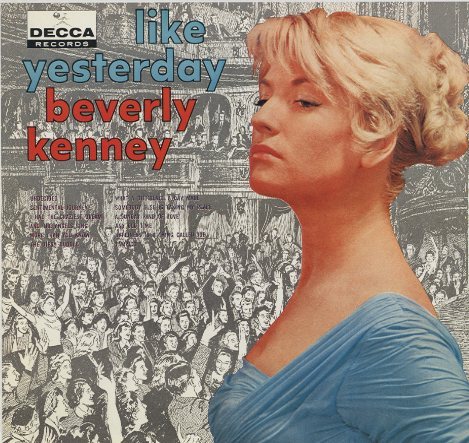
(1959)
2曲目のSENTIMENTAL JOURNEYなんか聴いていると本当にほっこりとしてしまうし、7曲目のWHAT A DIFFERENCE A DAY MADEを聴くとそのフレージングやさらっと流すところなど粋な歌い方だなぁと感心してしまうのだけれど、残念なことにこれが彼女の遺作のアルバムとなってしまった。
ジャズ歌手としては決して音域が広くはないので無理しない歌い方がどこかボサノバ的な雰囲気も醸し出して結果として気軽に聴いていられるものになっているけど、もちろんそれは彼女の巧みなフレージングや音程の確かさなどに裏打ちされて初めて可能な世界だということも確かだと思う。
[Personnel]
Beverly Kenney(vo)
Jerome Richardson(woodwinds)
Ed Shaughnessy(ds)
Bill Pemberton(b)
Chuck Wayne(g)
Stan Free(p,tp)
Johnny Rae(vibes,per)
Eddie Bert(tb)
Al Klink(ts)
曲により編成は異なる
Recorded in New York City, July 1959.
Originally issued on Decca D78948.
[Berverly Kelly]

■Beverly Kelly Sings

(1957)
彼女のアルバムは3枚しか持っていないのだけれど、ここに挙げた二枚はいずれもほぼ全曲がスタンダードナンバーなので聴く頻度は高い。このアルバムはパット・モラン・トリオがバックをつとめているがその中のベースはあのスコット・ラファロだ。
2曲目のThe Man I Loveはラファロの小気味のいいベースで始まりそれに乗るようなベブのハスキーボイスが光っている。ピアノを担当しているパット・モランは他のアルバムも持っているがぼく自身はバッキングとしては彼女の演奏は余り好きではない。目立ちすぎるし時にはうるさ過ぎるように感じる。ビル・エバンスのような上品な伴奏を期待するのは酷かもしれないけど…。
なおこのアルバムではBev Kellyではなく正式なBeverly Kelly名で出ている。最後の曲Spring is Hereはクリス・コナーそしてローズマリー・クルーニーと並んでぼくの中ではベスト・スリー。
[Personnel]
Beverly Kelly(vo)
Pat Moran(p)
Scott LaFaro(b)
Johnny Whited(ds)
■In Person

(1960)
録音はジャニス・ジョプリンもよく使っていたサンフランシスコのクラブCoffee Galleryでの録音。音質的には先のアルバムの方が良いけどクラブの雰囲気は満点。彼女自身での曲の紹介なども入って、こうやって聞くと彼女は生粋のクラブ歌手なんだなぁと思える。
全曲スタンダードナンバーだが、というかスタンダードナンバーナンバーだからこそ彼女の得意とするフレージングやフェイクを十分楽しめるのだと思う。彼女のハスキーなビブラートは先のアルバムではそれほど目につかなかったけれど、このアルバムではアーサー・キットを思い起こすほど全開だ。
8曲目のLove Lettersも素晴らしいし、最後のリクエストMy Funny Valentineまでジャズクラブの雰囲気に浸れるアルバムだ。後年アニー・ロスともアルバム録音しているポインデクスターのアルトサックスが光っている。
[Personnel]
Bev Kelly(vo)
Pony Poindexter(as)
Flip Nunez(p)
Johnny Allen(b)
Tony Johnson(ds)
recorded 10/14/1960
(Sept.2021)
gillman*s Choice Das Schweigende Klassenzimmer
ドイツ映画Review
僕たちは希望と言う名の列車に乗った
Das schweigende Klassenzimmer

まだベルリンの壁ができる前の東ドイツのベルリン郊外の町が舞台。確かに検問はあるがまだ列車で西ベルリンに行けたのだけど、冒頭の西ベルリンに行くその列車の緊張感は息が詰まりそうだ。祖父の墓参りの名目で西ベルリンに行った高校生テオとクルトは西ベルリンの映画館に忍び込みニュース映画でハンガリー動乱のニュースを観る。

東ドイツの高校に戻った二人は軽い気持ちで、ロシアを追い出すハンガリー動乱への連帯の気持ちで2分間の黙祷を教室で行う提案をし同級生たちの多数決で、授業の開始に2分間の黙とうを行うが、それは教育大臣にまであがるような大事になってしまう。校長は労働者の倅テオが進学クラスに入りアビトゥーア(卒業試験)を受けようとしていることを知り、励ますふりをして卒業試験をネタに首謀者を言うように迫る。

そして最後には筋金入りの社会主義者の群学務局の女、さらには大臣まで脅しにかかる。若い情熱から出たひょんなことで親たちも巻き込み、その親たちの生き様まで晒されてしまう。ストーリーは実話に基づいており、最後のところはこの実話の重みがずっしりと響いてくる。ぼくも少し経験したことがあるが、あの東側の息の詰まるような空気が肌身に伝わってくる。見ごたえのある映画だった。


ところでぼくはドイツ映画の楽しみの一つとしてそのタイトルを原題、日本公開時のタイトルそして英語圏での公開時のタイトルを比べてみるのが好きだ。配給会社が各々の国の事情をマーケティングして考えるのでどれが良いとか言うのではなく、その差を考えるのが楽しい。
この映画のドイツ語でのタイトルは「Das schweigende Klassenzimmer(沈黙の教室)」でぼくはやっぱりこれが一番響いてくる。冒頭の2分間の黙とうの沈黙に始まり、あらゆる局面で息の詰まるような沈黙が教室を支配する。このタイトルは全編を通じて実感できると思う。このタイトルを見るとドイツ人はエーリッヒ・ケストナーの学園小説「Das Fliegende Klassenzimmer(飛ぶ教室)」をすぐ思い出すと思う。
英語圏のタイトルは「The Silent Revolution」でアメリカは比較的「~革命」を使うのが好きみたいだけど、このタイトル自体は映画の中盤から後半にかけて目覚めた生徒たちの行動で実感される。
一方。日本語のタイトルは「僕たちは希望と言う名の列車に乗った」という長いもの。こう言うフルセンテンスの映画タイトルとしては昔の映画に「天使はこの森でバスを降りた(The Spitfire Grill)」というのがあるが、この映画を最後まで見るとまぁこのタイトルも悪くはないかな、と思えたりする。面白いのはタイトルで映画のどこに視点を当てているのかということがそれぞれ違うことだ。
話は逸れてしまったけれど、戦慄すべきはこの映画のようなことが完全に過去の話ではなく、今でもこの世界のどこかで現実に行われているということなのだと思う。

[Credit]
Year:2018
Director:Lars Kraume
Camera:Jens Harant
Stars:
Leonard Scheicher(Theo Lemke)
Tom Gramenz(Kurt Wächter)
Lena Klenke(Lena)
Jonas Dassler(Erik Babinski)

~16~
僕たちは希望と言う名の列車に乗った
Das schweigende Klassenzimmer

まだベルリンの壁ができる前の東ドイツのベルリン郊外の町が舞台。確かに検問はあるがまだ列車で西ベルリンに行けたのだけど、冒頭の西ベルリンに行くその列車の緊張感は息が詰まりそうだ。祖父の墓参りの名目で西ベルリンに行った高校生テオとクルトは西ベルリンの映画館に忍び込みニュース映画でハンガリー動乱のニュースを観る。

東ドイツの高校に戻った二人は軽い気持ちで、ロシアを追い出すハンガリー動乱への連帯の気持ちで2分間の黙祷を教室で行う提案をし同級生たちの多数決で、授業の開始に2分間の黙とうを行うが、それは教育大臣にまであがるような大事になってしまう。校長は労働者の倅テオが進学クラスに入りアビトゥーア(卒業試験)を受けようとしていることを知り、励ますふりをして卒業試験をネタに首謀者を言うように迫る。

そして最後には筋金入りの社会主義者の群学務局の女、さらには大臣まで脅しにかかる。若い情熱から出たひょんなことで親たちも巻き込み、その親たちの生き様まで晒されてしまう。ストーリーは実話に基づいており、最後のところはこの実話の重みがずっしりと響いてくる。ぼくも少し経験したことがあるが、あの東側の息の詰まるような空気が肌身に伝わってくる。見ごたえのある映画だった。


ところでぼくはドイツ映画の楽しみの一つとしてそのタイトルを原題、日本公開時のタイトルそして英語圏での公開時のタイトルを比べてみるのが好きだ。配給会社が各々の国の事情をマーケティングして考えるのでどれが良いとか言うのではなく、その差を考えるのが楽しい。
この映画のドイツ語でのタイトルは「Das schweigende Klassenzimmer(沈黙の教室)」でぼくはやっぱりこれが一番響いてくる。冒頭の2分間の黙とうの沈黙に始まり、あらゆる局面で息の詰まるような沈黙が教室を支配する。このタイトルは全編を通じて実感できると思う。このタイトルを見るとドイツ人はエーリッヒ・ケストナーの学園小説「Das Fliegende Klassenzimmer(飛ぶ教室)」をすぐ思い出すと思う。
英語圏のタイトルは「The Silent Revolution」でアメリカは比較的「~革命」を使うのが好きみたいだけど、このタイトル自体は映画の中盤から後半にかけて目覚めた生徒たちの行動で実感される。
一方。日本語のタイトルは「僕たちは希望と言う名の列車に乗った」という長いもの。こう言うフルセンテンスの映画タイトルとしては昔の映画に「天使はこの森でバスを降りた(The Spitfire Grill)」というのがあるが、この映画を最後まで見るとまぁこのタイトルも悪くはないかな、と思えたりする。面白いのはタイトルで映画のどこに視点を当てているのかということがそれぞれ違うことだ。
話は逸れてしまったけれど、戦慄すべきはこの映画のようなことが完全に過去の話ではなく、今でもこの世界のどこかで現実に行われているということなのだと思う。

[Credit]
Year:2018
Director:Lars Kraume
Camera:Jens Harant
Stars:
Leonard Scheicher(Theo Lemke)
Tom Gramenz(Kurt Wächter)
Lena Klenke(Lena)
Jonas Dassler(Erik Babinski)

(Aug.2021)
gillman*s Choice Good Bye Lenin!
ドイツ映画Review
~15~
グッバイレーニン
Good Bye Lenin!
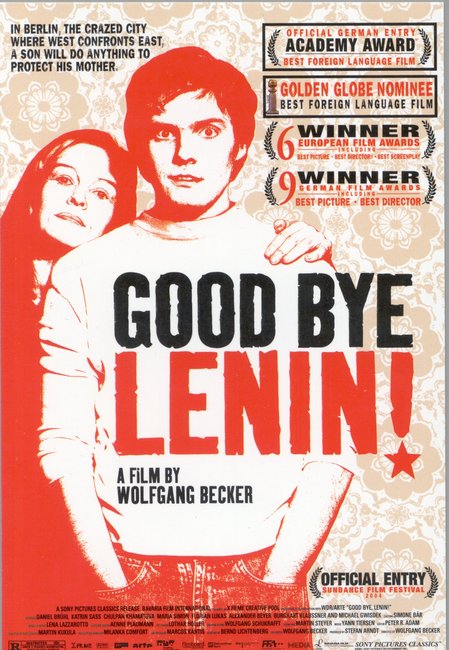
コロナのお籠りは相変わらず続いているのだけれど、オンラインによるリモートワークの環境が整うと同時にそちらの方の準備などに追われて今までみたいに週に何度も映画を観る時間がとりにくくなった。
ここにきてやっと少し余裕が出てきたので昨日は久しぶりにドイツ映画を観た。いつものようにDVDではなくアマゾン・プライムでドイツ映画を検索していたら以前見た「グッバイレーニン」が無料で観られるようになっていたので早速観た。
舞台は東西ベルリンの壁が崩壊した前後の東ベルリン。夫が西側に亡命して妻はそのショックもあってか逆に頑なな社会主義信奉者になってしまう。そんなある日彼女は心臓発作で昏睡状態に陥ってしまう。彼女の長い昏睡の間にベルリンの壁は崩壊しドイツは統一へとなだれ込んでいく。


そしてある日彼女が長い昏睡から目覚めると息子のアレックスは、母親の前にあたかも何もなかったように今までの東ドイツの生活を再現する。医師から何かのショックを受ければまた心臓発作を起こし、今度は助からないと言われていたからだ。
こうして彼女の周りで演出された偽りの東ドイツ生活が展開されるが、ある日彼女は歩けることに気づき外にでてしまう。そこで彼女が見たものは溢れかえる西側の物資と西側の人々。嘘がばれそうになるとアレックスはそれは西側から資本主義に疲れた難民が押し寄せているのだといって取り繕う。


アレックスは母のためにありとあらゆる手を使って理想の東ドイツを再現するが、それはもしかしたら母のためと言うよりアレックス自身の理想の東側世界の再現だったのかもしれない。
監督は「僕とカミンスキーの旅」のボルフガング・ベッカー監督で映画「わが教え子、ヒトラー」では俳優としても出演している。ドイツのアカデミー賞では9部門賞を受賞している。アレックス役のダニエル・ブリュールが実直でマザコン気味の青年を好演している。

[CREDIT]
Year:2003
Director:Wolfgang Becker
Writer:
Bernd Lichtenberg
Stars:
Daniel Brühl (Alex)
Katrin Saß (Mutter)
Chulpan Khamatova(Lara)
Maria Simon(Ariane)

(Jul.2021)
gillman*s Choice Blue Note Tshirts
gillman*s Choice...
Blue Note
のコラボTシャツ

ユニクロのUTシャツは色んなアーチストとのコラボのデザインがあって、夏になると安いし着やすいこともあって何枚か買うのだけれど、今回はブルーノートとのコラボが出るというので待っていた。
それが今週出たので早速手に入れたけど、結構良い。今回発売されるのはブルーノートの社長を務めたプロデューサーのドン・ウォズがセレクトした名盤のジャケットをモチーフにした全7柄。
7着もそんなに要らないから、中からソニー・クラークの「Sonny Clark Trio」とユタ・ヒップの「Jutta Hipp with Zoot Sims」のジャケットのヤツを選んだ。ソニー・クラークは日本で人気があるので頷けるけど、ドイツ人の女性ピアニストのユタ・ヒップのが出るとは思ってもいなかった。なんかちょっと嬉しくなって選んでしまった。
まぁ外で着るのはちょっと恥ずかしいけど、部屋着としてはアリなので早速明日から着ようと思っている。1500円/枚。
Jutta Hipp with Zoot Sims

(1956)
ユタ・ヒップは1950年代のドイツ人の女性ジャズピアニストだが、見出されてアメリカに渡りブルーノートからこのアルバムを出している。ズート・シムズとの共演は良い感じだったのだけれど、一説によると彼女は極度のあがり症でストレスフルなレコード録音は好きじゃなかったようで、恐らくこれが最後のアルバムかも知れない。
他にはその前に録音された「Jutta Hipp At The Hickory House」とさらに以前のフランクフルト時代の「Juttta Hipp Quintet Complete 1954 Recordings」を聴いているけど、スタンダードナンバーが多くてぼくは好きだ。
Sonny Clark Trio
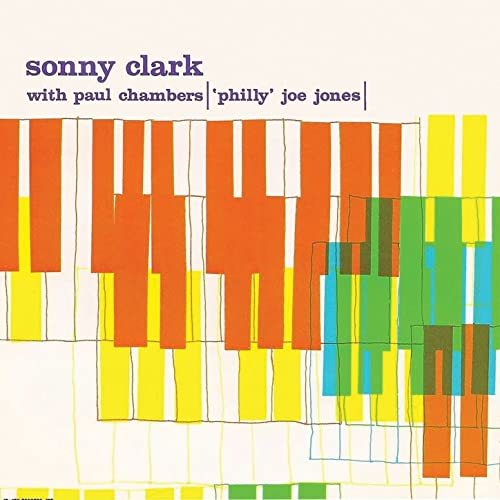
(1957)
ソニー・クラークは日本では特に人気のあるジャズピアニストでリーダーアルバム以外にも多くのブルーノートのそうそうたるプレーヤーのサイドマンとしても活躍した。日本では特にこのアルバムといわゆる美脚ジャケットの代表的なデザインで有名な「Cool Struttin'」が圧倒的に聴かれている。
Blue Note
のコラボTシャツ

ユニクロのUTシャツは色んなアーチストとのコラボのデザインがあって、夏になると安いし着やすいこともあって何枚か買うのだけれど、今回はブルーノートとのコラボが出るというので待っていた。
それが今週出たので早速手に入れたけど、結構良い。今回発売されるのはブルーノートの社長を務めたプロデューサーのドン・ウォズがセレクトした名盤のジャケットをモチーフにした全7柄。
7着もそんなに要らないから、中からソニー・クラークの「Sonny Clark Trio」とユタ・ヒップの「Jutta Hipp with Zoot Sims」のジャケットのヤツを選んだ。ソニー・クラークは日本で人気があるので頷けるけど、ドイツ人の女性ピアニストのユタ・ヒップのが出るとは思ってもいなかった。なんかちょっと嬉しくなって選んでしまった。
まぁ外で着るのはちょっと恥ずかしいけど、部屋着としてはアリなので早速明日から着ようと思っている。1500円/枚。
Jutta Hipp with Zoot Sims

(1956)
ユタ・ヒップは1950年代のドイツ人の女性ジャズピアニストだが、見出されてアメリカに渡りブルーノートからこのアルバムを出している。ズート・シムズとの共演は良い感じだったのだけれど、一説によると彼女は極度のあがり症でストレスフルなレコード録音は好きじゃなかったようで、恐らくこれが最後のアルバムかも知れない。
他にはその前に録音された「Jutta Hipp At The Hickory House」とさらに以前のフランクフルト時代の「Juttta Hipp Quintet Complete 1954 Recordings」を聴いているけど、スタンダードナンバーが多くてぼくは好きだ。
Sonny Clark Trio
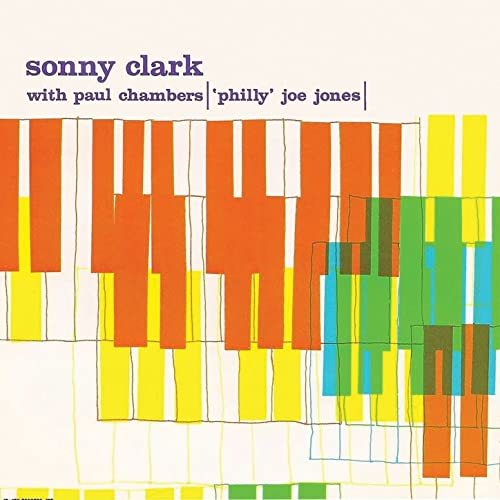
(1957)
ソニー・クラークは日本では特に人気のあるジャズピアニストでリーダーアルバム以外にも多くのブルーノートのそうそうたるプレーヤーのサイドマンとしても活躍した。日本では特にこのアルバムといわゆる美脚ジャケットの代表的なデザインで有名な「Cool Struttin'」が圧倒的に聴かれている。
(Jul.2021)
gillman*s Choice 掃除婦のための手引き書
Book Review...
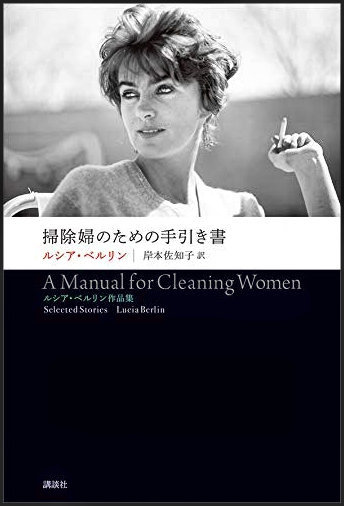
ルシア・ベルリン著
岸本佐知子訳/講談社
何のきっかけで読み出したのかは忘れてしまった。ルシア・ベルリン(Lucia Berlin)という名に惹かれて何人だろうと思って調べたらアメリカ人だったので、だったらベルリンじゃなくてバーリンなんじゃないかと。「ホワイトクリスマス」を作曲したアーヴィング・バーリン(Irving Berlin)はバーリンなのに…。
そんなことはどうでもいいのだけれど、それよりこの作家の生きざまが凄いのに驚いた。子供の頃は脊椎に障害があるため体育の時間は教室で待機、飛び級するほど頭は良いのに他の子とコミュニケーションがとれないで、どう話しかけて良いかも分からずいきなり「私の叔父さん、片目が義眼なの」とか「顔にウジがたかったアラスカヒグマの死体を見たことがあるよ」などと話しかけて「バ~カ」と罵られたり。
けっこう美人で、三十歳までに3度結婚、離婚。シングルマザーで4人の子供を抱えて色々な職業を転々とする。その上祖父や母や叔父同様アル中でも苦しんだ。彼女の作品がブレークしたのは死後大分たってかららしいが、晩年は(68歳没)大学で創作指導をするなどして准教授にまでなっている。
彼女は生涯に76の物語を6つの短編集で発表しているが、今回は43編が含まれている自伝的色彩の強い英語版短編集「A Manual for Cleaning Women(掃除婦のための手引き書)」から24編を選び出し2019年に出版された。彼女の文章はぼくが今まで読んだどの本よりもエキサイティングで小気味よいリズムを持ちユーモアに溢れしかし心に刺さるような鋭い棘がある。そして驚くような観察眼。
翻訳は岸本佐知子氏でこの翻訳がほんとに素晴らしい。あまり素晴らしいので元はどんな文章なのだろうとKindle英語版を買ってみたら、会話が多くしかも動詞のない短いフレーズが散りばめられており、それがリズムを作っている一因でもある。短編なのでKindleのバンドル辞書やWord Wise機能を使えばぼく程度の英語力でも何とか読み続けられる。(もちろん、既に翻訳を読んでいるからだけど…)
短編で一番短いのは「わたしの騎手」("My Jockey")で長さはたった1ページだけど素晴らしい。
「緊急救命室の仕事を私は気に入っている。なんといっても男に合える。ほんものの男、ヒーローたちだ。消防士に騎手。どっちも緊急救命室の常連だ。ジョッキーのレントゲン写真はすごい。彼らはしょっちゅう骨折しては、自分でテープを巻いて次のレースに出てしまう。…」
読んでいるうちに、残酷な現実の中でもがき苦しむ内になんだかやけくその元気が出てくるような不思議な世界。日本ではこの一冊だけだけど、残りの作品も是非読んでみたい。
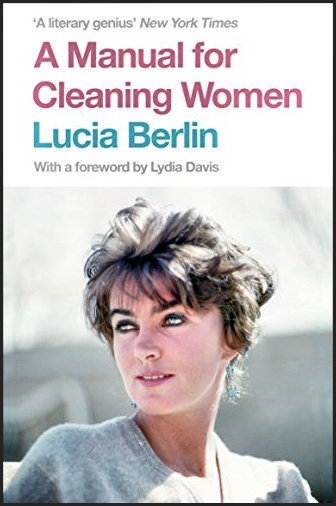
A Manual for Cleaning Women: Selected Stories (English Edition)
Kindle版
[電子書籍リーダーKindle]
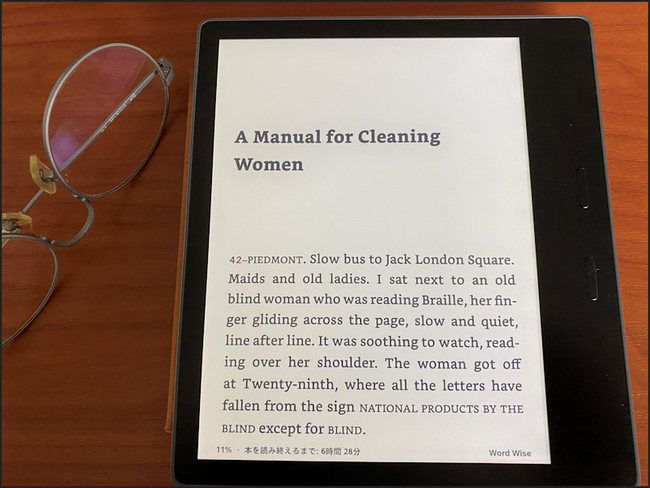
愛用している第一の理由は
①文字の大きさが自由に変えられること。(老眼で文庫本はもう殆ど無理)
②数百冊分のデータが入るので旅行に便利(現在250冊程入っている)
③一般的なタブレットのようには目が疲れず、昼間の戸外でも問題なく読める。
等だが、読後の達成感や所有するワクワク感は紙の書籍にはもちろん叶わない。
*Kindleバンドル辞書…電子書籍リーダーのKindleには英和辞書、英独辞書など各国語辞書が無料でダウンロードできるようになっており、分からない単語があればそこを長押しすると辞書がその単語の訳を表示してくれる機能がある。またその単語をマークしておけば、読後に単語帳ができる機能もある。
*Word Wise…この機能をオンにすると例えば英語の本であれば、難しい単語にはその上にルビのように小さな字で平易な英語で意味が説明されている。その頻度もかなり難しい単語のみにするなど、調整ができるようになっているが、行が乱れたり文章が見にくくなることがあるので、ぼくは辞書の方を使っている。
掃除婦のための手引き書
ルシア・ベルリン
作品集
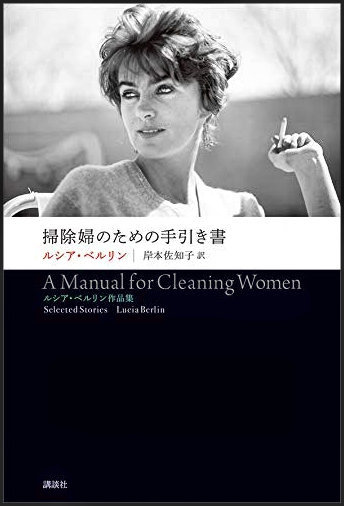
ルシア・ベルリン著
岸本佐知子訳/講談社
何のきっかけで読み出したのかは忘れてしまった。ルシア・ベルリン(Lucia Berlin)という名に惹かれて何人だろうと思って調べたらアメリカ人だったので、だったらベルリンじゃなくてバーリンなんじゃないかと。「ホワイトクリスマス」を作曲したアーヴィング・バーリン(Irving Berlin)はバーリンなのに…。
そんなことはどうでもいいのだけれど、それよりこの作家の生きざまが凄いのに驚いた。子供の頃は脊椎に障害があるため体育の時間は教室で待機、飛び級するほど頭は良いのに他の子とコミュニケーションがとれないで、どう話しかけて良いかも分からずいきなり「私の叔父さん、片目が義眼なの」とか「顔にウジがたかったアラスカヒグマの死体を見たことがあるよ」などと話しかけて「バ~カ」と罵られたり。
けっこう美人で、三十歳までに3度結婚、離婚。シングルマザーで4人の子供を抱えて色々な職業を転々とする。その上祖父や母や叔父同様アル中でも苦しんだ。彼女の作品がブレークしたのは死後大分たってかららしいが、晩年は(68歳没)大学で創作指導をするなどして准教授にまでなっている。
彼女は生涯に76の物語を6つの短編集で発表しているが、今回は43編が含まれている自伝的色彩の強い英語版短編集「A Manual for Cleaning Women(掃除婦のための手引き書)」から24編を選び出し2019年に出版された。彼女の文章はぼくが今まで読んだどの本よりもエキサイティングで小気味よいリズムを持ちユーモアに溢れしかし心に刺さるような鋭い棘がある。そして驚くような観察眼。
翻訳は岸本佐知子氏でこの翻訳がほんとに素晴らしい。あまり素晴らしいので元はどんな文章なのだろうとKindle英語版を買ってみたら、会話が多くしかも動詞のない短いフレーズが散りばめられており、それがリズムを作っている一因でもある。短編なのでKindleのバンドル辞書やWord Wise機能を使えばぼく程度の英語力でも何とか読み続けられる。(もちろん、既に翻訳を読んでいるからだけど…)
短編で一番短いのは「わたしの騎手」("My Jockey")で長さはたった1ページだけど素晴らしい。
「緊急救命室の仕事を私は気に入っている。なんといっても男に合える。ほんものの男、ヒーローたちだ。消防士に騎手。どっちも緊急救命室の常連だ。ジョッキーのレントゲン写真はすごい。彼らはしょっちゅう骨折しては、自分でテープを巻いて次のレースに出てしまう。…」
読んでいるうちに、残酷な現実の中でもがき苦しむ内になんだかやけくその元気が出てくるような不思議な世界。日本ではこの一冊だけだけど、残りの作品も是非読んでみたい。
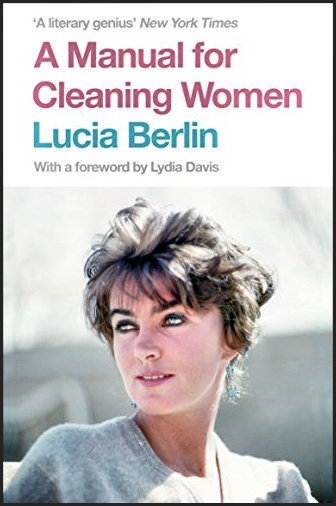
A Manual for Cleaning Women: Selected Stories (English Edition)
Kindle版
[電子書籍リーダーKindle]
愛用している第一の理由は
①文字の大きさが自由に変えられること。(老眼で文庫本はもう殆ど無理)
②数百冊分のデータが入るので旅行に便利(現在250冊程入っている)
③一般的なタブレットのようには目が疲れず、昼間の戸外でも問題なく読める。
等だが、読後の達成感や所有するワクワク感は紙の書籍にはもちろん叶わない。
*Kindleバンドル辞書…電子書籍リーダーのKindleには英和辞書、英独辞書など各国語辞書が無料でダウンロードできるようになっており、分からない単語があればそこを長押しすると辞書がその単語の訳を表示してくれる機能がある。またその単語をマークしておけば、読後に単語帳ができる機能もある。
*Word Wise…この機能をオンにすると例えば英語の本であれば、難しい単語にはその上にルビのように小さな字で平易な英語で意味が説明されている。その頻度もかなり難しい単語のみにするなど、調整ができるようになっているが、行が乱れたり文章が見にくくなることがあるので、ぼくは辞書の方を使っている。
(May 2021)
gillman*s Museum 渡辺省亭展
Museum of the Month...

[印象メモ]
コロナ禍でもう一年以上散歩と通院以外ほとんど外出はしていないので従って展覧会もほんの数えるくらいしか観ていないのが残念。でも上野あたりは近いので①混雑しない、②展覧会に直行・直帰を原則に月一くらいはこれからは行きたいなと思っていた。
そんな中、上野の東京藝術大学美術館で渡辺省亭の展覧会が開かれたので早速行ってみた。渡辺省亭については迎賓館赤坂離宮の花鳥の間の素晴らしい七宝の原画を書いたことくらいしか知らなかったが、今回展示されていた彼の数々の花鳥画を見てその味わい深さに魅了された。
若い頃はどちらかというと花鳥画にはあまり興味を抱いていなかったけれど、歳をとるにつれて日本の四季や花鳥風月というものが心に沁みるようになって、最近はよく観るようになった。そして何といっても決定的に魅了されたのは2018年に茅ヶ崎市美術館で開かれた「小原古邨展」で彼の作品に触れてからだった。
今回観た省亭の花鳥画の素晴らしさは、その小原古邨の花鳥画を初めて見た時以来の感激だった。省亭は画壇と距離をおいて市井の画家としての姿勢を全うしたということで評価展出品向けの屏風や大作は少なくほとんどが掛け軸などが多いのだけれど、その限られた世界の中に花鳥への限りない慈しみが込められている。ここら辺は古邨の世界と相通ずるものがあると思う。
渡辺省亭も川瀬巴水や小原古邨などと並んで日本よりも海外で先に評価が高まったという側面を持っている。省亭は日本画家で初めてパリに留学した人物でもあり日本画でありながら実に写実的なところはその影響もあるのかもしれないが、その時代においては逆にあのドガが省亭の画力に驚きその作品を所有していたということからも分かるように東西の美意識が直接接触し始めた時代なのかもしれない。
渡辺省亭 My Favourite 5
百舌鳥に蜘蛛図

(1914)
今回メトロポリタン美術館からの里帰り作品で元々はアメリカ人コレクターの依頼で「花鳥魚鰕画冊」の一環として描かれたものらしい。木の枝からその糸で垂れ下がった一匹の蜘蛛を、枝にとまった百舌がじっと見つめている。
この絵の凄みは何の迷いもなくすっと引かれた一本の蜘蛛の糸の存在感だろう。目を凝らさないとわからないような細さでしかもその下にぶる下がっている蜘蛛のわずかな重さを受けてピンと張っているのが伝わってくる。その張り詰めた緊張感がじっと見つめている百舌の次の動作を予感させ息をのませる。
鳥図/枝にとまる鳥

(1878)
この絵は印象派画家のドガが所蔵していたもので絵には「為ドガース君 省亭席画」という為書きがしたためてある。「席画」というのは宴会や集まり等の席で求めに応じて即興で描く絵のことで河鍋暁斎などは膨大な量の席画を残している。
この席画は省亭がパリにいる時日本の美術商林忠正と共にフランス人美術批評家のところを訪れた際にその場で描いたものらしい。林忠正とは親交があったからその場にドガもいたのかもしれない。さりげなくさっと描かれているが鳥の表情が生き生きとしている。ドガはその筆を借りて描いてみたという話も残っている。
塩谷判官の妻

今回の展覧会では花鳥画だけでなく美人画も多く出品されている。この絵は太平記に出てくる武将・塩谷高貞(えんやたかさだ)の美人で名高い妻、顔世(かおよ)に横恋慕した高師直(こうのもろなお)が彼女の湯あみの後を覗き見する場面を、省亭の師匠菊池容斎が描いたものをもとにしている。
容斎の方の絵は観たことがないけれど、この絵の方は歴史画というより美人画であり、ある意味では現代の裸体画のテイストも持っていると思う。省亭はもう一枚同様のモチーフで「塩谷高貞妻浴後図」というのも描いているがそちらも同様だ。
かつて西洋画の裸体画が神話や宗教画の形を借りて表現されたけど、ここでも歴史画を通じてそんな意図があったようにも思える。彼の美人画は後に鏑木清方に影響を与えたと言われているらしい。そう言われると女性の凛とした姿に面影を感じる。
雪中鴛鴦之図

(1909)
最初に一見してどこかで観たことのある絵だなと思ったけど、それは2016年に東京都美術館で開かれた「若冲展」の目玉の一つ「動植綵絵」の中にあった「雪中鴛鴦図」で、省亭がそれに倣って描いたものだ。絵の大きさも省亭にしては大きめでそれは若冲の作品の大きさに合わせたらしい。
ただし、そのままの模写ではなく画面の上半分は殆ど同じたけれど、若冲の絵では鴛鴦(おしどり)の雌は水に潜っているが、省亭の絵の方では雄と雌が寄り添っている。ぼくには水に潜って冷えた雌のからだを雄が「冷たかったね~」と温めてあげているように見えるのだけど…。省亭のウィットが利いている。省亭は若冲の絵を土台にしながらも省亭流にさらっと描いているように思う。

若冲の動植綵絵・雪中鴛鴦図
柳に雀図

これはロンドンの美術商マルコム・フェアリーの所有している作品だけど、何気に惹きつけられて見入ってしまった。題材も柳と雀という何処でも何時でも目にするようなものだが、それだけに親しみが湧いて一瞬実際に以前どこかで見たのではないかという錯覚にとらわれる。無駄なものを一切排して芽吹き始めた柳のもとで戯れる雀に意識を集中させる構図にも惹かれる。
[図 録]

126頁、2600円。大判の図録で価格的には多少高めには感じるけど、省亭の画集と言えば現在でも簡便なのが一冊とあとは小学館がこの展覧会に合わせるように出版した充実した画集があるが、それは6万円以上もして手が出しにくいことを考えると省亭の画業を俯瞰する上ではこの図録は貴重なものであると思う。また、今回の展覧会は前期と後期ではかなりの数の作品が入れ替えになるので一度の訪問では観られない作品も目にすることができるという利点もある。
渡辺省亭展

東京藝術大学美術館
2021年3月27日~5月23日
[印象メモ]
コロナ禍でもう一年以上散歩と通院以外ほとんど外出はしていないので従って展覧会もほんの数えるくらいしか観ていないのが残念。でも上野あたりは近いので①混雑しない、②展覧会に直行・直帰を原則に月一くらいはこれからは行きたいなと思っていた。
そんな中、上野の東京藝術大学美術館で渡辺省亭の展覧会が開かれたので早速行ってみた。渡辺省亭については迎賓館赤坂離宮の花鳥の間の素晴らしい七宝の原画を書いたことくらいしか知らなかったが、今回展示されていた彼の数々の花鳥画を見てその味わい深さに魅了された。
若い頃はどちらかというと花鳥画にはあまり興味を抱いていなかったけれど、歳をとるにつれて日本の四季や花鳥風月というものが心に沁みるようになって、最近はよく観るようになった。そして何といっても決定的に魅了されたのは2018年に茅ヶ崎市美術館で開かれた「小原古邨展」で彼の作品に触れてからだった。
今回観た省亭の花鳥画の素晴らしさは、その小原古邨の花鳥画を初めて見た時以来の感激だった。省亭は画壇と距離をおいて市井の画家としての姿勢を全うしたということで評価展出品向けの屏風や大作は少なくほとんどが掛け軸などが多いのだけれど、その限られた世界の中に花鳥への限りない慈しみが込められている。ここら辺は古邨の世界と相通ずるものがあると思う。
渡辺省亭も川瀬巴水や小原古邨などと並んで日本よりも海外で先に評価が高まったという側面を持っている。省亭は日本画家で初めてパリに留学した人物でもあり日本画でありながら実に写実的なところはその影響もあるのかもしれないが、その時代においては逆にあのドガが省亭の画力に驚きその作品を所有していたということからも分かるように東西の美意識が直接接触し始めた時代なのかもしれない。
渡辺省亭 My Favourite 5
百舌鳥に蜘蛛図

(1914)
今回メトロポリタン美術館からの里帰り作品で元々はアメリカ人コレクターの依頼で「花鳥魚鰕画冊」の一環として描かれたものらしい。木の枝からその糸で垂れ下がった一匹の蜘蛛を、枝にとまった百舌がじっと見つめている。
この絵の凄みは何の迷いもなくすっと引かれた一本の蜘蛛の糸の存在感だろう。目を凝らさないとわからないような細さでしかもその下にぶる下がっている蜘蛛のわずかな重さを受けてピンと張っているのが伝わってくる。その張り詰めた緊張感がじっと見つめている百舌の次の動作を予感させ息をのませる。
鳥図/枝にとまる鳥

(1878)
この絵は印象派画家のドガが所蔵していたもので絵には「為ドガース君 省亭席画」という為書きがしたためてある。「席画」というのは宴会や集まり等の席で求めに応じて即興で描く絵のことで河鍋暁斎などは膨大な量の席画を残している。
この席画は省亭がパリにいる時日本の美術商林忠正と共にフランス人美術批評家のところを訪れた際にその場で描いたものらしい。林忠正とは親交があったからその場にドガもいたのかもしれない。さりげなくさっと描かれているが鳥の表情が生き生きとしている。ドガはその筆を借りて描いてみたという話も残っている。
塩谷判官の妻

今回の展覧会では花鳥画だけでなく美人画も多く出品されている。この絵は太平記に出てくる武将・塩谷高貞(えんやたかさだ)の美人で名高い妻、顔世(かおよ)に横恋慕した高師直(こうのもろなお)が彼女の湯あみの後を覗き見する場面を、省亭の師匠菊池容斎が描いたものをもとにしている。
容斎の方の絵は観たことがないけれど、この絵の方は歴史画というより美人画であり、ある意味では現代の裸体画のテイストも持っていると思う。省亭はもう一枚同様のモチーフで「塩谷高貞妻浴後図」というのも描いているがそちらも同様だ。
かつて西洋画の裸体画が神話や宗教画の形を借りて表現されたけど、ここでも歴史画を通じてそんな意図があったようにも思える。彼の美人画は後に鏑木清方に影響を与えたと言われているらしい。そう言われると女性の凛とした姿に面影を感じる。
雪中鴛鴦之図

(1909)
最初に一見してどこかで観たことのある絵だなと思ったけど、それは2016年に東京都美術館で開かれた「若冲展」の目玉の一つ「動植綵絵」の中にあった「雪中鴛鴦図」で、省亭がそれに倣って描いたものだ。絵の大きさも省亭にしては大きめでそれは若冲の作品の大きさに合わせたらしい。
ただし、そのままの模写ではなく画面の上半分は殆ど同じたけれど、若冲の絵では鴛鴦(おしどり)の雌は水に潜っているが、省亭の絵の方では雄と雌が寄り添っている。ぼくには水に潜って冷えた雌のからだを雄が「冷たかったね~」と温めてあげているように見えるのだけど…。省亭のウィットが利いている。省亭は若冲の絵を土台にしながらも省亭流にさらっと描いているように思う。

若冲の動植綵絵・雪中鴛鴦図
柳に雀図

これはロンドンの美術商マルコム・フェアリーの所有している作品だけど、何気に惹きつけられて見入ってしまった。題材も柳と雀という何処でも何時でも目にするようなものだが、それだけに親しみが湧いて一瞬実際に以前どこかで見たのではないかという錯覚にとらわれる。無駄なものを一切排して芽吹き始めた柳のもとで戯れる雀に意識を集中させる構図にも惹かれる。
[図 録]
126頁、2600円。大判の図録で価格的には多少高めには感じるけど、省亭の画集と言えば現在でも簡便なのが一冊とあとは小学館がこの展覧会に合わせるように出版した充実した画集があるが、それは6万円以上もして手が出しにくいことを考えると省亭の画業を俯瞰する上ではこの図録は貴重なものであると思う。また、今回の展覧会は前期と後期ではかなりの数の作品が入れ替えになるので一度の訪問では観られない作品も目にすることができるという利点もある。
(Apr.2021)
gillman*s Choice 森の中に埋めた
Book Review...
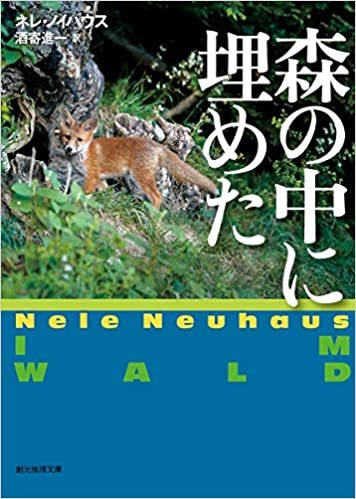
ネレ・ノイハウス著
創元推理文庫
フリードリヒ・デュレンマットでドイツ語圏のミステリー小説の、他とはちょっと違ったテイストに出会ったのに味をしめて、こちらはドイツの警察クリミナル小説の人気作家ネレ・ノイハウスの作品を読んでみることにした。
まずは人気シリーズの「刑事オリヴァー&ピア・シリーズ」の中から選んだのだけれど、素直に彼女の処女作の「悪女は自殺しない(Eine unbeliebte Frau)2006年」を選べば良かったんだろうけど、不用意にタイトルだけで選んだものだから、文庫本ではシリーズ7作目の「生者と死者(Die Lebenden und die Toten)2014年」そしてKindle版でシリーズ9作目の「森の中に埋めた(Im Wald)2016年」の二冊を注文した。
で、文庫本の方が手元に来たら案の定字が小さすぎて読めない。結局字の大きさを自由に変えられる電子ブックの「森の中に埋めた」を読むことになったのだけれど、これが最も厄介な選択だったということは読み始めてすぐに分かった。なにしろ筋に絡む重要な人物が26人も登場する。おまけにそれぞれが互いに複雑な関係にあってそれが頭に入っていないと筋そのものについていけない、という超やっかいな作品。デュレンマットの登場人物の少なさとは対照的だ。
まぁ、地名は実際の地名が舞台に使われているのでグーグルマップを見ながらだと徐々に親しみは湧いてくるのだけど、厄介なのは人名でジョンとかメアリーみたいには馴染みが無い名前だし、その上に親子だったり、夫婦だったり同じファミリーネームが度々出てくるので、まてよどっちがどっちだったっけ、と巻頭の登場人物一覧を見ながら確認しなければならなかった。
ということで、じゃつまらなかったのかというとそれを乗り越えれば実に面白い。人物描写の鋭さや犯罪捜査情報の詳しさなど「クリミ(Krimi)」と呼ばれるドイツの犯罪小説独特の偏執狂的な緻密さがある。
話は郊外のキャンプ場でキャンピングトレーラーが何台も炎上し、そこから男の焼死体が見つかる。放火が原因と思われるが刑事オリヴァーとピアが捜査を進めてゆくうちにオリヴァー警部自身の知り合いが次から次へと捜査線上に上がってくる。
小さな町の一見何事もないような日常の背後に誰もが触れたくないような闇が存在している。そしてその闇の源の一つがオリヴァー自身に関連していることが明らかになってくる。事件に絡む核心的な出来事は全て森の中で起きている。
原題の「In Wald」は直訳すれば「森の中で」ということで、全てが森の中でおこったという意味なのだろうけど、訳書のタイトルは「森の中に埋めた」となっていて、おいおいタイトルでいきなりネタばれかよと思ったけど、まぁここら辺はぎりぎりセーフかもしれない。長くてややこしいけど、読み終えたときの達成感は十分ある。これもいずれはドイツ語で読もうとは思っているけど、今はデュレンマットの方で手一杯。

Nele Neuhaus
[刑事オリヴァー&ピア・シリーズ]
・悪女は自殺しない(Eine unbeliebte Frau 自費出版2006年/2009年出版)
・死体は笑みを招く(Mordsfreunde 自費出版2007年/2009年出版)
・深い疵(Tiefe Wunden 2009年9月)
・白雪姫には死んでもらう(Schneewittchen muss sterben 2010年)
・風に種を蒔く者(Wer Wind sät 2011年)
・赤頭巾ちゃんご用心 (Böser Wolf 2012年)
・生者と死者 (Die Lebenden und die Toten 2014年)
・森の中に埋めた (Im Wald 2016年)
・母の日 (Muttertag 2018年)
(Apr.2021)
森の中に埋めた
Im Wald
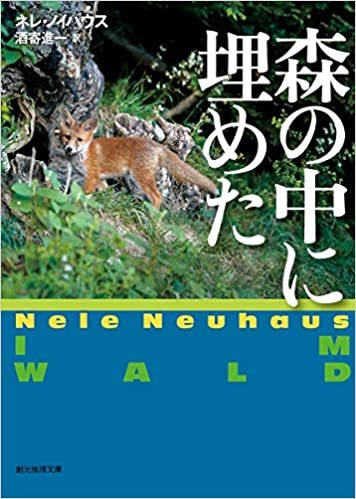
ネレ・ノイハウス著
創元推理文庫
フリードリヒ・デュレンマットでドイツ語圏のミステリー小説の、他とはちょっと違ったテイストに出会ったのに味をしめて、こちらはドイツの警察クリミナル小説の人気作家ネレ・ノイハウスの作品を読んでみることにした。
まずは人気シリーズの「刑事オリヴァー&ピア・シリーズ」の中から選んだのだけれど、素直に彼女の処女作の「悪女は自殺しない(Eine unbeliebte Frau)2006年」を選べば良かったんだろうけど、不用意にタイトルだけで選んだものだから、文庫本ではシリーズ7作目の「生者と死者(Die Lebenden und die Toten)2014年」そしてKindle版でシリーズ9作目の「森の中に埋めた(Im Wald)2016年」の二冊を注文した。
で、文庫本の方が手元に来たら案の定字が小さすぎて読めない。結局字の大きさを自由に変えられる電子ブックの「森の中に埋めた」を読むことになったのだけれど、これが最も厄介な選択だったということは読み始めてすぐに分かった。なにしろ筋に絡む重要な人物が26人も登場する。おまけにそれぞれが互いに複雑な関係にあってそれが頭に入っていないと筋そのものについていけない、という超やっかいな作品。デュレンマットの登場人物の少なさとは対照的だ。
まぁ、地名は実際の地名が舞台に使われているのでグーグルマップを見ながらだと徐々に親しみは湧いてくるのだけど、厄介なのは人名でジョンとかメアリーみたいには馴染みが無い名前だし、その上に親子だったり、夫婦だったり同じファミリーネームが度々出てくるので、まてよどっちがどっちだったっけ、と巻頭の登場人物一覧を見ながら確認しなければならなかった。
ということで、じゃつまらなかったのかというとそれを乗り越えれば実に面白い。人物描写の鋭さや犯罪捜査情報の詳しさなど「クリミ(Krimi)」と呼ばれるドイツの犯罪小説独特の偏執狂的な緻密さがある。
話は郊外のキャンプ場でキャンピングトレーラーが何台も炎上し、そこから男の焼死体が見つかる。放火が原因と思われるが刑事オリヴァーとピアが捜査を進めてゆくうちにオリヴァー警部自身の知り合いが次から次へと捜査線上に上がってくる。
小さな町の一見何事もないような日常の背後に誰もが触れたくないような闇が存在している。そしてその闇の源の一つがオリヴァー自身に関連していることが明らかになってくる。事件に絡む核心的な出来事は全て森の中で起きている。
原題の「In Wald」は直訳すれば「森の中で」ということで、全てが森の中でおこったという意味なのだろうけど、訳書のタイトルは「森の中に埋めた」となっていて、おいおいタイトルでいきなりネタばれかよと思ったけど、まぁここら辺はぎりぎりセーフかもしれない。長くてややこしいけど、読み終えたときの達成感は十分ある。これもいずれはドイツ語で読もうとは思っているけど、今はデュレンマットの方で手一杯。

Nele Neuhaus
[刑事オリヴァー&ピア・シリーズ]
・悪女は自殺しない(Eine unbeliebte Frau 自費出版2006年/2009年出版)
・死体は笑みを招く(Mordsfreunde 自費出版2007年/2009年出版)
・深い疵(Tiefe Wunden 2009年9月)
・白雪姫には死んでもらう(Schneewittchen muss sterben 2010年)
・風に種を蒔く者(Wer Wind sät 2011年)
・赤頭巾ちゃんご用心 (Böser Wolf 2012年)
・生者と死者 (Die Lebenden und die Toten 2014年)
・森の中に埋めた (Im Wald 2016年)
・母の日 (Muttertag 2018年)
(Apr.2021)
gillman*s Museum ドアノー展
Museum of the Month...
写真家

Bunkamura ザ・ミュージアム
[感想メモ]
コロナ禍になってからもうずっと散歩と通院くらいであとは家でおとなしくしているんだけど、写真家ロベール・ドアノー展の会期があと二日というところまできてやっぱりどうしても観ておきたいということになって渋谷のBunkamura ザ・ミュージアムに行った。
ここでは何回か好きな写真家の展覧会を見ている。最初は2002年に開かれたセバスチャン・サルガドの写真展「EXODUS 国境を越えて」が最初でその会場で彼を見かけたのを覚えている。その後二度のソール・ライター展があった。どれも充実して記憶に残る写真展だった。
ドアノーと言えばファッション写真からスナップ写真までそのフィールドは広いけど、ぼくは特に彼が撮ったパリのスナップ写真が好きだ。今回の展覧会は音楽とパリというキーワードでスナップ写真、ステージ写真そして著名人のポートレートなど7つの章に分けて展示されてる。
このところまたモノクロ写真が注目されているけど、彩度の高いデジタル写真や液晶画面を通した画像に慣れてしまった目には、印画紙に焼き付けられたモノクロの画面はかえって新鮮に映るかもしれない。モノクロの画面の向うから立ち上がるその時代の熱気に心が沸き立つ。
[My Favorite 5]
オランピア劇場のエディット・ピアフ

(1956)
画面の殆ど全部が漆黒の闇で、その左下に豆粒ほどの大きさでスポットライトを浴びたシャンソン歌手エディット・ピアフが立っている。今まで見た舞台写真の中で最も大胆な構図の写真だと思う。そう言えば、昔どこかでこれとそっくりの光景を見たことがあると思っていたけど、それは学生時代に見たミレイユ・マチューのオランピア劇場でのリサイタルでの光景だった。
マチューはピアフの再来と騒がれてデビューし、やはりオランピア劇場でリサイタルをやったのだけれど、その登場の仕方はそれはもちろんピアフへのオマージュだと思うのだけれど全くこの写真の通りだった。
昨日たまたまそのシーンをYoutubeで見つけてなんとも懐かしかった。舞台上の歌手の孤独と逆にスポットライトを浴びた栄光の両面が見事に表現されている。ドアノーはローライで桟敷席から撮ったのだろうか、それともライカだろうか。
オランピア劇場のミレイユ・マチュー
パリ祭のラストワルツ

(1949)
ドアノーの撮ったスナップ写真の中で一番好きな一枚。フランスでは「Fête nationale française(フランス国民祭)」と呼ばれるパリ祭はパリっ子が楽しみにしているイベントなのだが、その喧騒に満ちた一日が終わろうとする裏通りでまだ昼間の熱気が忘れられないように暗がりでダンスを踊る二人の若者。
解説によるとその日の昼間からドアノーはパリ祭の模様をあちこち撮り歩き、手持ちのフィルムの最後の一本で撮ったのがこの写真ということだ。一日の最後の最後にベストショットが…何事もあきらめてはいけないということか。
サン=ジェルマン=デ=プレのジュリエット・グレコ

(1947)
グレコはいわばその時代の女神で黒ずくめの衣装で映画、シャンソンで活躍しサン=ジェルマン=デ=プレのミューズと称えられた。この写真は彼女のホームグラウンドともいえるサン=ジェルマン=デ=プレの教会の前で撮ったもので、見慣れた彼女の他のポートレートのように黒ずくめで腕を組んでいるような女神然とした姿ではなく、犬と触れ合う一人のパリジェンヌとしての姿に温かみが感じられて素敵だ。
運河沿いのビエレット・ドリオンとマダム・ルル

(1953)
ビエレット・ドリオンとマダム・ルルは流しのアコーディオン弾きと歌い手で、ドアノーは二人が酒場や街を流し歩く姿をずっと追っている。今回会場には何カ所かにドアノーの写真のコンタクトシート(フィルムの密着焼き付け)が展示されていたけど、その中にこの二人を写した一連のショットがあった。
そこでこの二人が一日の最後にその日の実入りをテーブルの上に広げて山分けしているシーンも撮っているから、ドアノーは彼らとかなり親しかったのではないかと思う。それらの写真から伝わってくるのは二人の女の強かさと、そしてもの哀しさ。どこからともなく映画「道」の主題歌「ジェルソミーナ」が聞こえてきそうだ。
ポン・ド・クリメのジャック・プレヴェール
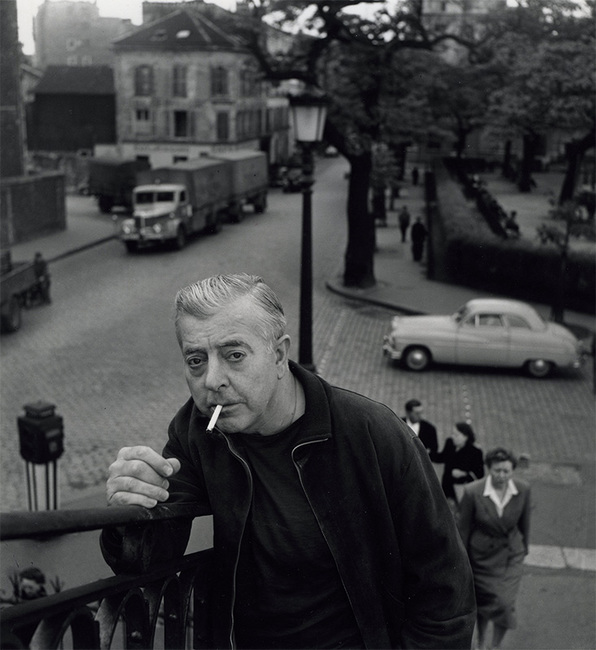
(1955)
ジャック・プレヴェールはシャンソン「枯葉」の作詞者であり映画のシナリオライターでもある。プレヴェールはドアノーとの親交の中でパリの味わい深い色々な場所を彼に教え、また多くの撮影にも立ち会ったらしい。写っている街もそうだけど、彼の顔自体がなんとも味わい深くパリの街角とこれ以上ないくらい釣り合っている。
会場には彼の写っている写真が8枚くらい展示されていたが、みごとに全ての写真で煙草をくわえている。もしかしてあのたばこは、ぼくらも学生時代イキがってすったことのあるあのあくの強い両切りたばこ「ジタン」かなと思いながら見ていたが…。たばこがポートレートの必須アイテムだった時代だな。
[図録]

303頁、2200円。図録としてはポケット版という感じのコンパクトなもの。Bunkamura ザ・ミュージアムでの写真展での図録は二度のソール・ライター展でもこのコンパクト版だった。持って帰るにはかさばらなくて良いのだけれど、殆どのページでせっかくの写真が2ページにまたがっているのでちょっと見ずらいし写真集的な雰囲気ではない。
もちろん図録なのでそれで良いのだという考え方もあるけど、写真集となると結構値もはるのでこういう機会に写真集としても後々見られるようなものにしてもらうとうれしいのだけれど…。以前、埼玉県立近代美術館で行わたジャック=アンリ・ラルティーグの写真展での図録は写真集としても十分楽しめるものだった。
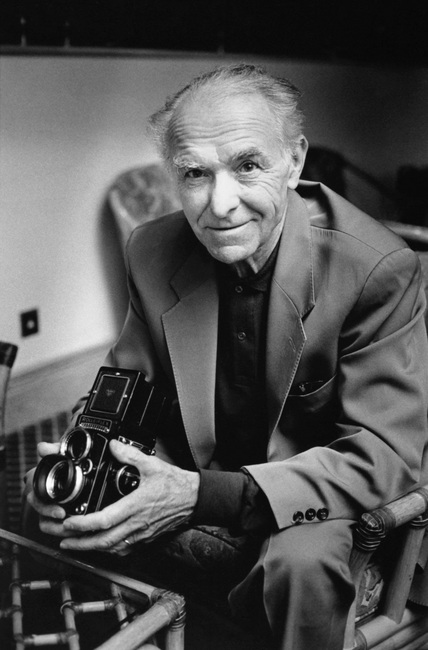
Robert Doisneau
(Apr.2021)
写真家
ドアノー/音楽/パリ

Bunkamura ザ・ミュージアム
[感想メモ]
コロナ禍になってからもうずっと散歩と通院くらいであとは家でおとなしくしているんだけど、写真家ロベール・ドアノー展の会期があと二日というところまできてやっぱりどうしても観ておきたいということになって渋谷のBunkamura ザ・ミュージアムに行った。
ここでは何回か好きな写真家の展覧会を見ている。最初は2002年に開かれたセバスチャン・サルガドの写真展「EXODUS 国境を越えて」が最初でその会場で彼を見かけたのを覚えている。その後二度のソール・ライター展があった。どれも充実して記憶に残る写真展だった。
ドアノーと言えばファッション写真からスナップ写真までそのフィールドは広いけど、ぼくは特に彼が撮ったパリのスナップ写真が好きだ。今回の展覧会は音楽とパリというキーワードでスナップ写真、ステージ写真そして著名人のポートレートなど7つの章に分けて展示されてる。
このところまたモノクロ写真が注目されているけど、彩度の高いデジタル写真や液晶画面を通した画像に慣れてしまった目には、印画紙に焼き付けられたモノクロの画面はかえって新鮮に映るかもしれない。モノクロの画面の向うから立ち上がるその時代の熱気に心が沸き立つ。
[My Favorite 5]
オランピア劇場のエディット・ピアフ

(1956)
画面の殆ど全部が漆黒の闇で、その左下に豆粒ほどの大きさでスポットライトを浴びたシャンソン歌手エディット・ピアフが立っている。今まで見た舞台写真の中で最も大胆な構図の写真だと思う。そう言えば、昔どこかでこれとそっくりの光景を見たことがあると思っていたけど、それは学生時代に見たミレイユ・マチューのオランピア劇場でのリサイタルでの光景だった。
マチューはピアフの再来と騒がれてデビューし、やはりオランピア劇場でリサイタルをやったのだけれど、その登場の仕方はそれはもちろんピアフへのオマージュだと思うのだけれど全くこの写真の通りだった。
昨日たまたまそのシーンをYoutubeで見つけてなんとも懐かしかった。舞台上の歌手の孤独と逆にスポットライトを浴びた栄光の両面が見事に表現されている。ドアノーはローライで桟敷席から撮ったのだろうか、それともライカだろうか。
オランピア劇場のミレイユ・マチュー
パリ祭のラストワルツ

(1949)
ドアノーの撮ったスナップ写真の中で一番好きな一枚。フランスでは「Fête nationale française(フランス国民祭)」と呼ばれるパリ祭はパリっ子が楽しみにしているイベントなのだが、その喧騒に満ちた一日が終わろうとする裏通りでまだ昼間の熱気が忘れられないように暗がりでダンスを踊る二人の若者。
解説によるとその日の昼間からドアノーはパリ祭の模様をあちこち撮り歩き、手持ちのフィルムの最後の一本で撮ったのがこの写真ということだ。一日の最後の最後にベストショットが…何事もあきらめてはいけないということか。
サン=ジェルマン=デ=プレのジュリエット・グレコ

(1947)
グレコはいわばその時代の女神で黒ずくめの衣装で映画、シャンソンで活躍しサン=ジェルマン=デ=プレのミューズと称えられた。この写真は彼女のホームグラウンドともいえるサン=ジェルマン=デ=プレの教会の前で撮ったもので、見慣れた彼女の他のポートレートのように黒ずくめで腕を組んでいるような女神然とした姿ではなく、犬と触れ合う一人のパリジェンヌとしての姿に温かみが感じられて素敵だ。
運河沿いのビエレット・ドリオンとマダム・ルル

(1953)
ビエレット・ドリオンとマダム・ルルは流しのアコーディオン弾きと歌い手で、ドアノーは二人が酒場や街を流し歩く姿をずっと追っている。今回会場には何カ所かにドアノーの写真のコンタクトシート(フィルムの密着焼き付け)が展示されていたけど、その中にこの二人を写した一連のショットがあった。
そこでこの二人が一日の最後にその日の実入りをテーブルの上に広げて山分けしているシーンも撮っているから、ドアノーは彼らとかなり親しかったのではないかと思う。それらの写真から伝わってくるのは二人の女の強かさと、そしてもの哀しさ。どこからともなく映画「道」の主題歌「ジェルソミーナ」が聞こえてきそうだ。
ポン・ド・クリメのジャック・プレヴェール
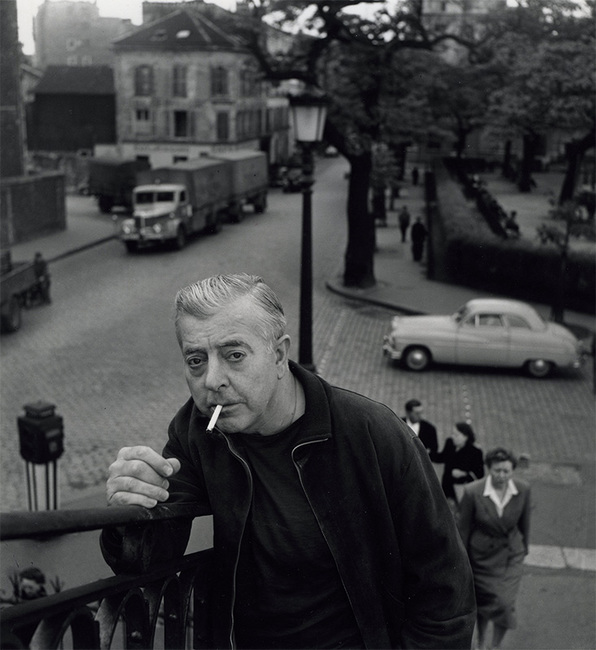
(1955)
ジャック・プレヴェールはシャンソン「枯葉」の作詞者であり映画のシナリオライターでもある。プレヴェールはドアノーとの親交の中でパリの味わい深い色々な場所を彼に教え、また多くの撮影にも立ち会ったらしい。写っている街もそうだけど、彼の顔自体がなんとも味わい深くパリの街角とこれ以上ないくらい釣り合っている。
会場には彼の写っている写真が8枚くらい展示されていたが、みごとに全ての写真で煙草をくわえている。もしかしてあのたばこは、ぼくらも学生時代イキがってすったことのあるあのあくの強い両切りたばこ「ジタン」かなと思いながら見ていたが…。たばこがポートレートの必須アイテムだった時代だな。
[図録]
303頁、2200円。図録としてはポケット版という感じのコンパクトなもの。Bunkamura ザ・ミュージアムでの写真展での図録は二度のソール・ライター展でもこのコンパクト版だった。持って帰るにはかさばらなくて良いのだけれど、殆どのページでせっかくの写真が2ページにまたがっているのでちょっと見ずらいし写真集的な雰囲気ではない。
もちろん図録なのでそれで良いのだという考え方もあるけど、写真集となると結構値もはるのでこういう機会に写真集としても後々見られるようなものにしてもらうとうれしいのだけれど…。以前、埼玉県立近代美術館で行わたジャック=アンリ・ラルティーグの写真展での図録は写真集としても十分楽しめるものだった。
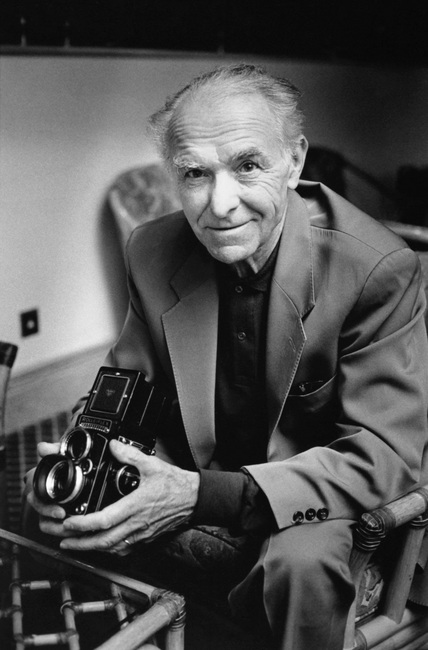
Robert Doisneau
(Apr.2021)
gillman*s choice 北欧のジャズシンガー
gillman*s choice...

Sinne Eeg
女性ジャズシンガーの歌が好きで主に1950年代から60年代のLPが多かったのだけれど、比較的最近のダイアナ・クラールやニッキ・パロットなんかも好きになって聴いているが、ここのところ北欧出身の女性ジャズシンガーの作品を聴くことも多くなった。
それを意識して聴いていたわけではないのだけれど、気が付いてみたら、あら結構多いなぁということで並べてみたのだけれど…。特徴はといえば、英語の歌詞が聴きやすい、これはオランダの歌手アン・バートンもそうなのだけれど、英語は彼女らにとって外国語なのだけど、逆に聴きやすいところがある。それに英語が地域語化しているアジアや他の地域の英語のように強い癖がないので日本人にも聞きやすいということもある。
さらに彼女達それぞれが皆大人の雰囲気を持っている。自国語でも歌っているし、歌う歌の範囲も広い。昔のジャズシンガーを知っている者からすれば彼女たちを純粋なジャズシンガーとみない向きもあるみたいだけれど、じゃなにが純粋なジャズなのかといったら、常に動き変化しているのがジャズだから余り硬いことは言わないことだ。
60年代だってローズ・マリークルーニーやダイナ・ショアみたいにジャズとポップスの両面の要素を持っていたシンガーだって多い。それは別にしても彼女たちの歌唱自体が素晴らしいことも共通している。表面的には静かで、しかしその底に強い情熱を秘めたような雰囲気を持っている。春の宵、北欧に思いをはせて彼女たちの青い炎のような歌声に静かに耳を傾けるのも楽しいひと時になると思う。
Monika Zetterlund

Waltz For Debby/Bill Evans & Monica Zetterlund(1964)
北欧のジャズシンガーといえばまず浮かんでくるのがMonika Zetterlund(モニカ・ゼッタールンド)というスウェーデンの歌手の名前だろう。ビル・エヴァンスとの共演で1964年に出されたLPはエヴァンスのアルバムの中でもぼくも大好きなものの一枚だ。
今ではエヴァンスの代名詞にもなった感のある「Waltz For Debby」をゼッタールンドはスウェーデン語で歌っているのだが、それが妙に心地よい。聴きこんでいるうちに彼女の一見クールな歌い方の向こうに時々垣間見える熱いものが感じられる。これは他の北欧出身のシンガーにも感じられる傾向だ。アメリカの黒人文化から発生したジャズという歌が遥か北欧にまでたどり着いてこういう空気を纏った歌に変化していったことを思うと、ちょっと感慨深い。
ぼくの持っているのはCDなのだけれど、LPの収録曲に加えて6曲も別テイクの録音のボーナストラックが入っている。ゼッタールンドのLPは少ないだけにこれは嬉しい。
Toruń Eriksen

Passage(2010)
ノルウェーのシンガーToruń Eriksen(トルン・エリクセン)の歌声を初めて聴いたとき、ジャニス・イアンに似ているなと思った。エリクセンの声はジャニスよりもうちょっと透明感があるけどスローテンポの曲になるととても似てくる。
彼女はオスロを中心にジャズとソウルの分野で活動しているということだが日本ではまだCDはリリースされていないみたいだ。他にもアルバムとしてはGrand white silkh、Visits、Luxury And Wasteなどがリリースされている。
Sinne Eeg
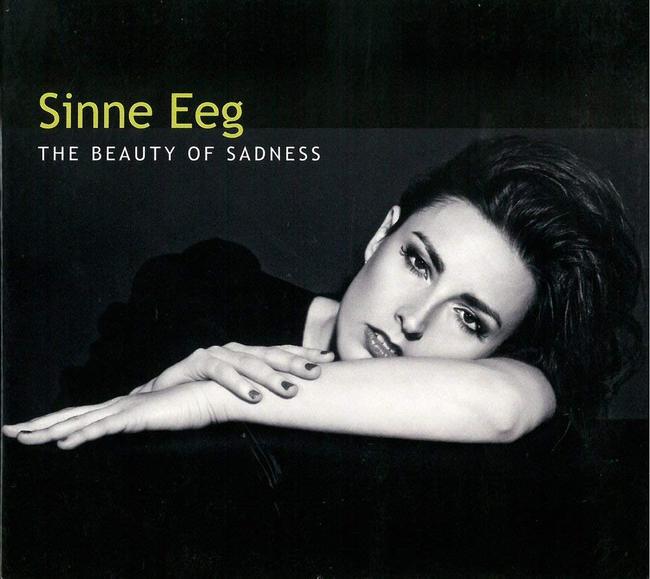
Beauty of Sadness(2012)
デンマークのジャズシンガーSinne Eeg(シーネ・エイ)は何度か来日もしている。ファンの中には彼女の事を「シー姐(しーねい)」と呼んでいる者もいるやに…。ぼくも北欧系のシンガーではゼッタールンドに次いで彼女の歌が好きだ。
ちょっと近寄りがたい美貌の持ち主で貫録もありぼくなんかは北欧のダイアナ・クラールみたいだと感じている。彼女の歌はしっとりとした趣があって容貌通りまさに大人の雰囲気で聴くものを包み込み魅了してしまう。
このアルバムの9曲目のThe Windmills of Your Mind(風のささやき)はミシェル・ルグラン作曲による映画「華麗なる賭け」の主題歌で多くのアーティストが歌っているが、その中でも彼女のこの一曲は抜きんでていると思う。アルバムは他にもDon’t be so blue、Dreams、Remembering Youなど。
Malene Mortensen
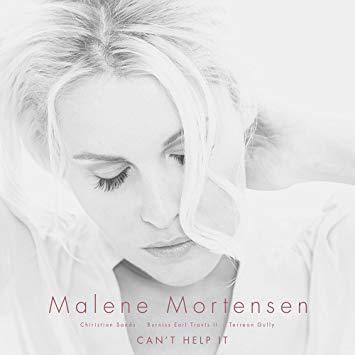
Can't Help It(2015)
デンマークのシンガーMalene Mortensen(マレン・モーテンセン)のデビューはデンマークのテレビ局のスタタン(スター誕生)番組が発端らしい。彼女の声は一聴してその声の透明感がまず印象に残る。ジャズシンガーであるとともにシンガソングライターでもあり、彼女のレパートリーにはヒュージョン的な曲も多い。
時にはソフトに時にはパワフルに一気に高音域に駆け上がっても音が濁ることがないのはさすが。このアルバムはジャケットも新たに日本でリリースされたもののようだ。2006年のアルバムMALENEではコペンハーゲンでの録音に加えてニューヨークで現地のミュージシャンとの録音も入っているようだ。他のアルバムとしてYou go to my head/Agony & Ecstasy/Malene Mortensenなどもある。
Sidsel Storm

Scandinavian Romance(2013)
Sidsel Storm(シゼル・ストーム)はデンマークのシンガー。2008年に彼女のファーストアルバム「Sidsel Storm」で音楽賞を獲得して人気シンガーになった。モーテンセンに劣らぬ美形だが、声の質は彼女のそれよりは少し軽い感じがする。だが節回しはぼくはシゼルの方が好きかもしれない。
このアルバムはいわばベスト盤でSidsel Stotm、Swedish Lullaby、Nothing in betweenのアルバムから選曲されているのでお得盤といえる。日本企画の国内版らしい。2014年にはジャパン・ツアーも行っているので日本にもファンが多い歌手の一人だ。昨年リリースされたアルバム「CLOSER」はまだ聴いていないのだけど楽しみだ。
Karin Krog

カーリン・クローグは最初に登場したモニカ・ゼッタールンドと奇しくも同じ年生まれで、ともに1937年生まれ。モニカがスウェーデン生まれなのに対してカーリンはノルウェイ生まれということだけれど、音楽的な守備範囲で言えばカーリンの方が広いかもしれない。というかカーリンの方はギンギンに攻めていると思われる時期もあったりしてこの二人を単純に比べるのは難しいかな、と。
カーリンは活動期間が長いのでぼくが聴いているのはほんの数枚のアルバムでこんなこと書くのもおこがましいのだけど、3枚だけ挙げるとすれば下の三枚のアルバムになるけど、その幅はすごく広い。
①JAZZMOMENTS

(1966/2017CD)
比較的初期のアルバムでお馴染みのスタンダードナンバーも入っていて聞きやすいアルバムといえる。ぼくは最初ケニー・ドリューのピアノに惹かれて聴きだしたのだけど歌も素晴らしかった。いわゆるヨーロピアン・ジャズの流れの代表的なアルバムでいつでも安心してここに戻ってこられるという感じがする。
②We Could Be Flying

(1976)
初めて聴いたときカーリンがギンギンに攻めているように感じた。裸の天使?が魔女の気球を引っ張りながら空を飛んでいるというぶっ飛んだジャケットにも驚かされるけど、彼女の歌にもドキッとしたがこれもアリですねという感じ。尤もぼくは保守的だから上のアルバムの方が良く聴くけど…。
③LIVE AT THE FESTIVAL

(1973)
これは元がLPで現在CD化されているかは分からないけどぼくはYoutubeで聴いた。スロベニアのリュブリャーナ音楽フェスティバルでの'70~'73年のライヴを収めたアルバムなのだけど、そのメンツがすごい。Bill Evans, Bobby Hutcherson, Karin Krog, Archie Sheppなどで、2曲目のRound About Midnightをカーリンがベースのソロだけをバックに歌っているんだけど、ベースはノルウェイのベーシストArild Andersenらしいのだけど、これが凄い。ネットに残っているうちに是非一度聴いてみてほしい。
Angelina Jordan

最後の一人はまだプロの歌手とは言えないと思うけれど、今どきの北欧のYouTubeスターと言う点では見逃せないと思う。
Angelina Jordan(アンジェリーナ・ジョーダン)はイギリスのテレビ番組「Britain's Got Talent」で一躍有名になったポール・ポッツなどと同じ経歴を持っている。
彼女は2006年生まれ現在は13歳だが、まだ8歳の時にノルウェーの「スター誕生」みたいなテレビ番組「Norway's Got Talent」でFly Me To the Moonを歌って一躍有名になった。その後北欧のテレビやYouTubeを通じて人気が沸騰、ロンドンでクインシー・ジョーンズの85歳の誕生パーティーでも歌を披露したりもしている。
彼女の母親はイラン出身で母方の祖父は日本人らしい。歌は全く子供らしくないどころか、逆に成熟した大人の崩れた、倦怠感さえ漂わせていて驚く。音域も決して広くはないし所どころ危なっかしさも感じるが、その歌い方、声の魅力には抗えないものがある。現在は15歳になって、YouTubeで自分のチャンネルを持ち歌を披露している。
Youtubeを観ると彼女の子供のころからの歌唱が載っていて時と共に成長しているさまがわかるし、一番最近の「Million Miles」を聴くと子供の頃のちょっとこましゃくれた危うさみたいなものがあって、ただ話題で騒がれているのかなというところもあったけど、今はノラ・ジョーンズばりの良い味を出している。これからが楽しみでもあると思う。
Angelina Jordan [Million Miles]
[蛇足]北欧のその他のジャズシンガー
調べてみたら特にデンマークなど活動しているジャズシンガーが結構多い。おいおい聴いてみようと思っている。
Cathrine Legardh (Denm)
Malene Kjaergaard(Denm)
Veronika Mortensen(Denm)
Clara Vuust(Denm)
Mini Terris(Swed)
Hanna Elmquist(Swed)
Christina Gustafsson(Swed)
Solveig Slettahjell(Norw)
Nina Mya(Fin)
北欧の
ジャズシンガー

Sinne Eeg
女性ジャズシンガーの歌が好きで主に1950年代から60年代のLPが多かったのだけれど、比較的最近のダイアナ・クラールやニッキ・パロットなんかも好きになって聴いているが、ここのところ北欧出身の女性ジャズシンガーの作品を聴くことも多くなった。
それを意識して聴いていたわけではないのだけれど、気が付いてみたら、あら結構多いなぁということで並べてみたのだけれど…。特徴はといえば、英語の歌詞が聴きやすい、これはオランダの歌手アン・バートンもそうなのだけれど、英語は彼女らにとって外国語なのだけど、逆に聴きやすいところがある。それに英語が地域語化しているアジアや他の地域の英語のように強い癖がないので日本人にも聞きやすいということもある。
さらに彼女達それぞれが皆大人の雰囲気を持っている。自国語でも歌っているし、歌う歌の範囲も広い。昔のジャズシンガーを知っている者からすれば彼女たちを純粋なジャズシンガーとみない向きもあるみたいだけれど、じゃなにが純粋なジャズなのかといったら、常に動き変化しているのがジャズだから余り硬いことは言わないことだ。
60年代だってローズ・マリークルーニーやダイナ・ショアみたいにジャズとポップスの両面の要素を持っていたシンガーだって多い。それは別にしても彼女たちの歌唱自体が素晴らしいことも共通している。表面的には静かで、しかしその底に強い情熱を秘めたような雰囲気を持っている。春の宵、北欧に思いをはせて彼女たちの青い炎のような歌声に静かに耳を傾けるのも楽しいひと時になると思う。
[My Favourite Albums+1]
Monika Zetterlund

Waltz For Debby/Bill Evans & Monica Zetterlund(1964)
北欧のジャズシンガーといえばまず浮かんでくるのがMonika Zetterlund(モニカ・ゼッタールンド)というスウェーデンの歌手の名前だろう。ビル・エヴァンスとの共演で1964年に出されたLPはエヴァンスのアルバムの中でもぼくも大好きなものの一枚だ。
今ではエヴァンスの代名詞にもなった感のある「Waltz For Debby」をゼッタールンドはスウェーデン語で歌っているのだが、それが妙に心地よい。聴きこんでいるうちに彼女の一見クールな歌い方の向こうに時々垣間見える熱いものが感じられる。これは他の北欧出身のシンガーにも感じられる傾向だ。アメリカの黒人文化から発生したジャズという歌が遥か北欧にまでたどり着いてこういう空気を纏った歌に変化していったことを思うと、ちょっと感慨深い。
ぼくの持っているのはCDなのだけれど、LPの収録曲に加えて6曲も別テイクの録音のボーナストラックが入っている。ゼッタールンドのLPは少ないだけにこれは嬉しい。
Toruń Eriksen

Passage(2010)
ノルウェーのシンガーToruń Eriksen(トルン・エリクセン)の歌声を初めて聴いたとき、ジャニス・イアンに似ているなと思った。エリクセンの声はジャニスよりもうちょっと透明感があるけどスローテンポの曲になるととても似てくる。
彼女はオスロを中心にジャズとソウルの分野で活動しているということだが日本ではまだCDはリリースされていないみたいだ。他にもアルバムとしてはGrand white silkh、Visits、Luxury And Wasteなどがリリースされている。
Sinne Eeg
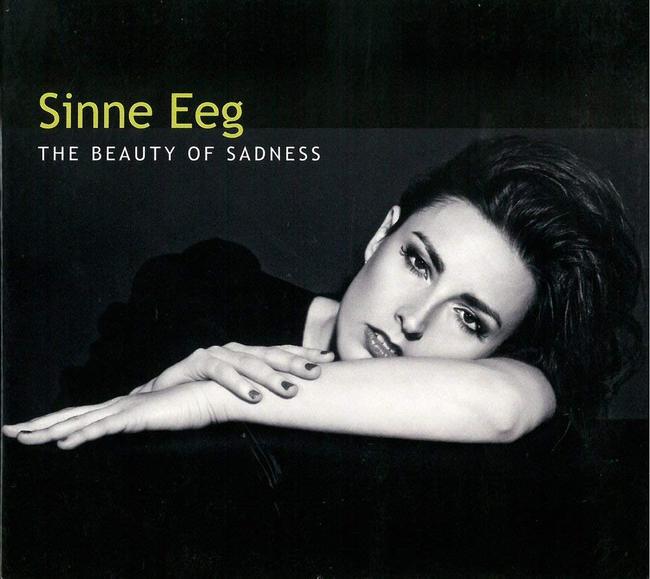
Beauty of Sadness(2012)
デンマークのジャズシンガーSinne Eeg(シーネ・エイ)は何度か来日もしている。ファンの中には彼女の事を「シー姐(しーねい)」と呼んでいる者もいるやに…。ぼくも北欧系のシンガーではゼッタールンドに次いで彼女の歌が好きだ。
ちょっと近寄りがたい美貌の持ち主で貫録もありぼくなんかは北欧のダイアナ・クラールみたいだと感じている。彼女の歌はしっとりとした趣があって容貌通りまさに大人の雰囲気で聴くものを包み込み魅了してしまう。
このアルバムの9曲目のThe Windmills of Your Mind(風のささやき)はミシェル・ルグラン作曲による映画「華麗なる賭け」の主題歌で多くのアーティストが歌っているが、その中でも彼女のこの一曲は抜きんでていると思う。アルバムは他にもDon’t be so blue、Dreams、Remembering Youなど。
Malene Mortensen
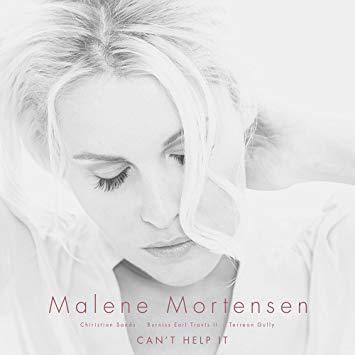
Can't Help It(2015)
デンマークのシンガーMalene Mortensen(マレン・モーテンセン)のデビューはデンマークのテレビ局のスタタン(スター誕生)番組が発端らしい。彼女の声は一聴してその声の透明感がまず印象に残る。ジャズシンガーであるとともにシンガソングライターでもあり、彼女のレパートリーにはヒュージョン的な曲も多い。
時にはソフトに時にはパワフルに一気に高音域に駆け上がっても音が濁ることがないのはさすが。このアルバムはジャケットも新たに日本でリリースされたもののようだ。2006年のアルバムMALENEではコペンハーゲンでの録音に加えてニューヨークで現地のミュージシャンとの録音も入っているようだ。他のアルバムとしてYou go to my head/Agony & Ecstasy/Malene Mortensenなどもある。
Sidsel Storm

Scandinavian Romance(2013)
Sidsel Storm(シゼル・ストーム)はデンマークのシンガー。2008年に彼女のファーストアルバム「Sidsel Storm」で音楽賞を獲得して人気シンガーになった。モーテンセンに劣らぬ美形だが、声の質は彼女のそれよりは少し軽い感じがする。だが節回しはぼくはシゼルの方が好きかもしれない。
このアルバムはいわばベスト盤でSidsel Stotm、Swedish Lullaby、Nothing in betweenのアルバムから選曲されているのでお得盤といえる。日本企画の国内版らしい。2014年にはジャパン・ツアーも行っているので日本にもファンが多い歌手の一人だ。昨年リリースされたアルバム「CLOSER」はまだ聴いていないのだけど楽しみだ。
Karin Krog

カーリン・クローグは最初に登場したモニカ・ゼッタールンドと奇しくも同じ年生まれで、ともに1937年生まれ。モニカがスウェーデン生まれなのに対してカーリンはノルウェイ生まれということだけれど、音楽的な守備範囲で言えばカーリンの方が広いかもしれない。というかカーリンの方はギンギンに攻めていると思われる時期もあったりしてこの二人を単純に比べるのは難しいかな、と。
カーリンは活動期間が長いのでぼくが聴いているのはほんの数枚のアルバムでこんなこと書くのもおこがましいのだけど、3枚だけ挙げるとすれば下の三枚のアルバムになるけど、その幅はすごく広い。
①JAZZMOMENTS

(1966/2017CD)
比較的初期のアルバムでお馴染みのスタンダードナンバーも入っていて聞きやすいアルバムといえる。ぼくは最初ケニー・ドリューのピアノに惹かれて聴きだしたのだけど歌も素晴らしかった。いわゆるヨーロピアン・ジャズの流れの代表的なアルバムでいつでも安心してここに戻ってこられるという感じがする。
②We Could Be Flying

(1976)
初めて聴いたときカーリンがギンギンに攻めているように感じた。裸の天使?が魔女の気球を引っ張りながら空を飛んでいるというぶっ飛んだジャケットにも驚かされるけど、彼女の歌にもドキッとしたがこれもアリですねという感じ。尤もぼくは保守的だから上のアルバムの方が良く聴くけど…。
③LIVE AT THE FESTIVAL

(1973)
これは元がLPで現在CD化されているかは分からないけどぼくはYoutubeで聴いた。スロベニアのリュブリャーナ音楽フェスティバルでの'70~'73年のライヴを収めたアルバムなのだけど、そのメンツがすごい。Bill Evans, Bobby Hutcherson, Karin Krog, Archie Sheppなどで、2曲目のRound About Midnightをカーリンがベースのソロだけをバックに歌っているんだけど、ベースはノルウェイのベーシストArild Andersenらしいのだけど、これが凄い。ネットに残っているうちに是非一度聴いてみてほしい。
Angelina Jordan

最後の一人はまだプロの歌手とは言えないと思うけれど、今どきの北欧のYouTubeスターと言う点では見逃せないと思う。
Angelina Jordan(アンジェリーナ・ジョーダン)はイギリスのテレビ番組「Britain's Got Talent」で一躍有名になったポール・ポッツなどと同じ経歴を持っている。
彼女は2006年生まれ現在は13歳だが、まだ8歳の時にノルウェーの「スター誕生」みたいなテレビ番組「Norway's Got Talent」でFly Me To the Moonを歌って一躍有名になった。その後北欧のテレビやYouTubeを通じて人気が沸騰、ロンドンでクインシー・ジョーンズの85歳の誕生パーティーでも歌を披露したりもしている。
彼女の母親はイラン出身で母方の祖父は日本人らしい。歌は全く子供らしくないどころか、逆に成熟した大人の崩れた、倦怠感さえ漂わせていて驚く。音域も決して広くはないし所どころ危なっかしさも感じるが、その歌い方、声の魅力には抗えないものがある。現在は15歳になって、YouTubeで自分のチャンネルを持ち歌を披露している。
Youtubeを観ると彼女の子供のころからの歌唱が載っていて時と共に成長しているさまがわかるし、一番最近の「Million Miles」を聴くと子供の頃のちょっとこましゃくれた危うさみたいなものがあって、ただ話題で騒がれているのかなというところもあったけど、今はノラ・ジョーンズばりの良い味を出している。これからが楽しみでもあると思う。
Angelina Jordan [Million Miles]
[蛇足]北欧のその他のジャズシンガー
調べてみたら特にデンマークなど活動しているジャズシンガーが結構多い。おいおい聴いてみようと思っている。
Cathrine Legardh (Denm)
Malene Kjaergaard(Denm)
Veronika Mortensen(Denm)
Clara Vuust(Denm)
Mini Terris(Swed)
Hanna Elmquist(Swed)
Christina Gustafsson(Swed)
Solveig Slettahjell(Norw)
Nina Mya(Fin)
(Mar.2021)
最新記事一覧
最近のコメント
gillman*s Museum 吉田博展
The Museum of the Month...
没後70年

[感想メモ]
吉田博は川瀬巴水や小原小邨と並んでぼくの好きな版画家だ。巴水が叙情の作家、小邨が花鳥風月の作家だとしたら、吉田博はさしずめ山岳の作家と言えるかもしれないが、もちろんそれは余りにもステレオタイプの表現で、各々の創作活動を極端にデフォルメしたことになり失礼に当たるかもしれない。
ぼくが吉田博の作品を初めてまとめて観ることができたのは2017年の損保ジャパン美術館での彼の生誕140年を記念した「吉田博展/山と水の風景」だった。彼の初めての本格的な回顧展とあって会場はかなりの混雑だった。作品の出品点数は今回の展覧会が190点あまりなのに対して、前回の展覧会では270点程が展示され、どちらも前期後期の二期に分けて展示されたため、全てを観たわけではない。
全体を通して感じたのは前に戻るけど彼の真骨頂はやはり山河など自然の姿を描いたものに尽きるような気がした。特に激しく流れる渓流の表現は版画とも思えないち密さと迫力に圧倒される。逆に今回気づいたのは下町の情景などで登場する人物の表現は余り得意でないらしく塗り絵的な感じがしたのは意外だった。
先日行ってきたが緊急事態宣言下でもあり、家に近い上野なのでさっと行って食事もせずにさっと帰ってきた。予約は要らないで入館できたし、会場は人もまばらでゆっくりと観ることができたので良かったけど、前回の展覧会の賑わいを考えるとちょっと寂しい感じもした。
渓流

1928年(No.51)
版画で流れ落ちる水の質感をここまで表現できるというのはまさに驚異だと言える。渓流の段差を流れ落ちる水の音まで聞こえてきそうな迫力。前回の展覧会でも会場で何度もこの絵の処に戻って来ては眺め直した。今回は同じ場所を油彩で描いた作品も展示されていたが、版画が規格外の大判であることもあって迫力はこちらの方が勝る。水の流れの部分は吉田が自ら版木を彫ったと言われており力を入れ過ぎて奥歯を痛めたという逸話も残っている。版画の表現にかける吉田の執念のようなものが感じられる。日本の版画の最高傑作の一つだと思う。
劔山の朝

1926年(No.25)
今回の展覧会の図録の表紙にも使われている吉田の山岳版画を代表するような作品。山岳シリーズ「日本アルプス十二題」の中のひとつ。朝日に染まって茜色に輝く剱山、手前のまだ明けきらぬ蒼い空間と残雪の純白が絶妙なバランスで大自然のドラマの一瞬を捉えている。
帆船 朝
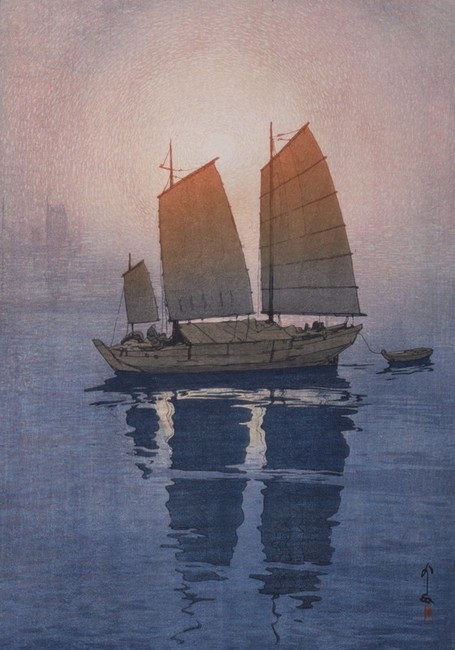
1926年(No.40)
吉田博も当初は川瀬巴水と同様、渡邊庄三郎のもとで制作しており、この帆船の最初の作品もその頃制作されたが、版木ともに関東大震災で失われたため後に再制作され、その頃には私家版として「自摺」をうたい自分で監修を行っている。吉田はこの帆船において同じ版木を使い朝・夜・午前・霧など色彩を変え多くのパターンを摺りだしている。会場でそのいくつかのパターンの変化を観るのも楽しい。風の凪いだ瀬戸内海の海面が、ねっとりとした液体のように帆船の影を映しているのが印象的だった。

[図 録]
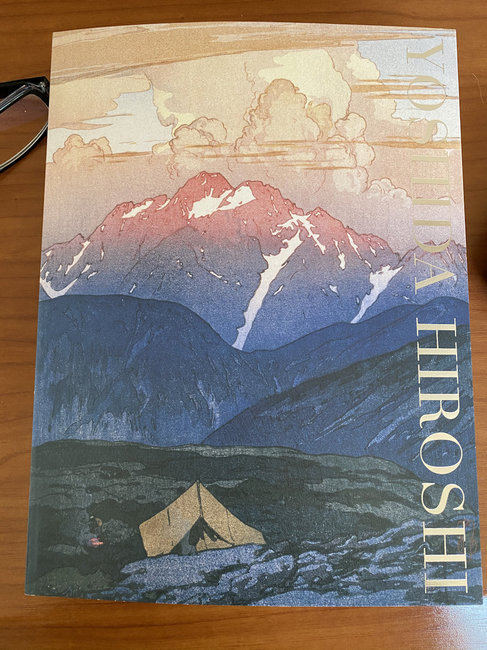
255頁。2200円。吉田博のこの回顧展は2019年の10月から始まった日本各地での巡回展で東京の後に三重県、静岡県の美術館も巡回予定されており図録は共通のものとなる。これはその共通の図録なので作品入れ替えで観られなかったり、中には一部の会場では広さなどで展示されない作品も含まれているので吉田の作品を網羅して観たいときには良いと思う。
没後70年
吉田博展
美が、摺り重なる

東京都美術館
2021年1月26日〜3月28日
[感想メモ]
吉田博は川瀬巴水や小原小邨と並んでぼくの好きな版画家だ。巴水が叙情の作家、小邨が花鳥風月の作家だとしたら、吉田博はさしずめ山岳の作家と言えるかもしれないが、もちろんそれは余りにもステレオタイプの表現で、各々の創作活動を極端にデフォルメしたことになり失礼に当たるかもしれない。
ぼくが吉田博の作品を初めてまとめて観ることができたのは2017年の損保ジャパン美術館での彼の生誕140年を記念した「吉田博展/山と水の風景」だった。彼の初めての本格的な回顧展とあって会場はかなりの混雑だった。作品の出品点数は今回の展覧会が190点あまりなのに対して、前回の展覧会では270点程が展示され、どちらも前期後期の二期に分けて展示されたため、全てを観たわけではない。
全体を通して感じたのは前に戻るけど彼の真骨頂はやはり山河など自然の姿を描いたものに尽きるような気がした。特に激しく流れる渓流の表現は版画とも思えないち密さと迫力に圧倒される。逆に今回気づいたのは下町の情景などで登場する人物の表現は余り得意でないらしく塗り絵的な感じがしたのは意外だった。
先日行ってきたが緊急事態宣言下でもあり、家に近い上野なのでさっと行って食事もせずにさっと帰ってきた。予約は要らないで入館できたし、会場は人もまばらでゆっくりと観ることができたので良かったけど、前回の展覧会の賑わいを考えるとちょっと寂しい感じもした。
[吉田博展 My Best 3]
渓流

1928年(No.51)
版画で流れ落ちる水の質感をここまで表現できるというのはまさに驚異だと言える。渓流の段差を流れ落ちる水の音まで聞こえてきそうな迫力。前回の展覧会でも会場で何度もこの絵の処に戻って来ては眺め直した。今回は同じ場所を油彩で描いた作品も展示されていたが、版画が規格外の大判であることもあって迫力はこちらの方が勝る。水の流れの部分は吉田が自ら版木を彫ったと言われており力を入れ過ぎて奥歯を痛めたという逸話も残っている。版画の表現にかける吉田の執念のようなものが感じられる。日本の版画の最高傑作の一つだと思う。
劔山の朝

1926年(No.25)
今回の展覧会の図録の表紙にも使われている吉田の山岳版画を代表するような作品。山岳シリーズ「日本アルプス十二題」の中のひとつ。朝日に染まって茜色に輝く剱山、手前のまだ明けきらぬ蒼い空間と残雪の純白が絶妙なバランスで大自然のドラマの一瞬を捉えている。
帆船 朝
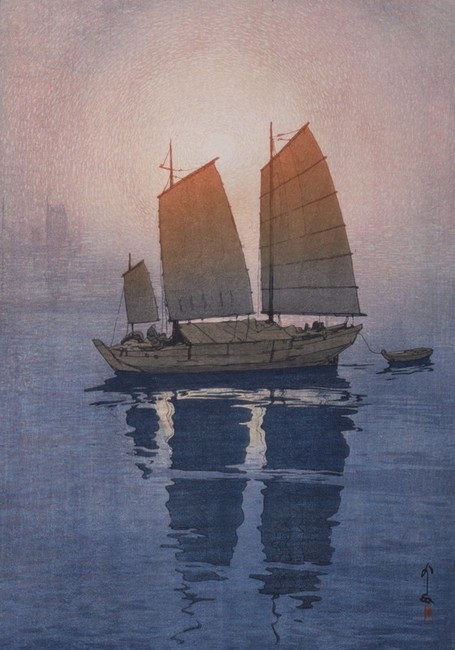
1926年(No.40)
吉田博も当初は川瀬巴水と同様、渡邊庄三郎のもとで制作しており、この帆船の最初の作品もその頃制作されたが、版木ともに関東大震災で失われたため後に再制作され、その頃には私家版として「自摺」をうたい自分で監修を行っている。吉田はこの帆船において同じ版木を使い朝・夜・午前・霧など色彩を変え多くのパターンを摺りだしている。会場でそのいくつかのパターンの変化を観るのも楽しい。風の凪いだ瀬戸内海の海面が、ねっとりとした液体のように帆船の影を映しているのが印象的だった。

[図 録]
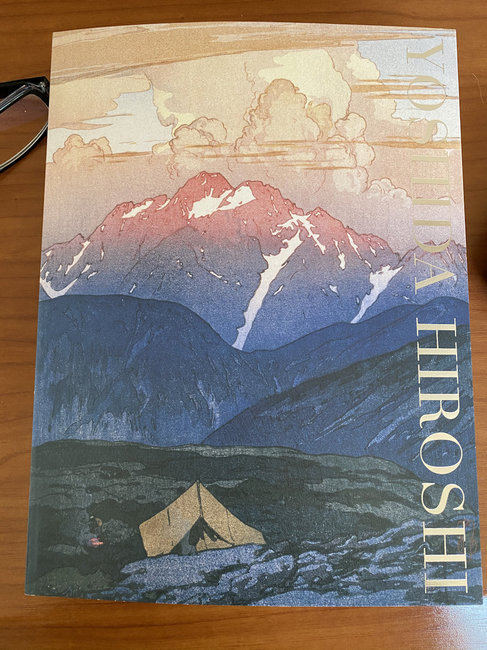
255頁。2200円。吉田博のこの回顧展は2019年の10月から始まった日本各地での巡回展で東京の後に三重県、静岡県の美術館も巡回予定されており図録は共通のものとなる。これはその共通の図録なので作品入れ替えで観られなかったり、中には一部の会場では広さなどで展示されない作品も含まれているので吉田の作品を網羅して観たいときには良いと思う。
(Mar.2021)
gillman*s Choice Das Versprechen
Book & Cinema Review...
BOOK 約束
Das Versprechen

F・デュレンマット著
早川書房
CINEMA プレッジ
The Pledge

ショーン・ペン監督
ジャック・ニコルソン主演
この間、ドイツ語圏スイスの作家デュレンマットの「判事と死刑執行人」を翻訳本で読んですごく面白かったので、今は少しづつドイツ語で読みながら併せてオーディオブックなんかも聴いているのだけど力不足でなかなか捗らない。ということでその間に彼の作品「約束(Das Versprechen)」も翻訳で読んで見ようと思って読んでみた。
こちらも同じミステリー小説だが、こちらの方はジャック・ニコルソン主演で「プレッジ(Pledge)」というタイトルで映画化もされている。小説を読んだあと映画を観て比べてみるのも面白いなと思いこれも観てみた。

この作業はとても興味深かった。映画は原作の筋にかなり忠実に創られているので、原作と映画とどちらを先にした方が良いかという論議があるけど、ぼくは原作を先に読んだ方が楽しめるような気がするけど…、この映画は観る順番によってミステリーにもサスペンスにもなりえる。
ミステリーとサスペンスの違いはアルフレッド・ヒッチコックが明確に区別したようにミステリーはその名の通り謎解きだが、サスペンスは読者や観客には最初から犯人が知らされていて、それを知らないのは主人公だけという図式になっている。その図式の中で観客は主人公に感情移入してハラハラ、ドキドキするのだ。そういう意味でヒッチコックの作品は殆ど全てサスペンスということになる。

最初に小説の方の「約束」を読んでから映画を見るということは、もう結末は判っているので謎解きの部分はなくなるけれど、どうやって話の運びをそこへ持ってゆくのか、どこにどんな映像的な伏線が張られているか等とても興味深いし、何か同じようなことを表現するのに必要とされる「文法」みたいなものが文章と映像では大きく違うことが如実にわかるのが面白い。
例えば後で重要な役割をするコトやモノが登場する場合には、映画ではその部分を一瞬アップにしたり、逆に長回しにしたりそれとなく観客の脳裏に印象が残るようにするのだけれど、文章ではそれが難しくわざとらしく提示すれば読者にすぐに見抜かれてしまうから、情景描写や人物描写の中にうまく紛れ込まさなければならない。

話がそれてしまったけれど、物語自体は女児連続殺人犯をチューリッヒ州警察のマーティ警部が追うという残酷でエグい内容のものだけれど、その警部が事件の一報を受けたのは自分の栄転が決まってデスクを整理している最中だった。物語の展開はデュレンマットがこの小説の副題に「推理小説へのレクイエム」と付けたあたりに象徴されるように前作の「判事と死刑執行人」とは傾向は大きく異なる。

この早川の翻訳本は2002年に出版されているが、実はそれは同じ訳者によって1960年に同じ早川から出されていたポケット・ミステリー・シリーズ(通称ポケミス)の中で出されていたものを後に同じ訳者が手を入れて復刻したものだ。原作がスイスで発表されたのが1958年なので当時の最新作の翻訳と言ってもよい。最近別の訳者でも出版されたのでそちらの翻訳で読んだ人もいるかもしれない。
蛇足になるけど、前作の「判事と死刑執行人」同様ドイツ語でのオーディオブックがYoutubeで聴くことができる。朗読は惜しくも先年亡くなったドイツの俳優ハンス・コルテで実に渋い声で思わず聴き入ってしまう。
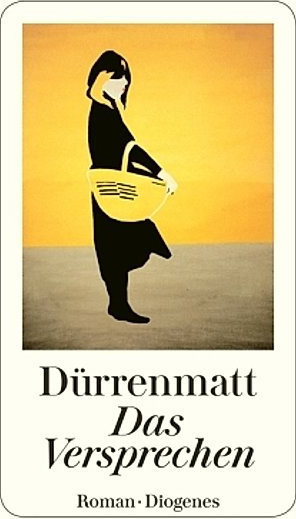
Youtube Audiobook
「約 束」
フリードリヒ・デュレンマット著
BOOK 約束
Das Versprechen

F・デュレンマット著
早川書房
CINEMA プレッジ
The Pledge

ショーン・ペン監督
ジャック・ニコルソン主演
この間、ドイツ語圏スイスの作家デュレンマットの「判事と死刑執行人」を翻訳本で読んですごく面白かったので、今は少しづつドイツ語で読みながら併せてオーディオブックなんかも聴いているのだけど力不足でなかなか捗らない。ということでその間に彼の作品「約束(Das Versprechen)」も翻訳で読んで見ようと思って読んでみた。
こちらも同じミステリー小説だが、こちらの方はジャック・ニコルソン主演で「プレッジ(Pledge)」というタイトルで映画化もされている。小説を読んだあと映画を観て比べてみるのも面白いなと思いこれも観てみた。

この作業はとても興味深かった。映画は原作の筋にかなり忠実に創られているので、原作と映画とどちらを先にした方が良いかという論議があるけど、ぼくは原作を先に読んだ方が楽しめるような気がするけど…、この映画は観る順番によってミステリーにもサスペンスにもなりえる。
ミステリーとサスペンスの違いはアルフレッド・ヒッチコックが明確に区別したようにミステリーはその名の通り謎解きだが、サスペンスは読者や観客には最初から犯人が知らされていて、それを知らないのは主人公だけという図式になっている。その図式の中で観客は主人公に感情移入してハラハラ、ドキドキするのだ。そういう意味でヒッチコックの作品は殆ど全てサスペンスということになる。

最初に小説の方の「約束」を読んでから映画を見るということは、もう結末は判っているので謎解きの部分はなくなるけれど、どうやって話の運びをそこへ持ってゆくのか、どこにどんな映像的な伏線が張られているか等とても興味深いし、何か同じようなことを表現するのに必要とされる「文法」みたいなものが文章と映像では大きく違うことが如実にわかるのが面白い。
例えば後で重要な役割をするコトやモノが登場する場合には、映画ではその部分を一瞬アップにしたり、逆に長回しにしたりそれとなく観客の脳裏に印象が残るようにするのだけれど、文章ではそれが難しくわざとらしく提示すれば読者にすぐに見抜かれてしまうから、情景描写や人物描写の中にうまく紛れ込まさなければならない。

話がそれてしまったけれど、物語自体は女児連続殺人犯をチューリッヒ州警察のマーティ警部が追うという残酷でエグい内容のものだけれど、その警部が事件の一報を受けたのは自分の栄転が決まってデスクを整理している最中だった。物語の展開はデュレンマットがこの小説の副題に「推理小説へのレクイエム」と付けたあたりに象徴されるように前作の「判事と死刑執行人」とは傾向は大きく異なる。

この早川の翻訳本は2002年に出版されているが、実はそれは同じ訳者によって1960年に同じ早川から出されていたポケット・ミステリー・シリーズ(通称ポケミス)の中で出されていたものを後に同じ訳者が手を入れて復刻したものだ。原作がスイスで発表されたのが1958年なので当時の最新作の翻訳と言ってもよい。最近別の訳者でも出版されたのでそちらの翻訳で読んだ人もいるかもしれない。
蛇足になるけど、前作の「判事と死刑執行人」同様ドイツ語でのオーディオブックがYoutubeで聴くことができる。朗読は惜しくも先年亡くなったドイツの俳優ハンス・コルテで実に渋い声で思わず聴き入ってしまう。
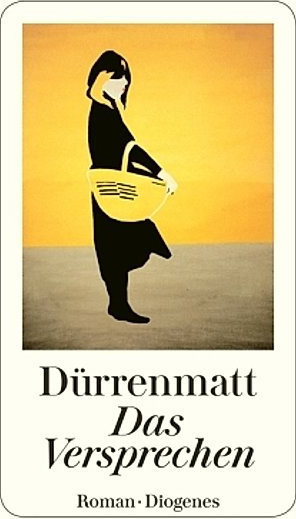
Youtube Audiobook
(Mar.2021)
gillman*s Choice 判事と死刑執行人
Book Review...
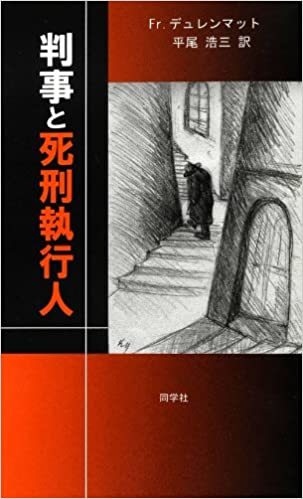
フリードリヒ・デュレンマット著
平尾浩三訳/同学社
F.デュレンマット(Friedrich Dürrenmatt、1921年1月5日-1990年12月14日)はドイツ語圏スイスの劇作家であり、この作品で推理作家としてもデビューし活躍していた人物だけれど日本ではあまり知られてはいないと思う。彼がこの作品の翌年に書いた推理小説「約束(Versprechen)」はハヤカワ・ミステリー文庫でも出ているし「プレッジ」(2000)というタイトルでジャック・ニコルソン主演で映画化されてもいる。この作品自体は先日ドイツ人の女性がサイトで面白いと紹介していたので読んでみる気になった。
物語はスイスの山村の道端に止まっていた一台のベンツの運転席で男が射殺されているのが警察官に発見されるところからはじまる。ヨーロッパの警察を渡り歩いて今はベルンの警部補に落ち着いている老警部補ベアラッハは部下のシャンツと共に捜査を開始するが…。謎の富豪ガストマンが殺害に関わっいてると疑われたが、そこには厚い捜査の壁が立ちふさがっていた。
スイス北東部が舞台になっておりGoogleマップや特にGoogle Earthを見ながら筋を追って行くと、具体的な地名が多く登場し土地の情景描写もすぐれているだけにずっと現実感が湧いてくる。もちろん架空の事件だけれど事件現場の辺りをめぼしをつけて航空写真で見ていると自分の中で段々とイメージが膨らんでくる楽しさがある。
ネタバレはできないけど、ずっと霧の中を手探りで歩いているような状況が最後の所で意外な形で真実が暴露されてくる。ふつうこういう筋書き中心のミステリー小説は一度読んでしまうと、結末が分かっているだけにまた読むという気にはならないものなのだが、この作品は読み返すと見えてくる状況が最初とは全く違って見えてまた新たな面白さに出会える。
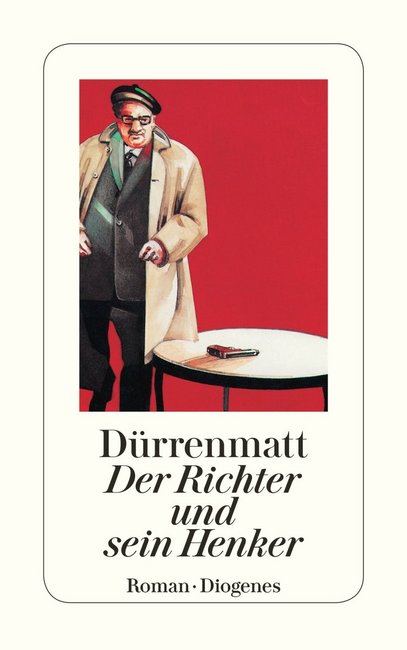
日本語の翻訳は紹介した一種類しかでていないが、ドイツ語版はKindleの電子書籍で安価にでているし、Youtubeを調べてみたらHörbuchというドイツ語版朗読のものもアップされていた。翻訳本+電子書籍の原書+原語での朗読版のセットで効率的勉強の材料にもなると思う。
判事と死刑執行人
Der Richter und sein Henker
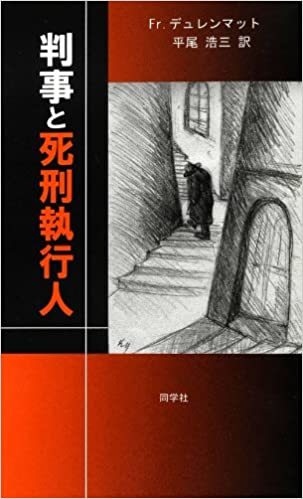
フリードリヒ・デュレンマット著
平尾浩三訳/同学社
F.デュレンマット(Friedrich Dürrenmatt、1921年1月5日-1990年12月14日)はドイツ語圏スイスの劇作家であり、この作品で推理作家としてもデビューし活躍していた人物だけれど日本ではあまり知られてはいないと思う。彼がこの作品の翌年に書いた推理小説「約束(Versprechen)」はハヤカワ・ミステリー文庫でも出ているし「プレッジ」(2000)というタイトルでジャック・ニコルソン主演で映画化されてもいる。この作品自体は先日ドイツ人の女性がサイトで面白いと紹介していたので読んでみる気になった。
物語はスイスの山村の道端に止まっていた一台のベンツの運転席で男が射殺されているのが警察官に発見されるところからはじまる。ヨーロッパの警察を渡り歩いて今はベルンの警部補に落ち着いている老警部補ベアラッハは部下のシャンツと共に捜査を開始するが…。謎の富豪ガストマンが殺害に関わっいてると疑われたが、そこには厚い捜査の壁が立ちふさがっていた。
スイス北東部が舞台になっておりGoogleマップや特にGoogle Earthを見ながら筋を追って行くと、具体的な地名が多く登場し土地の情景描写もすぐれているだけにずっと現実感が湧いてくる。もちろん架空の事件だけれど事件現場の辺りをめぼしをつけて航空写真で見ていると自分の中で段々とイメージが膨らんでくる楽しさがある。
ネタバレはできないけど、ずっと霧の中を手探りで歩いているような状況が最後の所で意外な形で真実が暴露されてくる。ふつうこういう筋書き中心のミステリー小説は一度読んでしまうと、結末が分かっているだけにまた読むという気にはならないものなのだが、この作品は読み返すと見えてくる状況が最初とは全く違って見えてまた新たな面白さに出会える。
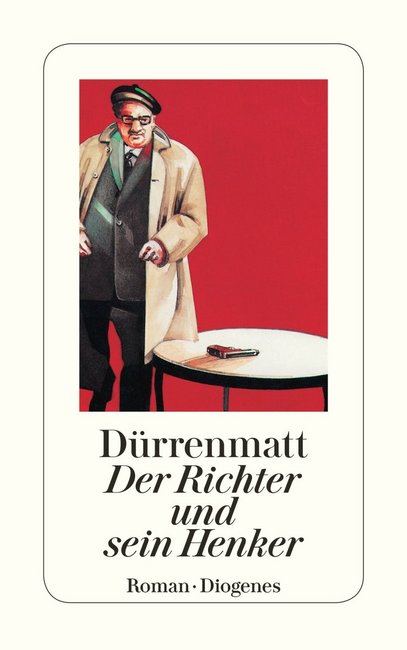
Kindle版ドイツ語
日本語の翻訳は紹介した一種類しかでていないが、ドイツ語版はKindleの電子書籍で安価にでているし、Youtubeを調べてみたらHörbuchというドイツ語版朗読のものもアップされていた。翻訳本+電子書籍の原書+原語での朗読版のセットで効率的勉強の材料にもなると思う。
(Feb.2021)
gillman*s Choice filmmaker's ey
Book Review...

ぼくは写真も好きだけれど映画も好きだ。もっとも最近は映画館に足を運ぶことは少なくなったけれどDVDではよく見る。昔は名画座と言って古い映画を専門にやっている映画館があったので、学生の頃休みなどには入り浸りになって観ていたこともある。
特にヒッチコックの映画が好きで、その内その撮り方にも興味が湧いてきて当時読んだ「映画術 ヒッチコック/トリュフォー」は今でもぼくのバイブルみたいになっている。そこには言わば映画作りの文法みたいなのが実例で満載されていて、そこを読んでは作品を観るのを繰り返していた時期があった。

最初は映画館で何度も居残ってみたりしたが、その内VTRで観られるようになって、今はDVDで頭出しや繰り返しも簡単なので見逃したシーケンスなども確認しやすくありがたい。ヒッチコックの作品だけでなく気に入った監督の作品を見ているうちに、例えばヴィムヴェンダースやコッポラそして小津安二郎や黒澤明などの作品はどのシーンを静止画で切り出してもちゃんと一枚の写真になることに気付いた。
映画はショットとシーケンス(順序)で成り立っている。写真の一枚もショットというけど映画のショットは短時間だが動画でありそれの集まりがシーンとなる。ちょっと前置きが長くなったけどこの本にはそのショットのあり方、意味などいわばショットの文法みたいなのが実例で満載されている。
ストーリーとショットの関係。超クローズアップレンズからロングショットまで。肩越しのショット主観ショット、ダッチアングルショットと呼ばれる意識的に斜めに傾いたショットなどはストーリーにどう関わってゆくか。これは写真で言う構図の問題と共通している。

本書は「filmmaker’s eye」の方が主に構図を中心とした部分、もう一冊の「レンズの言語」はレンズと主に登場人物やシーンの感情や情緒との関係をいずれも実際の作品の写真を使いながら解説している。もちろんこれは映画といういわば動画の世界のことなのだけれど、先に述べたように考え抜かれた優れた映画のショットは優れた写真にもなりうるということを考えると動画だけでなく写真を撮る人間にとっても興味深いと思う。
filmmaker’s eye
&
filmmaker’s eyeレンズの言語
グスタボ・メルカード著

ぼくは写真も好きだけれど映画も好きだ。もっとも最近は映画館に足を運ぶことは少なくなったけれどDVDではよく見る。昔は名画座と言って古い映画を専門にやっている映画館があったので、学生の頃休みなどには入り浸りになって観ていたこともある。
特にヒッチコックの映画が好きで、その内その撮り方にも興味が湧いてきて当時読んだ「映画術 ヒッチコック/トリュフォー」は今でもぼくのバイブルみたいになっている。そこには言わば映画作りの文法みたいなのが実例で満載されていて、そこを読んでは作品を観るのを繰り返していた時期があった。

最初は映画館で何度も居残ってみたりしたが、その内VTRで観られるようになって、今はDVDで頭出しや繰り返しも簡単なので見逃したシーケンスなども確認しやすくありがたい。ヒッチコックの作品だけでなく気に入った監督の作品を見ているうちに、例えばヴィムヴェンダースやコッポラそして小津安二郎や黒澤明などの作品はどのシーンを静止画で切り出してもちゃんと一枚の写真になることに気付いた。
映画はショットとシーケンス(順序)で成り立っている。写真の一枚もショットというけど映画のショットは短時間だが動画でありそれの集まりがシーンとなる。ちょっと前置きが長くなったけどこの本にはそのショットのあり方、意味などいわばショットの文法みたいなのが実例で満載されている。
ストーリーとショットの関係。超クローズアップレンズからロングショットまで。肩越しのショット主観ショット、ダッチアングルショットと呼ばれる意識的に斜めに傾いたショットなどはストーリーにどう関わってゆくか。これは写真で言う構図の問題と共通している。

本書は「filmmaker’s eye」の方が主に構図を中心とした部分、もう一冊の「レンズの言語」はレンズと主に登場人物やシーンの感情や情緒との関係をいずれも実際の作品の写真を使いながら解説している。もちろんこれは映画といういわば動画の世界のことなのだけれど、先に述べたように考え抜かれた優れた映画のショットは優れた写真にもなりうるということを考えると動画だけでなく写真を撮る人間にとっても興味深いと思う。
(Dec.2020)
gillman*s Museums 上田薫展
Museum of the Month...

[感想]
リアリズム作品が特に好きという訳ではないが、上田薫の作品は特別で前から観てみたくて画集も一冊持っているけれど、スーパーリアリズムと呼ばれる彼の作品は写真に撮って印刷するとよけいに写真ぽくなってしまうような気がして、どうしても実物を見てみたくなった。
幸い今月から埼玉県立近代美術館で彼の主要作品を集めた展覧会があり予約も必要ないので早速というか久々に展覧会に足を運んだ。画集で見ていたような作品が一堂に会していて、作品から伝わってくるモノの圧倒的な存在感そして絵に込められた質量の多さに驚かされた。
スーパーリアリズムで一見写真のようだけれども作家も言っているように実際に作品を見て写真と思う人はいないと思う。意識して作品の筆致は消しているということだけど、かと言ってエアブラシのようにマイクロの霧で描いたものでもない。微細なレベルで絶妙な省略がなされている。不思議な存在感としか言いようがない。
スーパーリアリズム作品を考えるときすぐぼくの頭に浮かんでくるのは吉村芳生の作品だ。自然の花や草原を描いた彼の晩年の作品は「写真のような」という点や共に写真を作品の元にしているという点では似ているがその手法は大きく異なる。
吉村の場合が撮った写真の上に方眼を描き、その一つ一つのマス目を拡大して転写してゆくという方法であるのに対し、上田薫は写真を以前はスライド、現在はプロジェクターでキャンバスなどに投影してアウトラインを鉛筆で描いて、その上からもしくはそれを転写して今度は写真と見比べながら作品を描いてゆくというやり方だ。
いずれにしても気の遠くなるような作業には違いない。リアリズム作品の持つ写真を凌駕するような存在感、質量の多さの原因の一つに対象と作品の間を行き交う何万回、何十万回という視線の集積量によるものと言った人もいるが、そういうこともあるかもしれない。彼の作品を見ていると時間とか光とかモノ自体について色々と考えさせられる。会期中にもう一度行きたいと思っている。
[上田薫展 My Best 5]
なま卵B(1976)

彼の作品からは思わず、ぶるっ、ぬるっ、とろ~っのようなオノマトペが浮かんでしまうけれど、その中でもこれは「とろ~っ、ぬる~っ」の極致のような作品。通常作品の元になる写真は彼自身で撮るらしいのだけれど、これだけは卵を200個も用意してプロに撮ってもらったらしい。いわば彼の代表作でもあるけど、そのイメージがあまりにも強烈で時にはそれだけが彼の作品のように思われるけど、もちろん他にも素晴らしいものが多くあるので…。しかしそれだけ強烈だったということだろう。この作品は現在は東京都現代美術館に収蔵されている。
ジェリーにスプーンC(1990)

今回の展覧会のポスターにも使われている作品で、スプーンの上のぷるっとしたピンクのジェリーが揺れながらとろけてゆく瞬間が定着されている。他にもスプーンの上で溶けかかっているアイスクリームやスプーンから垂れようとしている水あめなど時間を凍結して見せるという点では「なま卵」も同じであるかもしれない。
たまごにスプーンB(1987)

これは同じ卵でも半熟のゆで卵を割ってスプーンですくっているところ。半熟卵のぬめっとした感触、スプーンの冷たい金属感、そしてひびの入った殻の危うさ。それぞれの持つ材質感が現実の世界より現実らしく更に増幅したような感触で描かれている。
あわD(1979)

上田薫の作品を横断的に観てゆくと「映しこまれたもう一つの世界」というキーワードにたどり着く。ひんやりしたスプーンやぬめっとした卵の表面には部屋の様子や時にはカメラを構えた画家自身の姿が映し出されている。そこには現実の向こう側に映し出されたもう一つの現実が存在している。それを最も端的に表しているのが様々な「泡」を描いたシリーズだ。金属の表面などに映り込んだ世界を何とか写真に撮りたいといつも思っているぼくにとっては、泡に閉じ込められた虹色に彩られる世界はとても魅力的だ。
割れたびんC(1983)

上田薫の数少ないリトグラフの作品も何点か展示されていた。ロットをみると30部位だからリトグラフと言ってもまず手には入らないだろうけど…。その中でもとりわけ存在感のあるこの作品がぼくの目をひいた。分厚い緑色のビンが割れた切り口が細かく波打ち割れた時の衝撃をも想像させる。リトグラフでもこういう表現ができるのだと新鮮に感じられた。

[図録/画集]
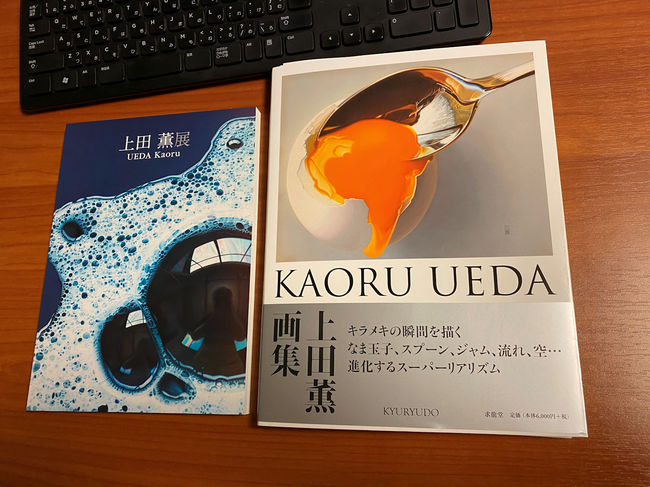
128頁、2200円。ぼくが知る限りでは上田薫の作品は多くの近代美術館に収蔵されているけど広い範囲の作品を収録した画集というのはあまり出ていないと思う。その一冊が写真の右側にある2018年に求龍堂が出した画集だが結構お高い(6600円)のでぼくも一年位散々迷った挙句買ったことを覚えている。
今回の図録は横須賀美術館と埼玉県立近代美術館での個展のために作られたものだけど画家の現在までの主要作品を網羅しており2200円というのは興味のある人には凄くお買い得と思う。また巻末の上田本人による文章も含めて載っている5編のエッセイも読みごたえがあった。
上田薫展
埼玉県立近代美術館
2020年11月14日~翌年1月11日

[感想]
リアリズム作品が特に好きという訳ではないが、上田薫の作品は特別で前から観てみたくて画集も一冊持っているけれど、スーパーリアリズムと呼ばれる彼の作品は写真に撮って印刷するとよけいに写真ぽくなってしまうような気がして、どうしても実物を見てみたくなった。
幸い今月から埼玉県立近代美術館で彼の主要作品を集めた展覧会があり予約も必要ないので早速というか久々に展覧会に足を運んだ。画集で見ていたような作品が一堂に会していて、作品から伝わってくるモノの圧倒的な存在感そして絵に込められた質量の多さに驚かされた。
スーパーリアリズムで一見写真のようだけれども作家も言っているように実際に作品を見て写真と思う人はいないと思う。意識して作品の筆致は消しているということだけど、かと言ってエアブラシのようにマイクロの霧で描いたものでもない。微細なレベルで絶妙な省略がなされている。不思議な存在感としか言いようがない。
スーパーリアリズム作品を考えるときすぐぼくの頭に浮かんでくるのは吉村芳生の作品だ。自然の花や草原を描いた彼の晩年の作品は「写真のような」という点や共に写真を作品の元にしているという点では似ているがその手法は大きく異なる。
吉村の場合が撮った写真の上に方眼を描き、その一つ一つのマス目を拡大して転写してゆくという方法であるのに対し、上田薫は写真を以前はスライド、現在はプロジェクターでキャンバスなどに投影してアウトラインを鉛筆で描いて、その上からもしくはそれを転写して今度は写真と見比べながら作品を描いてゆくというやり方だ。
いずれにしても気の遠くなるような作業には違いない。リアリズム作品の持つ写真を凌駕するような存在感、質量の多さの原因の一つに対象と作品の間を行き交う何万回、何十万回という視線の集積量によるものと言った人もいるが、そういうこともあるかもしれない。彼の作品を見ていると時間とか光とかモノ自体について色々と考えさせられる。会期中にもう一度行きたいと思っている。
[上田薫展 My Best 5]
なま卵B(1976)

彼の作品からは思わず、ぶるっ、ぬるっ、とろ~っのようなオノマトペが浮かんでしまうけれど、その中でもこれは「とろ~っ、ぬる~っ」の極致のような作品。通常作品の元になる写真は彼自身で撮るらしいのだけれど、これだけは卵を200個も用意してプロに撮ってもらったらしい。いわば彼の代表作でもあるけど、そのイメージがあまりにも強烈で時にはそれだけが彼の作品のように思われるけど、もちろん他にも素晴らしいものが多くあるので…。しかしそれだけ強烈だったということだろう。この作品は現在は東京都現代美術館に収蔵されている。
ジェリーにスプーンC(1990)

今回の展覧会のポスターにも使われている作品で、スプーンの上のぷるっとしたピンクのジェリーが揺れながらとろけてゆく瞬間が定着されている。他にもスプーンの上で溶けかかっているアイスクリームやスプーンから垂れようとしている水あめなど時間を凍結して見せるという点では「なま卵」も同じであるかもしれない。
たまごにスプーンB(1987)

これは同じ卵でも半熟のゆで卵を割ってスプーンですくっているところ。半熟卵のぬめっとした感触、スプーンの冷たい金属感、そしてひびの入った殻の危うさ。それぞれの持つ材質感が現実の世界より現実らしく更に増幅したような感触で描かれている。
あわD(1979)

上田薫の作品を横断的に観てゆくと「映しこまれたもう一つの世界」というキーワードにたどり着く。ひんやりしたスプーンやぬめっとした卵の表面には部屋の様子や時にはカメラを構えた画家自身の姿が映し出されている。そこには現実の向こう側に映し出されたもう一つの現実が存在している。それを最も端的に表しているのが様々な「泡」を描いたシリーズだ。金属の表面などに映り込んだ世界を何とか写真に撮りたいといつも思っているぼくにとっては、泡に閉じ込められた虹色に彩られる世界はとても魅力的だ。
割れたびんC(1983)

上田薫の数少ないリトグラフの作品も何点か展示されていた。ロットをみると30部位だからリトグラフと言ってもまず手には入らないだろうけど…。その中でもとりわけ存在感のあるこの作品がぼくの目をひいた。分厚い緑色のビンが割れた切り口が細かく波打ち割れた時の衝撃をも想像させる。リトグラフでもこういう表現ができるのだと新鮮に感じられた。

[図録/画集]
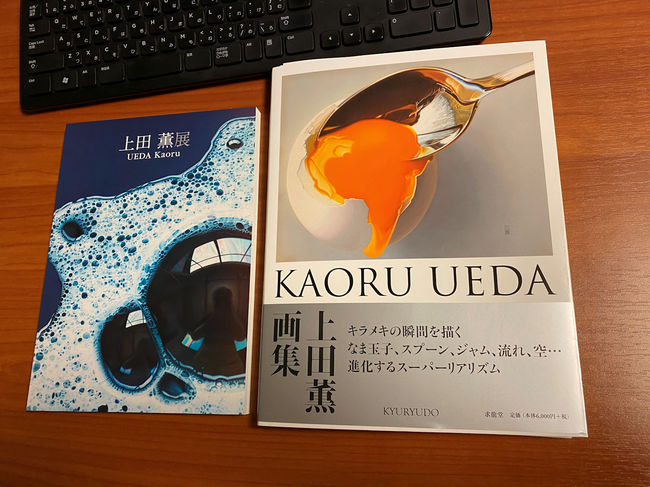
128頁、2200円。ぼくが知る限りでは上田薫の作品は多くの近代美術館に収蔵されているけど広い範囲の作品を収録した画集というのはあまり出ていないと思う。その一冊が写真の右側にある2018年に求龍堂が出した画集だが結構お高い(6600円)のでぼくも一年位散々迷った挙句買ったことを覚えている。
今回の図録は横須賀美術館と埼玉県立近代美術館での個展のために作られたものだけど画家の現在までの主要作品を網羅しており2200円というのは興味のある人には凄くお買い得と思う。また巻末の上田本人による文章も含めて載っている5編のエッセイも読みごたえがあった。
(Nov.2020)
gillman*s Museum ロンドンナショナルギャラリー展
The Museum of the Month...
ロンドン・ナショナル・ギャラリー展

[感想メモ]
当初は3月3日から6月14日までの予定だったけど、開始後すぐに新型コロナ禍で自粛期間に入ってしまったため諦めかけていたが、会期をずらして6月中旬に再オープンして10月18日までと延長された。再オープンしてももちろん全て予約制で時間指定という他の美術館同様制限を設けた開催となった。
展覧会はいうまでもなくロンドン・ナショナル・ギャラリーからこれだけの作品が大挙して海外で公開されるというのは稀有なことで、コロナ禍で会期が危うくなったけど延長されたことはぼくらにとっても幸いだった。
11時からのチケットを予約して行ったのだが入場までに20分ほど待たされたが、会場への人数コントロールがされていたので、比較的ゆったりと観ることができた。展示は西洋絵画史を追うような順序でされているので、見方としては素直に見ることができるし、その中で絵画部門では比較的後進と言われていたイギリス人が絵画とどう向かい合って来たかが想像できて興味深かった。
なお西洋美術館はこの展覧会が終わると約1年半の長い臨時休館に入る。具体的には現在特別展示場となっている増設した地下の建物の地表部分の防水工事の耐用年数が過ぎたため全面的に工事をしなければならないという事だ。工事対象の地表部分は植栽やロダンの「考える人」などがあるエントランスからの地上空間ほぼ全面にわたる。
この改修工事を機に植木などを全て取り払って全てフラットな空間にするらしい。世界遺産になったことによってユネスコから建設当時とかなり改変されているので元に戻すよう指摘を受けていたことによる。そう言えばぼくが大学時代通っていた頃には植木などは植わっておらず、広々とした広場だけが広がっていたのを思い出した。
現在のロダンの「考える人」や「カレーの市民」の像辺りはゆったりとして気の休まる空間だったので、とても残念な気はするのだけれど、一方当初コルビジェが意図した彼の弟子の前川國男が設計した隣の建物、東京文化会館と密接な関係を持って立ち並ぶという点からはこの二つの建物が分断された形になっているのも確かだ。
ウェリントン侯爵

フランシスコ・デ・ゴヤ(1812-14)
この展覧会の目玉となる作品は色々と紹介されているので、自分としては純粋に好みで6作品を選んだのだけれど、気づいてみるとその内3作品がスペイン絵画になっていた。でもこれはある意味ではイギリス人にとっては誇りと言えるかもしれない。というのもそれまではさして注目されていなかったスペイン絵画を評価し光を当てたのはイギリス人に他ならないからだ。
このウェリントン侯爵の肖像画は対フランス戦勝の立役者であるイギリス軍のウェリントン侯爵をゴヤがマドリッドで描いたものだ。ゴヤの肖像画の特徴であるその人物の内面を探るような表現が良く出ている。勇壮な軍人というより疲れ果ててどこか呆けたような表情が上半身の煌びやかな勲章類と対照的である。ダメ押しと言うか完成後も勲章を描き足させたようだが、余計に侯爵の疲労感を強調した結果となった気がする。
マルタとマリアの家のキリスト

ディエゴ・ベラスケス(1618)
体裁はボデゴンと呼ばれる居酒屋や市場の露店の情景を描いた言わば風俗画なのだけれど、画面の右端にある窓の中の情景が曲者だ。そこに描かれている情景はキリストがマルタとマリアの姉妹の自宅を訪れたときの逸話の場面なのだけれど、手前の風俗画部分との繋がりはいろいろな解釈が成り立つようだ。多分それは見る者の判断に委ねられていると思う。
それよりもぼくが気になったのはこの右端の光景が解説では「開口部」となっているけど、当時の住宅にこういう開口部があったのだろうかという興味。何のためにこんな室内窓が設けられているんだろうか。ぼくには一見すると開口部つまり室内窓というよりは絵が架けてあるように見えたのでけれど…。
窓枠に身を乗り出した農民の少年

バルトロメ・エステバン・ムリーリョ(1675-80)
小さな絵だけれど遠くから見ても一目でムリーリョと分かる絵だ。ムリーリョというと2015年に国立新美術館で開かれた「ルーヴル美術館展」で観た「物乞いの少年(蚤をとる少年)
」のように子供を描いた絵を思い浮かべるのだが、彼が生涯で描いた絵の中では子供の絵は決して多くはないようだ。ただ当時のスペイン絵画では子供を描くという事があまりなかったようなので目立つのかもしれない。
この少年の屈託のない笑顔を見るとほんとに癒されるのだけれども、実は近年これと対になっていたと思われるムリーリョの絵が発見されて、その絵は少女がショールを持ち上げて意味ありげな視線をこの少年に送っているというものらしい(「ショールを持ち上げる少女」1670年代)。その意味はこれから色々と想像を呼び起こすのだろうけど、出来ればこの少年の笑顔にあまり手垢を付けるような話であって欲しくないと思っている。
コルオートン・ホールのレイノルズ記念碑

ジョン・コンスタブル(1833-36)
レイノルズとはイギリスの初代アカデミー院長のジョシュア・レイノルズのこと。ナショナル・ギャラリーの貢献者の一人でもあるジョージ・ボーモントは彼を生涯尊敬しており自分の邸宅にレイノルズの記念碑を建てた。そこには彼の友人であった詩人のワーズワスの詩が彫られている。
それまでは絵画の分野では後進国的な位置づけだったイギリス絵画もこのコンスタブルやターナーあたりから本格的にイギリス絵画というジャンルが生まれてきたと言えるかもしれない。ちょっと離れた所から見るとこの絵の全体的なトーンや雰囲気がどこかアンドリュー・ワイエスの世界を想わせる。もちろんこれは油彩でワイエスのようにテンペラ画ではないけど、両端の胸像やモニュメントを除けばワイエスの静謐な世界に酷似していると感じた。
ばらの籠

アンリ・ファンタン=ラトゥール(1890)
ぼくは二人のラトゥールが大好きだ。このアンリ・ファンタン=ラトゥールとジョルジュ・ド・ラトゥールの二人で片や「花」ともう一人は「光と闇」と時代も画題や作風も異なるけれどどちらも素晴らしい。このアンリの方はフランス人だけどホイッスラーの招きでイギリスに渡ったのを機にその後もイギリスとの関係が深かった。
彼の花の絵の中でもとりわけバラの花は素晴らしく、その花びらに触れるとふわっという感触が手に伝わってきそうな繊細さを持っている。花が盛られている籠も背景も花を盛り立てるようにそっけなく、あくまでも花の美しさ、可憐さに焦点を当てて描いているのが何度見ても飽きの来ない秘密かもしれない。
花瓶の花

ポール・ゴーガン(1896)
本展では6点ある現存するゴッホの「ひまわり」の内の一点が展示されており、本展の目玉作品にもなっている。展示スペースも別格という感じだったがそのすぐ傍にこのゴーガンのやはり花の絵がひっそりといった感じで展示されていた。ぼくはゴーガンの絵はその色の濁りが少し苦手だったのだけれど、もちろんその中でも好きな絵は何点かあるが、その中の一枚がこの花の絵だ。
ここではゴーガンの濁ったような色彩が花の描写に深みを与えて単なる静物画を超えた存在になっているような気がする。テーブルの上にこぼれ花が落ちているのも盛りを過ぎた花を暗示させて意味ありげだ。この年タヒチでの若い娘との間に生まれた子が生後すぐに亡くなり、さらに翌年1897年にはヨーロッパに残してきた娘も亡くなる。その年にあの大作「我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのか」が描かれる。ぼくはどちらかと言えばゴッホの「ひまわり」よりはこちらの絵の方が好きだ。

[図 録]
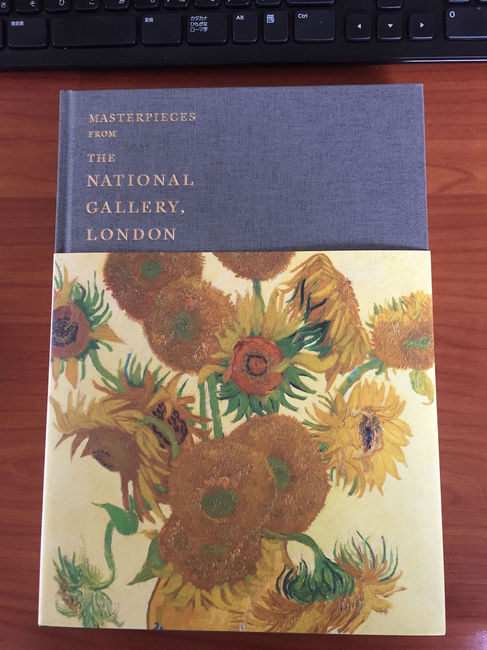
335頁、2900円。この展覧会の最初の会期は3月3日からだった。最初のうちは混んでいるだろうと高を括っているうちにコロナ禍で公開中止になってしまった。せめて図録だけでも見たいと取り寄せて眺めていたのだけれど、幸い展覧会は再開され予約して先週やっと見ることができた。お陰でゆっくりと予習ができたので会場では余裕をもって見られたから良かったのかもしれない。
図録はかなり力(リキ)が入っているのでお値段はいつもより少々高いが、それだけ内容も充実している。個々の作品の写真と解説は通例の形だけれど一点異なるのは各々の作品についてこのギャラリーに収蔵されることになった簡単な来歴がついているのでそれも読んでみると興味深い。また本書は展示に従って7つの章に分かれているが、各々の章の最初の解説がコンパクトで分かりやすい。ただ、かなり重いので帰りにどこかに寄るような場合はお勧めできないかも…。w
ロンドン・ナショナル・ギャラリー展
国立西洋美術館
~2020年10月18日

[感想メモ]
当初は3月3日から6月14日までの予定だったけど、開始後すぐに新型コロナ禍で自粛期間に入ってしまったため諦めかけていたが、会期をずらして6月中旬に再オープンして10月18日までと延長された。再オープンしてももちろん全て予約制で時間指定という他の美術館同様制限を設けた開催となった。
展覧会はいうまでもなくロンドン・ナショナル・ギャラリーからこれだけの作品が大挙して海外で公開されるというのは稀有なことで、コロナ禍で会期が危うくなったけど延長されたことはぼくらにとっても幸いだった。
11時からのチケットを予約して行ったのだが入場までに20分ほど待たされたが、会場への人数コントロールがされていたので、比較的ゆったりと観ることができた。展示は西洋絵画史を追うような順序でされているので、見方としては素直に見ることができるし、その中で絵画部門では比較的後進と言われていたイギリス人が絵画とどう向かい合って来たかが想像できて興味深かった。
なお西洋美術館はこの展覧会が終わると約1年半の長い臨時休館に入る。具体的には現在特別展示場となっている増設した地下の建物の地表部分の防水工事の耐用年数が過ぎたため全面的に工事をしなければならないという事だ。工事対象の地表部分は植栽やロダンの「考える人」などがあるエントランスからの地上空間ほぼ全面にわたる。
この改修工事を機に植木などを全て取り払って全てフラットな空間にするらしい。世界遺産になったことによってユネスコから建設当時とかなり改変されているので元に戻すよう指摘を受けていたことによる。そう言えばぼくが大学時代通っていた頃には植木などは植わっておらず、広々とした広場だけが広がっていたのを思い出した。
現在のロダンの「考える人」や「カレーの市民」の像辺りはゆったりとして気の休まる空間だったので、とても残念な気はするのだけれど、一方当初コルビジェが意図した彼の弟子の前川國男が設計した隣の建物、東京文化会館と密接な関係を持って立ち並ぶという点からはこの二つの建物が分断された形になっているのも確かだ。
My Best 5+1
ウェリントン侯爵

フランシスコ・デ・ゴヤ(1812-14)
この展覧会の目玉となる作品は色々と紹介されているので、自分としては純粋に好みで6作品を選んだのだけれど、気づいてみるとその内3作品がスペイン絵画になっていた。でもこれはある意味ではイギリス人にとっては誇りと言えるかもしれない。というのもそれまではさして注目されていなかったスペイン絵画を評価し光を当てたのはイギリス人に他ならないからだ。
このウェリントン侯爵の肖像画は対フランス戦勝の立役者であるイギリス軍のウェリントン侯爵をゴヤがマドリッドで描いたものだ。ゴヤの肖像画の特徴であるその人物の内面を探るような表現が良く出ている。勇壮な軍人というより疲れ果ててどこか呆けたような表情が上半身の煌びやかな勲章類と対照的である。ダメ押しと言うか完成後も勲章を描き足させたようだが、余計に侯爵の疲労感を強調した結果となった気がする。
マルタとマリアの家のキリスト

ディエゴ・ベラスケス(1618)
体裁はボデゴンと呼ばれる居酒屋や市場の露店の情景を描いた言わば風俗画なのだけれど、画面の右端にある窓の中の情景が曲者だ。そこに描かれている情景はキリストがマルタとマリアの姉妹の自宅を訪れたときの逸話の場面なのだけれど、手前の風俗画部分との繋がりはいろいろな解釈が成り立つようだ。多分それは見る者の判断に委ねられていると思う。
それよりもぼくが気になったのはこの右端の光景が解説では「開口部」となっているけど、当時の住宅にこういう開口部があったのだろうかという興味。何のためにこんな室内窓が設けられているんだろうか。ぼくには一見すると開口部つまり室内窓というよりは絵が架けてあるように見えたのでけれど…。
窓枠に身を乗り出した農民の少年

バルトロメ・エステバン・ムリーリョ(1675-80)
小さな絵だけれど遠くから見ても一目でムリーリョと分かる絵だ。ムリーリョというと2015年に国立新美術館で開かれた「ルーヴル美術館展」で観た「物乞いの少年(蚤をとる少年)
」のように子供を描いた絵を思い浮かべるのだが、彼が生涯で描いた絵の中では子供の絵は決して多くはないようだ。ただ当時のスペイン絵画では子供を描くという事があまりなかったようなので目立つのかもしれない。
この少年の屈託のない笑顔を見るとほんとに癒されるのだけれども、実は近年これと対になっていたと思われるムリーリョの絵が発見されて、その絵は少女がショールを持ち上げて意味ありげな視線をこの少年に送っているというものらしい(「ショールを持ち上げる少女」1670年代)。その意味はこれから色々と想像を呼び起こすのだろうけど、出来ればこの少年の笑顔にあまり手垢を付けるような話であって欲しくないと思っている。
コルオートン・ホールのレイノルズ記念碑

ジョン・コンスタブル(1833-36)
レイノルズとはイギリスの初代アカデミー院長のジョシュア・レイノルズのこと。ナショナル・ギャラリーの貢献者の一人でもあるジョージ・ボーモントは彼を生涯尊敬しており自分の邸宅にレイノルズの記念碑を建てた。そこには彼の友人であった詩人のワーズワスの詩が彫られている。
それまでは絵画の分野では後進国的な位置づけだったイギリス絵画もこのコンスタブルやターナーあたりから本格的にイギリス絵画というジャンルが生まれてきたと言えるかもしれない。ちょっと離れた所から見るとこの絵の全体的なトーンや雰囲気がどこかアンドリュー・ワイエスの世界を想わせる。もちろんこれは油彩でワイエスのようにテンペラ画ではないけど、両端の胸像やモニュメントを除けばワイエスの静謐な世界に酷似していると感じた。
ばらの籠

アンリ・ファンタン=ラトゥール(1890)
ぼくは二人のラトゥールが大好きだ。このアンリ・ファンタン=ラトゥールとジョルジュ・ド・ラトゥールの二人で片や「花」ともう一人は「光と闇」と時代も画題や作風も異なるけれどどちらも素晴らしい。このアンリの方はフランス人だけどホイッスラーの招きでイギリスに渡ったのを機にその後もイギリスとの関係が深かった。
彼の花の絵の中でもとりわけバラの花は素晴らしく、その花びらに触れるとふわっという感触が手に伝わってきそうな繊細さを持っている。花が盛られている籠も背景も花を盛り立てるようにそっけなく、あくまでも花の美しさ、可憐さに焦点を当てて描いているのが何度見ても飽きの来ない秘密かもしれない。
花瓶の花

ポール・ゴーガン(1896)
本展では6点ある現存するゴッホの「ひまわり」の内の一点が展示されており、本展の目玉作品にもなっている。展示スペースも別格という感じだったがそのすぐ傍にこのゴーガンのやはり花の絵がひっそりといった感じで展示されていた。ぼくはゴーガンの絵はその色の濁りが少し苦手だったのだけれど、もちろんその中でも好きな絵は何点かあるが、その中の一枚がこの花の絵だ。
ここではゴーガンの濁ったような色彩が花の描写に深みを与えて単なる静物画を超えた存在になっているような気がする。テーブルの上にこぼれ花が落ちているのも盛りを過ぎた花を暗示させて意味ありげだ。この年タヒチでの若い娘との間に生まれた子が生後すぐに亡くなり、さらに翌年1897年にはヨーロッパに残してきた娘も亡くなる。その年にあの大作「我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのか」が描かれる。ぼくはどちらかと言えばゴッホの「ひまわり」よりはこちらの絵の方が好きだ。

[図 録]
335頁、2900円。この展覧会の最初の会期は3月3日からだった。最初のうちは混んでいるだろうと高を括っているうちにコロナ禍で公開中止になってしまった。せめて図録だけでも見たいと取り寄せて眺めていたのだけれど、幸い展覧会は再開され予約して先週やっと見ることができた。お陰でゆっくりと予習ができたので会場では余裕をもって見られたから良かったのかもしれない。
図録はかなり力(リキ)が入っているのでお値段はいつもより少々高いが、それだけ内容も充実している。個々の作品の写真と解説は通例の形だけれど一点異なるのは各々の作品についてこのギャラリーに収蔵されることになった簡単な来歴がついているのでそれも読んでみると興味深い。また本書は展示に従って7つの章に分かれているが、各々の章の最初の解説がコンパクトで分かりやすい。ただ、かなり重いので帰りにどこかに寄るような場合はお勧めできないかも…。w
(Sept.2020)
gillman*s Choice Rhythm is it !
ドイツ映画View
~7~
Rhythm is It !
ベルリンフィルと子供たち
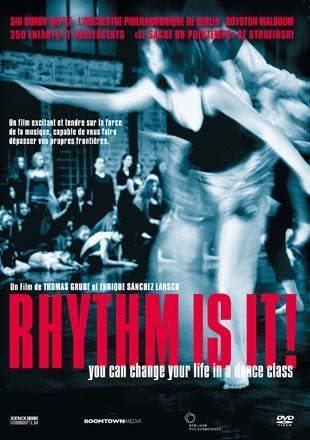
この映画は2004年に公開されたドキュメンタリー映画で、2003年1月ベルリンの250人の若者たちが一同に会しサイモン・ラトル指揮のベルリンフィルの演奏するストラヴィンスキーのバレエ音楽「春の祭典」に合わせて舞台上でダンスを踊るというプロジェクトの一部始終を記録している。
集まったのは25か国の国籍をもつ若者達。もちろん皆素人だ。内乱で両親を殺され国を追われた若者、身寄りのない若者、うまくコミュニケーションが取れないため家族と離れて一人暮らす若者など等。8歳から20歳までの彼らが大人に反発し、自分の不安と向き合いながら、そして自ら考えながら6週間の間ひたすら練習を重ねてゆく。

ラトルは音楽監督就任以来ベルリンフィルが力を入れている教育プロジェクトにかかわってきた。彼は自分の生い立ちも振り返りながら「芸術は今後生存をかけた闘いを強いられる。だが芸術はぜいたく品ではなく必需品だ。空気や水と同じように生きるために必要だ」と。
今のコロナ禍ではありとあらゆる業態が壊滅的と言われるダメージを受けているけど、それはアーティストにとっても、と言うかアーティストにとってこそ本当に深刻な問題となっている。困難な時代にあっては生存に直接響かないと思われている音楽などの芸術は脇に押しやられるからだ。
指揮者のラトルも素晴らしいけれど、このプロジェクトのダンス振付の責任者イギリス人の振付家ロイストン・マルドゥームもすごい。踊るというただ一点で子供たちと対峙してゆく。この映画にはいたるところに心に残る言葉がちりばめられているけど、練習で子供たちの私語が止まなかったときに彼が言った言葉も印象的だ。

「ダンスに私語は禁物だ。ダンスは身体で表現するものだ、口からエネルギーを出してしまってはいけない」衝突を恐れない、強制でなく自分で考え決めさせる。それを子供に寄り添うように優しく見つめる振付助手のスザンナ・ブロウトンや学校の女性教師がとても素敵に見える。なんか教育の本質みたいなものを見た気がする。
映画のラストの2003年1月28日、ベルリン郊外の工業地帯の川沿に設置されたベルリン・アリーナでの本番は意外と短時間にさらっとまとめられていて少し気を抜かれた感じはするが、この映画はそこに至るプロセスこそ眼目なのだからそれでも良かったのかもしれない。

例によって日本での公開時のタイトルは「ベルリンフィルと子供たち」という工夫もないつまらないものだけど、原題は“Rhythm is It !”でこれはストラビンスキーの強烈なリズムに対してのラトルの言葉「人類がまだ文明を持つ以前の脳、それはおそらく爬虫類の時代からの脳で、そこにはリズムが宿っている」からとったものだ。

[CREDIT]
Year:2004
Directors: Thomas Grube, Enrique Sánchez Lansch
Writers: Thomas Grube (screenplay), Enrique Sánchez Lansch
Stars: Simon Rattle, Royston Maldoom, Susannah Broughton
(Jul.2020)
gillman*s Choice Das Papst Attentat
ドイツ映画 Now
Deutsche Kinos
~1~
アルティメイタム
Das Papstattentat

ドイツ映画というと戦前のUFA(ウーファー)時代の映画「嘆きの天使」等や戦後であればニュージャーマン・シネマ時代のヴェンダース等の作品ばかりに目が行ってしまい、その他の映画にはなかなか目が向かなかったというのはぼくばかりではないと思う。
しかしここ数年、時間のある時に意識してドイツ映画を観るようにしていたら、随分ぼくが今まで考えていた(と言っても、さして考えていたわけではないけれど…)ドイツ映画とはずいぶんと変わっていることに気付いた。
日本では今はドイツ映画と言うとあまり馴染みはないけれど、実は映画館だけでなくDVDを含めればかなりの数の作品が見られるようになっている。この間数えてみたら250本以上になった。ぼく自身はまだその中の80本位しか観ていないと思うが、このコロナ騒ぎで外にも出られないのでこれを機会に一日一本観てやろうとまた観始めたので、順次このサイドバーで紹介してゆきたい。
現代のドイツ映画というといくつかの傾向に分かれると思う。ドラマでいえば他の国同様恋愛ものとか若者向けのも多いけれど、特徴的なのは旧東ドイツ時代を描いたものとか、第二次大戦やナチス時代を舞台にしたものも多いし、また結構多いのは特にアクションものに多いのだけれどハリウッドで当たった作品のパクリっぽいものも多い。
なんちゃってカリブの海賊やレイダース風やミッション・インポシブル的な作品も少なくない。もちろんドイツだから文学作品をもとにしたものやヴェンダース監督の作品みたいなものもあるので観始めると面白い。ここに紹介するようなドイツ映画はあまり日本の映画館では上映されていないけれど、レンタルの中で探すと結構あるものだ。そういう中から自分の気に入った作品を見つけることも楽しい。

今日の一本もそんな一本。さっき書いたようにパクリ作品も多いので日本に輸入してレンタルにまわす時も配給会社がひどいタイトルをつけることが多い。ちゃんとした作品でもメインストリームの国の作品じゃないということでいい加減なタイトルにするのは制作者にほんとに失礼だと思う。
この映画のタイトルは「アルティメイタム」となっていて、これを見れば誰だってジェイソン・ボーンのアルティメイタムを思い浮かべるけど、この映画の原題は"Das Papst Attentat"「法王の暗殺」でかなりしっかりした見ごたえのあるアクション映画作品なのだ。(英語題は「FINAL PROCLAMATION」でこちらの方がまとも)レンタル屋さんでいかにも間違って手に取ることを意識したようなふざけたタイトル…。安直すぎて失礼だぞ。
「外科医」と呼ばれる引退した凄腕のヒットマンがある依頼を受けて法王の暗殺を企てるのだが、その裏には昔殺された愛する妻の復讐が潜んでいるという設定はボーンの背景と似ていなくはないけどパクリというのは酷過ぎる。サスペンスとしてのテンポもいいし、複線の貼り方も好い。随所に監督のセンスが光っている。実はこの映画の監督は日系ドイツ人のライナー・マツタニ監督。
少年の頃からの根っからの映画好きで、若いころからいくつも賞もとっている。サスペンスものが好きらしく「ルーム205」というホラーっぽいものも撮っている。尤もほんとにパクリ的な感じのする「エアポート2010」や「タワーリング・インフェルノ’08」という邦題の作品もあるのでどうなんだか今度観てみようと思っている。

[CREDIT]
製作年:2008年(TV Film)
監督:Rainer Matsutani
脚本:Holger Karsten Schmidt
カメラ:Clemens Messow
音楽:Wolfram de Marco
配役:
・Heiner Lauterbach…Rami Hamdan役
・Gesine Cukrowski…Sara Stertz役
・Max von Thun…Frank Dabrock役
(Apr.2020)
gillman*s Museum Batliner Collection
Museum of the Month...

新型コロナウィルスの騒ぎで、トレーニングのためのジムにも行けない、唯一できる散歩も花粉症が始まったので長時間公園もうろつけない、と言うことで毎日お籠り状態。そんなことで家で画集なんかを観ていたら、そう言えば去年行ったウィーンの美術館のいくつかの感想をまだ整理していなかったのを想い出して、書きだした。
ウィーンのアルベルティーナ美術館は国立オペラ座のすぐ裏にあって場所も便利なことからぼくの好きな美術館の一つなのだけれども、この間トリップ・アドバイザーを見ていたら展示作品数が少なすぎるとボロクソに書かれていた口コミもあって、誤解とは言えあまりに気の毒なのでちゃんと説明しておかなければ、とも思った。
確かにアルベルティーナ美術館のコンセプトは判りにくいというのもある。この美術館の特性は、①モダンアート・ギャラリー+②バトリナーコレクション+③特別展スペース+④宮殿部分とデューラーの国宝級作品という大きく4つの領域に分かれている。それが散漫と言えばそうとも言えなくはないのだけれども、どれ一つをとってみてもそのレベルは高いと思う。ぼくも最初は戸惑って見逃したスペースもあるけど、何回か行くうちに飲み込めてきた。
まず、①のモダンアート・ギャラリーは地下の階にあって入り口を見逃してパスする人も多いけど、そこにはアンディ・ウォホールやリキテンシュタインの作品など多くのモダンアート作品が展示されていて見ごたえもある。②が表題のバトリナー・コレクションが展示されているスペースでムンク、シャガール、ピカソ、ノルデ、ココシュカなど魅力的な作品が多く展示されている。残念なことにネットを見てもあまり紹介がされていないけれど、どこに出しても遜色のないコレクションだと思う。
③の特別展はもちろん時期によって違うのだけれど、大規模な特別展はこの美術館の売りでもある。今までぼくが観たのは「ゲルハルト・リヒター展」「ラファエロ展」そして昨年の「アルブレヒト・デューラー展」だが、どれも展示作品数も多くレベルの高い展覧会だった。
そして④は実はこの美術館はもともとはアルベルト公のアルベルティーナ宮殿でその部分も公開されているのでそれ自体も見どころなのだけれど、その一番奥の一室にさりげなく国宝級のデューラーの「野兎」や「祈る手」他数点が壁に掛けられている。またその傍にはエコン・シーレやクリムトの作品も数点並んでいる。まぁ、これだけ観ても元は取れると思うんだけど…。
ここの美術館のミュージアム・ショップはとても充実しているし、何よりもぼくが気に入っているのは美術館カフェのテラスで飲むビール。このテラスはカフェを抜けた所にあるので入り口からは分からないから結構空いている。ここまでなら入場料はかからないので目抜き通りのケルントナー通りを散策して疲れたら、へたなカフェに入るよりここでビールと言うのも良いかもしれない。
■オスカー・ココシュカ
ロンドン、テムズ川の風景

(1926年)
ドレスデン美術アカデミーの教授を辞した後1925年からココシュカはフランスやスペイン、ポルトガルなどを訪れ主要都市で何点かの作品を制作して、翌1926年にはロンドンに半年ほど滞在した。(最終的に1947年にはイギリス国籍を取得) その時はテムズ川が見渡せるサボイホテルの8階に部屋をとった。
そこから見える議事堂やウエストミンスター橋がパノラミックビューで描かれている。他の都市での風景画でも見られる彼のパノラマミックビューの風景画は構図的には16世紀のドイツのアルトドルファーの風景画のようだけれど、そのダイナミックな筆致は彼独特のもので、風景画にダイナミズムを与えている。
そこにははるか昔に描いた彼の代表作「風の花嫁」の筆遣いの面影があるようにも思う。絵の左下にしてあるココシュカのサインがもちろん彼のイニシャルなのだけれど「OK」とどこか満足げに収まっているような気がした。ちなみに2016年の上野での「デトロイト美術館展」で観た彼の風景画「エルサレムの眺め」(1929/30年)はやはりこの絵のようにパノラミックビューで聖地の遠景を大画面に描いており実に堂々としていた。数ある近代風景画の中でも傑出した作品だと思った。
■アンリ・マチス
アルクイユの通り

(1903/04年)
とにかくこの色が好きだ。もちろんマチスの赤は素晴らしいのだけれど、影の色だろうかこの薄紫の通りの色が建物の黄色と空の青と相まって強烈な印象を与えている。これは1905年マチスがヴラマンク達とパリのドートンヌで後にフォービズムと呼ばれる奔放な色彩の絵を発表する前に描かれた作品で興味深い。
他にも何点か、もちろん赤の美しいマチスの作品が展示されていたけれど、ぼくはマチスの色のセンスがギュッと凝縮されているようで、この作品にくぎ付けになった。
■エドゥアルド・ムンク
冬の風景

(1915年)
ムンクは「自然とは目に見えるものがそのすべてではない。それは内なる魂の像をも含んでいる」と述べている。つまり彼のいう「Landscape of the Soul」がよく表れている絵だと思う。彼独特のうねるようなフォームで描かれた岩や岩の上に残されている雪は生き物のように息づいている。これはノルウェーの海岸なのだが、その年の夏彼は2018年に東京都美術館で開かれた「ムンク展」にも展示されていた「水浴する岩の上の男たち」をやはりノルウェーの海岸で描いているが、その絵でも男たちの前にはうねるような風景が広がっている。
■エミール・ノルデ
月夜

(1914年)
ノルデは大きな括りとしてはドイツ表現主義に分類されるけど、ドイツ表現主義の「ブリュッケ」や「青騎士」とは一定の距離を置いていたようだ。ノルデの絵の魅力はその幻想的な色と直感的なフォルムにあるような気がする。
この絵を描く前の年の1913年ノルデは南の海への探検旅行に参加した。その旅行でパプア・ニューギニアを航行している際、或る時大海原の真っただ中で錨を下ろし船が停泊している時の静けさに大いに心打たれたようだ。見渡す限りの大海原の中の静寂と冴えわたる月光の中にポツンと揺蕩う船の姿がノルデの心に深く刻み込まれていたのが分かる。
同じく展示されていた彼の作品「冬の太陽」等も良かった。ノルデの作品はあまり観る機会がないので数点がまとめて観られるのはありがたい。日本では2016年に上野の森美術館で開かれた「デトロイト美術館展」で彼の作品「ヒマワリ」を観たことがあるのだけれど、ゴッホへのオマージュともいえるこの絵の強烈な色彩が今でも目に焼き付いている。
■ポール・デルヴォー
街灯のある風景

(1958年)
ベルギーのシュルレアリスムの流れをくむデルヴォーの絵は一目見ただけでそれと分かる特徴的な絵だ。大抵は遠近法が強調された不思議な空間にディペイズマン(物をそれが本来あるはずがない場所、時間や環境に置くこと)というのだろうか、シュルレアリスム独特の手法で一見脈絡のない人や物が置かれている。
言ってみれば、いつか夢の中でみたことがあるような街、世界が画面の中に展開されている。この絵の中でも不思議な景色の中に一人の女性がたたずんでいる。遠近法的に描かれているが、よく見ると街灯の高さに対して女性の背が高すぎることや、出入り口だらけの役目の分からない塀など等。ブリューゲルの絵のようにその一つ一つの意味を読み解いてゆくというよりは、全体としてのこの不思議な世界に身を置いてみるという方が、この絵の楽しみ方としては面白いような気がする。
デルヴォーの作品も日本ではあまりお目かかれないけれど、2017年にBunkamuraザ・ミュージアムで開かれた「ベルギー奇想の系譜展」で「海は近い」という作品が展示されていた。この作品では女性の顔が見えるのだけれど、その女性の顔は彼の作品にたびたび登場する彼の妻アンヌ=マリー・ド・マルトラール(愛称タム)の顔だ。ここら辺は何となくダリとも共通しているような気がする。デルヴォーは1994年に97歳で生涯を閉じた。妻のタムもその3年前まで存命だった。

(Mar.2020)
ウィーン
アルベルティーナ美術館
バトリナー・
コレクション
新型コロナウィルスの騒ぎで、トレーニングのためのジムにも行けない、唯一できる散歩も花粉症が始まったので長時間公園もうろつけない、と言うことで毎日お籠り状態。そんなことで家で画集なんかを観ていたら、そう言えば去年行ったウィーンの美術館のいくつかの感想をまだ整理していなかったのを想い出して、書きだした。
ウィーンのアルベルティーナ美術館は国立オペラ座のすぐ裏にあって場所も便利なことからぼくの好きな美術館の一つなのだけれども、この間トリップ・アドバイザーを見ていたら展示作品数が少なすぎるとボロクソに書かれていた口コミもあって、誤解とは言えあまりに気の毒なのでちゃんと説明しておかなければ、とも思った。
確かにアルベルティーナ美術館のコンセプトは判りにくいというのもある。この美術館の特性は、①モダンアート・ギャラリー+②バトリナーコレクション+③特別展スペース+④宮殿部分とデューラーの国宝級作品という大きく4つの領域に分かれている。それが散漫と言えばそうとも言えなくはないのだけれども、どれ一つをとってみてもそのレベルは高いと思う。ぼくも最初は戸惑って見逃したスペースもあるけど、何回か行くうちに飲み込めてきた。
まず、①のモダンアート・ギャラリーは地下の階にあって入り口を見逃してパスする人も多いけど、そこにはアンディ・ウォホールやリキテンシュタインの作品など多くのモダンアート作品が展示されていて見ごたえもある。②が表題のバトリナー・コレクションが展示されているスペースでムンク、シャガール、ピカソ、ノルデ、ココシュカなど魅力的な作品が多く展示されている。残念なことにネットを見てもあまり紹介がされていないけれど、どこに出しても遜色のないコレクションだと思う。
③の特別展はもちろん時期によって違うのだけれど、大規模な特別展はこの美術館の売りでもある。今までぼくが観たのは「ゲルハルト・リヒター展」「ラファエロ展」そして昨年の「アルブレヒト・デューラー展」だが、どれも展示作品数も多くレベルの高い展覧会だった。
そして④は実はこの美術館はもともとはアルベルト公のアルベルティーナ宮殿でその部分も公開されているのでそれ自体も見どころなのだけれど、その一番奥の一室にさりげなく国宝級のデューラーの「野兎」や「祈る手」他数点が壁に掛けられている。またその傍にはエコン・シーレやクリムトの作品も数点並んでいる。まぁ、これだけ観ても元は取れると思うんだけど…。
ここの美術館のミュージアム・ショップはとても充実しているし、何よりもぼくが気に入っているのは美術館カフェのテラスで飲むビール。このテラスはカフェを抜けた所にあるので入り口からは分からないから結構空いている。ここまでなら入場料はかからないので目抜き通りのケルントナー通りを散策して疲れたら、へたなカフェに入るよりここでビールと言うのも良いかもしれない。
バトリナー・コレクション
My Favourite 5
■オスカー・ココシュカ
ロンドン、テムズ川の風景
(1926年)
ドレスデン美術アカデミーの教授を辞した後1925年からココシュカはフランスやスペイン、ポルトガルなどを訪れ主要都市で何点かの作品を制作して、翌1926年にはロンドンに半年ほど滞在した。(最終的に1947年にはイギリス国籍を取得) その時はテムズ川が見渡せるサボイホテルの8階に部屋をとった。
そこから見える議事堂やウエストミンスター橋がパノラミックビューで描かれている。他の都市での風景画でも見られる彼のパノラマミックビューの風景画は構図的には16世紀のドイツのアルトドルファーの風景画のようだけれど、そのダイナミックな筆致は彼独特のもので、風景画にダイナミズムを与えている。
そこにははるか昔に描いた彼の代表作「風の花嫁」の筆遣いの面影があるようにも思う。絵の左下にしてあるココシュカのサインがもちろん彼のイニシャルなのだけれど「OK」とどこか満足げに収まっているような気がした。ちなみに2016年の上野での「デトロイト美術館展」で観た彼の風景画「エルサレムの眺め」(1929/30年)はやはりこの絵のようにパノラミックビューで聖地の遠景を大画面に描いており実に堂々としていた。数ある近代風景画の中でも傑出した作品だと思った。
■アンリ・マチス
アルクイユの通り
(1903/04年)
とにかくこの色が好きだ。もちろんマチスの赤は素晴らしいのだけれど、影の色だろうかこの薄紫の通りの色が建物の黄色と空の青と相まって強烈な印象を与えている。これは1905年マチスがヴラマンク達とパリのドートンヌで後にフォービズムと呼ばれる奔放な色彩の絵を発表する前に描かれた作品で興味深い。
他にも何点か、もちろん赤の美しいマチスの作品が展示されていたけれど、ぼくはマチスの色のセンスがギュッと凝縮されているようで、この作品にくぎ付けになった。
■エドゥアルド・ムンク
冬の風景
(1915年)
ムンクは「自然とは目に見えるものがそのすべてではない。それは内なる魂の像をも含んでいる」と述べている。つまり彼のいう「Landscape of the Soul」がよく表れている絵だと思う。彼独特のうねるようなフォームで描かれた岩や岩の上に残されている雪は生き物のように息づいている。これはノルウェーの海岸なのだが、その年の夏彼は2018年に東京都美術館で開かれた「ムンク展」にも展示されていた「水浴する岩の上の男たち」をやはりノルウェーの海岸で描いているが、その絵でも男たちの前にはうねるような風景が広がっている。
■エミール・ノルデ
月夜
(1914年)
ノルデは大きな括りとしてはドイツ表現主義に分類されるけど、ドイツ表現主義の「ブリュッケ」や「青騎士」とは一定の距離を置いていたようだ。ノルデの絵の魅力はその幻想的な色と直感的なフォルムにあるような気がする。
この絵を描く前の年の1913年ノルデは南の海への探検旅行に参加した。その旅行でパプア・ニューギニアを航行している際、或る時大海原の真っただ中で錨を下ろし船が停泊している時の静けさに大いに心打たれたようだ。見渡す限りの大海原の中の静寂と冴えわたる月光の中にポツンと揺蕩う船の姿がノルデの心に深く刻み込まれていたのが分かる。
同じく展示されていた彼の作品「冬の太陽」等も良かった。ノルデの作品はあまり観る機会がないので数点がまとめて観られるのはありがたい。日本では2016年に上野の森美術館で開かれた「デトロイト美術館展」で彼の作品「ヒマワリ」を観たことがあるのだけれど、ゴッホへのオマージュともいえるこの絵の強烈な色彩が今でも目に焼き付いている。
■ポール・デルヴォー
街灯のある風景
(1958年)
ベルギーのシュルレアリスムの流れをくむデルヴォーの絵は一目見ただけでそれと分かる特徴的な絵だ。大抵は遠近法が強調された不思議な空間にディペイズマン(物をそれが本来あるはずがない場所、時間や環境に置くこと)というのだろうか、シュルレアリスム独特の手法で一見脈絡のない人や物が置かれている。
言ってみれば、いつか夢の中でみたことがあるような街、世界が画面の中に展開されている。この絵の中でも不思議な景色の中に一人の女性がたたずんでいる。遠近法的に描かれているが、よく見ると街灯の高さに対して女性の背が高すぎることや、出入り口だらけの役目の分からない塀など等。ブリューゲルの絵のようにその一つ一つの意味を読み解いてゆくというよりは、全体としてのこの不思議な世界に身を置いてみるという方が、この絵の楽しみ方としては面白いような気がする。
デルヴォーの作品も日本ではあまりお目かかれないけれど、2017年にBunkamuraザ・ミュージアムで開かれた「ベルギー奇想の系譜展」で「海は近い」という作品が展示されていた。この作品では女性の顔が見えるのだけれど、その女性の顔は彼の作品にたびたび登場する彼の妻アンヌ=マリー・ド・マルトラール(愛称タム)の顔だ。ここら辺は何となくダリとも共通しているような気がする。デルヴォーは1994年に97歳で生涯を閉じた。妻のタムもその3年前まで存命だった。
(Mar.2020)
gillman*s Museum 大浮世絵展
Museum of the Month...

[感想メモ]
2014年に江戸東京博物館で開催された時「大浮世絵展」とはまた大そうなタイトルだなぁと思ったけれど、実際に行ってみると確かにそうそうたる作品が海外からも里帰りしたり大満足の展覧会だった。
その時の展示構成は、「浮世絵前夜」として屏風絵から岩佐又兵衛等の風俗画にいたるまでいわば浮世絵を生み出すもとになる美人図なども織り交ぜて紹介し、次の「浮世絵のあけぼの」そして「錦絵の誕生」さらに「浮世絵の黄金期」に至って鳥居清長、歌麿、写楽をはじめとした浮世絵文化が花咲く時期へと進展してゆく。
そして展示は「さらなる発展」「新たなるステージへ」へと続き明治錦絵から伊東深水の美人画さらには川瀬巴水などのいわゆる新版画へと繋がるという浮世絵を取り巻く流れの俯瞰が得られるような構成になっていた。
それに対して今回はズバリ「歌麿、写楽、北斎、広重、国芳 夢の競演」と題してまさに前回の浮世絵の黄金期のトップスターの作品を贅沢にちりばめている。前回同様海外からの里帰り作品も多く、こんなにまとめて観られるのは滅多にないことだが、さらに12月17日からかなりの作品の入れ替えが行われたのでもう二回も行ってしまったけれど、まだ再々々チャレンジをしなければならないなぁと…。
ぼくは下手な横好きで写真を観るのも撮るのも好きなのだけれど、浮世絵に限らず日本画は写真にも共通するもの(というかある意味ではいまだにそれを凌駕するもの)を見出すことができて興味が尽きない。
例えば北斎の「富嶽三十六景」とか広重の「東海道五十三次」などを見ると単調な西洋の風景画とは異なり、現在の風景写真にも通用するアングルや情景把握がみられるし、広重の特に「名所江戸百景」の中にはあのブレッソンやドアノーが捉えようとした近代都市の情景の一瞬を捉えたスナップ写真の構図の全ての要素が既に入っているように思える。
今回の会場の展示順は時代に従って歌麿→写楽→北斎→広重と来るのだけれどその最後に国芳ワールドにたどり着いてもう一つの強烈なメッセージを受け取ることになる。それは日本人の美意識のある意味では最も重要な要素の一つに「余白の美」というものがあると思うのだけれど、国芳の世界はそれを嘲笑うようにどこまでも画面を埋め尽くしたいという情熱に溢れている。
それは西洋ではゴッホのように暑苦しいまでの情熱というか…。ただし、国芳の凄いところはゴッホのように救いのない真面目さに押しつぶされることなく、一方では天衣無縫のユーモアと洒脱さも兼ね備えているところだと思う。とにかくすごいし、面白い。もう一回行かなきゃ。
[My Favourite One]
5人の浮世絵トップスターの展示されていた作品の中から各々1点だけお気に入りを上げると…
喜多川歌麿/針仕事

(1794/95)
国芳なんかもよく使っていた3枚続きのいわばパノラマ版浮世絵といった風情の作品。風俗画と言っていいと思うが女性の日常生活を描いており左の絽の生地を透かして見ている女性の表現などため息が出るほどすばらしい。これが本当に版画なのだろうかと信じられない思いだ。
その女性のひざ元で戯れる子供や鏡で猫をじゃらしている男の子など実に微笑ましい庶民の日常が描かれているのだけれど、真ん中の女性などは胸がはだけており後ろの女性は虫かごを観ている。いったいどういうシチュエーションなのか、と想像してみるのも楽しい。
東洲斎写楽/初代市川男女蔵の奴一平

(1794)
会場には展示時期はことなるものの大英博物館、メトロポリタン美術館そしてベルギー王立美術史博物館から同じこの作品が里帰りして展示されているのでそれぞれに擦り具合も異なり興味深い。(今後巡回する福岡、愛知美術館では展示内容が多少異なるらしいが…)
ぼく自身は写楽の作品をこんなにまとめて多数観たことは今までなかった。図柄は奴一平が刀に手をかけてまさに江戸兵衛に切りかかろうとする場面で、会場では縞柄の着物を着て両手を広げた江戸兵衛と向かい合って展示されていた。写楽作品の黄金コンビといったところだ。
葛飾北斎/富岳三十六景 神奈川沖浪裏

(1831/33)
これを選ぶのはあまりにも月並みと言われそうだけれど、何回観ても見れば見るほどその構図の完璧さに感動してしまう。この小さな画面に大自然の厳しさ、動と静の対比、一瞬と悠久の時の共存などいろいろなことを感じされせてくれる。会場にはミネアポリス美術館と江戸東京博物館所蔵のものが展示されていたが、前者の方が状態が良い感じだった。
浮世絵は版画だから、他の作品についても言えるのだけれども特に浮世絵は保存状態と刷りによって同じ作品でも印象が大きく変わる。この作品もいろいろなところで何点も観たけれどミネアポリス美術館のは素晴らしいと思う。
歌川広重/名所江戸百景 大はしあたけの夕立

(1857)
これも月並みなチョイスだが素晴らしいものは素晴らしいので仕方がない。だいたい広重の作品の中から一点を選ぶというのが無茶なのだが…。広重の特にこの「名所江戸百景」には写真の世界で言えばいわゆる広角レンズで捉えた江戸の情景と、標準レンズ的な画角で江戸の街なかをスナップショットしたような作品と大きく分けて二種類の絵作りがある。
特に後者では画面からはみ出している屋形船(吾妻橋金龍山遠望)や通り過ぎてしまったぼてぶりの桶(日本橋江戸ばし)など動きを表現するためにいわばシャッターをわざと遅らせて切ったような絵作りも見られたりして、広重の近代性に目を見張る。話を戻してこの「大はしあたけの夕立」はまさに篠突く雨の音まで聞こえてくるような雨の表現のすばらしさに尽きる。この作品の雨と白雨(東海道五十三次之内 庄野 白雨)の雨、実に多様な雨の表現の仕方を持っている。
そこら辺の遺産は後世の川瀬巴水などに至るまでしっかりと伝わっているように思うのだが。この「大はしあたけの夕立」の本物を初めて見たのはサントリー美術館での原安三郎コレクション展でだったのだが、その時の驚きとその絵の前を立ち去りがたかった気持ちを今でも覚えている。
歌川国芳/讃岐院眷属をして為朝をすくふ図

(1851)
会場をずっと観てきてここで雰囲気はガラッと変わる。ここからは勝手に言わせてもらえば言わば国芳のスペクタクル浮世絵の世界。画面の隅々まで絵で埋め尽くしたいという国芳の情熱がほとばしり出ている。このスペクタクル性とくどさはこの歌川国芳(1798-1861)においては好きなのだけれど、一方河鍋暁斎(1831-1889)までゆくとぼくにはついてゆけない感じがするのだ。
この作品は国芳のスペクタクル浮世絵の真骨頂である3枚続きのパノラマ版一杯に巨大な鰐鮫が描かれており一瞬ぎょっとする。よく見ると白抜きで烏天狗が刷られていたり一つの画面に異なる時間が展開されている。物語を知っている者がみればその人の頭の中で物語が展開してゆくような絵柄になっているようだ。
[図録]

346頁、2600円。2014年の「大浮世絵展」の図録と同じような構成、装丁だ。前半に作品の図録があり、巻末に個々の作品の簡単な解説がついている。今回の展覧会も会期の途中でかなり大幅な作品の入れ替えがあるので、ぼくもそうだけれど二度行かなければならなかった。
会場が近いのでそれ自体は苦にならないけれど作品同士の刷りの違いなどを並べて比べるのには図録が便利だし、概して浮世絵も画集は高価なのでこの値段でスーパースター五人の画集が手に入ると思えば手ごろかもしれない。
*写真左が2014年の図録で右が今回の図録。
大浮世絵展
江戸東京博物館
~2020年1月19日
[感想メモ]
2014年に江戸東京博物館で開催された時「大浮世絵展」とはまた大そうなタイトルだなぁと思ったけれど、実際に行ってみると確かにそうそうたる作品が海外からも里帰りしたり大満足の展覧会だった。
その時の展示構成は、「浮世絵前夜」として屏風絵から岩佐又兵衛等の風俗画にいたるまでいわば浮世絵を生み出すもとになる美人図なども織り交ぜて紹介し、次の「浮世絵のあけぼの」そして「錦絵の誕生」さらに「浮世絵の黄金期」に至って鳥居清長、歌麿、写楽をはじめとした浮世絵文化が花咲く時期へと進展してゆく。
そして展示は「さらなる発展」「新たなるステージへ」へと続き明治錦絵から伊東深水の美人画さらには川瀬巴水などのいわゆる新版画へと繋がるという浮世絵を取り巻く流れの俯瞰が得られるような構成になっていた。
それに対して今回はズバリ「歌麿、写楽、北斎、広重、国芳 夢の競演」と題してまさに前回の浮世絵の黄金期のトップスターの作品を贅沢にちりばめている。前回同様海外からの里帰り作品も多く、こんなにまとめて観られるのは滅多にないことだが、さらに12月17日からかなりの作品の入れ替えが行われたのでもう二回も行ってしまったけれど、まだ再々々チャレンジをしなければならないなぁと…。
ぼくは下手な横好きで写真を観るのも撮るのも好きなのだけれど、浮世絵に限らず日本画は写真にも共通するもの(というかある意味ではいまだにそれを凌駕するもの)を見出すことができて興味が尽きない。
例えば北斎の「富嶽三十六景」とか広重の「東海道五十三次」などを見ると単調な西洋の風景画とは異なり、現在の風景写真にも通用するアングルや情景把握がみられるし、広重の特に「名所江戸百景」の中にはあのブレッソンやドアノーが捉えようとした近代都市の情景の一瞬を捉えたスナップ写真の構図の全ての要素が既に入っているように思える。
今回の会場の展示順は時代に従って歌麿→写楽→北斎→広重と来るのだけれどその最後に国芳ワールドにたどり着いてもう一つの強烈なメッセージを受け取ることになる。それは日本人の美意識のある意味では最も重要な要素の一つに「余白の美」というものがあると思うのだけれど、国芳の世界はそれを嘲笑うようにどこまでも画面を埋め尽くしたいという情熱に溢れている。
それは西洋ではゴッホのように暑苦しいまでの情熱というか…。ただし、国芳の凄いところはゴッホのように救いのない真面目さに押しつぶされることなく、一方では天衣無縫のユーモアと洒脱さも兼ね備えているところだと思う。とにかくすごいし、面白い。もう一回行かなきゃ。
[My Favourite One]
5人の浮世絵トップスターの展示されていた作品の中から各々1点だけお気に入りを上げると…
喜多川歌麿/針仕事

(1794/95)
国芳なんかもよく使っていた3枚続きのいわばパノラマ版浮世絵といった風情の作品。風俗画と言っていいと思うが女性の日常生活を描いており左の絽の生地を透かして見ている女性の表現などため息が出るほどすばらしい。これが本当に版画なのだろうかと信じられない思いだ。
その女性のひざ元で戯れる子供や鏡で猫をじゃらしている男の子など実に微笑ましい庶民の日常が描かれているのだけれど、真ん中の女性などは胸がはだけており後ろの女性は虫かごを観ている。いったいどういうシチュエーションなのか、と想像してみるのも楽しい。
東洲斎写楽/初代市川男女蔵の奴一平

(1794)
会場には展示時期はことなるものの大英博物館、メトロポリタン美術館そしてベルギー王立美術史博物館から同じこの作品が里帰りして展示されているのでそれぞれに擦り具合も異なり興味深い。(今後巡回する福岡、愛知美術館では展示内容が多少異なるらしいが…)
ぼく自身は写楽の作品をこんなにまとめて多数観たことは今までなかった。図柄は奴一平が刀に手をかけてまさに江戸兵衛に切りかかろうとする場面で、会場では縞柄の着物を着て両手を広げた江戸兵衛と向かい合って展示されていた。写楽作品の黄金コンビといったところだ。
葛飾北斎/富岳三十六景 神奈川沖浪裏

(1831/33)
これを選ぶのはあまりにも月並みと言われそうだけれど、何回観ても見れば見るほどその構図の完璧さに感動してしまう。この小さな画面に大自然の厳しさ、動と静の対比、一瞬と悠久の時の共存などいろいろなことを感じされせてくれる。会場にはミネアポリス美術館と江戸東京博物館所蔵のものが展示されていたが、前者の方が状態が良い感じだった。
浮世絵は版画だから、他の作品についても言えるのだけれども特に浮世絵は保存状態と刷りによって同じ作品でも印象が大きく変わる。この作品もいろいろなところで何点も観たけれどミネアポリス美術館のは素晴らしいと思う。
歌川広重/名所江戸百景 大はしあたけの夕立

(1857)
これも月並みなチョイスだが素晴らしいものは素晴らしいので仕方がない。だいたい広重の作品の中から一点を選ぶというのが無茶なのだが…。広重の特にこの「名所江戸百景」には写真の世界で言えばいわゆる広角レンズで捉えた江戸の情景と、標準レンズ的な画角で江戸の街なかをスナップショットしたような作品と大きく分けて二種類の絵作りがある。
特に後者では画面からはみ出している屋形船(吾妻橋金龍山遠望)や通り過ぎてしまったぼてぶりの桶(日本橋江戸ばし)など動きを表現するためにいわばシャッターをわざと遅らせて切ったような絵作りも見られたりして、広重の近代性に目を見張る。話を戻してこの「大はしあたけの夕立」はまさに篠突く雨の音まで聞こえてくるような雨の表現のすばらしさに尽きる。この作品の雨と白雨(東海道五十三次之内 庄野 白雨)の雨、実に多様な雨の表現の仕方を持っている。
そこら辺の遺産は後世の川瀬巴水などに至るまでしっかりと伝わっているように思うのだが。この「大はしあたけの夕立」の本物を初めて見たのはサントリー美術館での原安三郎コレクション展でだったのだが、その時の驚きとその絵の前を立ち去りがたかった気持ちを今でも覚えている。
歌川国芳/讃岐院眷属をして為朝をすくふ図

(1851)
会場をずっと観てきてここで雰囲気はガラッと変わる。ここからは勝手に言わせてもらえば言わば国芳のスペクタクル浮世絵の世界。画面の隅々まで絵で埋め尽くしたいという国芳の情熱がほとばしり出ている。このスペクタクル性とくどさはこの歌川国芳(1798-1861)においては好きなのだけれど、一方河鍋暁斎(1831-1889)までゆくとぼくにはついてゆけない感じがするのだ。
この作品は国芳のスペクタクル浮世絵の真骨頂である3枚続きのパノラマ版一杯に巨大な鰐鮫が描かれており一瞬ぎょっとする。よく見ると白抜きで烏天狗が刷られていたり一つの画面に異なる時間が展開されている。物語を知っている者がみればその人の頭の中で物語が展開してゆくような絵柄になっているようだ。
[図録]
346頁、2600円。2014年の「大浮世絵展」の図録と同じような構成、装丁だ。前半に作品の図録があり、巻末に個々の作品の簡単な解説がついている。今回の展覧会も会期の途中でかなり大幅な作品の入れ替えがあるので、ぼくもそうだけれど二度行かなければならなかった。
会場が近いのでそれ自体は苦にならないけれど作品同士の刷りの違いなどを並べて比べるのには図録が便利だし、概して浮世絵も画集は高価なのでこの値段でスーパースター五人の画集が手に入ると思えば手ごろかもしれない。
*写真左が2014年の図録で右が今回の図録。
(Dec/2019)
gillman*s Museum カラヴァッジョ展
Museum of the Month...

[印象メモ]
ここはウィーンで一番好きな美術館ではあるけど、最近はすぐ傍のレオポルド美術館も好きになって自分の中では同じくらいのウエイトになっている。とは言え美術館全体の雰囲気からすれば断トツに美術史美術館に軍配が上がるのだけれど…。
他方特別展という観点からみるとここのところレオポルド美術館の方が積極的かもしれない。数年前に美術史美術館を訪れた時にはロイスダールなどの風景画展が行われていたけど、一昨年来た時には特別展はなかったし、その前にも出会えなかった。というよりもここ数年は常設展示の大幅な改革に取り組んでいたようだ。
その改革も一段落したのか今年は訪れた時、丁度美術史美術館で「カラヴァッジョ&ベルリーニ展」が行われており、その開幕数日後に観ることができた。特別展の切符はタイムスロット方式といって時間指定のチケットになりその時間を外すと無効になってしまう。幸いぼくは朝9時から9時15分入場のチケットを手に入れることができて、特別展入場とさらに一般客への常設展開場前の時間帯だったので誰もいない状態で常設展示もゆっくりと観ることができた。

美術史美術館にはカラヴァッジョ&カラヴァジェスキのギャラリーがありブリューゲルのギャラリーと並んで好きな部屋なのだが、今回は特別展のために並べ替えられていた。特別展示の方はタイトルの「カラヴァッジョ&ベルリーニ展」とあるようにイタリアのほぼ同時代の二人の作家それも絵画と彫刻という異なる分野で、さらに一方は放浪し若くして死んだ芸術家とローマを拠点に80歳過ぎまで生きた二人の作家という異色の取り合わせになっている。
この展示のカラヴァッジョ作品だけについて言うなら、2016年に東京の国立西洋美術館で行われた「カラヴァッジョ展」の方が充実していたように思う。もちろんその雰囲気は人ごみの背後から作品を観るのと、今回のように殆ど人の気配のないシンとした美術館の中で観るのとでは鑑賞という点からいえば大きな違いはあるのだけれど…。
展示されているカラヴァッジョ作品を下にあげてみると全部で11点でその内4点は美術史美術館の所蔵作品なので純粋に新規展示というのは7点となる。一方、2016年国立西洋美術館における「カラヴァッジョ展」には12点(内帰属1点及び「法悦のマグダラのマリア」を含む)のカラヴァッジョ作品が展示されていた。(下の表でJとあるのは今回展示されていた作品のうち西洋美術館でも展示されていた作品)
[今回の特別展で展示されたカラヴァッジョ作品]
・ナルチウス(1600)(J)
・トカゲに咬まれた少年(1597/98)(J)
・ゴリアテの首を持つダビデ(1600/01)(W)
・洗礼者聖ヨハネ(1602)(W)
・原野の洗礼者ヨハネ(1603/06)
・法悦の聖フランツィスコ(1595/96)
・ロザリオの聖母(1601/03)(W)
・茨の冠(1603)(W)
・イサクの犠牲(1612)
・マルタ騎士団員の肖像(1607/08)
・マッフェオ・バルベリーニの肖像(1956/57)(J)
以上11点(内3点は美術史美術館所蔵作品)
*(W)…美術史美術館の所蔵作品、(J)…西洋美術館でも展示された作品
もちろん、今回は二人の作家展ということだからこれだけで比較するのはフェアじゃないかもしれないが、それでも前回の西洋美術館での展示は結構頑張っていたんだなぁということは言えると思う。
それに加えて、美術史美術館の今回の特別展には「法悦のマグダラのマリア」が展示されていたのだけれど、それはカラヴァッジョの作ではなくてその早い時期のコピーであるLouis Finsonによる模写の方だった。

「法悦のマグダラのマリア」Finson
「法悦のマグダラのマリア」といえば2016年に国立西洋美術館でカラヴァッジョ展が開かれた際、世界で初めて彼の真筆と言われる「法悦のマグダラのマリア」が公開されたという記憶が鮮明に残っている。(この作品は今大阪で公開されている「カラヴァッジョ展」にあるはず)
西洋美術館の同展の図録にもこのFinsonの模写の事も触れられているが、真筆と見られるこの作品が見つかるまではFinson版がこの失われた作品の指標的な作品だったようだ。両方の実物を観たけれど、もちろんぼくなどには真贋は分からないが肌のきめの細かさや顔の表情の描写などは確かに西洋美術館で展示されたものの方が表現が豊かな印象を持った。
*ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ(1571-1610)
*ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ(1598-1680)

暗い展示会場内

ゴリアテの首を持つダビデ

法悦の聖フランツィスコ

イサクの犠牲

茨の冠

ロザリオの聖母
[図 録]

324頁、39.95€。とにかく紙が厚くてやたらに重い。今回の企画展のサブタイトルがローマにおける初期バロックとなっており、巻頭の数本のエッセイでこの時代の絵画と彫刻についての俯瞰を述べている。図録部分は作品の写真と右頁にその解説といった標準的な構成だが、巻末の脚注や出典リスト、索引などがしっかりしているのは如何にもという感じ。
図録における二つの「法悦のマグダラのマリア」の比較
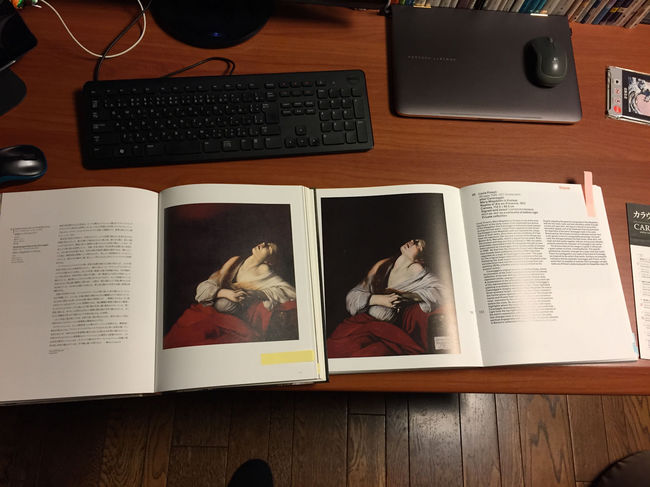
[蛇 足]

ぼくも大好きな世界一美しいカフェと言われた美術館内のカフェ・レストラン。ずっと老舗カフェのゲルストナーの運営だったのだけれど、この間行ったら何か雰囲気が違う感じがした。メニューも素っ気無いし…、何気なく紙ナプキンのロゴを見たらゲルストナーではなくユリウス・マインルのになっていた。
ユリウス・マインルは元はコーヒー商だったらしいが今はウイーンで勢いのある日本で言えば成城石井みたいな高級スーパーなのだ。そこに運営権を譲ったのかもしれない。たぶん。
老舗カフェでいえば、カフェ・デーメルもオーナーがトルコ人に変わって味も変わったとのもっぱらの噂だ。ウイーンも日々変わっているのだ。
カラヴァッジョ
&
ベルニーニ展
ウィーン美術史美術館
2019年10月15日
~2020年1月19日
[印象メモ]
ここはウィーンで一番好きな美術館ではあるけど、最近はすぐ傍のレオポルド美術館も好きになって自分の中では同じくらいのウエイトになっている。とは言え美術館全体の雰囲気からすれば断トツに美術史美術館に軍配が上がるのだけれど…。
他方特別展という観点からみるとここのところレオポルド美術館の方が積極的かもしれない。数年前に美術史美術館を訪れた時にはロイスダールなどの風景画展が行われていたけど、一昨年来た時には特別展はなかったし、その前にも出会えなかった。というよりもここ数年は常設展示の大幅な改革に取り組んでいたようだ。
その改革も一段落したのか今年は訪れた時、丁度美術史美術館で「カラヴァッジョ&ベルリーニ展」が行われており、その開幕数日後に観ることができた。特別展の切符はタイムスロット方式といって時間指定のチケットになりその時間を外すと無効になってしまう。幸いぼくは朝9時から9時15分入場のチケットを手に入れることができて、特別展入場とさらに一般客への常設展開場前の時間帯だったので誰もいない状態で常設展示もゆっくりと観ることができた。
美術史美術館にはカラヴァッジョ&カラヴァジェスキのギャラリーがありブリューゲルのギャラリーと並んで好きな部屋なのだが、今回は特別展のために並べ替えられていた。特別展示の方はタイトルの「カラヴァッジョ&ベルリーニ展」とあるようにイタリアのほぼ同時代の二人の作家それも絵画と彫刻という異なる分野で、さらに一方は放浪し若くして死んだ芸術家とローマを拠点に80歳過ぎまで生きた二人の作家という異色の取り合わせになっている。
この展示のカラヴァッジョ作品だけについて言うなら、2016年に東京の国立西洋美術館で行われた「カラヴァッジョ展」の方が充実していたように思う。もちろんその雰囲気は人ごみの背後から作品を観るのと、今回のように殆ど人の気配のないシンとした美術館の中で観るのとでは鑑賞という点からいえば大きな違いはあるのだけれど…。
展示されているカラヴァッジョ作品を下にあげてみると全部で11点でその内4点は美術史美術館の所蔵作品なので純粋に新規展示というのは7点となる。一方、2016年国立西洋美術館における「カラヴァッジョ展」には12点(内帰属1点及び「法悦のマグダラのマリア」を含む)のカラヴァッジョ作品が展示されていた。(下の表でJとあるのは今回展示されていた作品のうち西洋美術館でも展示されていた作品)
[今回の特別展で展示されたカラヴァッジョ作品]
・ナルチウス(1600)(J)
・トカゲに咬まれた少年(1597/98)(J)
・ゴリアテの首を持つダビデ(1600/01)(W)
・洗礼者聖ヨハネ(1602)(W)
・原野の洗礼者ヨハネ(1603/06)
・法悦の聖フランツィスコ(1595/96)
・ロザリオの聖母(1601/03)(W)
・茨の冠(1603)(W)
・イサクの犠牲(1612)
・マルタ騎士団員の肖像(1607/08)
・マッフェオ・バルベリーニの肖像(1956/57)(J)
以上11点(内3点は美術史美術館所蔵作品)
*(W)…美術史美術館の所蔵作品、(J)…西洋美術館でも展示された作品
もちろん、今回は二人の作家展ということだからこれだけで比較するのはフェアじゃないかもしれないが、それでも前回の西洋美術館での展示は結構頑張っていたんだなぁということは言えると思う。
それに加えて、美術史美術館の今回の特別展には「法悦のマグダラのマリア」が展示されていたのだけれど、それはカラヴァッジョの作ではなくてその早い時期のコピーであるLouis Finsonによる模写の方だった。
「法悦のマグダラのマリア」Finson
「法悦のマグダラのマリア」といえば2016年に国立西洋美術館でカラヴァッジョ展が開かれた際、世界で初めて彼の真筆と言われる「法悦のマグダラのマリア」が公開されたという記憶が鮮明に残っている。(この作品は今大阪で公開されている「カラヴァッジョ展」にあるはず)
西洋美術館の同展の図録にもこのFinsonの模写の事も触れられているが、真筆と見られるこの作品が見つかるまではFinson版がこの失われた作品の指標的な作品だったようだ。両方の実物を観たけれど、もちろんぼくなどには真贋は分からないが肌のきめの細かさや顔の表情の描写などは確かに西洋美術館で展示されたものの方が表現が豊かな印象を持った。
*ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ(1571-1610)
*ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ(1598-1680)
暗い展示会場内
ゴリアテの首を持つダビデ
法悦の聖フランツィスコ
イサクの犠牲
茨の冠
ロザリオの聖母
[図 録]
324頁、39.95€。とにかく紙が厚くてやたらに重い。今回の企画展のサブタイトルがローマにおける初期バロックとなっており、巻頭の数本のエッセイでこの時代の絵画と彫刻についての俯瞰を述べている。図録部分は作品の写真と右頁にその解説といった標準的な構成だが、巻末の脚注や出典リスト、索引などがしっかりしているのは如何にもという感じ。
図録における二つの「法悦のマグダラのマリア」の比較
[蛇 足]
ぼくも大好きな世界一美しいカフェと言われた美術館内のカフェ・レストラン。ずっと老舗カフェのゲルストナーの運営だったのだけれど、この間行ったら何か雰囲気が違う感じがした。メニューも素っ気無いし…、何気なく紙ナプキンのロゴを見たらゲルストナーではなくユリウス・マインルのになっていた。
ユリウス・マインルは元はコーヒー商だったらしいが今はウイーンで勢いのある日本で言えば成城石井みたいな高級スーパーなのだ。そこに運営権を譲ったのかもしれない。たぶん。
老舗カフェでいえば、カフェ・デーメルもオーナーがトルコ人に変わって味も変わったとのもっぱらの噂だ。ウイーンも日々変わっているのだ。
(Dec.2019)
gillman*s Museums キスリングとメスキータ
Museum of the Month...

体調が中々戻らないので今回は無理かなと思っていたけど、あと数日で東京都庭園美術館で開催されている「キスリング展」が終わるとあって重い腰を上げて行くことにした。行ってみて大正解。とても充実した展覧会だったし、庭園美術館も庭も整備されレストランもできて本当に良い美術館になったなぁと実感もできた。自分のペースで歩き観ていたので思いのほか疲れなかったから、思い切って帰りには東京ステーションギャラリーで行われている「メスキータ展」にも寄って久しぶりに美術館の梯子はしないという自分の禁を破ってしまった。
意識したわけではないのだけれど、その日訪れた二つの展覧会はどちらもユダヤ人作家の展覧会だった。その二人の作家の作風がまるで異なるように、彼らの生涯、運命も大きく異なっていた。キスリングが南仏で穏やかにその生涯を閉じたのに対して、メスキータは妻、子供もろともアウシュビッツで殺害されている。個々の作品にその作家の人生を投影しすぎる見方はあまり好きではないけれど、この二人の展覧会を続けて観た結果として、どうしても対比的に観てしまった感じがする。
[キスリング展]

全面的な整備で東京都庭園美術館は本当に良い美術館になった感じがする。個々の作品をそれがいかにも日常の風景の中で置かれているような展示も好感が持てる。そんな雰囲気の中でキスリングの人物、裸婦、花といったモチーフがとてもうまく溶け込んでいたように思う。
ベル=ガズー(1933)…

作家コレットの娘の肖像は多く飾られていた肖像画の中でもひときわ輝きを放っていた。鮮やかなタータンチェックの衣服とその背後のアンリ・ルソーを思わせるような植物との色の対比。キスリングの肖像画に共通する虚空を見つめるような人物の視線に引き込まれる。
モンパルナスのキキ(1925)

モンパルナスのキキはフジタの絵やマン・レイの写真にも登場する当時売れっ子のモデル。キスリングの描くキキの裸婦像は四角いふんわりとしたスフレのようなベッドの上に量感がありながらも沈み込まずに浮いているようにも見える。画面手前の暖色系と背後の寒色系との対比が心地よい。図録では残念ながら色が強すぎてその微妙な色の感じがでていないが、ぼくが今まで見た裸婦像の中では最も素晴らしい作品の一つに数えられる。
ミモザの花束(1946)

キスリングはミモザの花が好きだったらしくよく描いている。よく見ると実に細かい筆致でミモザの金の粒ひとつひとつが立体的に描かれている。1946年と言えばキスリングがアメリカの亡命生活を終えてフランスに戻った年である。帰還は8月だったのでこの絵が米仏のどちらで描かれたかは分からないが、沸き立つような生気がみなぎっている。
[メスキータ展]

今回のメスキータ展のサブタイトルが「エッシャーが命懸けで守った男」というものだが、これからも推測できるようにエッシャーはメスキータの弟子にあたる。そのエッシャーもナチスから命懸けでメスキータの作品を守りとおしたが、メスキータ本人の命そのものを守ることはできなかった。
ウォーターバック/木版(1921)

メスキータは版画で数多くの動物のシリーズを残している。その中でもぼくが一番惹かれたのは漆黒の闇のような黒い画面に陰刻というのだろうか細い線を彫り込んだだけの作品なのだけれど、本当に数少ない繊細な線のみで闇の中にウォーターバックの姿を浮かび上がらせている。
メメント・モリ/木版(1926)

会場に入って最初に目にする作品なのだが、この時点で既にメスキータの人生の俯瞰を予感させるような作品に出くわす。還暦の頃のメスキータの横顔の自画像が頭骸骨と向き合っている。このメメント・モリ(死を思え)やヴァニタスといった画題自体は昔からある古典的な題材ではあるけど、そこに自画像を当て込んでくるというのは、その後の彼の運命を知っている者にすれば余りにも、預言的で直截的な表現に感じられてしまう。
椅子に座る女/パステル(1898)

今回、点数は少なかったが初期の頃のパステル画も数点展示されていた。この作品もその一つである。白いブラウスに黒のスカートをはいた婦人が椅子に座っているところを横から描いている。構図自体はハンマスホイやホイッスラーの絵にも登場するものだが、メスキータは抑えた色調のパステルを使い夫人が居る部屋の空間も含めて一つの世界として描こうとしているように思える。

Mesquita展パンフレット
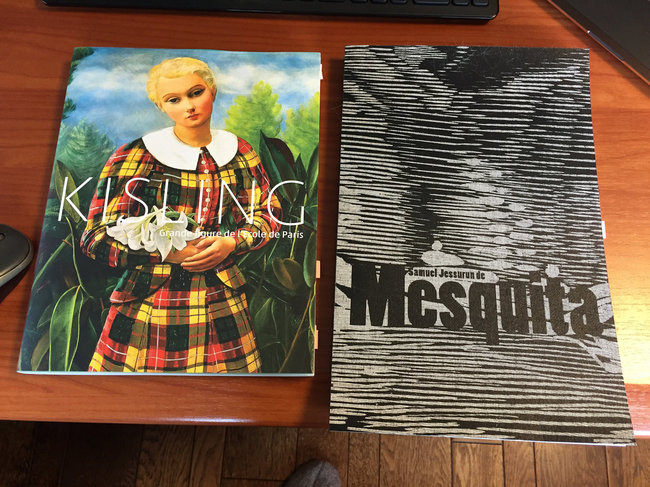
両展の図録
庭園美術館の庭を美術館のテラスから見下ろすと、どこかヴァロットンのあの名作「ボール」のシーンのように見えた。

(July 2019)
キスリング展
と
メスキータ展
体調が中々戻らないので今回は無理かなと思っていたけど、あと数日で東京都庭園美術館で開催されている「キスリング展」が終わるとあって重い腰を上げて行くことにした。行ってみて大正解。とても充実した展覧会だったし、庭園美術館も庭も整備されレストランもできて本当に良い美術館になったなぁと実感もできた。自分のペースで歩き観ていたので思いのほか疲れなかったから、思い切って帰りには東京ステーションギャラリーで行われている「メスキータ展」にも寄って久しぶりに美術館の梯子はしないという自分の禁を破ってしまった。
意識したわけではないのだけれど、その日訪れた二つの展覧会はどちらもユダヤ人作家の展覧会だった。その二人の作家の作風がまるで異なるように、彼らの生涯、運命も大きく異なっていた。キスリングが南仏で穏やかにその生涯を閉じたのに対して、メスキータは妻、子供もろともアウシュビッツで殺害されている。個々の作品にその作家の人生を投影しすぎる見方はあまり好きではないけれど、この二人の展覧会を続けて観た結果として、どうしても対比的に観てしまった感じがする。
[キスリング展]
全面的な整備で東京都庭園美術館は本当に良い美術館になった感じがする。個々の作品をそれがいかにも日常の風景の中で置かれているような展示も好感が持てる。そんな雰囲気の中でキスリングの人物、裸婦、花といったモチーフがとてもうまく溶け込んでいたように思う。
ベル=ガズー(1933)…

作家コレットの娘の肖像は多く飾られていた肖像画の中でもひときわ輝きを放っていた。鮮やかなタータンチェックの衣服とその背後のアンリ・ルソーを思わせるような植物との色の対比。キスリングの肖像画に共通する虚空を見つめるような人物の視線に引き込まれる。
モンパルナスのキキ(1925)

モンパルナスのキキはフジタの絵やマン・レイの写真にも登場する当時売れっ子のモデル。キスリングの描くキキの裸婦像は四角いふんわりとしたスフレのようなベッドの上に量感がありながらも沈み込まずに浮いているようにも見える。画面手前の暖色系と背後の寒色系との対比が心地よい。図録では残念ながら色が強すぎてその微妙な色の感じがでていないが、ぼくが今まで見た裸婦像の中では最も素晴らしい作品の一つに数えられる。
ミモザの花束(1946)

キスリングはミモザの花が好きだったらしくよく描いている。よく見ると実に細かい筆致でミモザの金の粒ひとつひとつが立体的に描かれている。1946年と言えばキスリングがアメリカの亡命生活を終えてフランスに戻った年である。帰還は8月だったのでこの絵が米仏のどちらで描かれたかは分からないが、沸き立つような生気がみなぎっている。
[メスキータ展]
今回のメスキータ展のサブタイトルが「エッシャーが命懸けで守った男」というものだが、これからも推測できるようにエッシャーはメスキータの弟子にあたる。そのエッシャーもナチスから命懸けでメスキータの作品を守りとおしたが、メスキータ本人の命そのものを守ることはできなかった。
ウォーターバック/木版(1921)

メスキータは版画で数多くの動物のシリーズを残している。その中でもぼくが一番惹かれたのは漆黒の闇のような黒い画面に陰刻というのだろうか細い線を彫り込んだだけの作品なのだけれど、本当に数少ない繊細な線のみで闇の中にウォーターバックの姿を浮かび上がらせている。
メメント・モリ/木版(1926)

会場に入って最初に目にする作品なのだが、この時点で既にメスキータの人生の俯瞰を予感させるような作品に出くわす。還暦の頃のメスキータの横顔の自画像が頭骸骨と向き合っている。このメメント・モリ(死を思え)やヴァニタスといった画題自体は昔からある古典的な題材ではあるけど、そこに自画像を当て込んでくるというのは、その後の彼の運命を知っている者にすれば余りにも、預言的で直截的な表現に感じられてしまう。
椅子に座る女/パステル(1898)

今回、点数は少なかったが初期の頃のパステル画も数点展示されていた。この作品もその一つである。白いブラウスに黒のスカートをはいた婦人が椅子に座っているところを横から描いている。構図自体はハンマスホイやホイッスラーの絵にも登場するものだが、メスキータは抑えた色調のパステルを使い夫人が居る部屋の空間も含めて一つの世界として描こうとしているように思える。

Mesquita展パンフレット
両展の図録
庭園美術館の庭を美術館のテラスから見下ろすと、どこかヴァロットンのあの名作「ボール」のシーンのように見えた。
(July 2019)
Museum of hte Month 吉村芳生展
Museum of the Month...

[感想メモ]
鉛筆画家の作品というのはぼくにとってそれほど親しいものではないし、鉛筆画家という範疇の作家の存在も一人を除いてはそれまで知らなかったのが実のところだ。その一人というのが木下晋なのだけれど、2014年4月に那覇の沖縄県立博物館美術館で観た彼の個展「木下晋展 - 生命の旅路」を観た衝撃は今でも覚えている。
大判の紙に鉛筆で克明に描かれたハンセン病患者や身近な老人の姿。紙の上には細部にいたるまで実物と寸分たがわぬイメージが展開されているのだけれど、写真とは違う。写真よりはるかにその存在感が抜きんでている。ホキ美術館の超写実の絵を観るときにもいつも素朴な疑問が湧くのだけれど…。それは写真が好きで撮る人間としては、写真はその存在感という点でなぜ絵画に負けるのだろうかということだった。
ある評論家の超写実主義絵画に対する論文を読んで、なるほどと思った点がある。それは存在感という点で写実が写真に勝るのは、超写実が生まれる過程で行われる対象と作品との間を往復する視線の累積が比類なき存在感を生み出しているというものだった。気の遠くなるような時間をかけて作家の視線は対象と自分の手元の作品の間を何万回、何十万回と往復している。そこにあるというのだ。確かにそれもある。
吉村芳生の作品もいわゆる超写実の範疇に入ると思うのだけど、その存在感の由来は木下の場合とは少し違うような気もする。吉村の手法は身の回りのありふれたモノ、シーンを写真に撮りそれを微細な方眼に分割して、そのひとつひとつのセルを描き写していくというものだ。印刷と見まごうほどの手書きの新聞紙、365日撮り続けた自分の顔の写真を鉛筆画にしてゆく。
後年モノクロの鉛筆画からカラー鉛筆画になってからの鮮やかな色彩で描かれた彼の家の近所の秋桜畑、ポピーの野原そして河原の土手、どれもじっと見つめるていると息苦しくなるほど美しい。木下の作品を観るときと同様にその背後にある膨大な製作時間を想像して感動するという点もあるとは思うのだけれど、ぼくは吉村芳生の描いた新聞紙などの作品を観ていると、身の回りのほんとうにありふれたモノが、今自分の目の前で「ありふれたモノ」→「唯一のモノ」に変貌してゆくまさにその瞬間に立ち会っているような感動を覚えた。彼の絶筆の巨大な「コスモス」が途中で、彼の死によって突然白紙の方眼紙に還ってゆく姿は胸が締め付けられる。見ごたえのある展覧会だった。



[図 録]
215頁。2500円。吉村芳生の作品について言えば、彼の作品を鑑賞するという意味からすれば図録は殆どその意味を成さないと思う。彼の作品を写真にとって印刷した時点で彼の作品の持つ大事なモノが既に失われているような気がする。もしこの図録に意味があるとしたら、図録が彼の作品を観た記憶を呼び戻す引き金になりえるということで、その意味では役割は果たしていると思う。
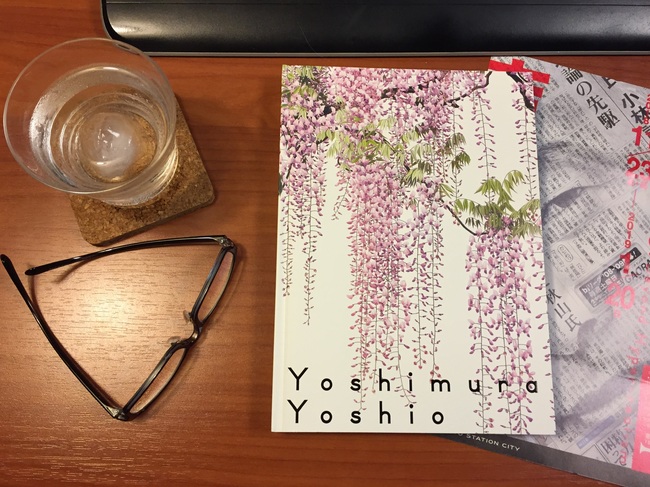

吉村芳生展
東京ステーションギャラリー
~2019年1月20日

[感想メモ]
鉛筆画家の作品というのはぼくにとってそれほど親しいものではないし、鉛筆画家という範疇の作家の存在も一人を除いてはそれまで知らなかったのが実のところだ。その一人というのが木下晋なのだけれど、2014年4月に那覇の沖縄県立博物館美術館で観た彼の個展「木下晋展 - 生命の旅路」を観た衝撃は今でも覚えている。
大判の紙に鉛筆で克明に描かれたハンセン病患者や身近な老人の姿。紙の上には細部にいたるまで実物と寸分たがわぬイメージが展開されているのだけれど、写真とは違う。写真よりはるかにその存在感が抜きんでている。ホキ美術館の超写実の絵を観るときにもいつも素朴な疑問が湧くのだけれど…。それは写真が好きで撮る人間としては、写真はその存在感という点でなぜ絵画に負けるのだろうかということだった。
ある評論家の超写実主義絵画に対する論文を読んで、なるほどと思った点がある。それは存在感という点で写実が写真に勝るのは、超写実が生まれる過程で行われる対象と作品との間を往復する視線の累積が比類なき存在感を生み出しているというものだった。気の遠くなるような時間をかけて作家の視線は対象と自分の手元の作品の間を何万回、何十万回と往復している。そこにあるというのだ。確かにそれもある。
吉村芳生の作品もいわゆる超写実の範疇に入ると思うのだけど、その存在感の由来は木下の場合とは少し違うような気もする。吉村の手法は身の回りのありふれたモノ、シーンを写真に撮りそれを微細な方眼に分割して、そのひとつひとつのセルを描き写していくというものだ。印刷と見まごうほどの手書きの新聞紙、365日撮り続けた自分の顔の写真を鉛筆画にしてゆく。
後年モノクロの鉛筆画からカラー鉛筆画になってからの鮮やかな色彩で描かれた彼の家の近所の秋桜畑、ポピーの野原そして河原の土手、どれもじっと見つめるていると息苦しくなるほど美しい。木下の作品を観るときと同様にその背後にある膨大な製作時間を想像して感動するという点もあるとは思うのだけれど、ぼくは吉村芳生の描いた新聞紙などの作品を観ていると、身の回りのほんとうにありふれたモノが、今自分の目の前で「ありふれたモノ」→「唯一のモノ」に変貌してゆくまさにその瞬間に立ち会っているような感動を覚えた。彼の絶筆の巨大な「コスモス」が途中で、彼の死によって突然白紙の方眼紙に還ってゆく姿は胸が締め付けられる。見ごたえのある展覧会だった。



[図 録]
215頁。2500円。吉村芳生の作品について言えば、彼の作品を鑑賞するという意味からすれば図録は殆どその意味を成さないと思う。彼の作品を写真にとって印刷した時点で彼の作品の持つ大事なモノが既に失われているような気がする。もしこの図録に意味があるとしたら、図録が彼の作品を観た記憶を呼び戻す引き金になりえるということで、その意味では役割は果たしていると思う。
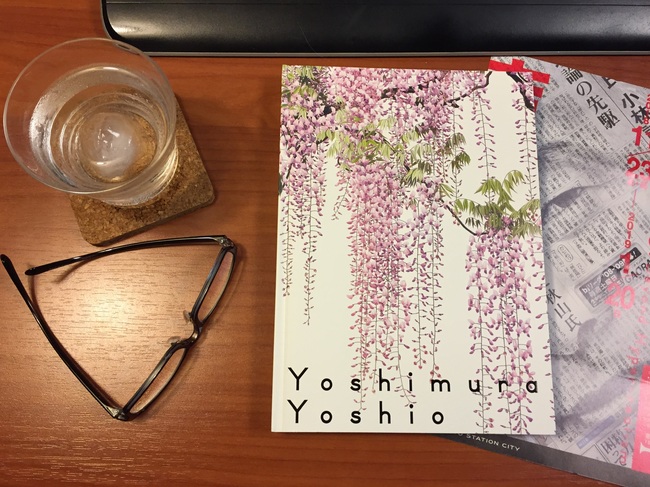

(Dec.2018)
Museum of the Month Rubens展
Museum of the Month...

[感想メモ]
ここ一年足腰の痛みのせいで旅行や美術館にほとんど行けていなかったのだけれど、昨日やっと近場の上野に行くことができた。「ルーベンス展」といえばもちろんその多くが宗教画なのだが、これまた久しぶりにまとめて多くの宗教画を観ることになった。
ぼくはキリスト教徒でもないので、昔はヨーロッパの美術館などで次から次へと宗教画を見せられると正直言って辟易した時期もあるけど、少し宗教画のことを勉強するようになってからは興味が湧いてきた。
宗教画にはアトリビュート(聖ヒエロニムスなら本、聖ペテロなら鍵というような目印のようなもの)やエピソード、主題やアレゴリー毎の状況設定など色々な決まり事があって全ての垣根を取り払った近代絵画とは大きく異なっている。
それが表現を抑圧していた部分もあるけど、ぼくはそれこそが西洋絵画をここまで発展させてきた原動力の一つだと思っている。よく建築家の人から聞くのだけれど、予算も規模も様式も好きなようにしてよいから建ててくれと言われるのが、一番困るらしい。
予算や工期や立地等の制約があって初めて色々な工夫が生まれてくるらしい。宗教画においても画家たちは、もちろん宗教心に突き動かされてという点もあるが、その制約の中でいかにして自分の表現を可能にするかに命を懸けていたようなところがある。
決められた範疇の中で想像力を働かせて、それこそ想像力が創造力へと結びついていったのではないかと思う。ということで宗教画では同じテーマを色々な画家が描いている。キリスト教という大きな器の中で時代や地方、画家それぞれの表現がある。それを比べて観る楽しさは近代絵画では中々味わえない点だと思う。
①キリスト哀悼(1612)

No.25…画面の左上から右下に対角線上に横たわるキリストという大胆な構図にまず惹かれる。以前はヴァン・ダイクの作とされていたが、今はルーベンス作となっているらしい。横たえられたキリストの無造作に投げ出された脚の表現が妙に現実感を生み出している。群像を構成する各々の人物の表情や視線もドラマチックな効果をあげている。
②聖アンデレの殉教(1638)

No.33…聖アンデレというより、セント・アンドリュースという名前の方がぼくらにはしっくりくるけど、彼は兄弟のペテロとともに最初にキリストの弟子になった人物だが、ギリシャで殉教した。全体が速い筆致で描かれ素早い動きが感じられる。
彼が掛けられている十字架がX型なのが聖アンデレの特徴らしくフランクフルトの美術館にあるこれより200年位前に描かれたロナッホーの絵でもX型の十字架に掛けられているのでこれが聖アンデレのアトリビュートなのかもしれない。そういえば名門ゴルフ場のセント・アンドリュースのワッペンにも、このXの図案が配されている。
③クララ・セレーナ・ルーベンスの肖像(1615)

No.35…会場の最初に飾れらている。小さな絵だがルーベンスが本当に愛情をこめて娘の姿を映していることが伝わってくる。この絵にお目にかかるのはこれが二度目。確か2012年に国立新美術館で開かれた「リヒテンシュタイン 華麗なる侯爵家の秘宝」展の時の目玉作品の一つだったと思う。隣には国立西洋美術館の所有する「眠る二人の子供」の絵が掛けられていて、まず良きパパ、ルーベンスのアピールをしているけど、これから幾多の厳しい宗教画を観る前にまず心を和ませるというのはニクイ演出だ。
④パエトンの墜落(1604)

No.43…宗教画を観るときもう一つ忘れてならないのがギリシャ神話の世界だ。もちろんその二つは別のモノなのだけれど多くの宗教画家が神話の世界も描いているし、例えばぼくらが見てもエンジェル、プット(天使)とクピド(キューピッド)など紛らわしいものもある。天使はキリスト教だしクピドはギリシャ神話の世界のものだ。
パエトンの墜落はあのイカロスの墜落と並んで墜落伝説の話だけど、ファエトンと表記しているケースもある。彼はアポロの息子で、ある日父の日輪の馬車を持ち出していい気になって天空を懸けているうちに天の道を外れ地上の山々を焼き尽くしたために雷に打たれて死んでしまう。図に乗ると大変な目にあうというアレゴリーともなっているかもしれない。ギリシャ神話の絵にも聖書画と同じように三又の鉾はポセイドン、鹿を従えていればアルテミスのようにそれぞれのアトリビュートがあるようだ。
⑤聖ゲオルギウスと龍(1601)

No.45…前段で画家はルーベンスのように聖書画と神話画の両方を描くケースがあるのだということなのだけれど、そこら辺からぼくなどの初心者からすると絵の区別がややこしくなることもあって、例えばこの「聖ゲオルギウスと龍」を一目見ただけでは、ギリシャ神話の「ペルセウスとアンドロメダ姫」との区別がしにくい。絵柄的にはどちらも甲冑に身を固めた青年が龍から乙女を助け出すという図柄なのだ。
一説によるとギリシャ神話からキリスト関連伝説の中に組み入れられたという話もあるが、ゲオルギウスの甲冑に十字架でも入っていない限り分かりにくい。もっとも、それなぞはどちらでも良いことなのかもしれないけれど、絵を観ながらどちらかなぁと考えるとこも楽しみの一つではあると思うのだけど…。

[図 録]
291頁。3000円。通常の展覧会の図録は概ね2500円くらいが多いのだけれど、今回のはリキが入っているらしく3000円と割高だけれど、それだけに良くできている。作品ごとに解説が出ているほかに、読みごたえのある論文が7編も入っていて読み物としても面白いと思う。
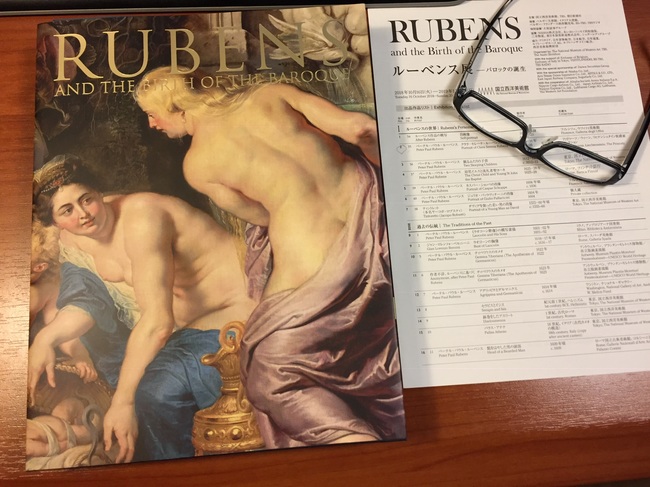
[お薦め本]
宗教画やギリシャ神話にまつわる絵画は、例えばアトリビュートと言って特定の人物を示す持ち物などを絵の中に描き入れたり、テーマ毎の状況設定が決められていたり、言わば絵を見る時の約束事があったりして、最初はとっつきにくい感じがするのだけれど、少し分かってくると逆に興味が湧いてくる。
宗教画などを観るときぼくがよく参考にしている本が写真の二冊で、特に聖書編は旧約聖書、新約聖書両方の主題が170位の場面に分かれて、その意味と代表的な作品例が載せてあるので、宗教画ばかりでなく、通して読んで行くと聖書の概要も分かるお勧めの二冊です。
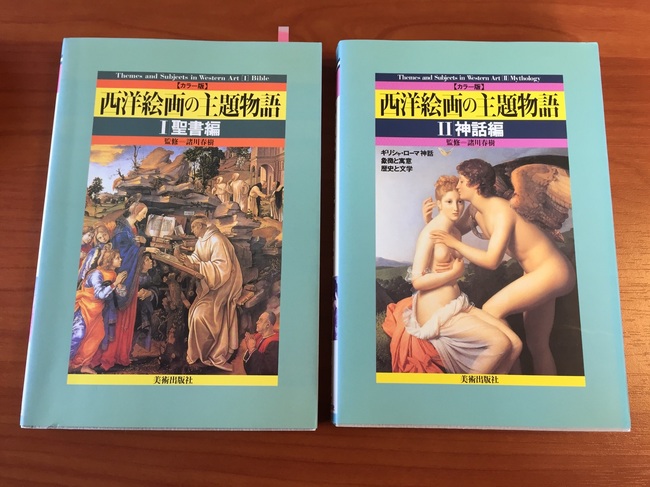
ルーベンス展
国立西洋美術館
2018年10月16日
~2019年1月20日

[感想メモ]
ここ一年足腰の痛みのせいで旅行や美術館にほとんど行けていなかったのだけれど、昨日やっと近場の上野に行くことができた。「ルーベンス展」といえばもちろんその多くが宗教画なのだが、これまた久しぶりにまとめて多くの宗教画を観ることになった。
ぼくはキリスト教徒でもないので、昔はヨーロッパの美術館などで次から次へと宗教画を見せられると正直言って辟易した時期もあるけど、少し宗教画のことを勉強するようになってからは興味が湧いてきた。
宗教画にはアトリビュート(聖ヒエロニムスなら本、聖ペテロなら鍵というような目印のようなもの)やエピソード、主題やアレゴリー毎の状況設定など色々な決まり事があって全ての垣根を取り払った近代絵画とは大きく異なっている。
それが表現を抑圧していた部分もあるけど、ぼくはそれこそが西洋絵画をここまで発展させてきた原動力の一つだと思っている。よく建築家の人から聞くのだけれど、予算も規模も様式も好きなようにしてよいから建ててくれと言われるのが、一番困るらしい。
予算や工期や立地等の制約があって初めて色々な工夫が生まれてくるらしい。宗教画においても画家たちは、もちろん宗教心に突き動かされてという点もあるが、その制約の中でいかにして自分の表現を可能にするかに命を懸けていたようなところがある。
決められた範疇の中で想像力を働かせて、それこそ想像力が創造力へと結びついていったのではないかと思う。ということで宗教画では同じテーマを色々な画家が描いている。キリスト教という大きな器の中で時代や地方、画家それぞれの表現がある。それを比べて観る楽しさは近代絵画では中々味わえない点だと思う。
[Rubens My Best 5]
①キリスト哀悼(1612)

No.25…画面の左上から右下に対角線上に横たわるキリストという大胆な構図にまず惹かれる。以前はヴァン・ダイクの作とされていたが、今はルーベンス作となっているらしい。横たえられたキリストの無造作に投げ出された脚の表現が妙に現実感を生み出している。群像を構成する各々の人物の表情や視線もドラマチックな効果をあげている。
②聖アンデレの殉教(1638)

No.33…聖アンデレというより、セント・アンドリュースという名前の方がぼくらにはしっくりくるけど、彼は兄弟のペテロとともに最初にキリストの弟子になった人物だが、ギリシャで殉教した。全体が速い筆致で描かれ素早い動きが感じられる。
彼が掛けられている十字架がX型なのが聖アンデレの特徴らしくフランクフルトの美術館にあるこれより200年位前に描かれたロナッホーの絵でもX型の十字架に掛けられているのでこれが聖アンデレのアトリビュートなのかもしれない。そういえば名門ゴルフ場のセント・アンドリュースのワッペンにも、このXの図案が配されている。
③クララ・セレーナ・ルーベンスの肖像(1615)

No.35…会場の最初に飾れらている。小さな絵だがルーベンスが本当に愛情をこめて娘の姿を映していることが伝わってくる。この絵にお目にかかるのはこれが二度目。確か2012年に国立新美術館で開かれた「リヒテンシュタイン 華麗なる侯爵家の秘宝」展の時の目玉作品の一つだったと思う。隣には国立西洋美術館の所有する「眠る二人の子供」の絵が掛けられていて、まず良きパパ、ルーベンスのアピールをしているけど、これから幾多の厳しい宗教画を観る前にまず心を和ませるというのはニクイ演出だ。
④パエトンの墜落(1604)

No.43…宗教画を観るときもう一つ忘れてならないのがギリシャ神話の世界だ。もちろんその二つは別のモノなのだけれど多くの宗教画家が神話の世界も描いているし、例えばぼくらが見てもエンジェル、プット(天使)とクピド(キューピッド)など紛らわしいものもある。天使はキリスト教だしクピドはギリシャ神話の世界のものだ。
パエトンの墜落はあのイカロスの墜落と並んで墜落伝説の話だけど、ファエトンと表記しているケースもある。彼はアポロの息子で、ある日父の日輪の馬車を持ち出していい気になって天空を懸けているうちに天の道を外れ地上の山々を焼き尽くしたために雷に打たれて死んでしまう。図に乗ると大変な目にあうというアレゴリーともなっているかもしれない。ギリシャ神話の絵にも聖書画と同じように三又の鉾はポセイドン、鹿を従えていればアルテミスのようにそれぞれのアトリビュートがあるようだ。
⑤聖ゲオルギウスと龍(1601)

No.45…前段で画家はルーベンスのように聖書画と神話画の両方を描くケースがあるのだということなのだけれど、そこら辺からぼくなどの初心者からすると絵の区別がややこしくなることもあって、例えばこの「聖ゲオルギウスと龍」を一目見ただけでは、ギリシャ神話の「ペルセウスとアンドロメダ姫」との区別がしにくい。絵柄的にはどちらも甲冑に身を固めた青年が龍から乙女を助け出すという図柄なのだ。
一説によるとギリシャ神話からキリスト関連伝説の中に組み入れられたという話もあるが、ゲオルギウスの甲冑に十字架でも入っていない限り分かりにくい。もっとも、それなぞはどちらでも良いことなのかもしれないけれど、絵を観ながらどちらかなぁと考えるとこも楽しみの一つではあると思うのだけど…。

[図 録]
291頁。3000円。通常の展覧会の図録は概ね2500円くらいが多いのだけれど、今回のはリキが入っているらしく3000円と割高だけれど、それだけに良くできている。作品ごとに解説が出ているほかに、読みごたえのある論文が7編も入っていて読み物としても面白いと思う。
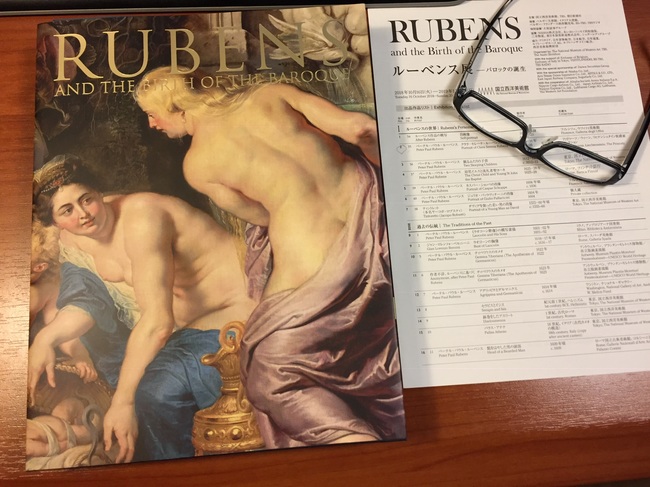
[お薦め本]
宗教画やギリシャ神話にまつわる絵画は、例えばアトリビュートと言って特定の人物を示す持ち物などを絵の中に描き入れたり、テーマ毎の状況設定が決められていたり、言わば絵を見る時の約束事があったりして、最初はとっつきにくい感じがするのだけれど、少し分かってくると逆に興味が湧いてくる。
宗教画などを観るときぼくがよく参考にしている本が写真の二冊で、特に聖書編は旧約聖書、新約聖書両方の主題が170位の場面に分かれて、その意味と代表的な作品例が載せてあるので、宗教画ばかりでなく、通して読んで行くと聖書の概要も分かるお勧めの二冊です。
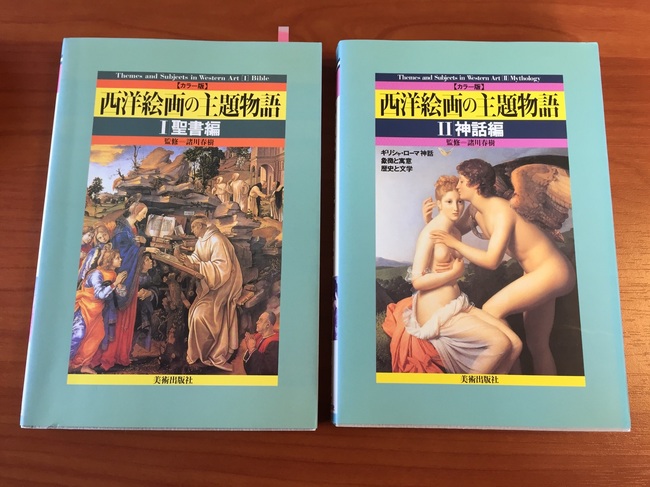
(Dec.2018)
gillman*s Museums Phillips Collection
Museum of the Month

ルーブル美術館などの大美術館ベースの展覧会とちがって、例えばプライス・コレクションや先日のビュールレ・コレクションなどの個人コレクションの展覧会はまた一味違った楽しさがあると思う。なぜこれをコレクションに加えたんだろうという、その人の見識や美意識を想像するのも楽しいものだ。
そのコレクターと趣味の合わない場合もあるし、やっぱりこれを選ぶかみたいに自分の見方とぴったり合うと妙にうれしくなったりもする。そういう意味では今回の展覧会は違和感がなかった。もちろんそれはコレクションの一部に過ぎないので全体のバランスを現しているとは限らないけど…。
ここのところ体調の加減で美術館に遠ざかっていたけれど、久しぶりの美術館はやっぱり良いなとおもった。三菱一号館美術館ができた当初は年間パスポートを買っていたんだけど、ある時から急に高くなってそれからは買っていなかった。でも、昨日行ったら年間パスポートが二種類になって、一つの方は一年間観放題で4000円なのでこれなら元はとれそうなので、また買うことにした。今回の展覧会は2月までやっているので、東京駅近くに来た時はまた観にこようと思った。
①「画家のアトリエ」 ラウル・デュフィ

(1935年)No.40
デュフィはぼくが高校生の頃画集で見た一枚の絵「La Vie en rose」ですっかりその色使いに魅せられているしまった。特にデュフィ・ブルーと言われるその青はぼくの深い所を揺さぶる。
この絵はモンマルトルにあった彼のアトリエを描いているが、殆ど同じ構図で右側に人物が描かれているものもある。デュフィ独特の輪郭線と色の微妙なずれ、ピンク系と青系のコントラスト、そして踊るような筆先どれをとってもデュフィらしい記憶に残る一枚だ。
②「プラムを盛った鉢と桃、水差し」 ジャン・シメオン・シャルダン

(1728年)No.1
この絵が三菱一号館美術館に展示されるのは2012年の素晴らしかったシャルダン展以来だと思う。その時もこの作品は最初のコーナーに展示されていたと思うけど、今回はこの展覧会の一枚目に展示されていた。
ごく小さな絵だけれども、ぼくもシャルダンの絵の中でも一番好きな絵の一枚だ。これを手に入れたダンカン・フィリップスは「…それが置かれた建築空間の気配に至るまで余すところなく再現されている。まさに至高の静物画」と絶賛している。
③「クールマイヨールとダン・デュ・ジェアン」 オスカー・ココシュカ

(1927年)No.55
ココシュカの作品はあまり観たことがなかったのだけれど、昨年ウィーンに行ったときにアルベルティーナ美術館を始め彼の多くの作品に触れることができ、その色彩や独特の震えるようなタッチに魅せられた。色彩感覚は違うけれどどこかしらエゴン・シーレを思い浮かべる。(シーレの方が4歳年下がだか…)
この絵はイタリア側から見たモンブランでまさに山が迫ってくるような迫力がある。ココシュカは作曲家マーラーの妻、アルマ・マーラーと愛人関係にあり二人でイタリアにも旅行している。その後二人は破局したのだけれどココシュカはアルマが忘れられず、一時期アルマの等身大人形を作り、外出にも連れて行ったという。
この絵はそれからずいぶんと時間が経ってから描かれているが、想い出のイタリアでどんな心境で描かれたのだろうか。日本でのココシュカの回顧展は1978年に神奈川、京都で行われてから久しい、またやって欲しい作家の一人だ。
④「サン=ミシェル河岸のアトリエ」 アンリ・マチス

(1916年)No.41
舞台はパリのマチスのアトリエ。大きな窓の向こうにはパリの街並みが見える。デュフィの青に対して、マチスの赤が好きなのだけれど、この絵でも室内に横たわっているマチスのお気に入りのモデル、ローレットが横たわっているのが赤いベットカヴァーなのだ。少し暗めの室内だけによけい赤が引き立つ。
描かれている時間帯は定かでないが、画面には静謐な時が流れている。こんなシチュエーションをどこかで見たような気がしたけど、それはたぶんエドワード・ホッパーの「Eleven A.M.(1926)」や「Morning Sun(1952)」なのだが、それはシチュエーションというよりも、そこに流れている時間の質が酷似しているということかもしれない。エドワード・ホッパーがこの絵の状況を描いたらどんな風になるだろうか、と絵の前で考え込んでしまった。
⑤「驟雨」 ジョルジュ・ブラック

(1952年)No.73
フィリップス・コレクションにはブラックの作品が多い。フィリップス自身はブラックをピカソよりも評価していた。彼に言わせれば「ブラックにとって抽象とは生からの逃避ではない。それは興味深く時に精緻な生の関係性を讃える誌なのだ」ということらしいが…。
ぼくは抽象画はどちらかと言えば苦手でマチスあたりが限界と言えば限界なのだが、この「驟雨」は一目で了解できただけでなく、その空気感まで感じることができた。俳句の季語に「麦秋」という言葉があり夏の季語なのだけど、それは麦の熟する初夏の頃なのだが、この絵を観ると色づいた麦畑の傍の道を歩いていると突然空が掻き曇り激しい雨が降り出した、そんな瞬間のように見える。
⑥「ハム」 ポール・ゴーガン

(1889年)No.22
この絵にお目にかかるのは2016年東京都美術館での「ゴッホとゴーギャン展」以来二度目になる。その時はゴッホの「タマネギの皿のある静物」とゴーガンのこの「ハム」が並べられて展示されていた。描かれたのは両方とも1889年、二人が袂を分かった後のことだ。
その展覧会の時のぼくのメモ「…まずゴッホのタマネギ~の方については観るのはクレラーミュラー美術館と先年の国立新美術館でのゴッホ展に続いて三度目となるけど、観るたびにそのピュアーな色彩に引き込まれる。これも残念ながら印刷では再現しにくい色だ。絵が光を放っているような明るい、そして混じりけのない画面。描かれた静物一つ一つにゴッホにとっての意味が込められている。
それに対してゴーギャンのハム。もしかしたらぼくはゴーギャンの絵の中でこれが一番好きかもしれない。色は紛れもなくゴーギャンの色になっているが、構図はセザンヌのようで、しかしそれほどには冷たくなく、静かな音楽のようだ。ゴッホのようには描かれた静物自体には何の思い入れもなくハムはあくまでハムなのだけれど、描かれたものからはもっと別なものが伝わってくる」
[図録]
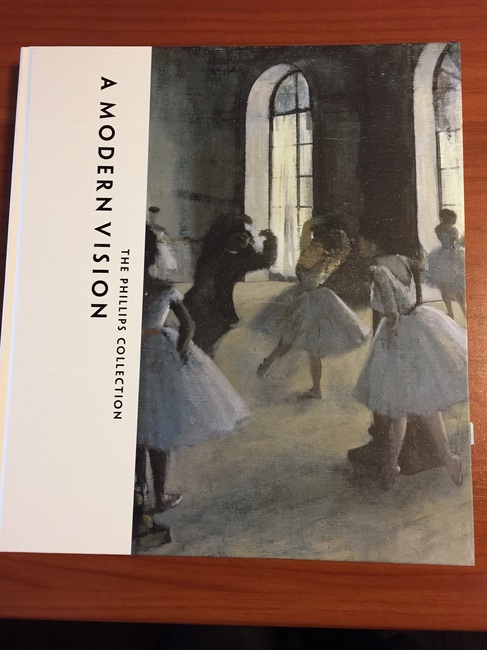
195頁、2500円。大判の図録で内容は標準的なスタイルだが、すべての展示75作品について簡単な解説がついているのは親切。会場には要所要所にダンカン・フィリップス氏の各作家や作品に対する考え方が短い言葉で示されていて、彼がコレクションを選定するときの考え方が分かり、とても興味深かったのだが、そこら辺も図録の構成に取り込んでもらえるとよかったと思う。(開設の中には随所にそのような言葉は入っているが) 色は良く出ている。

作品目録の他に切り離すとカード式になっている作品写真がついてくる。
(Nov.2018)
フィリップス・コレクション展
三菱一号館美術館
2018年10月17日~2月11日

ルーブル美術館などの大美術館ベースの展覧会とちがって、例えばプライス・コレクションや先日のビュールレ・コレクションなどの個人コレクションの展覧会はまた一味違った楽しさがあると思う。なぜこれをコレクションに加えたんだろうという、その人の見識や美意識を想像するのも楽しいものだ。
そのコレクターと趣味の合わない場合もあるし、やっぱりこれを選ぶかみたいに自分の見方とぴったり合うと妙にうれしくなったりもする。そういう意味では今回の展覧会は違和感がなかった。もちろんそれはコレクションの一部に過ぎないので全体のバランスを現しているとは限らないけど…。
ここのところ体調の加減で美術館に遠ざかっていたけれど、久しぶりの美術館はやっぱり良いなとおもった。三菱一号館美術館ができた当初は年間パスポートを買っていたんだけど、ある時から急に高くなってそれからは買っていなかった。でも、昨日行ったら年間パスポートが二種類になって、一つの方は一年間観放題で4000円なのでこれなら元はとれそうなので、また買うことにした。今回の展覧会は2月までやっているので、東京駅近くに来た時はまた観にこようと思った。
[Phillips Collection
My Best 5+1]
①「画家のアトリエ」 ラウル・デュフィ

(1935年)No.40
デュフィはぼくが高校生の頃画集で見た一枚の絵「La Vie en rose」ですっかりその色使いに魅せられているしまった。特にデュフィ・ブルーと言われるその青はぼくの深い所を揺さぶる。
この絵はモンマルトルにあった彼のアトリエを描いているが、殆ど同じ構図で右側に人物が描かれているものもある。デュフィ独特の輪郭線と色の微妙なずれ、ピンク系と青系のコントラスト、そして踊るような筆先どれをとってもデュフィらしい記憶に残る一枚だ。
②「プラムを盛った鉢と桃、水差し」 ジャン・シメオン・シャルダン

(1728年)No.1
この絵が三菱一号館美術館に展示されるのは2012年の素晴らしかったシャルダン展以来だと思う。その時もこの作品は最初のコーナーに展示されていたと思うけど、今回はこの展覧会の一枚目に展示されていた。
ごく小さな絵だけれども、ぼくもシャルダンの絵の中でも一番好きな絵の一枚だ。これを手に入れたダンカン・フィリップスは「…それが置かれた建築空間の気配に至るまで余すところなく再現されている。まさに至高の静物画」と絶賛している。
③「クールマイヨールとダン・デュ・ジェアン」 オスカー・ココシュカ

(1927年)No.55
ココシュカの作品はあまり観たことがなかったのだけれど、昨年ウィーンに行ったときにアルベルティーナ美術館を始め彼の多くの作品に触れることができ、その色彩や独特の震えるようなタッチに魅せられた。色彩感覚は違うけれどどこかしらエゴン・シーレを思い浮かべる。(シーレの方が4歳年下がだか…)
この絵はイタリア側から見たモンブランでまさに山が迫ってくるような迫力がある。ココシュカは作曲家マーラーの妻、アルマ・マーラーと愛人関係にあり二人でイタリアにも旅行している。その後二人は破局したのだけれどココシュカはアルマが忘れられず、一時期アルマの等身大人形を作り、外出にも連れて行ったという。
この絵はそれからずいぶんと時間が経ってから描かれているが、想い出のイタリアでどんな心境で描かれたのだろうか。日本でのココシュカの回顧展は1978年に神奈川、京都で行われてから久しい、またやって欲しい作家の一人だ。
④「サン=ミシェル河岸のアトリエ」 アンリ・マチス

(1916年)No.41
舞台はパリのマチスのアトリエ。大きな窓の向こうにはパリの街並みが見える。デュフィの青に対して、マチスの赤が好きなのだけれど、この絵でも室内に横たわっているマチスのお気に入りのモデル、ローレットが横たわっているのが赤いベットカヴァーなのだ。少し暗めの室内だけによけい赤が引き立つ。
描かれている時間帯は定かでないが、画面には静謐な時が流れている。こんなシチュエーションをどこかで見たような気がしたけど、それはたぶんエドワード・ホッパーの「Eleven A.M.(1926)」や「Morning Sun(1952)」なのだが、それはシチュエーションというよりも、そこに流れている時間の質が酷似しているということかもしれない。エドワード・ホッパーがこの絵の状況を描いたらどんな風になるだろうか、と絵の前で考え込んでしまった。
⑤「驟雨」 ジョルジュ・ブラック

(1952年)No.73
フィリップス・コレクションにはブラックの作品が多い。フィリップス自身はブラックをピカソよりも評価していた。彼に言わせれば「ブラックにとって抽象とは生からの逃避ではない。それは興味深く時に精緻な生の関係性を讃える誌なのだ」ということらしいが…。
ぼくは抽象画はどちらかと言えば苦手でマチスあたりが限界と言えば限界なのだが、この「驟雨」は一目で了解できただけでなく、その空気感まで感じることができた。俳句の季語に「麦秋」という言葉があり夏の季語なのだけど、それは麦の熟する初夏の頃なのだが、この絵を観ると色づいた麦畑の傍の道を歩いていると突然空が掻き曇り激しい雨が降り出した、そんな瞬間のように見える。
⑥「ハム」 ポール・ゴーガン

(1889年)No.22
この絵にお目にかかるのは2016年東京都美術館での「ゴッホとゴーギャン展」以来二度目になる。その時はゴッホの「タマネギの皿のある静物」とゴーガンのこの「ハム」が並べられて展示されていた。描かれたのは両方とも1889年、二人が袂を分かった後のことだ。
その展覧会の時のぼくのメモ「…まずゴッホのタマネギ~の方については観るのはクレラーミュラー美術館と先年の国立新美術館でのゴッホ展に続いて三度目となるけど、観るたびにそのピュアーな色彩に引き込まれる。これも残念ながら印刷では再現しにくい色だ。絵が光を放っているような明るい、そして混じりけのない画面。描かれた静物一つ一つにゴッホにとっての意味が込められている。
それに対してゴーギャンのハム。もしかしたらぼくはゴーギャンの絵の中でこれが一番好きかもしれない。色は紛れもなくゴーギャンの色になっているが、構図はセザンヌのようで、しかしそれほどには冷たくなく、静かな音楽のようだ。ゴッホのようには描かれた静物自体には何の思い入れもなくハムはあくまでハムなのだけれど、描かれたものからはもっと別なものが伝わってくる」
[図録]
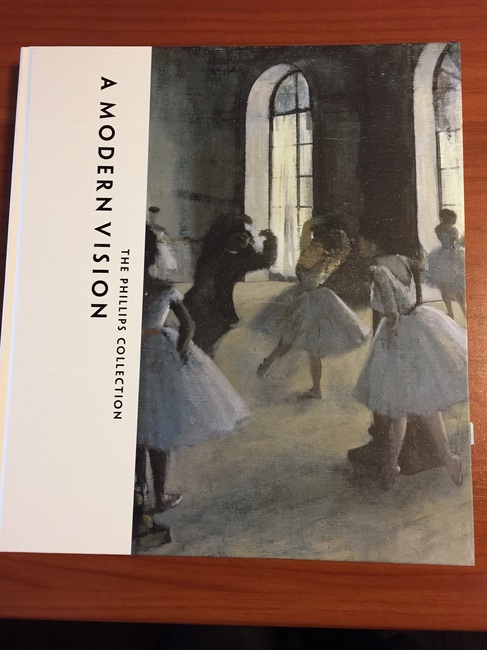
195頁、2500円。大判の図録で内容は標準的なスタイルだが、すべての展示75作品について簡単な解説がついているのは親切。会場には要所要所にダンカン・フィリップス氏の各作家や作品に対する考え方が短い言葉で示されていて、彼がコレクションを選定するときの考え方が分かり、とても興味深かったのだが、そこら辺も図録の構成に取り込んでもらえるとよかったと思う。(開設の中には随所にそのような言葉は入っているが) 色は良く出ている。

作品目録の他に切り離すとカード式になっている作品写真がついてくる。
(Nov.2018)
The Museum of the Month Larsson展
The Museum of the Month

北欧の画家というとぼくなんかは真っ先に大好きなデンマークの画家であるヴィルヘルム・ハンマースホイの名前が浮かぶし先年、国立西洋美術館で行われた「スケーエン派絵画展」でのアンカー夫妻の絵が特に印象に残っているのだけれど、時期的に言えば今は当然ノルウェーの画家ムンクの名が浮かんでくる。
それに、ちょっとマイナーかもしれないけど、以前東京藝術大学美術館で行われたフィンランドの女流画家、ヘレン・シャフベックの一連の絵も魅力的だったのを覚えている。
で、今度は北欧のもう一つの国スウェーデンの画家カール・ラーションの展覧会が今損保ジャパン美術館(名前が長すぎるので短くしてます)で開かれているので、新宿に出た折に寄ってみた。
ぼくはこのラーションという画家について寡聞にして知らなかったのだけれど、展示物は絵画に限らずラーション夫人の手芸やインテリア家具まであり、どうもスウェーデンではそのラーション夫妻のライフ・スタイル自体が一つのコンセプト、作品としてとらえられているらしいことに気付いた。
とはいえラーションのデッサンの手堅さはやっぱり特筆に値する感じがして「絵葉書を描くモデル」などは一見アールヌーボーふうでもあるが、その線の確かさ(浮世絵の影響を受けているらしい)や色遣いの素晴らしさに見入った。
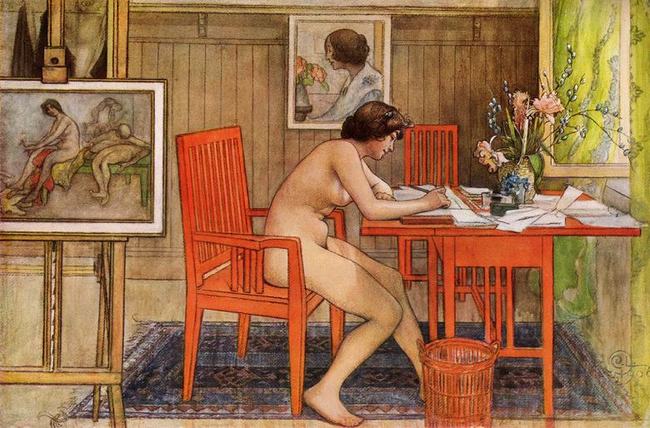
北欧絵画を一つに括るのはとっても失礼だけれど、それを承知であえて言えばやっぱり冬の長さとか厳しさとかの関係か、ハンマースホイの室内絵画のように感性が自己の内面や室内などに向けられる傾向があるみたいに思う。
会場の最後のコーナーにはラーション家風の部屋のインテリアがしつらえられており家具などはIKEAのものだった。会場の表示にもラーション一家のライフ・スタイルを具現化しようとするものがIKEAでもあるというようなプレートがあって、なるほどと思った。

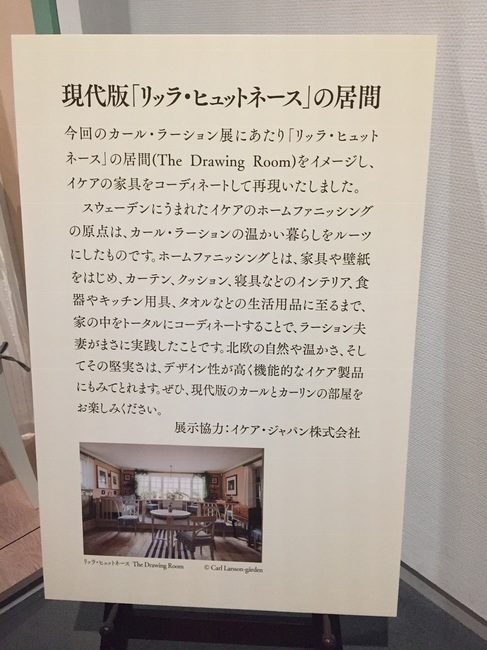
カール・ラーション展
損保ジャパン日本興亜美術館
2018年9月22日~12月24日

北欧の画家というとぼくなんかは真っ先に大好きなデンマークの画家であるヴィルヘルム・ハンマースホイの名前が浮かぶし先年、国立西洋美術館で行われた「スケーエン派絵画展」でのアンカー夫妻の絵が特に印象に残っているのだけれど、時期的に言えば今は当然ノルウェーの画家ムンクの名が浮かんでくる。
それに、ちょっとマイナーかもしれないけど、以前東京藝術大学美術館で行われたフィンランドの女流画家、ヘレン・シャフベックの一連の絵も魅力的だったのを覚えている。
で、今度は北欧のもう一つの国スウェーデンの画家カール・ラーションの展覧会が今損保ジャパン美術館(名前が長すぎるので短くしてます)で開かれているので、新宿に出た折に寄ってみた。
ぼくはこのラーションという画家について寡聞にして知らなかったのだけれど、展示物は絵画に限らずラーション夫人の手芸やインテリア家具まであり、どうもスウェーデンではそのラーション夫妻のライフ・スタイル自体が一つのコンセプト、作品としてとらえられているらしいことに気付いた。
とはいえラーションのデッサンの手堅さはやっぱり特筆に値する感じがして「絵葉書を描くモデル」などは一見アールヌーボーふうでもあるが、その線の確かさ(浮世絵の影響を受けているらしい)や色遣いの素晴らしさに見入った。
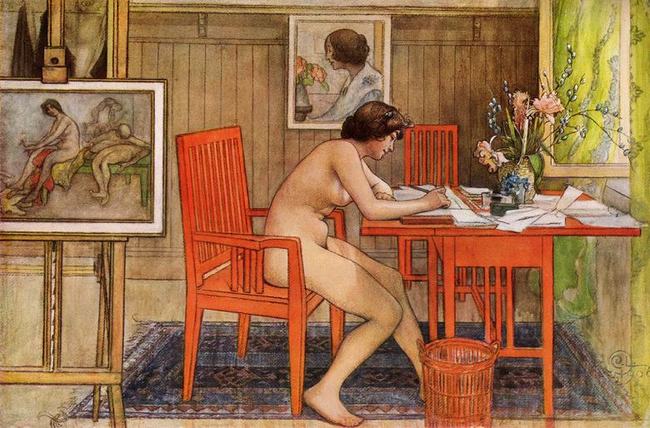
北欧絵画を一つに括るのはとっても失礼だけれど、それを承知であえて言えばやっぱり冬の長さとか厳しさとかの関係か、ハンマースホイの室内絵画のように感性が自己の内面や室内などに向けられる傾向があるみたいに思う。
会場の最後のコーナーにはラーション家風の部屋のインテリアがしつらえられており家具などはIKEAのものだった。会場の表示にもラーション一家のライフ・スタイルを具現化しようとするものがIKEAでもあるというようなプレートがあって、なるほどと思った。

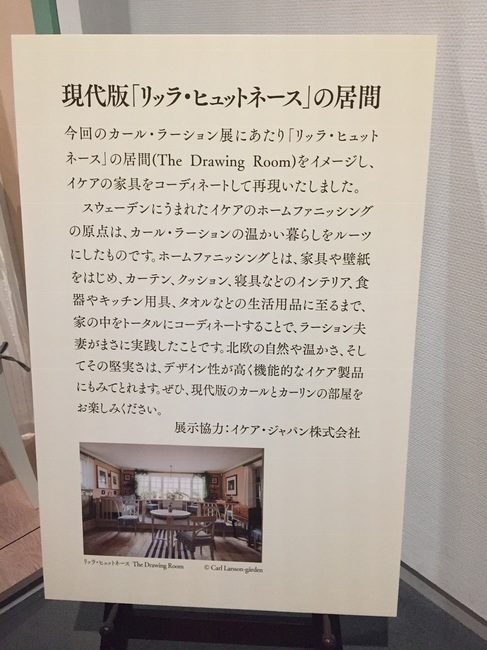
(Nov.2018)
Museum of the Month POLA美術館
■The Museum of the Month

[感想メモ]
箱根は好きなところだけれど、例の噴火騒ぎでしばらくご無沙汰だったが先日一泊二日で友人と温泉目当てで行った。箱根は近年温泉の町であると同時に美術館の町にもなっている。
中にはいかにも観光客向けのものもあるれど、本格的なレベルの高い美術館も増えて来たのは嬉しい限りだ。というわけで初日はPOLA美術館そして翌日は岡田美術館とちょっと贅沢に1日1館を観た。
POLA美術館は今年15周年を迎え、それを記念して所蔵作品の中から名作100展を選んで展示しているがどれも名作展の名に恥じないすばらしい作品が並んでおり滅多にな良いい機会だった。
[My Best 5+1]
①マント家の人々(1880)/エドガー・ドガ…パステル画というのは保存が難しいらしいれど独特の温かみがあってぼくは大好きだ。パステル画の特質に色彩が鮮やかというのもあり、例えばルドンなんかはその代表かもしれない、
そういう意味ではドガのこの絵はパステルでも派手な色は避けて実に落ち着いた画面で一見母娘のこまやかな関係を示す絵柄のように見えるが、よく見ると左側の茶色い洋服を着た少女の存在がミステリアスではある。

②バラ色のボート(1890)/クロード・モネ…横が170センチもある大作でぼくはモネの作品の中でも最も好きな作品の一つだ。まずシンプルな構図が良い。ボートとオールの直線の交点をセンターからちょっとずらしてボートの動きを感じさせている。ボートの直線に対して画面手前の大きくとられたスペースには今度は曲線を主体とした水草が水中で揺れるような風情で描かれている。深い緑の中に薄いピンクの二人の女性のおぼろげな姿がゆっくりと流れてゆく時を感じさせる。


③浴槽 ブルーのハーモニー(1917)/ピエール・ボナール…ボナールの色はいつも優しい。ナビ派の中でも日常の光景や近しい人たちを題材として描くアンティミストとしての目が日常の一瞬を鋭く切り取っている。妻のマルトの湯あみの光景だが、立膝をしてスポンジで体をぬぐっている刹那を捉えている。全体が青で統一されている空間を俯瞰しているアングルで空間が少しゆがんだような不思議な感じに襲われる。

④リュート(1943)/アンリ・マチス…赤といえば関根正二のバーミリオン、鴨井玲の深い赤、画家それぞれに色に対する深い思い入れがあるが、マチスも鮮やかな赤色に独特の思い入れを持っているようだ。マチスのこの赤色は下地に黄色が塗られているということでより鮮やかな赤となっている。印刷業界ではイエローにマゼンタをのせたものを「金赤」と言っているけど、その金赤に近いかもしれない。2009年にPOLA美術館で開かれた所蔵作品を中心とした展覧会「ボナールの庭、マティスの室内」も楽しい展覧会だったけど、そこにも展示されていた。

⑤パリ(1937)/ラウル・デュフロイ…デュフィは大好きな作家だがこの作品に初めて出会ったのは2014年に東急Bunkamuraで開かれた「デュフィ展」だった。デュフィはコスチュームを始め色々な意匠デザインを行なっているが、この作品も元はタピスリー用のデザインだったようだ。本作ではそのデザインを踏襲しながら屏風仕立てのような縦長の四枚の絵にしている。パリの朝から夜までの時間を四つのシーンで表現しタピスリーではできなかった線と色彩の微妙な関係の描き方がとてもいい。

⑤アンドレ ド リュー ド シャトー(1925)/佐伯祐三…佐伯祐三のあの重厚な画面が好きで、都市をああいう感じで写真にしてみたいと思うのだけれど、もちろん不可能なのだけれど。といっても佐伯の作品をそんなに多く観たわけではない、作品数自体があまり多くないのかもしれない。佐伯の描く建物の質感が好きだ。建物が自分の歴史を語っているようだ。佐伯の絵はこの頃からユトリロのように建物だけでなく横丁や街自体の物語を語り始めている。

[図録]
213頁、3240円。今回の展示のための図録は無く写真左のものはPOLA美術館の名作選なのだが、今回の展覧会が美術館の名作100点ということで、その大半が収録されている。同じ名作選で5年前のも持っているが掲載されている作品は多少変わっている。内容は掲載作品の解説が主で、英語でも解説があるので外国人にも便利なようになっている。
右の方は2009年に開かれた所蔵作品を中心とした展覧会「ボナールの庭、マティスの室内」のさいの図録。
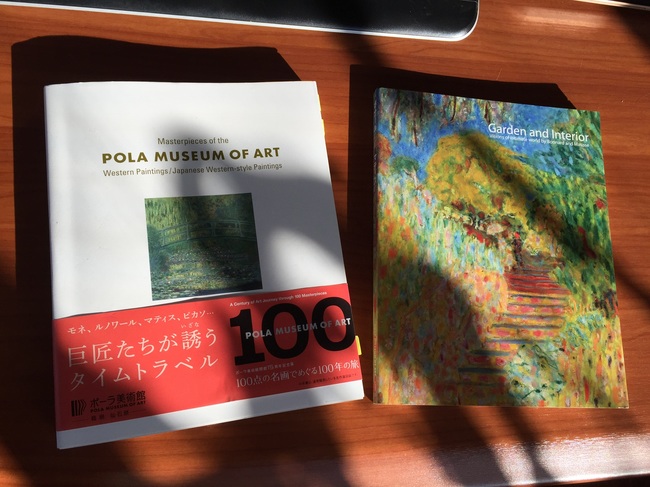
岡田美術館
についても少々…

この美術館がちょっと凄すぎるので、一回では印象もまとまらないし、冷静にちゃんと観たとは言いがたいので一言だけ…。
前からずっと行きたいと思っていながら中々行く機会がなくて行けなかった岡田美術館にやっと行くことができた。友人と箱根に一泊旅行をして初日にはPOLA美術館に行って翌日に岡田美術館というゆったりとした日程で行くことができた。
入場料が2800円ということにちょっと驚いて、続いて携帯やスマホもカメラもロッカーに預けてボディチェックというのも驚いたけど、美術館を観ているうちに納得した。館内は独特の雰囲気で心から日本の美意識に浸りきれる環境になっている。ここにカメラは似合わない。
館内の闇に浮かび上がるため息の出るような作品群。展示ケースのガラスもたぶん特注のものだと思うのだけれど、他の美術館とは透明度が違うように感じるし、作品がケースの中に入っていてもかなり近くに置かれているので細部まで観察することができる。
特別展示として「仁清と乾山展」が行われていた。特別展といっても展示作品は全て岡田美術館の所蔵品なのでそれもすごいと思う。
ぼくが中々その場を離れがたかったのは日本画の部門。ため息を通り越してちょっと涙も…。陶器部門はこの美術館を作った岡田和生氏のコレクションが陶器から始まったとあって、その規模はまさに圧巻。
ちなみに、今思いついたものだけでも…
・尾形乾山/色絵竜田川文透彫反鉢
・尾形光琳/菊図屏風
・酒井抱一/月に秋草図屏風
・伊藤若冲/三十六歌仙図屏風
・伊藤若冲/月に叭々鳥図
・菱田春草/海月
・河合玉堂/渓村秋晴 など等、きりが無い。
さらに驚くべきは、これはコレクターの執念なのかその全てにおいて保存状態が素晴らしいということ。これにも驚ろかされる。
車で行ったので時間は気にしないで済んだのだけど、最低でも二時間はほしいし、半日いてもぼくは飽きない。春になったら是非また行きたいと思う。

100点の名画で巡る100年の旅
POLA美術館
2017年10月1日〜'18年3月11日

[感想メモ]
箱根は好きなところだけれど、例の噴火騒ぎでしばらくご無沙汰だったが先日一泊二日で友人と温泉目当てで行った。箱根は近年温泉の町であると同時に美術館の町にもなっている。
中にはいかにも観光客向けのものもあるれど、本格的なレベルの高い美術館も増えて来たのは嬉しい限りだ。というわけで初日はPOLA美術館そして翌日は岡田美術館とちょっと贅沢に1日1館を観た。
POLA美術館は今年15周年を迎え、それを記念して所蔵作品の中から名作100展を選んで展示しているがどれも名作展の名に恥じないすばらしい作品が並んでおり滅多にな良いい機会だった。
[My Best 5+1]
①マント家の人々(1880)/エドガー・ドガ…パステル画というのは保存が難しいらしいれど独特の温かみがあってぼくは大好きだ。パステル画の特質に色彩が鮮やかというのもあり、例えばルドンなんかはその代表かもしれない、
そういう意味ではドガのこの絵はパステルでも派手な色は避けて実に落ち着いた画面で一見母娘のこまやかな関係を示す絵柄のように見えるが、よく見ると左側の茶色い洋服を着た少女の存在がミステリアスではある。

②バラ色のボート(1890)/クロード・モネ…横が170センチもある大作でぼくはモネの作品の中でも最も好きな作品の一つだ。まずシンプルな構図が良い。ボートとオールの直線の交点をセンターからちょっとずらしてボートの動きを感じさせている。ボートの直線に対して画面手前の大きくとられたスペースには今度は曲線を主体とした水草が水中で揺れるような風情で描かれている。深い緑の中に薄いピンクの二人の女性のおぼろげな姿がゆっくりと流れてゆく時を感じさせる。


③浴槽 ブルーのハーモニー(1917)/ピエール・ボナール…ボナールの色はいつも優しい。ナビ派の中でも日常の光景や近しい人たちを題材として描くアンティミストとしての目が日常の一瞬を鋭く切り取っている。妻のマルトの湯あみの光景だが、立膝をしてスポンジで体をぬぐっている刹那を捉えている。全体が青で統一されている空間を俯瞰しているアングルで空間が少しゆがんだような不思議な感じに襲われる。

④リュート(1943)/アンリ・マチス…赤といえば関根正二のバーミリオン、鴨井玲の深い赤、画家それぞれに色に対する深い思い入れがあるが、マチスも鮮やかな赤色に独特の思い入れを持っているようだ。マチスのこの赤色は下地に黄色が塗られているということでより鮮やかな赤となっている。印刷業界ではイエローにマゼンタをのせたものを「金赤」と言っているけど、その金赤に近いかもしれない。2009年にPOLA美術館で開かれた所蔵作品を中心とした展覧会「ボナールの庭、マティスの室内」も楽しい展覧会だったけど、そこにも展示されていた。

⑤パリ(1937)/ラウル・デュフロイ…デュフィは大好きな作家だがこの作品に初めて出会ったのは2014年に東急Bunkamuraで開かれた「デュフィ展」だった。デュフィはコスチュームを始め色々な意匠デザインを行なっているが、この作品も元はタピスリー用のデザインだったようだ。本作ではそのデザインを踏襲しながら屏風仕立てのような縦長の四枚の絵にしている。パリの朝から夜までの時間を四つのシーンで表現しタピスリーではできなかった線と色彩の微妙な関係の描き方がとてもいい。

⑤アンドレ ド リュー ド シャトー(1925)/佐伯祐三…佐伯祐三のあの重厚な画面が好きで、都市をああいう感じで写真にしてみたいと思うのだけれど、もちろん不可能なのだけれど。といっても佐伯の作品をそんなに多く観たわけではない、作品数自体があまり多くないのかもしれない。佐伯の描く建物の質感が好きだ。建物が自分の歴史を語っているようだ。佐伯の絵はこの頃からユトリロのように建物だけでなく横丁や街自体の物語を語り始めている。

[図録]
213頁、3240円。今回の展示のための図録は無く写真左のものはPOLA美術館の名作選なのだが、今回の展覧会が美術館の名作100点ということで、その大半が収録されている。同じ名作選で5年前のも持っているが掲載されている作品は多少変わっている。内容は掲載作品の解説が主で、英語でも解説があるので外国人にも便利なようになっている。
右の方は2009年に開かれた所蔵作品を中心とした展覧会「ボナールの庭、マティスの室内」のさいの図録。
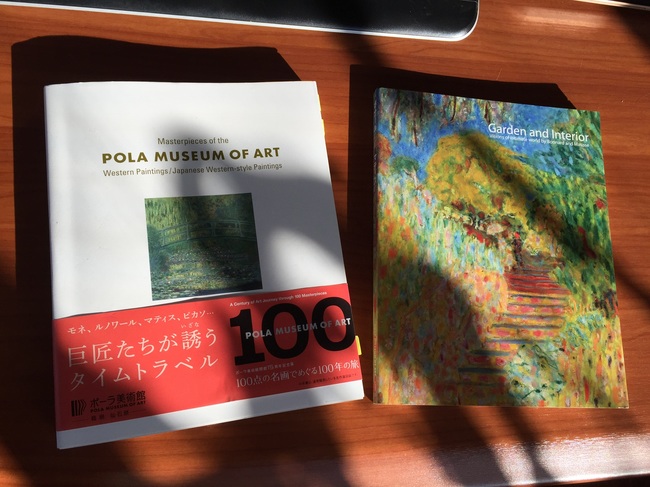
岡田美術館
についても少々…

この美術館がちょっと凄すぎるので、一回では印象もまとまらないし、冷静にちゃんと観たとは言いがたいので一言だけ…。
前からずっと行きたいと思っていながら中々行く機会がなくて行けなかった岡田美術館にやっと行くことができた。友人と箱根に一泊旅行をして初日にはPOLA美術館に行って翌日に岡田美術館というゆったりとした日程で行くことができた。
入場料が2800円ということにちょっと驚いて、続いて携帯やスマホもカメラもロッカーに預けてボディチェックというのも驚いたけど、美術館を観ているうちに納得した。館内は独特の雰囲気で心から日本の美意識に浸りきれる環境になっている。ここにカメラは似合わない。
館内の闇に浮かび上がるため息の出るような作品群。展示ケースのガラスもたぶん特注のものだと思うのだけれど、他の美術館とは透明度が違うように感じるし、作品がケースの中に入っていてもかなり近くに置かれているので細部まで観察することができる。
特別展示として「仁清と乾山展」が行われていた。特別展といっても展示作品は全て岡田美術館の所蔵品なのでそれもすごいと思う。
ぼくが中々その場を離れがたかったのは日本画の部門。ため息を通り越してちょっと涙も…。陶器部門はこの美術館を作った岡田和生氏のコレクションが陶器から始まったとあって、その規模はまさに圧巻。
ちなみに、今思いついたものだけでも…
・尾形乾山/色絵竜田川文透彫反鉢
・尾形光琳/菊図屏風
・酒井抱一/月に秋草図屏風
・伊藤若冲/三十六歌仙図屏風
・伊藤若冲/月に叭々鳥図
・菱田春草/海月
・河合玉堂/渓村秋晴 など等、きりが無い。
さらに驚くべきは、これはコレクターの執念なのかその全てにおいて保存状態が素晴らしいということ。これにも驚ろかされる。
車で行ったので時間は気にしないで済んだのだけど、最低でも二時間はほしいし、半日いてもぼくは飽きない。春になったら是非また行きたいと思う。

(Dec.2017)
gillman*s gallery もっと光を!
■gillman*s gallery
「もっと光を!」というのはゲーテの最期の言葉として有名で、いろいろな解釈がされているようだけど、実際は"Macht doch den zweiten Fensterladen auf, damit mehr Licht hereinkomme." つまり、「もっと光が入るように二番目の窓の鎧戸を開けておくれ」というもので特に形而上学的な意味があるわけではないらしいのだけれど…。
とは言え、人はいつの時代にも光の中に希望を見出そうとするものかもしれない。特に現代のように不安感にさいなまれつつ闇夜の中を歩いているように先の見えない時代においては。

Firenze
サンロレンツォ教会隣接の旧サン・マルコ修道院回廊の外光

Tokyo
六本木国立新美術館、夕刻建物の奥まで差し込む光は美しい

Vienna
ウィーン・レオポルド美術館のこの光景も一つの展示作品だ

Aries
ゴッホが一時収容されていたアルルの療養院中庭に溢れる天上からの光
※写真はクリックすると大きくなります。
Mehr Licht!
More Light !
もっと光を!
「もっと光を!」というのはゲーテの最期の言葉として有名で、いろいろな解釈がされているようだけど、実際は"Macht doch den zweiten Fensterladen auf, damit mehr Licht hereinkomme." つまり、「もっと光が入るように二番目の窓の鎧戸を開けておくれ」というもので特に形而上学的な意味があるわけではないらしいのだけれど…。
とは言え、人はいつの時代にも光の中に希望を見出そうとするものかもしれない。特に現代のように不安感にさいなまれつつ闇夜の中を歩いているように先の見えない時代においては。

Firenze
サンロレンツォ教会隣接の旧サン・マルコ修道院回廊の外光
Tokyo
六本木国立新美術館、夕刻建物の奥まで差し込む光は美しい
Vienna
ウィーン・レオポルド美術館のこの光景も一つの展示作品だ
Aries
ゴッホが一時収容されていたアルルの療養院中庭に溢れる天上からの光
※写真はクリックすると大きくなります。
(Dec.2017)
Museum of the Month Chagall
■Museum of the Month

[感想メモ]
シャガールというと個人的に想いだすのは、大昔のバブル華やかりし頃ある大手商社の会議室に呼ばれ、これを巧くさばけないかと見せられたのが、大量の大型のリトグラフでそれらは全てシャガールの作品だった。バブル景気もピークに達し上がりきった美術品の価格の下落も囁かれ始めたころだった。
シャガールにはなんとも気の毒だけれども、即物的な投資としての美術品の世界を見たようで想いだすといまだに釈然としない気持ちになる。とは言え、もちろんシャガールの作品自体は本来ファンタジックで色彩の美しさは群を抜いており、今回の展覧会でその造形力もとても趣のあるということも知った。
この東京駅のステーション・ギャラリーが出来て以来、良い企画展が多いので東京駅の近くに来たときなどによく訪れるのだけれど、今回の展示もとても良かった。シャガールの三次元の作品を観られることもそうだけれど、絵画の展示も充実しておりその殆どが美術館などではなく個人所有の作品なので貴重な機会だと思う。また紳士服でお馴染みのAOKIがシャガールの素晴らしい作品をこんなに多く所有していることも知らなかった。
[シャガール展 My Best 5]
①紫色の裸婦(1967)/No.114-6…会場には本作と二点の下絵が展示されている。本作は大型の油彩で絵具はかなりの厚塗りになっている。本作も素晴らしいが、ぼくはその下絵に見入ってしまった。
図柄はタイトルの通り紫色の裸婦と道化師そしてシャガールお得意のヤギなのだが、下絵の方は裸婦の部分と道化師の部分に分かれているが両方とも油彩でなくグワッシュと墨、コラージュ等で描かれており実に鮮やかな色彩が美しい。ぼくはどちらかというと下絵の方が気に入っている。

②天蓋の花嫁(1949)/No.159…シャガールの絵にはよく二重肖像が登場し、それは一見、一つのものを違う角度から見た構図の合成のようなキュビズム的なものに思えるのだけれど、シャガールの場合視覚と言うよりそれは心理的な二重性を表していると思った方が良いようだ。この絵の花嫁も二つの顔を持っている。それは恐らく亡き妻ベラと当時の恋人ハガードの二重像だと思える。
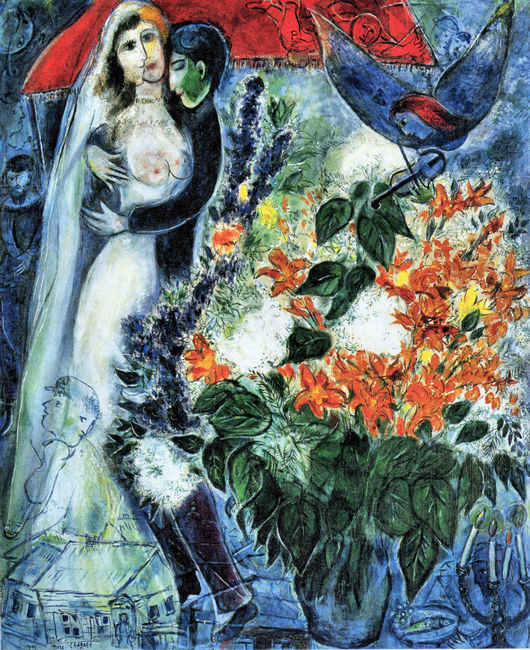
③赤い背景の花(1968)/No.109…まさに真紅の画面。会場でもひときわ目を引く作品だ。窓のある赤い壁の背景に溶け込むように花瓶に活けられた大きな花束が置いてある。右側から妻のヴァヴァだろうか女性が手に花を持って近づいてくる。強烈な残像のように脳裏に残る光景。

[参考]
ちなみに下の絵は今回ウィーンのアルベルティーナ美術館で観たシャガールの「花と共に眠る女性」(1972)だけれど、シャガールの花の絵は大抵このように人物や動物、故郷の風景などが書き込まれていることが多い。

④青いロバ[陶器](1954)/No.026…シャガールの手がけた陶器の作品も何点か展示されているが水差しにしろ、壺にしろ実用的な普通の形というよりは、その形態をかりたオブジェという感じだ。
このロバの水差しも取っ手が馬の脚(というか手というか)のようにもなっていて何ともユーモラスでおおらかな姿だ。周りに施されている彩色もいかにもシャガールというもので、全体の雰囲気としてはまさに彼の絵から三次元の世界に抜け出てきた感じがする。
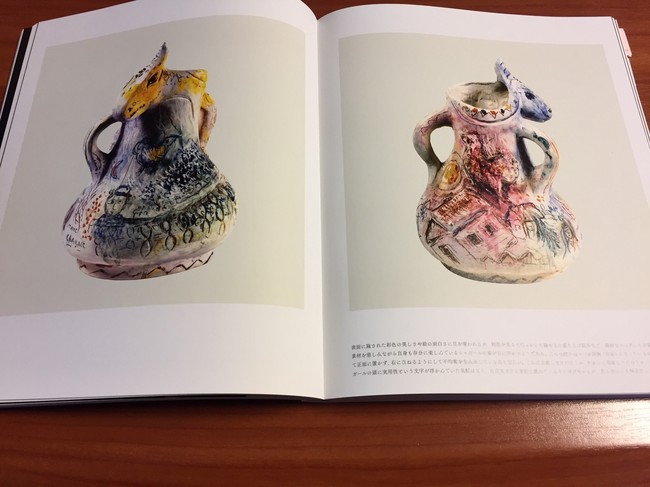
⑤カーネーションを持つベラ(1925)/No.006…初期の頃の作品で、妻のベラの姿ががっしりとした骨太の体格で描かれている。この展覧会にもあったけどシャガールの1910年代の作品にはキュビズムの影響が見られるが、この作品は首の太さや骨格のダイナミックさなどピカソの新古典主義の時代(1918年~1925年頃)と共通するものがあるように思う。
ピカソはこの頃オルガと結婚しており、キュビズムの時代とは作風は大きく変わっている。その影響もあったのかもしれないが、色合いと言い、画面構成と言いその後のシャガールの作風からは想像がつきにくい。

[参考]

ピカソ「母と子」(1921)
[図録]
250頁。2592円。通常よりちょっと高いが、かなり力の入った図録に思える。多少くすんではいるが、色も比較的よく出ているし何よりも見ていて楽しい作りになっている。
シャガールの彫刻など三次元の作品を見ることができるのも楽しいが、ただ作品を並べるだけでなくその下絵や絵画作品と関連づけたり工夫がみられるのも好感が持てる。今回の展示は個人所蔵の作品が多いのでそういう意味でも他の画集には載っていない作品も多いと思う。
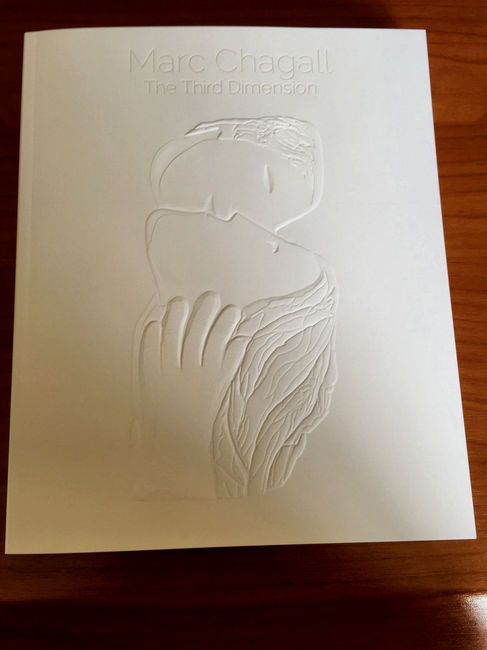


シャガール展
~三次元の世界~
東京ステーションギャラリー
2017年9月16日~12月3日

[感想メモ]
シャガールというと個人的に想いだすのは、大昔のバブル華やかりし頃ある大手商社の会議室に呼ばれ、これを巧くさばけないかと見せられたのが、大量の大型のリトグラフでそれらは全てシャガールの作品だった。バブル景気もピークに達し上がりきった美術品の価格の下落も囁かれ始めたころだった。
シャガールにはなんとも気の毒だけれども、即物的な投資としての美術品の世界を見たようで想いだすといまだに釈然としない気持ちになる。とは言え、もちろんシャガールの作品自体は本来ファンタジックで色彩の美しさは群を抜いており、今回の展覧会でその造形力もとても趣のあるということも知った。
この東京駅のステーション・ギャラリーが出来て以来、良い企画展が多いので東京駅の近くに来たときなどによく訪れるのだけれど、今回の展示もとても良かった。シャガールの三次元の作品を観られることもそうだけれど、絵画の展示も充実しておりその殆どが美術館などではなく個人所有の作品なので貴重な機会だと思う。また紳士服でお馴染みのAOKIがシャガールの素晴らしい作品をこんなに多く所有していることも知らなかった。
[シャガール展 My Best 5]
①紫色の裸婦(1967)/No.114-6…会場には本作と二点の下絵が展示されている。本作は大型の油彩で絵具はかなりの厚塗りになっている。本作も素晴らしいが、ぼくはその下絵に見入ってしまった。
図柄はタイトルの通り紫色の裸婦と道化師そしてシャガールお得意のヤギなのだが、下絵の方は裸婦の部分と道化師の部分に分かれているが両方とも油彩でなくグワッシュと墨、コラージュ等で描かれており実に鮮やかな色彩が美しい。ぼくはどちらかというと下絵の方が気に入っている。

②天蓋の花嫁(1949)/No.159…シャガールの絵にはよく二重肖像が登場し、それは一見、一つのものを違う角度から見た構図の合成のようなキュビズム的なものに思えるのだけれど、シャガールの場合視覚と言うよりそれは心理的な二重性を表していると思った方が良いようだ。この絵の花嫁も二つの顔を持っている。それは恐らく亡き妻ベラと当時の恋人ハガードの二重像だと思える。
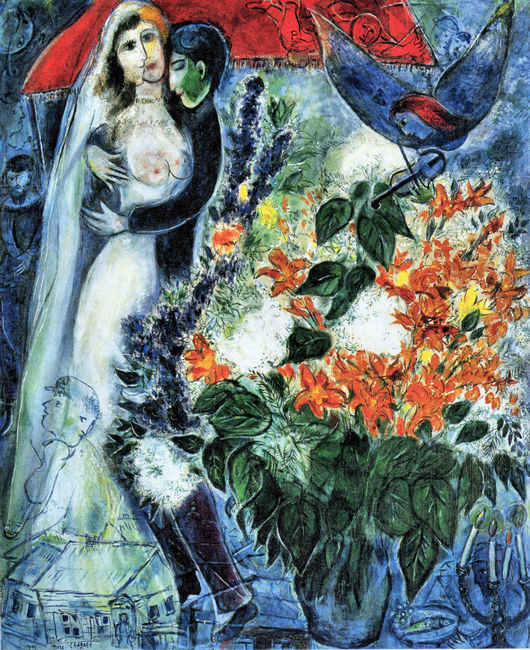
③赤い背景の花(1968)/No.109…まさに真紅の画面。会場でもひときわ目を引く作品だ。窓のある赤い壁の背景に溶け込むように花瓶に活けられた大きな花束が置いてある。右側から妻のヴァヴァだろうか女性が手に花を持って近づいてくる。強烈な残像のように脳裏に残る光景。

[参考]
ちなみに下の絵は今回ウィーンのアルベルティーナ美術館で観たシャガールの「花と共に眠る女性」(1972)だけれど、シャガールの花の絵は大抵このように人物や動物、故郷の風景などが書き込まれていることが多い。
④青いロバ[陶器](1954)/No.026…シャガールの手がけた陶器の作品も何点か展示されているが水差しにしろ、壺にしろ実用的な普通の形というよりは、その形態をかりたオブジェという感じだ。
このロバの水差しも取っ手が馬の脚(というか手というか)のようにもなっていて何ともユーモラスでおおらかな姿だ。周りに施されている彩色もいかにもシャガールというもので、全体の雰囲気としてはまさに彼の絵から三次元の世界に抜け出てきた感じがする。
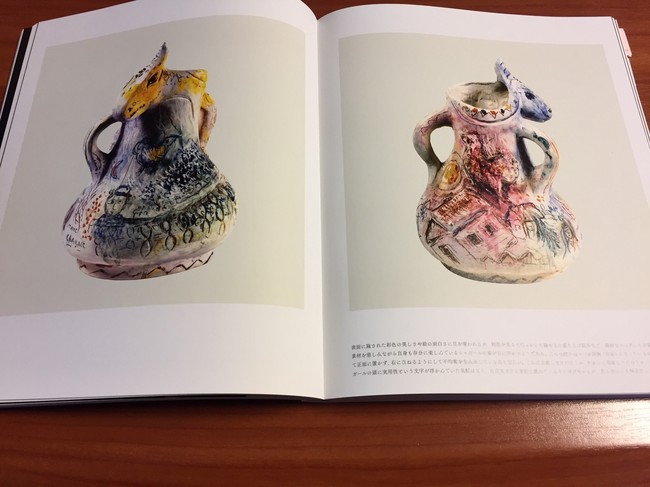
⑤カーネーションを持つベラ(1925)/No.006…初期の頃の作品で、妻のベラの姿ががっしりとした骨太の体格で描かれている。この展覧会にもあったけどシャガールの1910年代の作品にはキュビズムの影響が見られるが、この作品は首の太さや骨格のダイナミックさなどピカソの新古典主義の時代(1918年~1925年頃)と共通するものがあるように思う。
ピカソはこの頃オルガと結婚しており、キュビズムの時代とは作風は大きく変わっている。その影響もあったのかもしれないが、色合いと言い、画面構成と言いその後のシャガールの作風からは想像がつきにくい。

[参考]

ピカソ「母と子」(1921)
[図録]
250頁。2592円。通常よりちょっと高いが、かなり力の入った図録に思える。多少くすんではいるが、色も比較的よく出ているし何よりも見ていて楽しい作りになっている。
シャガールの彫刻など三次元の作品を見ることができるのも楽しいが、ただ作品を並べるだけでなくその下絵や絵画作品と関連づけたり工夫がみられるのも好感が持てる。今回の展示は個人所蔵の作品が多いのでそういう意味でも他の画集には載っていない作品も多いと思う。
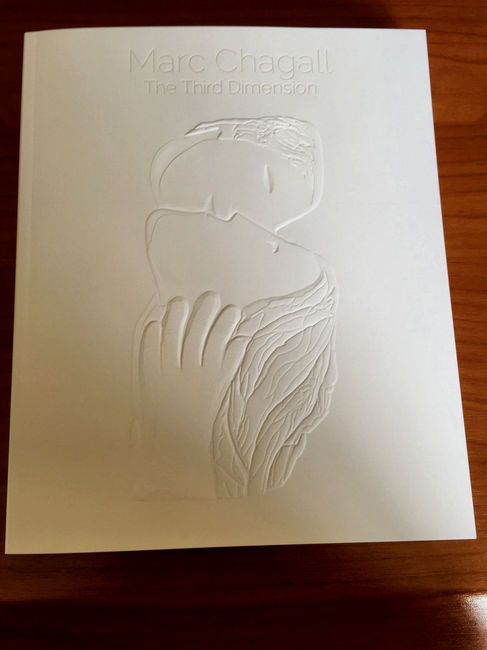


(Okt.2017)
gillman*s Museums ボストン美術館展
■The Museum of the Month

[感想メモ]
ボストン美術館と言えば、ぼくが近年行った展覧会だけでも森アーツセンターギャラリーでの「ボストン美術館展/西洋絵画の巨匠たち」(2010年)、国立博物館での「ボストン美術館/日本美術の至宝展」(2012年)、三菱一号館美術館での「ボストン美術館/ミレー展」(2014年)やBunkamura Museumでの「ボストン美術館所蔵/俺の国芳、わたしの国貞展」(2016年)など日本美術関係も含めて日本でも多くの展覧会が開かれており、その収蔵作品の豊富さに驚く。
今までのボストン美術館展は上記の展覧会でも分かるようにボストン美術館の豊富な収蔵品の中から特定の分野を選んで収蔵品をチョイスして展覧会を構成していたが、今回のは古代エジプト美術から現代美術まで幅広い分野を横断的に網羅している。出品点数80点余りで全時代を網羅するというのも多少辛い面もあるけれど、実際に現地に行っても美術館ツアーなんかで行ったら一回の滞在時間で80点を観て回れるかさえもとないので、向こうから来てくれるというのはありがたい機会だと思う。

[My Best 5]
①涅槃図(1713)/英一蝶…日本画においても色々な涅槃図があるけれど、この涅槃図も素晴らしい。入滅する仏陀を囲む菩薩をはじめとして諸々の生き物の表情がなんとも活き活きとしていつまで見ていても飽きない。近年に修復されてその美しさを取り戻している。ボストン美術館はこの作品を1911年にフェノロサから寄贈された。

②卓上の花と果物(1865)/アンリ・ファンタン=ラトゥール…ファンタン=ラトゥールはぼくの大好きな画家の一人だが、この「卓上の花と果物」と同じ年に描かれたと思われる作品「花と果物、ワイン容れのある静物」が国立西洋美術館にある(現時点では展示されていない)。国立西洋美術館にはぼくの好きな二人のラトゥールの作品がある、それは「光のジョルジュ・ド・ラトゥール」とこの「花のアンリ・ファンタン=ラトゥール」だ。この作品の瑞々しさを見つめ続けていると、シャルダンに通じるような揺るぎのないヨーロッパ絵画の力を感じさせる。

③郵便配達人ジョセフ・ルーラン(1888)/フィンセント・ファン・ゴッホ…ジョセフ・ルーランの肖像は以前クレラー・ミュラー美術館で見たことがあるけど、それは上半身の絵だったと思うが、今回の肖像はほぼ全身が描かれており画面も大きい。会場ではルーランの夫人の絵が並んで展示されていて、この展示会の目玉的な扱いがなされていた。画面の青がとても鮮烈で印象に残る。襟元や手の表現を観るとゴッホが何度か試行錯誤したような感じがする。

④ロベール・ド・セヴリュー(1879)/ジョン・シンガー・サージェント…サージェントの絵を一目見て思うのはまず巧いなぁということ。全体から描かれた人物の第一印象が真っ直ぐに伝わってくる。それは多分実際にその人物に会ってみても同じような第一印象を受けるのではないかと、錯覚するほど。かと言って超リアル絵画のように事細かに細部が描き込まれているわけではない。この子供を描いた肖像画をよく観るとその目元や口元から育ちの良い、利発そうな子供の印象を受ける。

⑤線路(1922)/エドワード・ホッパー…本作品はエッチングの小品だけれど、ホッパー特有の空気に満ち溢れている。ホッパーは都会を描くホッパーと荒涼たる地方の光景を描くホッパーの両面をもっているが、この絵には線路、電線、家といった後者のポッパーの面が表れている。コントラストのつよいモノクロの画面がこの情景の孤独さを強めている。ホッパーはぼくの大好きな画家で画集も何冊か持っているけど、実際の作品は数点しか見られていない。日本でのホッパー展を待ち望んでいるのだけど…。

[図録]
210頁。1900円。標準的な図録の作りだが、ボストン美術館の特徴ともいえる美術館を支える寄贈者について巻頭にかなりのスペースをさいている。展示場でもコレクション毎に寄贈者が紹介されていた。
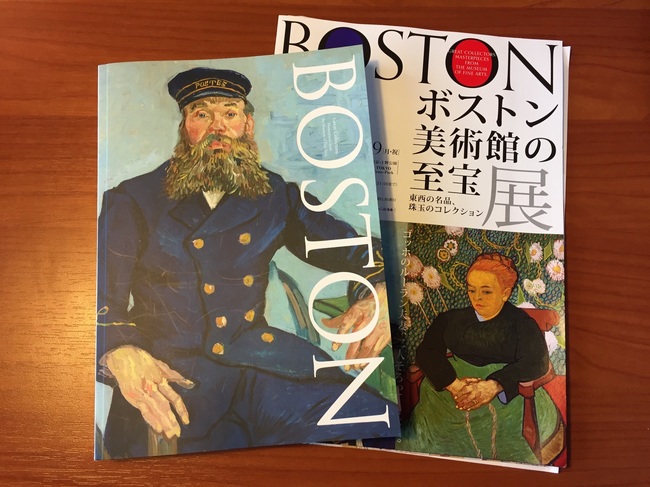
ボストン美術館の至宝展
東西の名画、珠玉のコレクション
東京都美術館
2017年7月20日〜10月9日

[感想メモ]
ボストン美術館と言えば、ぼくが近年行った展覧会だけでも森アーツセンターギャラリーでの「ボストン美術館展/西洋絵画の巨匠たち」(2010年)、国立博物館での「ボストン美術館/日本美術の至宝展」(2012年)、三菱一号館美術館での「ボストン美術館/ミレー展」(2014年)やBunkamura Museumでの「ボストン美術館所蔵/俺の国芳、わたしの国貞展」(2016年)など日本美術関係も含めて日本でも多くの展覧会が開かれており、その収蔵作品の豊富さに驚く。
今までのボストン美術館展は上記の展覧会でも分かるようにボストン美術館の豊富な収蔵品の中から特定の分野を選んで収蔵品をチョイスして展覧会を構成していたが、今回のは古代エジプト美術から現代美術まで幅広い分野を横断的に網羅している。出品点数80点余りで全時代を網羅するというのも多少辛い面もあるけれど、実際に現地に行っても美術館ツアーなんかで行ったら一回の滞在時間で80点を観て回れるかさえもとないので、向こうから来てくれるというのはありがたい機会だと思う。

[My Best 5]
①涅槃図(1713)/英一蝶…日本画においても色々な涅槃図があるけれど、この涅槃図も素晴らしい。入滅する仏陀を囲む菩薩をはじめとして諸々の生き物の表情がなんとも活き活きとしていつまで見ていても飽きない。近年に修復されてその美しさを取り戻している。ボストン美術館はこの作品を1911年にフェノロサから寄贈された。

②卓上の花と果物(1865)/アンリ・ファンタン=ラトゥール…ファンタン=ラトゥールはぼくの大好きな画家の一人だが、この「卓上の花と果物」と同じ年に描かれたと思われる作品「花と果物、ワイン容れのある静物」が国立西洋美術館にある(現時点では展示されていない)。国立西洋美術館にはぼくの好きな二人のラトゥールの作品がある、それは「光のジョルジュ・ド・ラトゥール」とこの「花のアンリ・ファンタン=ラトゥール」だ。この作品の瑞々しさを見つめ続けていると、シャルダンに通じるような揺るぎのないヨーロッパ絵画の力を感じさせる。

③郵便配達人ジョセフ・ルーラン(1888)/フィンセント・ファン・ゴッホ…ジョセフ・ルーランの肖像は以前クレラー・ミュラー美術館で見たことがあるけど、それは上半身の絵だったと思うが、今回の肖像はほぼ全身が描かれており画面も大きい。会場ではルーランの夫人の絵が並んで展示されていて、この展示会の目玉的な扱いがなされていた。画面の青がとても鮮烈で印象に残る。襟元や手の表現を観るとゴッホが何度か試行錯誤したような感じがする。

④ロベール・ド・セヴリュー(1879)/ジョン・シンガー・サージェント…サージェントの絵を一目見て思うのはまず巧いなぁということ。全体から描かれた人物の第一印象が真っ直ぐに伝わってくる。それは多分実際にその人物に会ってみても同じような第一印象を受けるのではないかと、錯覚するほど。かと言って超リアル絵画のように事細かに細部が描き込まれているわけではない。この子供を描いた肖像画をよく観るとその目元や口元から育ちの良い、利発そうな子供の印象を受ける。

⑤線路(1922)/エドワード・ホッパー…本作品はエッチングの小品だけれど、ホッパー特有の空気に満ち溢れている。ホッパーは都会を描くホッパーと荒涼たる地方の光景を描くホッパーの両面をもっているが、この絵には線路、電線、家といった後者のポッパーの面が表れている。コントラストのつよいモノクロの画面がこの情景の孤独さを強めている。ホッパーはぼくの大好きな画家で画集も何冊か持っているけど、実際の作品は数点しか見られていない。日本でのホッパー展を待ち望んでいるのだけど…。

[図録]
210頁。1900円。標準的な図録の作りだが、ボストン美術館の特徴ともいえる美術館を支える寄贈者について巻頭にかなりのスペースをさいている。展示場でもコレクション毎に寄贈者が紹介されていた。
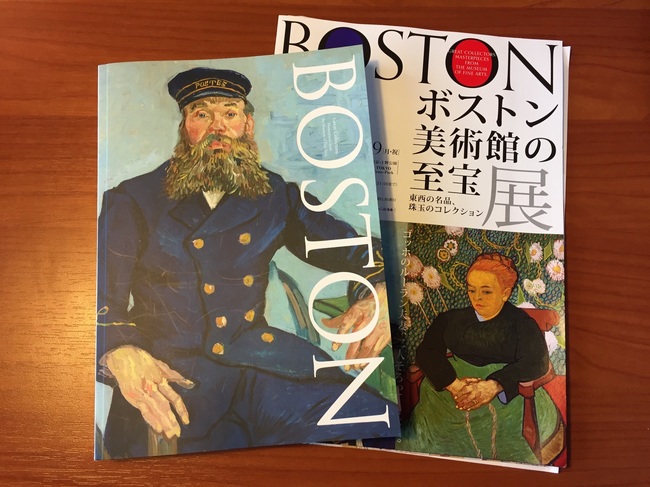
(Aug.2017)
gillman* Museums ナビ派展
■Museum of the Month

[感想メモ]
ナビ派というと日本ではあまりなじみがないような感じがするけれど、ぼくは若いころから国立西洋美術館で特にモーリス・ドニ等の作品に馴染んでいたのでかえって懐かしい感じがした。ドニについて言えば西洋美術館は「踊る女たち」をはじめとして50点近い作品を所蔵している。
ナビ派は平面的な表現やその装飾性の高い構図などが特徴的なものだと思っていたけれど、今回の展示を見てみると思ったよりもその表現の幅は広いように思う。ナビ派の作品でもボナールやドニの作品は西洋美術館をはじめとして、ブリヂストン美術館やポーラ美術館など日本の美術館でも観ることが出来るけれども、これだけの作品を俯瞰的に観る機会は中々ないのでとても楽しかった。

[ナビ派展 My Best 5]
①ボール/フェリックス・ヴァロットン(No.57)
ヴァロットンのこの「ボール」に再会できたのは全く期待していなかっただけに、驚きでもあり喜びでもあった。この「ボール」は2014年の7月に同じこの美術館で開催された「ヴァロットン展」の目玉作品だった。それまで図録でしか見たことがなかったこの作品を観られるとは思っていなかったので望外の喜びがあったけれど今回の再会もそれに匹敵する。
今度はホントにさりげなく、ひっそりと展示されていて心なしか絵の前で立ち止まる人も少なかったように思った。今や絵画展でも前宣伝というのは大したものなんだなぁと…。それともぼくがヴァロットンが好きだから一人で感心しているのか。もっともヴァロットンはナビ派といっても「外国人のナビ」と言われたように他のナビ派の作家とはちょっとテイストが異なる。ナビ派独特の装飾性や神秘性よりも日常に潜む怪しげな瞬間に目を凝らしている。ぼくはそれが好きなのだけれど…。

②猫と女性/ピエール・ボナール(No.44)
ボナールはなんといってもその色使いが魅力だ。色の配色と特に初期は日本絵画の影響を受けたといわれる平面的な画面構成が実に洗練されていて日常の変哲のない光景がとても特別で大切な瞬間のように画面に定着されている。この「猫と女性」は後年の色彩が鮮やかさを増した時代の作品で正にアンティミストとしての日常への眼差しが光っている。白猫の表情がとても活き活きとしていて素敵だ。

③エッセル家旧蔵の昼食/エドゥアール・ヴュイヤール(No.34)
ボナールの絵が色彩が踊っているとするならば、ヴュイヤールのそれはちょっと抑え気味の色彩がハーモニーを大事にして連なっていてるという感じがする。この室内情景画は一歩引いて食卓全体を見渡す位置から一家の食後のひと時を見つめている。今回は彼の大作「公園」も展示されているが、それからも分かるように彼の絵はナビ派の装飾性をもった代表的なものだと思う。

④髪を整える女性/フェリックス・ヴァロットン(No.28)
この絵と並んで展示されている「室内、戸棚を探る青い服の女性」も好きな絵だが、この二枚はヴァロットンお得意の日常の情景に潜む意味ありげなシーンを描いている。「ボール」もそうだけれどもヴァロットンの絵には、その画面を見てその暗示するもの、もしくは描かれたそのシーンの直前・直後の情景を想像してみるという楽しみがある。そういう意味ではナビ派のアンティミスト傾向が、日常の幸せで静謐な瞬間を定着させたいというものであるとしたら、それとはかなり傾向の違う題材であり表現だとも思える。(この二枚の絵もヴァロットン展以来の再会)
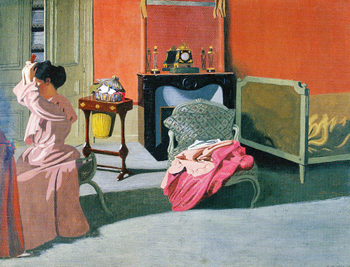
⑤マレーヌ姫のメヌエット/モーリス・ドニ(No.41)
ナビ派の中でもドニは恐らく、特にその後期においてもっとも装飾性の高い画家だと思うのだけれど、ぼくはどちらかと言えば比較的初期の作品の方が好きだ。この「マレーヌ姫」はその後ドニと結婚することになるマルトを描いた初期のものだが、優しい色使いと繊細な筆致にドニのモデルに対する愛情が感じられる。ドニの妻になる「マルト」はマルタ・モリエールの愛称だが、ぼくなんかは「マルト」というとボナールの妻マリア・ブールサンを思い浮かべてしまう。彼女も「マルト」と呼ばれてボナールの絵によく出てくる。

[図録]
206頁。2400円。新たな試みとして今回の図録はKindle版の電子ブックが発売されている。(2200円) 書籍版はページの角が丸くなっているなど丁寧な作りが伺われる。色彩はナビ派の絵はパステルカラーのような淡い色が多いので難しそうだがそれなりに出ていると思う。オルセー美術館の総裁へのインタビューや掲載されている論文も興味深く、これ一冊でナビ派の全容がよく分かりそう。
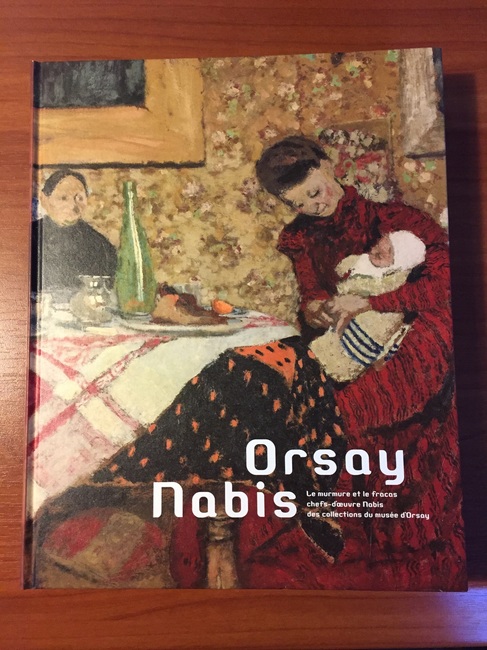
(Feb.2017)
オルセーのナビ派展
2017年2月4日~5月21日
三菱一号館美術館

[感想メモ]
ナビ派というと日本ではあまりなじみがないような感じがするけれど、ぼくは若いころから国立西洋美術館で特にモーリス・ドニ等の作品に馴染んでいたのでかえって懐かしい感じがした。ドニについて言えば西洋美術館は「踊る女たち」をはじめとして50点近い作品を所蔵している。
ナビ派は平面的な表現やその装飾性の高い構図などが特徴的なものだと思っていたけれど、今回の展示を見てみると思ったよりもその表現の幅は広いように思う。ナビ派の作品でもボナールやドニの作品は西洋美術館をはじめとして、ブリヂストン美術館やポーラ美術館など日本の美術館でも観ることが出来るけれども、これだけの作品を俯瞰的に観る機会は中々ないのでとても楽しかった。

[ナビ派展 My Best 5]
①ボール/フェリックス・ヴァロットン(No.57)
ヴァロットンのこの「ボール」に再会できたのは全く期待していなかっただけに、驚きでもあり喜びでもあった。この「ボール」は2014年の7月に同じこの美術館で開催された「ヴァロットン展」の目玉作品だった。それまで図録でしか見たことがなかったこの作品を観られるとは思っていなかったので望外の喜びがあったけれど今回の再会もそれに匹敵する。
今度はホントにさりげなく、ひっそりと展示されていて心なしか絵の前で立ち止まる人も少なかったように思った。今や絵画展でも前宣伝というのは大したものなんだなぁと…。それともぼくがヴァロットンが好きだから一人で感心しているのか。もっともヴァロットンはナビ派といっても「外国人のナビ」と言われたように他のナビ派の作家とはちょっとテイストが異なる。ナビ派独特の装飾性や神秘性よりも日常に潜む怪しげな瞬間に目を凝らしている。ぼくはそれが好きなのだけれど…。

②猫と女性/ピエール・ボナール(No.44)
ボナールはなんといってもその色使いが魅力だ。色の配色と特に初期は日本絵画の影響を受けたといわれる平面的な画面構成が実に洗練されていて日常の変哲のない光景がとても特別で大切な瞬間のように画面に定着されている。この「猫と女性」は後年の色彩が鮮やかさを増した時代の作品で正にアンティミストとしての日常への眼差しが光っている。白猫の表情がとても活き活きとしていて素敵だ。

③エッセル家旧蔵の昼食/エドゥアール・ヴュイヤール(No.34)
ボナールの絵が色彩が踊っているとするならば、ヴュイヤールのそれはちょっと抑え気味の色彩がハーモニーを大事にして連なっていてるという感じがする。この室内情景画は一歩引いて食卓全体を見渡す位置から一家の食後のひと時を見つめている。今回は彼の大作「公園」も展示されているが、それからも分かるように彼の絵はナビ派の装飾性をもった代表的なものだと思う。

④髪を整える女性/フェリックス・ヴァロットン(No.28)
この絵と並んで展示されている「室内、戸棚を探る青い服の女性」も好きな絵だが、この二枚はヴァロットンお得意の日常の情景に潜む意味ありげなシーンを描いている。「ボール」もそうだけれどもヴァロットンの絵には、その画面を見てその暗示するもの、もしくは描かれたそのシーンの直前・直後の情景を想像してみるという楽しみがある。そういう意味ではナビ派のアンティミスト傾向が、日常の幸せで静謐な瞬間を定着させたいというものであるとしたら、それとはかなり傾向の違う題材であり表現だとも思える。(この二枚の絵もヴァロットン展以来の再会)
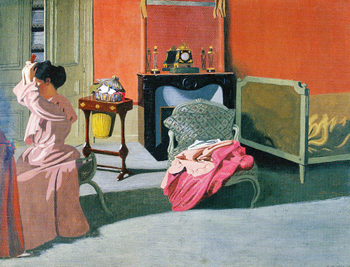
⑤マレーヌ姫のメヌエット/モーリス・ドニ(No.41)
ナビ派の中でもドニは恐らく、特にその後期においてもっとも装飾性の高い画家だと思うのだけれど、ぼくはどちらかと言えば比較的初期の作品の方が好きだ。この「マレーヌ姫」はその後ドニと結婚することになるマルトを描いた初期のものだが、優しい色使いと繊細な筆致にドニのモデルに対する愛情が感じられる。ドニの妻になる「マルト」はマルタ・モリエールの愛称だが、ぼくなんかは「マルト」というとボナールの妻マリア・ブールサンを思い浮かべてしまう。彼女も「マルト」と呼ばれてボナールの絵によく出てくる。

[図録]
206頁。2400円。新たな試みとして今回の図録はKindle版の電子ブックが発売されている。(2200円) 書籍版はページの角が丸くなっているなど丁寧な作りが伺われる。色彩はナビ派の絵はパステルカラーのような淡い色が多いので難しそうだがそれなりに出ていると思う。オルセー美術館の総裁へのインタビューや掲載されている論文も興味深く、これ一冊でナビ派の全容がよく分かりそう。
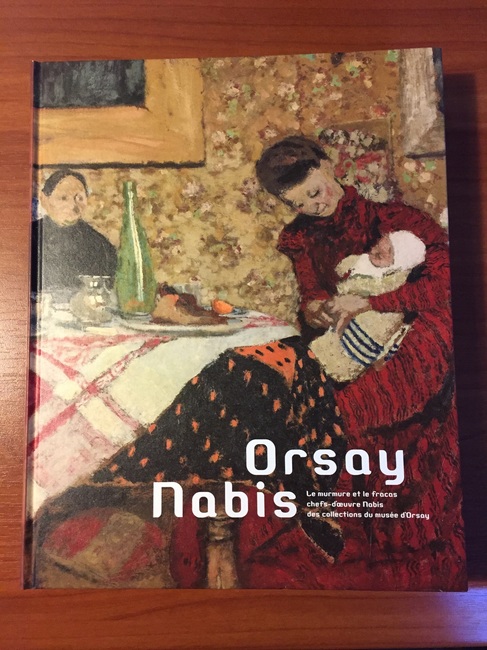
(Feb.2017)
gillman*s Museum デトロイト美術館展
■Museum of the Month
上野の森美術館

[感想メモ]
上野の森美術館は今年はポール・スミス展に続いて、このデトロイト美術館展で二回目。この美術館の展示スペース自体があまり広くはないので(とは言っても山種美術館や太田美術館などよりは広いと思う)展示作品数は50点ちょっと。その範囲で印象派から20世紀前半までを駆け足で廻るような慌ただしさはあるけど、考えようによっては厳選された作品を一点一点じっくりと見る良い機会ではあるかもしれない。
特に今回少ない展示数の中でもドイツ表現主義を中心とする20世紀のドイツ絵画が10点強展示されているので、見方によっては今後の近代フランス絵画以外への興味の足がかりとなるかもしれない。


[デトロイト美術館展 My Best5]
①肘掛け椅子の女性/パブロ・ピカソ(No.45)…一口にピカソが好きだと言っても、ピカソの画風は時代によって千変万化するので難しい。ぼくはどちらかと言えば青の時代やこの古典主義様式時代の作品が好きだ。この作品の実物は初めて見たけれど、実に堂々としている。骨太な骨格の女性像はどこか神々しくてそれでいて全てを優しく包み込むような母性のようなものを感じる。この絵を観られただけでも元はとれたかなと…。

②エルサレムの眺め/オスカー・ココシュカ(No.35)…会場には日本ではあまり見られないドイツ表現主義の絵画も何点かあったが、その一画にココシュカの絵も二点ほどあった。ココシュカは人物画が多いように思うけど、ぼくはどちらかと言えば彼の風景画の方が好きだ。展示されていたのは「エルベ川、ドレスデン近郊」と本作の二点とも風景画でぼくはどちらも気に入った。こちらの方は横が1.3メーターあまりの大作で、ココシュカ独特の明るい色でエルサレムの街の俯瞰が描かれている。1930年ころの作品なので、この頃には翻弄され続けた女性アルマ・マーラー(マーラーの未亡人)の幻影からやっと抜け出せた頃か。この後ナチスの台頭で彼はプラハに逃れることになるのだけれど。

③犬と女性/ピエール・ボナール(No.24)…ボナールはぼくの大好きな画家の一人。その何とも言えない色彩の取り合わせにいつも魅了されてしまう。本作もアンティミスト(親密派)としてのボナールのいつもの画題通りに妻のマルトを描いている。彼には装飾性の高い作品もあり、変則な縦型の本作もそのような雰囲気を持っている。彼の描き出す日常の場面、日常の光に包まれた静謐な時間に引き付けられてしまう。
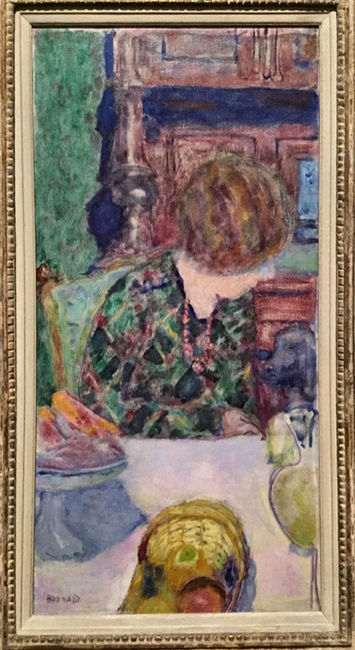
④画家の夫人/ポール・セザンヌ(No.15)…セザンヌはリンゴやサント・ヴクィトワール山や妻など同じ画題を繰り返し描いている。画面構成や平面の扱いなど専門的に見れば興味が尽きないし凄い画家でもあるのだろうけれど、ぼくみたいな素人からすると時に退屈な絵に見えないこともない。それは多分良く言えばクール、悪く言えば絵画構成等に傾注して描く対象物への興味なんかあったのだろうかという疑念を抱かせる点にあるのかもしれない。そういう意味では妻もリンゴも同じであったと言えるのかもしれないが、この作品では珍しくその妻そのものへの視線が光っているような気がする。絵には全く興味のなかった妻、夫婦とは名ばかりだったような二人の関係が妻の表情によく表れているような…気がする。

⑤バイオリニストと若い女性/エドガー・ドガ(No.4)…5番目は散々迷った。ルノアールも入っていないし、マチスだって良かった、ジェルヴェクスも捨てがたい。で結局ドガのこの作品となった。というのもこの作品の解説のところにドガの作品と当時台頭しつつあった写真との関係が述べられていたからだ。以前からドガの作品はスナップショットのようだと思っていたんだけれど、ドガも一時は写真機を使って自分で撮っていたこともあるらしい。もちろんそれはドガが写真をなぞったということではなくて、目の前を過ぎてゆく一瞬を捕捉するということを写真の登場によってより明確に意識したということではないかと思っている。

[図録]
174頁。2000円。展示作品数が52展と比較的コンパクトなものなので図録もコンパクトになっている。内容は作品と解説が見開きになっている通常のスタイル。写真の色の再現性は悪くはないと思う。印象派から20世紀前半までの絵画を駆け足で振り返るにしても作品数は少ないという思いはあるが、図録の中ではそこら辺をデトロイト美術館名誉館長のビール氏と千足伸行氏の読み応えのある論文でカバーしている感じがある。
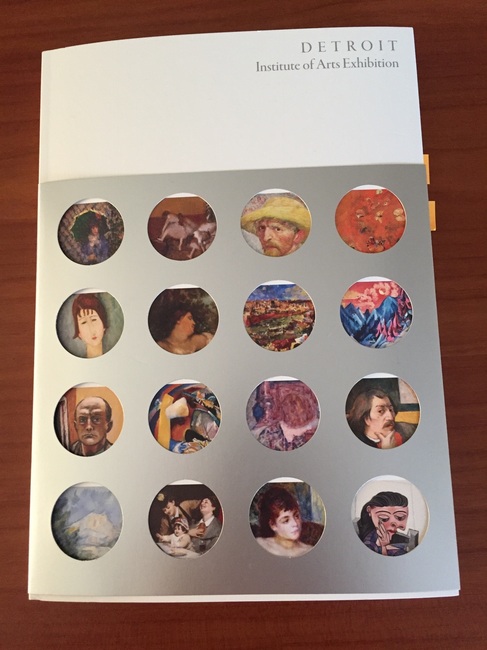
デトロイト美術館展
上野の森美術館
2016年10月7日~1月21日

[感想メモ]
上野の森美術館は今年はポール・スミス展に続いて、このデトロイト美術館展で二回目。この美術館の展示スペース自体があまり広くはないので(とは言っても山種美術館や太田美術館などよりは広いと思う)展示作品数は50点ちょっと。その範囲で印象派から20世紀前半までを駆け足で廻るような慌ただしさはあるけど、考えようによっては厳選された作品を一点一点じっくりと見る良い機会ではあるかもしれない。
特に今回少ない展示数の中でもドイツ表現主義を中心とする20世紀のドイツ絵画が10点強展示されているので、見方によっては今後の近代フランス絵画以外への興味の足がかりとなるかもしれない。


[デトロイト美術館展 My Best5]
①肘掛け椅子の女性/パブロ・ピカソ(No.45)…一口にピカソが好きだと言っても、ピカソの画風は時代によって千変万化するので難しい。ぼくはどちらかと言えば青の時代やこの古典主義様式時代の作品が好きだ。この作品の実物は初めて見たけれど、実に堂々としている。骨太な骨格の女性像はどこか神々しくてそれでいて全てを優しく包み込むような母性のようなものを感じる。この絵を観られただけでも元はとれたかなと…。

②エルサレムの眺め/オスカー・ココシュカ(No.35)…会場には日本ではあまり見られないドイツ表現主義の絵画も何点かあったが、その一画にココシュカの絵も二点ほどあった。ココシュカは人物画が多いように思うけど、ぼくはどちらかと言えば彼の風景画の方が好きだ。展示されていたのは「エルベ川、ドレスデン近郊」と本作の二点とも風景画でぼくはどちらも気に入った。こちらの方は横が1.3メーターあまりの大作で、ココシュカ独特の明るい色でエルサレムの街の俯瞰が描かれている。1930年ころの作品なので、この頃には翻弄され続けた女性アルマ・マーラー(マーラーの未亡人)の幻影からやっと抜け出せた頃か。この後ナチスの台頭で彼はプラハに逃れることになるのだけれど。

③犬と女性/ピエール・ボナール(No.24)…ボナールはぼくの大好きな画家の一人。その何とも言えない色彩の取り合わせにいつも魅了されてしまう。本作もアンティミスト(親密派)としてのボナールのいつもの画題通りに妻のマルトを描いている。彼には装飾性の高い作品もあり、変則な縦型の本作もそのような雰囲気を持っている。彼の描き出す日常の場面、日常の光に包まれた静謐な時間に引き付けられてしまう。
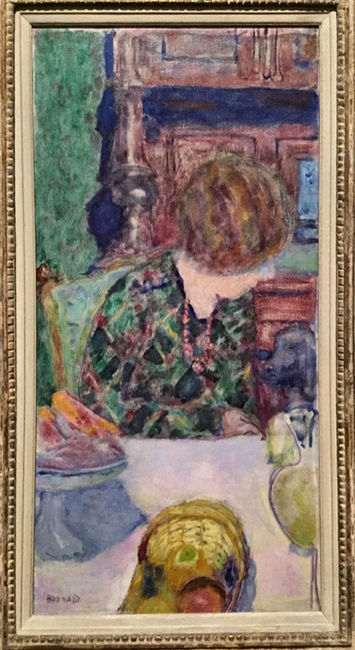
④画家の夫人/ポール・セザンヌ(No.15)…セザンヌはリンゴやサント・ヴクィトワール山や妻など同じ画題を繰り返し描いている。画面構成や平面の扱いなど専門的に見れば興味が尽きないし凄い画家でもあるのだろうけれど、ぼくみたいな素人からすると時に退屈な絵に見えないこともない。それは多分良く言えばクール、悪く言えば絵画構成等に傾注して描く対象物への興味なんかあったのだろうかという疑念を抱かせる点にあるのかもしれない。そういう意味では妻もリンゴも同じであったと言えるのかもしれないが、この作品では珍しくその妻そのものへの視線が光っているような気がする。絵には全く興味のなかった妻、夫婦とは名ばかりだったような二人の関係が妻の表情によく表れているような…気がする。

⑤バイオリニストと若い女性/エドガー・ドガ(No.4)…5番目は散々迷った。ルノアールも入っていないし、マチスだって良かった、ジェルヴェクスも捨てがたい。で結局ドガのこの作品となった。というのもこの作品の解説のところにドガの作品と当時台頭しつつあった写真との関係が述べられていたからだ。以前からドガの作品はスナップショットのようだと思っていたんだけれど、ドガも一時は写真機を使って自分で撮っていたこともあるらしい。もちろんそれはドガが写真をなぞったということではなくて、目の前を過ぎてゆく一瞬を捕捉するということを写真の登場によってより明確に意識したということではないかと思っている。

[図録]
174頁。2000円。展示作品数が52展と比較的コンパクトなものなので図録もコンパクトになっている。内容は作品と解説が見開きになっている通常のスタイル。写真の色の再現性は悪くはないと思う。印象派から20世紀前半までの絵画を駆け足で振り返るにしても作品数は少ないという思いはあるが、図録の中ではそこら辺をデトロイト美術館名誉館長のビール氏と千足伸行氏の読み応えのある論文でカバーしている感じがある。
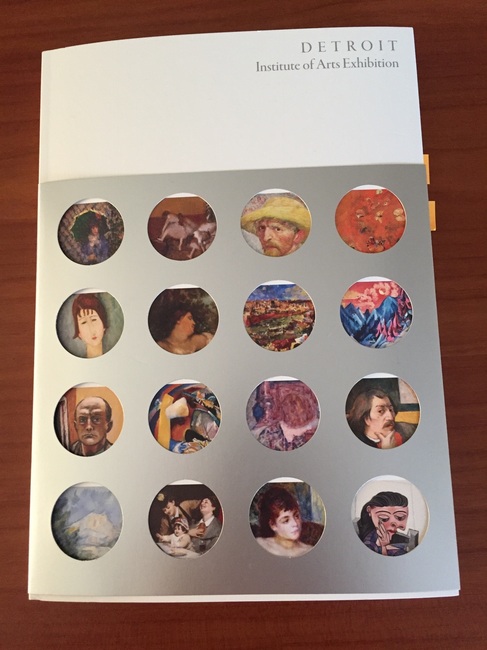
(Okt.2016)
記事検索
gillman*s Choice 新版画 立春
gillman*s Choice...
二十四節気というのは節目節目のところでぼくらの生活に挟みこまれた栞みたいなもので伝統的季節感の基本となっている。その中でも立春、立夏、立秋、立冬といった四節気は今でもぼくらの日常にも深くかかわっている。
昔の人は季節によって床の間の絵や活ける花を替えることで季節の変化をいつも身近に感じていたのだけれど、ぼくも少しだけ真似て四節気には壁にかける好きな新版画の絵を替えるようにしている。
梅花に鷽

小原古邨(祥邨)
小原古邨が祥邨名で渡邊版画店の渡邊正三郎のもとで作成した作品。鷽(うそ)は鳴き声の美しい小型の鳥だが鶯(うぐいす)の字と似ているので間違えやすい。絵は全体が明るい色調でいかにも春めいた雰囲気に満ちている。分かり易くといういう正三郎のプロデュース感覚が前面に出ている感じがするが、春が近づいた気分でぼくは節分にこの絵にかけ替えるのを楽しみにしている。
大手門の春の夕暮

川瀬巴水
巴水の作品の中では比較的地味な作品だけれど、芽吹き始めた柳の新芽の向こうに茜空が見える様は今でもお堀端を歩いていると出合いそうなシーンで親しみがわく。戦後の昭和27年(1952年)の作品で、東京の復興後の姿を映した「新東京風景版画」に収められている。巴水は関東大震災後も東京の復興の姿を積極的に残しているが、戦後の東京の復興の姿もとらえている。
立冬の時期の新版画

小原古邨(祥邨)/南天と瑠璃鳥
川瀬巴水/平泉金色堂
新版画の四季
古邨と巴水
~立春~
二十四節気というのは節目節目のところでぼくらの生活に挟みこまれた栞みたいなもので伝統的季節感の基本となっている。その中でも立春、立夏、立秋、立冬といった四節気は今でもぼくらの日常にも深くかかわっている。
昔の人は季節によって床の間の絵や活ける花を替えることで季節の変化をいつも身近に感じていたのだけれど、ぼくも少しだけ真似て四節気には壁にかける好きな新版画の絵を替えるようにしている。
梅花に鷽

小原古邨(祥邨)
小原古邨が祥邨名で渡邊版画店の渡邊正三郎のもとで作成した作品。鷽(うそ)は鳴き声の美しい小型の鳥だが鶯(うぐいす)の字と似ているので間違えやすい。絵は全体が明るい色調でいかにも春めいた雰囲気に満ちている。分かり易くといういう正三郎のプロデュース感覚が前面に出ている感じがするが、春が近づいた気分でぼくは節分にこの絵にかけ替えるのを楽しみにしている。
大手門の春の夕暮

川瀬巴水
巴水の作品の中では比較的地味な作品だけれど、芽吹き始めた柳の新芽の向こうに茜空が見える様は今でもお堀端を歩いていると出合いそうなシーンで親しみがわく。戦後の昭和27年(1952年)の作品で、東京の復興後の姿を映した「新東京風景版画」に収められている。巴水は関東大震災後も東京の復興の姿を積極的に残しているが、戦後の東京の復興の姿もとらえている。
立冬の時期の新版画
小原古邨(祥邨)/南天と瑠璃鳥
川瀬巴水/平泉金色堂
(Feb.2024)






後ろ姿もパッシャで抜け目ない調理人。
by hagemaizo (2023-02-10 15:57)
メモを見ないで料理が作れるのは素晴らしいことです。
そうやって作れる料理がいくつもあれば怖いものありません。
わたしも料理の手伝いをするのですが、必ずメモ片手で...修行します。
by ナツパパ (2023-02-10 19:33)
1年も腕を磨いたら大したものでしょうね。お二人でキッチンに立つとはほほえましい。調理検査官もついているのですから一層成果が上がることでしょう。
by JUNKO (2023-02-10 19:42)
奥さんの怪我からとは言え、
メモなしで一品は料理されるとは凄いですね。
私は、独身アパート住まいの時に少し自炊したことがありますが
結婚してからは妻に任せっきりです。
by そらへい (2023-02-10 20:37)
2にゃん、面白い行動ですね。
見つめられて「果報」かも…
by 夏炉冬扇 (2023-02-10 20:40)
眼光鋭い厳しい検査官ですね。これは気が抜けない。
何かやらかしちゃったら、莫大な賄賂を要求されますね。
by 親知らず (2023-02-11 09:46)
ハルさん、レオさんの並んだ真剣そのものの後姿^^
なかなか厳しい検査官のようですね。
ウチのも子猫の頃はサラダに飛び込んだり、トマトソースの肉球スタンプを付けて歩いたり大変でしたが、今はもう知らん顔です。
ただ・・炊飯器だけは大好き。
蒸気の吹き出し口あたりを舐めようとして油断できません。
猫なのに肉よりも米が好き、本当に肉食なのか疑問に感じるこの頃です^^
by ゆきち (2023-02-11 11:05)
見ているだけで手も足もよだれも出さないのはワンコと大違いですね。
ウチのワンコならよだれの海ができます^^
by ZZA700 (2023-02-12 18:20)
こんなお話を読むと、猫ちゃんが欲しくなります…
可愛いですね。それぞれ性格も違って。
by めぎ (2023-02-13 03:06)
これはかなり厳しい調理検査官のようですね。
最後のショットは2にゃんで相談でしょうか^^
by kuwachan (2023-02-14 01:26)
いいなぁ~~
うちの主人も見習ってほしいです!(^^
by たま (2023-02-20 15:31)